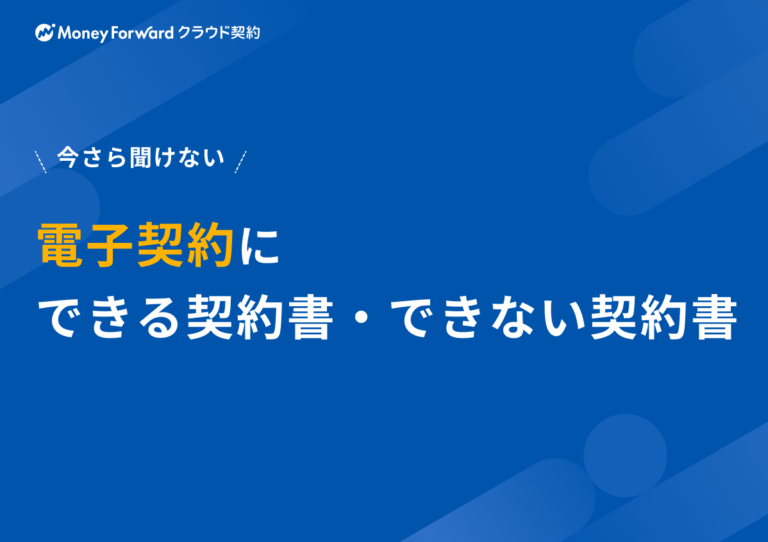- 更新日 : 2025年3月6日
建設業で電子契約は利用できる!メリットや注意点、保存について解説
電子契約には多くのメリットがあり、公共工事を含む建設業でも導入が盛んです。この記事では、建設業における電子契約の法的根拠や、グレーゾーン解消制度がどのように関係しているのかに加えて、実際に電子契約を結ぶ際に注意すべきポイントをご紹介します。求められている要件を確認し、電子契約への移行を検討してみてください。
目次
公共工事を含む建設工事で電子契約の利用が可能!
2001年4月の建設業法改正によって、公共工事を含む建設工事での電子契約が可能になりました。それまで、建設工事の請負契約では書面化が義務とされていましたが、この法改正により、一定の技術的基準をはじめとする要件を満たし、相手の承諾を得れば、情報通信技術の利用による代替措置(電子契約)が認められることとなりました。電子契約ができれば、労力や時間、人件費や経費などを削減できます。
建設業の請負工事が電子契約可能になった経緯
公共工事を含む建設工事での電子契約は、2001年4月に施行された、IT書面一括法に基づいています。このIT書面一括法は、それまで義務付けられていた民間商取引において、相手の承諾が得られた場合、書面に記載すべき内容を電磁的措置で行えるようにする法律です。
この法改正に続き、2001年から建設業法も改正されました。この法改正により、書面の交付が必要だった建設請負工事も電子契約が可能になったのです。
電子契約を行うために必要な条件
公共工事を含む建設工事で電子契約を結ぶためには、「見読性」「原本性」「本人性」の3つが必要です。「見読性」により閲覧・検索ができ、「本人性」により契約しようとしている当人であることを証明し、「原本性」により、当事者が作成した契約書であることを証明できる状態で保管される必要があります。
2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
加えて、お互いに電子契約を結ぶことに了承があれば、電子契約が可能です。
グレーゾーン解消制度について
グレーゾーン解消制度は、経済産業省による新規事業創出の一環となる制度です。産業競争力強化法に基づいて制定されており、電子契約のような新制度やサービスなどが、既存の法律や規制に則っているか照会できます。
問題になっていたこと
一般的な商取引よりも契約金額が大きくなりやすい建設工事では、契約書の「原本性」と「見読性」が重要視されます。建設業法施行規則第13条の4第2項の技術的基準である、「当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること」、「ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること」が求められるでしょう。
2020年に建設業法施行規則が改正された当初は、建設業で電子契約が可能になったあとも、書面契約が原則となる場合が多く、「電子化はどこまで可能か」と、議論されていました。
グレーゾーンの解消制度で変わったこと
建設業の電子契約におけるグレーゾーン解消制度により、住宅の施工やリフォームといった、大きな金額になる工事において、印紙税をはじめとするコストの削減や業務効率化が進んでいます。産業競争力強化法により明確になるグレーゾーン解消制度の利用は、安心して工事を発注・受注でき、トラブルを避けられるなど、多くのメリットがあるでしょう。
建設業において電子契約化できる書面・できない書面
建設業における契約書類の電子化は、2021年のデジタル改革関連法の施行により、さらに適用範囲が拡大されました。以下で、建築業で電子契約化できる書面とそうでない書面を紹介します。
電子契約化できる書面
電子契約化できる書面は、以下のとおりです。
- 工事請負契約書
- 工事発注契約書
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- 保証契約書
- 見積書
- 追加・変更契約書
- 竣工確認立会書
- 引渡確認書
- 秘密保持誓約書
請負契約書以外にも、さまざまな書面の電子化が可能です。
電子契約化できない書面
多くの契約書面が電子化できるようになった一方、事業用定期借地契約は電子契約化が認められていません。契約書を公正証書によって作成することが定められている文章であるためです。
ただし、公正証書についての電子化も検討されており、近い将来電子化する可能性があります。
請負工事を電子契約化するメリット
請負工事を電子契約化すると、コスト削減や作業の効率化など、数多くのメリットがあります。ここでは、電子契約によって改善されるポイントをみていきましょう。
各種コストが削減できる
電子契約では、さまざまなコストを削減可能です。たとえば、紙の書類では必須だった収入印紙の貼り付けが、電子契約では不要になります。また、工事が終了後に保存しておかなければならない書類を保管するスペースも必要ありません。
こうした、収入印紙代や保管コストのほか、印刷コスト・郵送料・各雑務の人件費などのコストなども削減できるのが電子契約のメリットです。
効率よく契約手続きをできる
電子契約では、書類のやりとりによるタイムラグがありません。印刷した紙の書類を使った契約では、押印してから郵送するやりとりだけで、2〜3営業日が必要になります。また、オフィスに訪問して契約書類を完成させる場合は、双方のスケジュール調整も必要となるでしょう。
一方、電子契約であれば、契約書面が完成した直後に相手と契約が締結できるため、場所の制限はありません。
コンプライアンスが強化される
電子契約では、契約書の閲覧にアクセス権が必要になるため、セキュリティが向上し、コンプライアンスの強化にもつながります。電子契約では、印鑑の代わりに電子署名とタイプスタンプを使用するため、改ざんや不正などのトラブル防止が可能です。大きな金額の工事において信頼性が確保できることは、発注側・受注側双方にとってメリットがあります。
請負工事を電子契約化する方法
請負工事に電子契約を導入する際は、建設業法施行規則に定められた技術的基準を満たす必要があります。
電子契約の技術的基準は、以下の3つです。
- 見読性:契約書が常に明確で画面表示や印刷が可能であること
- 原本性:電子署名やタイムスタンプによる改ざん防止が保証されていること
- 本人性:契約当事者の本人確認が確実に行えること
こうした要件を満たすため、請負契約の電子契約化には電子契約サービスを利用するのが一般的です。技術要件の詳細については、後述します。
電子契約サービスの導入
電子契約サービスは、従来の紙の契約書作成から締結までのプロセスを、インターネットを通じてクラウド上で完結できるシステムです。契約書のPDFファイルをクラウド上にアップロードし、契約当事者双方が電子署名を行うことで契約が成立します。
電子契約サービスには、契約当事者本人が電子署名を行う「当事者型」と、サービス提供事業者が当事者の指示に基づいて電子署名を付与する「立会人型」があります。
いずれの方式でも、電子署名による本人確認、タイムスタンプによる存在証明、厳格なアクセス管理による改ざん防止などの機能が実装されているのが一般的です。そのため、適正な電子契約サービスを選択することで先述した技術要件である見読性(契約書の閲覧・印刷が可能)、原本性(改ざん防止)、本人性(契約当事者の本人確認)という技術要件を満たせます。
電子契約サービスを導入する流れ
ここからは紙ベースの契約から電子契約に移行する際の、一般的な流れを紹介します。
現状分析と目的の明確化
まず自社の契約業務の現状を詳細に分析し、電子化による改善点を明確にしていきます。契約書の作成から締結、保管までの一連の業務フローを見直し、年間の契約件数や契約書の種類、取引先との関係性なども考慮に入れて、電子契約によって解決できる課題を特定していきましょう。
この作業によって、自社に適したサービスを選ぶ基準が明確になります。
サービスの選定と導入準備
電子契約サービスの選定では、建設業法施行規則第13条の2に基づく技術的基準を満たすサービスを選ぶことが求められます。それ以外にもランニングコストや使い勝手、社内ルールに併せたカスタマイズができるか、サポートは充実しているかなどもチェックしましょう。
選定したサービスは、まず一部の部門や特定の契約種別から試験的に導入し、運用上の課題を洗い出していきます。この際、契約相手方からの承諾取得手続きや、電子署名の運用ルール、データの保存方法などを具体化して業務フローを整え、必要に応じてマニュアルなども整備します。
本格導入と展開
電子契約の導入にあたっては、社内の関係部門はもちろん、取引先との調整を丁寧に進める必要があります。
従来の紙での契約を希望する取引先への対応方針も、明確にしておきましょう。また、電子帳簿保存法の要件も満たすよう、適切なデータ保存体制を整えることも求められます。
請負工事を電子契約化する際の注意点
メリットの多い電子契約ですが、契約における信頼性は紙の書類と変わりません。請負工事を電子契約化する際には、先述した「見読性」「原本性」「本人性」の要件が満たされているかチェックしておきましょう。なお、請負工事の契約には条件や内容を確認のうえ、相互の承認が必要です。
電子契約の条件1.「見読性」
電子契約を結ぶ条件のひとつ「見読性」を満たすためには、契約を締結する相手が、データを出力でき、書面を作成し、ディスプレイや書面などにわかりやすく表示できる必要があります。
また、契約書などのデータは、契約に関わる人すべてがアクセスするため、アクセス管理のほか、読み出し不可やデータの破壊といったトラブルを防ぐシステムも必要です。
電子契約の条件2.「原本性」
電子契約を結ぶ条件のひとつ「原本性」を満たすためには、公開鍵暗号方式によって作成された電子署名を使用し、改ざんがないかを確認できる状態にしなければなりません。
公開鍵暗号方式は、データの暗号化には「公開鍵」を使い、閲覧には「秘密鍵」を使用するシステムです。この公開鍵暗号方式により改ざんされていないことを証明できますが、秘密鍵や公開鍵の外部流出を防ぐ管理もしなければなりません。
電子契約の条件3.「本人性」
電子契約を結ぶ条件のひとつ「本人性」を満たすためには、当事者のものであることが確認できる、電子証明書が添付された公開鍵を使用する必要があります。公開鍵を使用する場合も本人確認が必要となります。
電子契約を利用する際の電子帳簿保存法への対応
電子契約の利用が拡大する中、適切なデータ保存の重要性が高まっています。2024年1月からは電子取引データの保存が完全義務化され、紙での保存は認められなくなりました。電子契約を導入する企業は、電子帳簿保存法に基づいた確実な対応が求められます。
電子保存の要件
電子契約書を保存する際には、「可視性」と「真実性」の要件を満たさなければなりません。
- パソコンやプリンタなどの機器とその操作マニュアルを備えいつでも確認できる状態を維持する
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付ける
- ファイル名・取引年月日・取引先名や金額などで検索できること
- タイムスタンプの付与後に契約書を授受する
- 変更履歴が残る、または改ざん防止措置が施されシステムでの保管
- 契約書の授受後遅延なくタイムスタンプを付与したうえで保管を行う者、もしくは監査者に関する情報を明確にする
- 正当な理由がない訂正・削除の防止のための事務処理規程を設定し、規定に沿って運用する
真実性の確保についてはいずれかを満たせばよいとされていますが、可視性の確保については3項目をすべて満たす必要があります。
要件を満たさない場合の罰則
電子帳簿保存法違反の場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。白色申告は青色申告よりも控除が少なく、欠損金の繰り越しも不可であることに加え、「青色申告が取り消された」という事実が会社の信頼を損なうリスクも否定できません。
また、会社法976条違反となり100万円以下の過料が科せられる可能性もあります。なお、電子データの改ざんによる故意の偽装や隠蔽などが行われた場合、発覚すると通常の重加算税に10%が上乗せされるため、保存要件を確実に満たした状態でデータを保管しましょう。
国土交通省も書面の電子化を後押ししている
電子契約システムは、民間だけで推進されているわけではなく、国としても後押しをしています。建設業法を管轄している国土交通省では、電子契約をめぐる法令整備の状況や判例を調査したり、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を公開したりするなど、公共工事でも電子契約を推進できる環境を整えている状況です。
参考:国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について
要件を満たして積極的な電子契約化を
民間の建設工事や公共工事における電子契約は、2001年4月の建設業法改正により可能になりました。契約金額が大きくなりがちな建設工事では、「見読性」「原本性」「本人性」の要件を満たし、相手の承諾が必要です。グレーゾーン解消制度によって、建設業法の法解釈が明確になり、電子契約は広がりを続けています。
よくある質問
公共工事でも電子契約が可能ですか?
2001年4月の建設業法改正により、民間の建設工事だけでなく、公共工事でも電子契約が可能になりました。電子契約でも「見読性」「原本性」「本人性」の要件が満たされ、予め相手による承諾が得られている必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
グレーゾーン解消制度とは何ですか?
グレーゾーン解消制度とは、経済産業省が行っている新規事業創出の一環で、新しいサービスや制度が、既存の法律や規則に則っているかを照会できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
注文書や注文請書は電子契約にできる?電子化のメリットや保存要件も解説
注文書や注文請負書はさまざまな方法で電子化が可能です。電子帳簿保存法の改正やコロナ禍をきっかけにデジタルへの移行を試みているものの、よく分からないとお悩みの方も多いでしょう。 この記事では注文書や注文請負書、それぞれの電子契約の方法を詳しく…
詳しくみる電子化できる契約書とできない契約書一覧 – 関連する法律から紹介!
近年はさまざまな分野でデジタル社会に向けた取り組みが行われており、契約書についても電子化の流れが進んでいます。ただし、すべての契約書を電子化できるわけではなく、電子化が可能な契約書とそうでない契約書があります。 この記事では、電子化できる契…
詳しくみる産業廃棄物委託契約書は電子化できる?電子契約の注意点や電子マニフェストも解説
産業廃棄物委託契約書は、産業廃棄物の排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分などを委託する際に作成する書類です。契約の締結では契約書の作成が義務付けられていますが、電子契約にすることもできます。 本記事では、産業廃棄物委託契約書の電子化に関連する…
詳しくみる電子契約の文言は書面とどう違う?変更方法や併用の場合の例文を紹介
電子契約の普及に伴い、契約書の文言や形式にも変化が生じています。2024年の電子帳簿保存法改正など相次ぐ、法令の制定・改正を踏まえ、適切な表現や記載方法が求められる中、多くの企業が対応に苦慮しています。 本記事では、電子契約特有の文言、紙の…
詳しくみる契約書作成システムのおすすめは?トレンドと合わせて解説
契約書作成システムとは、契約書作成の支援から契約締結、管理まで、契約書関連の業務を効率化できるシステムです。導入により、契約書の保管や管理、更新手続きなどを自動化でき、大幅なコスト削減と業務改善を実現します。 本記事では、契約書作成システム…
詳しくみる契約書のバージョン管理とは?課題や効率化の方法を解説
ビジネスにおける契約書は、相手方との交渉などによりたびたび修正や変更が加えられます。更新されたバージョンの契約書も、その都度管理しておく必要があります。 この記事では、契約書のバージョン管理が必要な理由や注意点、効率的なバージョン管理方法に…
詳しくみる