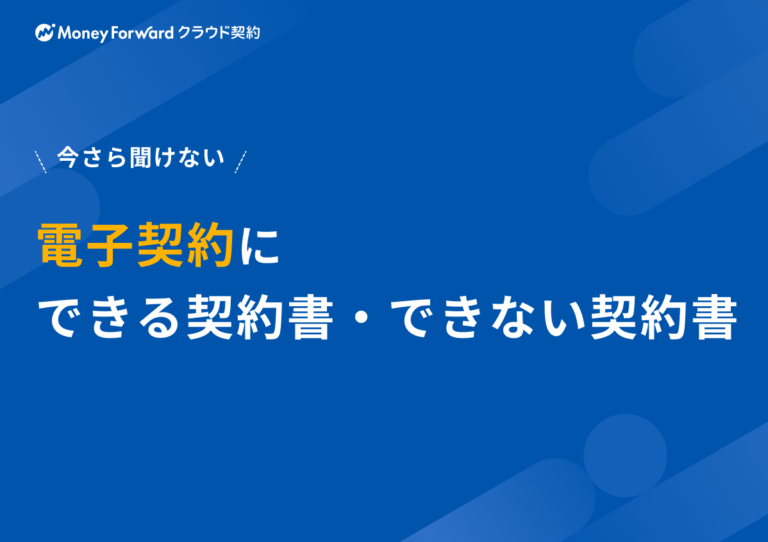- 更新日 : 2025年3月6日
電子契約の要件とは?各種法律をもとに解説
電子契約を行う場合、さまざまな法律の要件を満たす必要があります。ここでは、電子契約に関連が深い3つの法律、「電子署名法」「e-文書法」「電子帳簿保存法」からその要件を解説するとともに、電子契約の注意点を紹介します。
目次
電子契約の要件に関わる法律
ここでは、電子契約に深く関係する3つの法律で定められている、電子契約の要件について解説します。
ポイントは、契約当事者を特定できることと、改ざんされていないことを証明できること、そして検索性です。
なおそれぞれの法律には細かな技術要件や、事務処理の方法、および例外などが定められている場合がありますが、ここでは詳細な解説は割愛します。
電子署名法で定められている要件
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)は電子契約における電子署名の定義と、電子署名の推定効について定めています。
まず、電子署名法第2条1項において、電子署名の要件が定義されています。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
ここで定義されている電子署名のポイントは3つです。
- 電子署名とは、電磁的記録(電子ファイル)に施す措置
- 電磁的記録に電子署名を行ったものが、その電磁的記録を作成したことを表示する目的
- 電磁的記録に改変が行われていないことを確認できる
次に電子署名法第3条です。ここでは電子署名について、推定効がおよぶ要件について定められています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
要約すると、「電磁的記録に対して本人だけが行える電子署名を、本人によって行っていれば、真正に成立したと推定する」となります。
電子署名法で定められている要件は、この電子署名法第2章第2条と第3条です。これらをまとめると、次のようになります。
- 電子ファイルに電子署名がなされている
- 電子署名は、本人だけが行える電子署名を、電子ファイルの作成者本人が行う
- 電子ファイルが改ざんされていないことを確認できる
電子帳簿保存法で定められている要件
電子契約を行った場合、電子帳簿保存法で定められている方法に従い、契約書を電子ファイルで保存する必要があります。なお、電子帳簿保存法は、主に国税関係書類に関する書類を電子データで保存することを認め、さらのその方法について規定している法律です。
電子帳簿保存法は大きく3つの内容に分けられます。電子的に作成した帳簿、書類をそのまま保存する「電子帳簿等保存」と、紙の書類をスキャナで電子ファイル化し保存する「スキャナ保存」、そして電子的に授受した取引情報をデータで保存する「電子取引」です。ここでは、電子契約に関わる「電子帳簿等保存」と「電子取引」について解説します。
なお、それぞれに細かな技術要件や、事務処理の方法、および例外などが定められている場合がありますが、ここでは詳細な解説は割愛します。
電子帳簿における保存要件
まず、電子帳簿等保存、すなわち電子帳簿における保存要件です。保存要件は「優良」と「その他」に分けられます。優良は、さまざまな要件を満たすことで、青色申告特別控除が適用できるものです。ここでは最低限の要件である「その他」のみを解説します。要件は、以下のような内容となっています(優良の要件については説明を割愛します)。
- システム概要書/仕様書/操作説明書/事後処理マニュアルといった、システム関係書類を備え付けること
- 保管場所にパソコンやディスプレイ、プリンタなどを備え付け、速やかかつ明瞭、そして整然と内容を確認できること
- 税務署員からのダウンロード要請に応じられるようにしておくこと(優良の検索要件を満たすことで、本要件は不要となります)
電子取引における保存要件
次に電子取引の保存要件です。要件は「真実性の要件」と「可視性の要件」に分けられ、それぞれ以下のいずれかの措置を行うことが定められています。
【真実性の要件】
- タイムスタンプが付与された後に取引情報の授受を行う
- 取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付与するとともに、保管を行う者または、監督者に関する情報を確認できるようにする
- 記録事項の訂正や削除を行った場合、これらの事実/内容を確認できるシステムを利用して保存する。または、訂正や削除ができないシステムを利用して保存する。
- 正当な理由のない訂正や削除の防止に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用を行う
【可視性の要件】
- 保管場所にパソコンやディスプレイ、プリンタなどを備え付け、速やかかつ明瞭、そして整然と内容を確認できること
- システムの概要書を備え付けること
- 取引日付/取引金額/取引先で検索できること(※1)
- 日付または金額の範囲指定で検索できること(※1 ※2)
- 2つ以上の検索項目を組み合わせて検索できること(※1 ※2)
(※1)税務署員からのダウンロード要請に応じられる場合は不要(小規模事業者)
(※2)税務署員からのダウンロード要請に応じられる場合は不要(小規模事業者以外)
e-文書法で定められている要件
e-文書法は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律を総称したものです。e-文書法には契約書などの文書を電子データで保存する際のルールが定められています。
基本要件は4つあります。「見読性(読みやすさ)」「完全性(作成後に改ざんされていないこと)」「機密性(盗難や漏洩、不正アクセス等の防止)」「検索性(文書を必要に応じて探せること)」です。
e-文書法の詳細については、下記記事も参考にしてください
電子契約を用いる上での注意点
電子契約を導入する場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。ここでは電子契約化を急ぐあまり、忘れてしまいがちな2つの注意点を解説します。
契約書の種類によっては電子契約が使用できないものもある
すべての契約行為を電子契約に置き換えたいといっても、法律上認められていないものがあります。例えば現在、土地や建物の賃貸借契約(借地借家法)や、訪問販売や電話勧誘販売(特定商取引法)などでは、相手方に紙の書類を交付する義務があるため、電子契約できません。なお、2022年2月時点で電子契約が行えなくても、法改正によって電子契約が可能となるものや、法改正の準備が進んでいるもの、実証実験が行われているものもあります。そのため、将来的に電子契約が可能となる契約も増えていくと考えられます。
電子契約を用いた契約締結には、電子契約を用いることへの双方の同意が必要
契約を電子契約で行う場合には、相手の承諾を得てから進めることが大切です。もちろん電子契約にしたいからといって、相手先に電子契約を強要してはなりません。
電子契約を行う場合、先に上げたさまざまな要件を満たす必要があります。そのため、相手先はまだ電子契約の準備ができていない場合も考えられます。電子契約を行う場合には、必ず前もって相手先に同意を得て、両社で電子契約のフローなどを確認してから行いましょう。
電子契約を用いる場合は法律で定められた要件を満たしているかを確認
契約書の作成や、契約するタイミングだけでなく、契約後の電子ファイルの保存方法について、法律で要件が定められている場合があるため、注意が必要です。また、法律上電子契約ができない契約があることにも注意が必要です。電子契約はいままさに導入の過渡期と言えます。そのため、すでに電子契約の整備が進んでいるものや、将来的に電子契約が導入されるものもあります。業務でこれらに該当する契約を行っている場合は、最新情報のチェックを怠らないようにしましょう。
よくある質問
電子契約を用いる上での注意点を教えてください
電子契約を導入する際は、相手方の同意が必要です。一方的に電子契約で契約を行うことはできません。また、契約内容によっては紙の書類が必要なものもあるため、注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
電子契約に関わる法律にはどういったものがありますか?
電子署名法、電子帳簿保存法、e-文書法の3つが主にかかわります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
契約書をペーパーレス化する方法と進め方を解説
契約書を電子化すれば職場のペーパーレスが進み、保管や管理がしやすくなります。ただ法整備が進んでいる段階で移行期にある企業も多いため「全部ペーパーレスにしてもよいのか」という不安を持つ方も少なくないでしょう。 今回は契約書のペーパーレス化の方…
詳しくみる電子印鑑とは?作り方やメリット、デメリットを解説
印鑑には認印やシャチハタ、銀行印、実印などたくさんの種類がありますが、最近認知度が上がっているのが「電子印鑑」です。電子印鑑は特別なソフトがなくても無料で作成できるため、気軽に導入できます。 電子印鑑を導入すれば、わざわざ紙を出力しなくても…
詳しくみる誓約書にも電子契約を利用できる?電子化する方法やメリット・デメリットも解説
誓約書とは、当事者が遵守すべき事項を文書に記した書類です。誓約書でも電子契約の利用ができます。電子契約を利用することで、コストを削減や業務効率化が実現可能です。 本記事では、誓約書の電子化について解説します。誓約書を電子化するメリット・デメ…
詳しくみるスマートコントラクトの活用で電子契約はどう変わる?ブロックチェーンとの関係も解説
今、電子取引に関連する新しい技術として「スマートコントラクト」が注目を集めています。スマートコントラクトを活用することで、契約や取引そのもののかたちも大きく変わるかもしれません。 今回はスマートコントラクトの仕組みやメリット、これまでの電子…
詳しくみる電子契約システムの導入方法と注意点について解説
電子契約を締結する機会が増えたことに伴い、電子契約システムを導入する企業が増えています。 そこで、電子契約システムの導入を検討している事業者に向けて、導入の際の注意点や手順などを紹介します。トラブルなくスムーズに導入したい方は、ぜひ参考にし…
詳しくみる不動産仲介会社の電子契約の流れは?メリット・デメリットや注意点も解説
不動産仲介会社の電子契約は、2022年5月の宅建業法改正により全面的に解禁され、重要事項説明書から契約書まで、ほぼすべての書類を電子化できるようになりました。 この記事では、不動産仲介取引の電子契約について、導入のメリットや具体的な手順、注…
詳しくみる