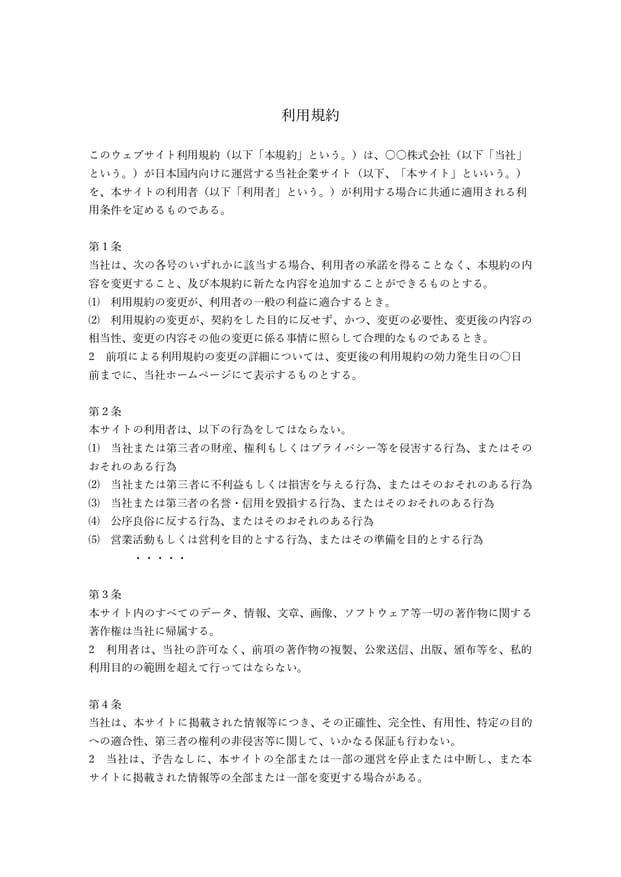- 更新日 : 2025年4月30日
利用規約とは?テンプレートをもとに作り方や例文、同意ボタンの注意点などを解説
利用規約とはサービス提供者の権利義務や、利用者がサービスを利用するにあたって遵守しなければならない内容などを定めたものです。 特にWebやアプリなどでサービスを提供する場合は、サービスの利用を開始する前に利用規約を画面に表示し、利用者に同意を求めるのが一般的です。
今回は利用規約の作成方法や利用規約が無効になるケース、利用規約の必須事項など、利用規約を作成する際の注意点について解説します。
目次
利用規約とは
利用規約とは、サービス内容に関してサービス提供者が有する権利義務や、サービス利用者がサービスを利用するにあたって遵守すべき内容をまとめたものです。利用規約の読み方は「りようきやく」、英語表記は「Terms of Use」です。
特に不特定多数の利用者に対して同一内容のサービスを提供する場合では、個別に契約書を作成し契約を締結するとサービス提供者側の事務作業が煩雑になります。内容を画一化させた利用規約であれば、サービス提供者と利用者間の契約締結がスムーズになります。
2020年4月施行の改正民法によって定型約款に関するルールが整備されたため、利用規約についても基本的に定款約款のルールに沿った運用が必要になります。
改正民法の施行前に制定された利用規約についても、定型約款に関する新たなルールが適用されることとなっているため、場合によっては改定が必要になることがあります。
ここからは利用規約はなぜ必要なのか、利用規約に強制力はあるのか、について説明します。
利用規約の必要性
法律上、サービス提供者に利用規約を作成する義務はありません。しかし利用規約を作成しなければ、サービス提供者は利用者に対して、サービス提供者・利用者間での権利義務関係や利用者に遵守してもらいたい事項について、個別に説明・交渉しなければならなくなります。
提供するサービスの具体的な内容やサービス利用方法、解約の方法、利用停止の条件などを明確にしておかないと、後でトラブルになるおそれがあるからです。これらを利用規約として明文化しておくことで、トラブルの多くは回避できます。
特に不特定多数の利用者を対象にサービスを提供する場合、利用者ごとに個別で契約交渉を行い契約を締結するのは現実的ではありません。利用規約はサービス提供者が作成するものですが、利用者にとってもサービス内容や利用方法などを知るうえで重要なものといえます。したがって、利用規約を定めておく必要性は極めて高いといえます。
利用規約を作成せず個別契約も締結しなければ、民法の規定にしたがってサービス提供者・利用者間の権利義務は処理されることになります。
利用規約の法的拘束力
利用規約は、利用者との交渉を経て作成されるものではなく、サービスを提供する側が一方的に作成するものです。
2020年4月施行の改正民法には、定型約款についての規定が追加されました。
- 不特定多数の者を相手方として行う取引
- 取引の内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものであること
この条件を満たす取引は「定型取引」と呼ばれます。定型取引において契約の内容とすることを目的にサービス提供者が準備した条項の総体は「定型約款」に該当し、サービスの利用を開始する前に利用規約を画面に表示して利用者の同意を得ることで、利用者が定型約款の個別の条項を認識していなくても、個別の条項に合意したものとみなされます(みなし合意)。
ただし、利用者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、かつ信義則に反して利用者の利益を一方的に害すると認められるものについては「不当条項」として利用者が合意をしなかったものとみなされるので、強制力はありません。例えば、利用者に予見し難い義務を加重する条項が置かれている場合は、不意打ち的な不当条項として利用者の合意があったとは認められないのです。
利用規約と契約の違い
契約とは、特定の行為に関する2当事者(またはそれ以上)間の意思表示が合致することで成立する法律行為全般を指す用語です。
利用規約は、特定のサービスを受けるにあたって利用者が提供者側から遵守を求められるものであり、利用者は規約内容に関して同意した結果、当該サービスを利用できるため、形式としては契約の一種とも考えられます。
一般的な契約は当事者間の交渉によって内容を決定するのが原則ですが、利用規約はサービス提供者がすべて作成し、利用者には同意を求めるのみである点が大きく異なります。
また、契約は当事者それぞれの権利義務を盛り込むものであるのに対し、利用規約は利用者が負う義務や提供者の免責事項に関する条項のみが記載される点も違います。
さらに、契約内容の変更には通常当事者間の同意が必要ですが、利用規約が定型約款に該当すれば、提供者側が一方的に内容を変更することができます。
利用規約と約款の違い
利用規約と約款は、ともに「事業者が不特定多数の者と同一内容の契約をする」際に用いるもので、一般的には同義語として扱われています。ただし、約款には事業者側の義務に関する条項も記載されるケースが多いなど、細かい部分が異なります。
利用規約の無料テンプレート・ひな形・例文
利用規約は法的にも重要な文章ですので、作成の際は専門家に相談すると安心でしょう。しかし、自身で作成する場合はテンプレートを活用すると効率的です。
下記より、利用規約のワード形式テンプレートを無料でダウンロードできます。テンプレートは一般的な項目を記載しているので、自身のサービスに合わせて文言を調整してください。
フリーソフトやオンラインショップの利用規約のテンプレートも用意しています。こちらも自身のサービスに合わせて文言を調整して使用してください。
利用規約の作り方・記載内容
ひな形を活用すればある程度利用規約が作成できますが、記載すべき内容はサービスによって大きく異なるため、オリジナルで作成すべき部分も多いです。
Web上で他社が公開している利用規約も閲覧できますので、類似サービスを提供している企業の利用規約も見てみると良いでしょう。具体的なサービスに即した注意点を把握できるかもしれません。ただし、同業でもサービス内容は異なるため、あくまで参考にとどめ、「サービスを通じて会社が何をしたいのか」「利用者にどのようなことを遵守してもらいたいのか」を自社で考える必要があります。
以下で、利用規約を作成する際の注意点を詳しく見ていきましょう。
利用規約への同意
定型約款に該当する利用規約の場合は、サービスを提供する前にWebやアプリ上で「利用規約を契約の内容とする」旨を記載したページを表示させましょう。
これによって、利用者が個別の条項を認識していなくても、利用者は利用規約の個別条項に合意をしたものとみなすことができ、個別条項に拘束されることになります。
しかし、利用者から「利用規約に同意していない」と主張されてトラブルになることが想定されるため、サービス利用の条件として、利用規約全文を読み内容に同意をすべきであることを定めた上で、Webやアプリ上でも利用規約に同意しなければサービスを利用できないように設計するべきです。
このような仕組みで利用者から同意を得ることで、トラブルが発生した場合でもスムーズに解決しやすくなるでしょう。
使用する用語に関する定義
利用規約で使用される用語が複数の意味に解釈できる場合は、利用規約に記載された条項についても解釈が異なるおそれがあります。用語の定義が曖昧であったためにトラブルが発生しては、利用規約を作成する意味がありません。そのため、用語の定義は必ず条項として規定しておきましょう。
サービス内容の詳細と範囲
利用規約には、必ずサービスの内容を記載する必要があります。利用者から「十分なサービスを受けられなかった」といったクレームを受けたとしても、利用規約にサービス内容やその範囲を明記し、利用規約の通りにサービスを提供していることが明らかであればクレームに対抗できるからです。
サービス内容を抽象的に規定すると、利用者が求めるサービスが提供されるサービス内容に含まれるかどうかを判断できず、クレームを受けた場合に対抗できなくなるため、できるだけ具体的に規定しましょう。
利用規約が変わる際の手続き方法
サービス内容に変更があった場合、あるいは法律が改正されたり社会情勢が変化したりしたなどの理由で、利用規約を変更しなければならないことがあります。
利用規約が変更された場合は、改めて同意を得るという方法でも構いません。利用者から同意を得ることが困難な場合、定型約款に該当する利用規約については、定型約款の変更について定める民法548条の4の要件を満たせば変更できます。
(定型約款の変更)
民法548条の4
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。引用:民法|e-Gov法令検索
料金と支払方法
有料サービスの場合は、料金と支払方法を明確に定めておく必要があります。とりわけ最近流行しているサブスクリプションの場合は定期的に支払いが発生するため、口座振替やクレジットカードによる支払いができるかどうかも定めておきましょう。
サービス利用に関する権利の帰属先
自社でサービスを提供する場合、提供サービスに関する画像などを利用者に無断で使用されるおそれもあるため、コンテンツなどに関する知的財産権が自社に帰属する旨およびコンテンツの利用者による無断使用を禁止する旨を記載しておく必要があります。
利用者参加型サービスの場合は、利用者が投稿またはアップロードしたデータの権利の帰属先を定めておく必要があります。利用者に権利を残したままサービス提供者に利用許諾を与える場合と、利用者からサービス提供者に権利を譲渡する場合があります。いずれにせよ、その内容を利用規約に定めておきましょう。
自社サービスの利用における禁止事項
サービスを悪用した詐欺などの犯罪行為をされないようにするため、利用規約に法令に違反する行為を禁止することを定めておきましょう。また、画像を盗用するなどサービス提供者や他の利用者の著作権を侵害するような行為を禁止することも定めておく必要があります。
投稿型のサービスの場合は他人を誹謗中傷する、勧誘行為をするといった、他の利用者の迷惑となる行為も禁止しておきましょう。
利用規約に違反した場合のペナルティ
利用規約を定めても、それを守ってもらえなければ意味がありません。利用規約の実効性を担保するためにも、「利用規約に違反した場合にはペナルティを科す」という内容にしておくと良いでしょう。
具体的には、「利用規約に違反した場合はサービスの提供を停止する(強制退会)」という措置が考えられます。ただし、場合によっては一方的に強制退会させるのではなく、まずは利用規約に違反していることを利用者に通知することをおすすめします。
利用者が、利用規約に違反していることに気づいていないケースもあるからです。通知しても利用者が違反を是正しなかったり、違反行為を繰り返したりする場合は、強制退会などの措置を取ると良いでしょう。
サービス提供の停止や終了について
サービスの提供を事業として行っている以上、採算が取れなくなった場合はサービスの提供を停止、または終了せざるを得ません。そのような場合を想定して、利用規約にはサービスの提供を停止または終了する場合がある旨を定めておくとよいでしょう。
サービスの提供を停止または終了する場合は、例えば「2ヶ月以上前に通知する」などと規定した上で、誠意ある対応を行うことをおすすめします。予告なく一方的にサービスを停止・終了すると利用者に不利益をもたらし、トラブルにつながる恐れがあるからです。
損害賠償について
一般消費者を対象とした利用規約に、「サービス提供者の損害賠償責任をすべて免責する」といった、利用者が一方的に不利となる条項を入れると無効となります(消費者契約法8条1項1号、3号ほか参照)。社会常識と照らし合わせた上で一定程度の責任を認め、賠償に応じられるような内容にしておいたほうがよいでしょう。
合意管轄裁判所
合意管轄裁判所には法律上さまざまなルールがありますが、利用規約で合意管轄管轄裁判所を決めておくことができます。利用規約はサービス提供者が作成するため、サービス提供者の本店所在地を専属的合意管轄裁判所として規定するのが一般的です。例えば東京に本社がある会社の場合は、合意管轄裁判所を「東京地方裁判所」に定めるということです。
個人情報の取り扱い
利用規約には個人情報の取り扱いに関しても必ず記載しておきましょう。個人情報の取得方法や利用目的、扱い方、第三者への提供に関して定めます。原則として個人情報の取り扱いは個人情報保護法に従って規定・運用する必要があります。
反社会的勢力の排除
サービス提供者、サービス利用者が暴力団や総会屋などの反社会勢力の構成員もしくは関係者でないこと、あるいは相手方に暴力的な要求行為など反社会的な行為をしないことを確約するための条項です。
サービス提供者自身はもちろん、利用者側も反社会的勢力でないことを明らかにしておくことが大切です。仮に反社会的勢力にサービスを提供した場合、提供者側も利益供与を行ったということで法的あるいは社会的な制裁を受けるリスクがあります。
著作権の帰属と利用範囲
サービスに使われている文章、画像、動画、デザインなどの著作権と利用範囲についても定めておきましょう。提供するコンテンツを個人で利用できるのか、商用利用できるのか、どのような条件を満たせば商用利用も認めるのかを明らかにします。
利用規約を作成するときの注意点
利用規約を作成する際に最も注意すべきポイントは、規約に法的拘束力を持たせる内容にすることです。民法や消費者契約法など、自社のサービスが関連する法令をすべて読み込み、無効な条項を入れてしまわないように気をつけましょう。無効とされるのは規約の該当条項のみですが、そのような規約を作成したことは事業者にとって大きなイメージダウンにつながります。
特にWebサイトに表示し、利用者に同意を求める形式の利用規約は誰でもが見ることができるため、しばしばその内容がいわゆる「炎上」の種になります。一方的に押し付けるのでなく、利用者の立場も考えた規約になるよう心がけましょう。
また、Webやアプリでのサービス提供における利用規約には、著作権の帰属についての条項を入れておくことをおすすめします。
利用規約の同意画面や同意ボタンを作成するときの注意点
Webサイトなどの利用規約は、インターネット上で同意画面や同意ボタンを作成する方法が一般的です。作成にあたっては以下の点に注意する必要があります。
読みやすい文字の大きさやフォントを使用する
利用規約の同意画面は、読みやすい文字の大きさやフォントで作成するようにしましょう。Webサイトやシステムなどは、スマートフォンなどで利用する場面も考えられるため、モバイル端末で表示した際にも読みやすくしておくことが重要です。
利用規約全文スクロールした後に同意ボタンを表示させる
利用規約は全文を表示し、画面のスクロールなどによりユーザーがすべての条項を確認できるようにしましょう。
また、同意ボタンは規約の画面をすべてスクロールした後でないと押せないような設計にすると良いでしょう。
このような設計にすることで、ユーザーに利用規約の内容を認識させることができ、利用規約に同意したことを明らかにできます。
「同意します」などのチェックボックスを設ける
利用規約への同意について、「同意します」などといったチェックボックスを設けることがあります。チェックボックスにチェックを入れる方法は、ユーザーが同意したという事実を明らかにできるため有効です。
ただし、これは必ずしも必要なものではなく、別の方法で利用者の同意を取ることもできます。例としては、利用規約を掲載したページのリンクを貼るなどの方法があります。チェックボックスを設置するか、その他の方法を取るかは必要に応じて判断しましょう。
「同意したものとみなす」は注意が必要
利用規約の文言に「このサービスを利用する場合は、利用規約に同意したものとみなします」などの表現を用いることがありますが、これらの表現はトラブルになる恐れがあるため、避けたほうが良いでしょう。
2020年4月に施行された改正民法では、「みなし同意」というルールが設けられました。定型約款の要件を満たさない場合は同意をしていないなどのトラブルになることもあるため、注意が必要です。
利用規約の内容に相手が同意しないとどうなる?
ユーザーから利用規約に対して同意が得られなかった場合は、次のようなトラブルが生じることが考えられます。
サービスを二次利用される恐れがある
利用規約には提供するサービスについての二次利用の項目についての規制を設けることがあります。しかし、二次利用の規制について同意が得られていない場合、事業者の提供するサービスを無断で利用されてしまうことがあります。
自社で提供するサービスを無断で二次利用されると、商品やコンテンツの価値が失われる恐れがあるため、注意が必要です。
悪質な投稿などを削除できない
SNSや口コミサイトなど、ユーザーからの投稿をもとにサービスを運営する場合は、悪意のある投稿や誹謗中傷などの書き込みを削除できなくなることがあります。このようなトラブルが生じると、サービスを提供する側には大きなデメリットとなり、事業者の信頼を失うほか新規顧客の獲得に大きく影響を与えることが考えられます。
サービス提供の終了や利用料金の改定が難しくなる
サービスを運営していく中で何らかの事情により、それまで提供してきたサービスの終了や利用料金の改定を行うことが考えられます。このような場面で利用規約に同意がないと、ユーザー側からサービスの終了や利用料金の改定に納得が得られず、トラブルに発展する恐れがあります。
利用規約が無効になる場合はある?
利用規約はサービス提供者が作成するものなので、どうしても自社にとって有利な内容になりがちです。
しかし、利用者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、かつ信義則に反して利用者の利益を一方的に害すると認められるものについては「不当条項」として、利用者が合意をしなかったものとみなされる可能性があります。
また、利用者の利益を不当に害する条項は、消費者契約法で無効とされる可能性もあります。
利用者の利益を不当に害する契約条項とは、先述のサービス提供者の損害賠償責任をすべて免責する条項や、利用者に高額なキャンセル料を課す条項、利用者の解除権を放棄させる条項などです。これらは利用者の利益を侵害しているとみなされるため、無効となります。
利用規約の必須項目を押さえておきましょう
今回は利用規約の概要や、利用規約を作成する場合の留意点などについて解説しました。最近はWebやアプリでさまざまなサービスが提供されるようになり、それに伴って利用規約の内容も多岐にわたるようになりました。
利用規約はサービスの内容に即して作成する必要があるため、利用規約を作成する際は基本的な留意点をおさえたうえで、提供するサービスに合った内容にしなければなりません。
この記事で紹介した利用規約の概要と留意点を参考に、サービスに応じた内容を加味して利用規約を作成してください。ただし、定型約款に該当する利用規約において、利用者の同意を得ずに利用規約を変更したい場合は、民法548条の4に定める内容の変更しかできないため、必要に応じて弁護士など専門家の意見を聞きながら利用規約を作成することをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
注文請書とは?注文書となにが違う?
商取引を行う際に、注文を受けた側が「注文請書」を発行することがあります。取引先から「注文請書を発行してください」と言われたものの、作成方法がわからず戸惑う人は少なくありません。 今回は、注文請書の概要や記載すべき内容、作成時の注意点、注文書…
詳しくみる定款を変更する際の書き方のポイントや手順を解説
創業当初定めた定款の内容に変更が生じることもあるでしょう。事業範囲が広がったり社名が変わったり、様々なケースが考えられます。株主総会での承認を経て変更ができるところ、実務上は株主総会議事録の作成も行わなければなりません。 定款変更があったと…
詳しくみる法令遵守とは? 意味やコンプライアンスとの違いを簡単にわかりやすく解説
法令遵守とは、法律や省令・規則、条例などをしっかりと守ることです。企業において、法律や規制などの法令遵守は、社会的信頼の構築につながり、企業の持続的な成長に不可欠といえます。 本記事では、法令遵守の意味やコンプライアンスとの違いをわかりやす…
詳しくみる二重価格表示とは?8週間ルールや不当表示の事例を解説
二重価格表示とは、販売価格のほかに通常価格を記載する表示方法です。二重価格表示自体は問題ありませんが、表示方法によっては消費者に誤認を与え、景品表示法に違反する不当表示にあたる場合もあります。 本記事では、二重価格表示の概要や景品表示法によ…
詳しくみる商標登録とは?メリットや出願のやり方、区分、費用、有効期間などを解説
商標登録は、自社の商標(マークやロゴなど)について独占権を得る手続です。特許庁に申請をして商標登録を行うことにより、他社からの模倣や不正使用を防ぎ、企業のブランド力を強化できます。 今回は、商標登録の概要や区分を説明した上で、登録をするメリ…
詳しくみる契約更新とは?雇用契約・賃貸契約・業務委託契約の更新手続きや注意点などを解説
契約更新とは、契約期間が満了した後に契約期間を延長することです。 賃貸契約、雇用契約、業務委託契約など、あらゆる契約で契約更新の手続きが行われます。 ただし、契約によって更新の方法が異なる場合があるため、契約更新を行う際は注意が必要です。 …
詳しくみる