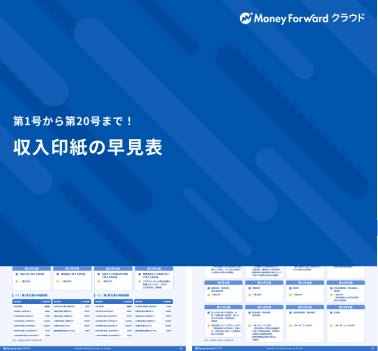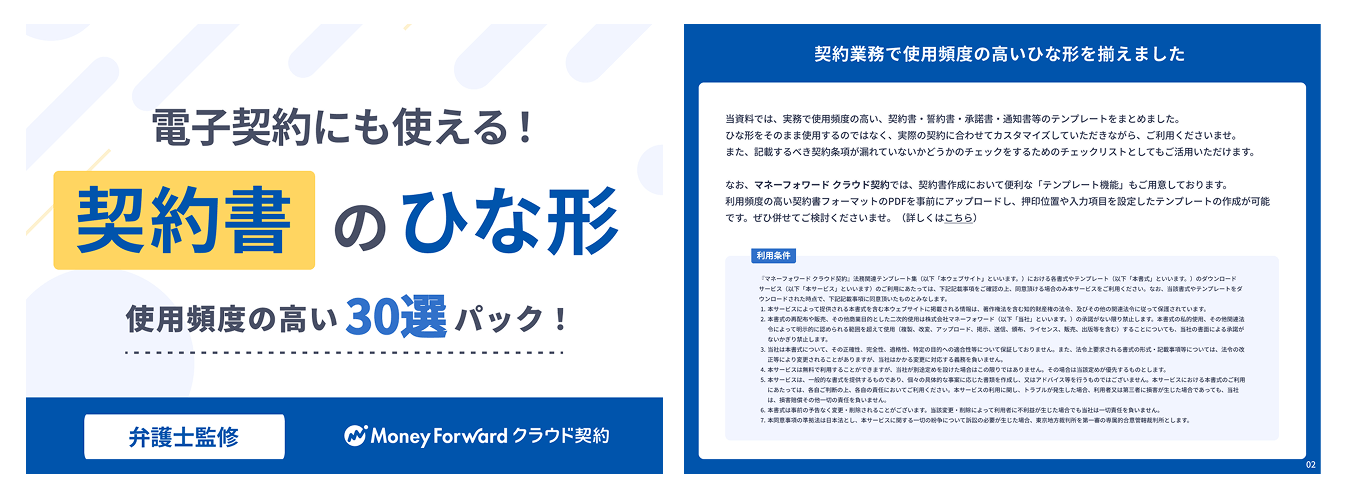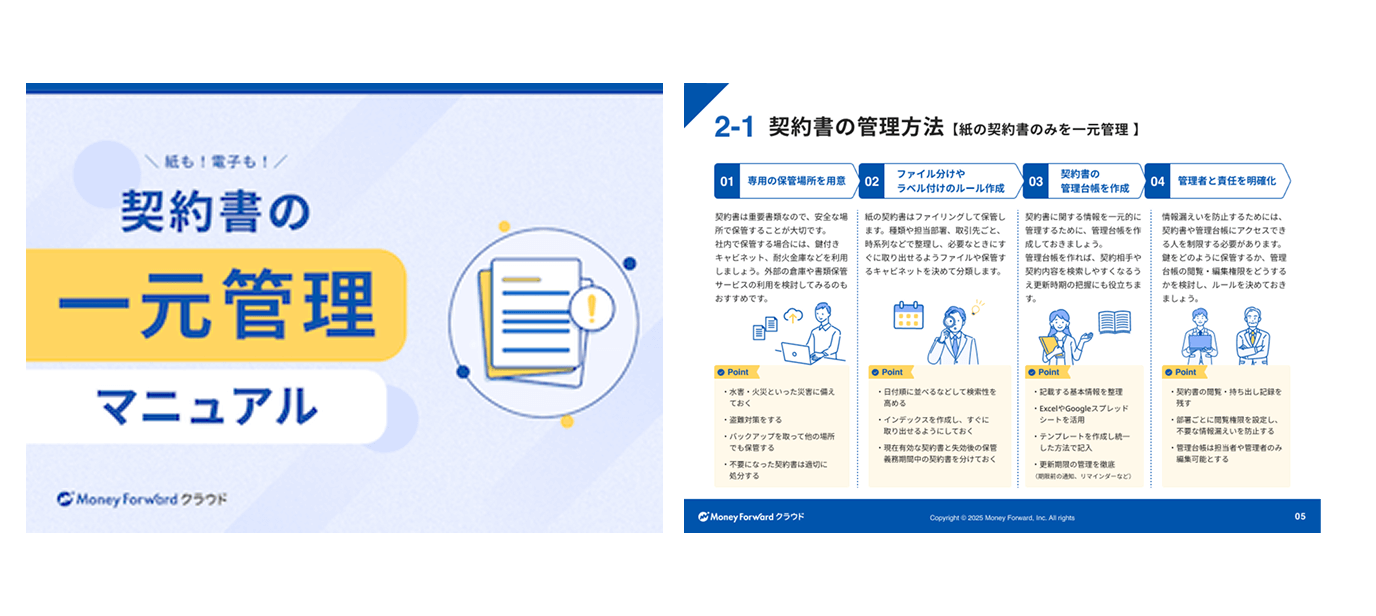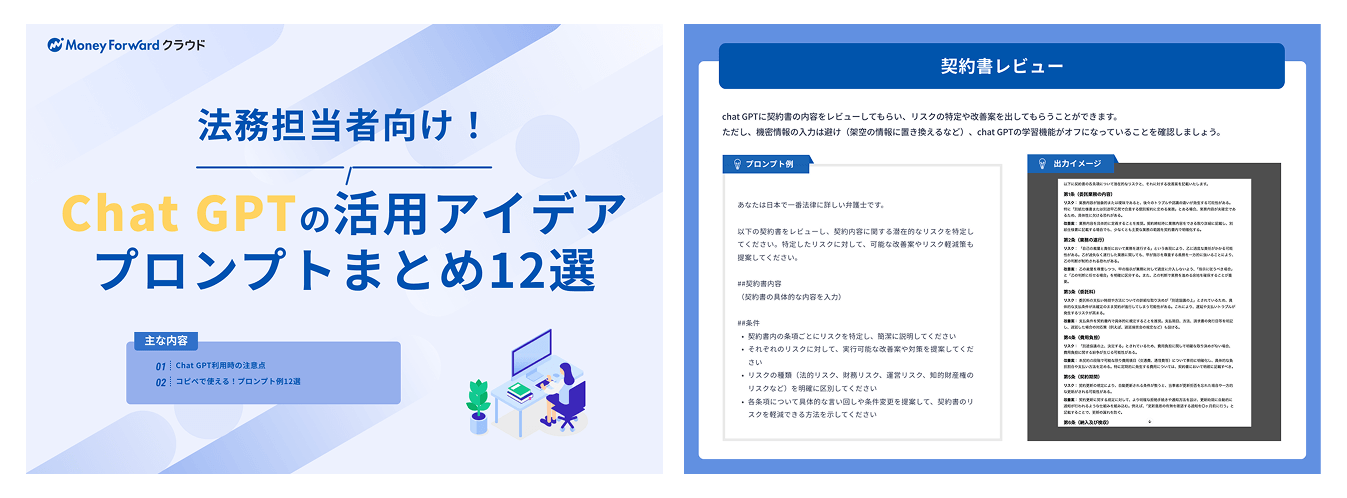- 更新日 : 2025年12月30日
収入印紙とは?なんのために必要?種類や金額、貼り方などをわかりやすく解説
収入印紙は、印紙税を納めるために使用する証票です。
使う機会が限られているため、なんのために使用するのかを知らない方もいるかもしれません。
この記事では、収入印紙の金額表や似た証票の種類、収入印紙が不要な場面や、誰が払うのか、どこで買えるかなどをわかりやすく解説します。さらに、収入印紙が時代遅れといわれる理由や、納付を忘れた時の罰則についても触れていきます。
目次
収入印紙とは
収入印紙は、契約書や領収書などの課税文書を作成する際に必要な印紙税を納付するための証票です。課税文書とは、印紙税法により印紙税の課税対象となることが定められた文書で、作成する際に収入印紙によって印紙税を納める必要があります。課税文書に、決められた金額の収入印紙を貼付・消印をすることで印紙税の納付が完了します。
収入印紙は誰が払う?
収入印紙は、課税文書を作成する当事者が負担するのが原則です。「作成」とは、単に文書を作成した時ではなく、文書に記載した課税事項を、文書の目的に従って行使することをいいます。そのため、「作成する時」のタイミングは文書の目的となる内容によってさまざまです。
当事者である作成者が2人以上いる場合には、連帯して納付の義務を負い、契約の当事者同士で負担割合を決めることができます。一般的に契約書は2通作成し、お互いが1通ずつ保管するため、双方がそれぞれに貼り付ける印紙代を負担するケースが多いです。領収書の場合は発行者側が作成者となるため、発行者が印紙税を負担する義務があります。
収入印紙はなんのために必要?
収入印紙は、国が特定の文書に課税する印紙税を納付するために必要な証票です。金銭的な取引などで発生する文書に収入印紙を貼って印紙税を納めることで、国に対して納税の事実を証明できます。
印紙税は、単に書類を作成した事実に対して課税されるのではありません。その背後にある経済的な利益や、書類による当事者間の法的なつながりの強化といった点に着目して制定された税金です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ30選
業務委託契約書など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド
電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。
社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。
紙も!電子も!契約書の一元管理マニュアル
本ガイドでは、契約書を一元管理する方法を、①紙の契約書のみ、②電子契約のみ、③紙・電子の両方の3つのパターンに分けて解説しています。
これから契約書管理の体制を構築する方だけでなく、既存の管理体制の整備を考えている方にもおすすめの資料です。
自社の利益を守るための16項目!契約書レビューのチェックポイント
法務担当者や経営者が契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
弁護士監修で安心してご利用いただけます。
法務担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ
法務担当者がchat GPTで使えるプロンプトのアイデアをまとめた資料を無料で提供しています。
chat GPT以外の生成AIでも活用できるので、普段利用する生成AIに入力してご活用ください。
収入印紙が時代遅れといわれる理由
収入印紙は明治時代に導入された徴税方法です。しかし、書面による文書作成を前提とした仕組みであり、ペーパーレス化が進んだ現代には適合していないという声も挙がっています。
ここからは、収入印紙が時代遅れといわれる理由について説明します。
ペーパーレス化に対応していないため
収入印紙は、物理的な紙の証票であるため、作業の電子化や書類のペーパーレス化が進む今の時代にはあまりそぐわない制度となっています。オンラインだけで書類のやり取りが完結することも多い現代において、紙の収入印紙の利用は合理的ではないと感じる方が多いのが実情です。
印紙の購入・保管・貼付・消印といった一連の作業は手間がかかるだけでなく、金額や作業のミスを起こすリスクも伴います。さらに、テレワークが普及する中、在宅で働く社員が収入印紙を扱うことの難しさも問題視されています。
電子契約なら収入印紙が不要となるため
現行の印紙税法では、電磁的データで作成・保存される契約書は「文書の作成」が行われないため、印紙税が課されない扱いになっています。つまり、契約内容や契約者が同じであっても、紙の契約書を作成すれば収入印紙が必要、電子契約の場合には不要という不均衡が生じているのです。
このように、現代における契約電子化の流れと合致しない制度であることも、収入印紙の使用が時代遅れといわれる一因と考えられます。
収入印紙の種類
一般的な収入印紙の他に、債権の手数料や税金を納付するために使用する類似の証票がいくつか存在します。収入印紙との違いを理解して、誤った使用をしないよう注意しましょう。
一般的な収入印紙
一般的に印紙という言葉で日常的に使用されるものが収入印紙です。
収入印紙は、不動産売買契約書や一定金額以上となる売買の領収書といった課税文書に貼付することで印紙税を納付する証票です。収入印紙の額面は、1円から10万円までの31種類で、課税文書の種類や記載金額に応じて必要な金額が異なります。課税文書に必要な金額の印紙を貼付して消印をすることにより、納付の効力が生じます。
電子記録債権用収入印紙
電子記録債権とは、手形や売掛債権に代わる制度として作られた、電子化された金銭債権です。電子記録債権は電磁的なデータによるものであるため、印紙税は課されません。
電子記録債権システムを利用する際に債権金額の他に支払いが発生することがありますが、これはシステムへの手数料であり、印紙税ではありません。そのため、電子記録債権用の収入印紙は用意されていないのです。
収入証紙
収入証紙は、地方自治体が徴収する各種手数料や税金を納付するための証票です。名称が似ているため収入印紙と混同されることが多いですが、支払いの相手先が地方公共団体の時に使用する証票であり、国に納める印紙税の納付に使用することはできません。
収入証紙は、取り扱いをしていない自治体もあり、東京都では平成22年3月31日をもって廃止となっています。
収入印紙が必要となる印紙税の課税文書
収入印紙は、印紙税法で定められた20種類の課税文書を作成した場合に必要となる証票です。ここからは、代表的な課税文書の具体例を説明していきます。
契約書
契約書は、最も一般的な課税文書です。すべての契約書が課税対象となるわけではなく、以下のような契約書が該当となります。
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 消費貸借契約書
- 請負契約書
- 業務委託契約書
契約の種類や記載されている金額により印紙税の納付額が異なり、基本的に記載金額が大きくなるほど印紙税も高くなります。
5万円以上の領収書・レシート
売買の時に発行する領収書やレシートで、記載金額が5万円以上のものには収入印紙が必要となります。ただし、電子で作成・送付・保存するものは、課税文書の作成に該当しないため印紙税が非課税です。
また、クレジットカードを利用した際の控えは、その場で金銭の授受がされているわけではないため、領収書という名称であっても収入印紙は不要です。
10万円以上の約束手形・為替手形
約束手形や為替手形は、記載金額が10万円以上の場合に収入印紙が必要です。収入印紙の金額は、記載金額に応じて異なります。手形の収入印紙は、原則として手形の振出人が購入して貼付する必要があります。しかし、作成時に金額が記入されていない手形や振出人の名前が記載されていない手形などは、振出人以外が作成者として印紙税を納付する場合もあります。
会社設立時の定款
株式会社や合同会社などを設立する際に作成する定款は、印紙税の課税文書であり、収入印紙の貼付が必要です。ただし、最近は電子定款による設立も可能となっており、電子定款で設立をする場合には、印紙税が課税されないため収入印紙は不要となります。
株式発行時の株券
会社が発行する株券も印紙税の課税文書であり、金額に応じて収入印紙の貼付が必要となります。ただし、現在は株券が電子化され、紙の株券が廃止されているため、株券に対する印紙税の課税機会はほとんど発生しません。
収入印紙の金額表
必要となる収入印紙の金額は、課税文書の種類や記載されている金額により異なります。ここからは、代表的な課税文書である「契約書」と「領収書」に必要な収入印紙の金額表を見ていきましょう。
契約書に貼る収入印紙の金額表
印紙税の課税対象となる契約書に対する印紙税について、次の3つの分類を例に挙げて説明します。
不動産売買契約書/土地賃貸借契約書/消費貸借契約書など
| 領収書の記載金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え 50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1千円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※不動産の譲渡に関する契約書は、令和9年3月31日まで印紙税の軽減措置があります。
請負契約書
| 領収書の記載金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 6万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
※「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日から令和9年1月31日までの間に作成されるものは、軽減措置があります。
業務委託契約書
業務委託契約書で必要な収入印紙は、記載された金額にかかわらず一律で4,000円です。ただし、契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのない契約書については、業務委託契約書ではなく、他の課税文書に該当する可能性があります。国税庁の「印紙税の手引」を参考に、どの課税文書に該当するかを確認してください。
領収書に貼る収入印紙の金額表
領収書に貼付する収入印紙の金額は、領収書に記載された受取金額に応じて決まります。
主な領収書の印紙税額は以下のとおりです。
| 領収書の記載金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
収入印紙はどこで買える?
収入印紙を購入できる場所はいくつかありますが、場所によって取り扱う印紙に制限があるケースもあります。ここでは、収入印紙がどこで買えるのか、主な購入場所と取り扱われている収入印紙の種類について解説します。
郵便局
郵便局は収入印紙を購入できる最も一般的な場所です。郵便局では豊富な種類の収入印紙を取り扱っています。店舗によっては大きい額面の印紙を取り扱っていない場合もあるため、購入する際は事前に確認をしておくと安心です。
郵便局は全国に店舗が多数あり、一部では土日も営業しているところがあるため、収入印紙が急に必要になった時にも利用しやすい、便利な購入場所といえます。
法務局
法務局では、基本的に全31種類すべての収入印紙を取り扱っています。そのため、不動産登記や法人設立などの際に必要な大きい額面の収入印紙も購入可能です。さらに、登記申請は法務局で行うため、印紙の購入と申請を同時にできる利点もあります。
ただし、法務局は平日の日中のみの営業となるため、購入できる時間が限られている点に注意が必要です。また、一部の支局や出張所では、収入印紙を取り扱っていない場合や、一部金額の収入印紙の取り扱いがない場合もあります。
役所(基本的に取り扱いなし)
区役所・市役所などでは、基本的に収入印紙の取り扱いはしていません。役所で主に販売されているのは地方自治体への税金や手数料を支払う際に使用する「収入証紙」です。収入証紙は、収入印紙と違って国税である印紙税の納付に使用することはできません。
一部の役所では収入印紙を販売している場合もありますが、取り扱う種類が限られているため、郵便局や法務局など他の場所での購入をおすすめします。
コンビニ
コンビニエンスストアでも、収入印紙を購入できる店舗が多く存在します。しかし、コンビニで購入できるのは、基本的に額面が少額の収入印紙のみです。
コンビニでは年中無休で手軽に購入できるというメリットがありますが、必要な金額の印紙が手に入らないかもしれません。確実に購入したい時は郵便局の大きな店舗や法務局に行くことが望ましいです。
収入印紙の貼り方
収入印紙は、課税文書に貼り付けて消印をすることにより印紙税を納付します。ここからは、収入印紙の貼り方と消印について解説します。
収入印紙を貼る位置
収入印紙を貼る位置は、法律の定めはありません。ただし、文書の内容が隠れないように、文字や図柄などを避けた場所に貼付する必要があります。
契約書であれば右上か左上、領収書の場合は空いているところに貼り付けるのが一般的です。 複数枚の印紙を貼る場合は、上下左右に並べて貼ることで見栄えがよくなります。
消印の押し方
収入印紙の消印は、印紙の再利用を防ぎ、納税済みであることを証明するための行為です。
消印は、文書の作成者のほか、代理人や使用人が印章または署名によって行います。複数人で作成した文書の場合は、1名の消印があれば有効となります。ただし、「印」と記載したり、斜線を引くだけでは印章または署名にあたらないため無効です。また、通常の方法では消せないようにする必要があるため、鉛筆書きの署名も認められません。
収入印紙を貼り忘れた場合の罰則
収入印紙を貼付や消印を忘れた場合は、印紙税法に基づき過怠税が課されます。
印紙を貼り忘れた場合、自主的に未納税を申告した場合は本来支払うべき印紙税額の1.1倍の納付が必要です。税務調査などにより指摘を受けた場合は、通常分の印紙税に2倍の額を加えた、本来の3倍の納付が必要になります。
消印がされていない収入印紙についても、貼り忘れと同様に過怠税が発生します。消印がされていない場合は、収入印紙の額面に相当する過怠税を支払わなければなりません。
ただし、収入印紙の貼り忘れがあっても、契約書などの法的効力自体には影響しません。あくまでも、税法上の問題として過怠税が発生する点に注意しましょう。
印紙税を貼付・消印して納付することは、課税文書作成者の義務です。貼り漏れや消印漏れのないように必ず確認しましょう。
収入印紙の現状と電子化のメリット
収入印紙は歴史のある納税の仕組みです。しかし、近年において普及した電子契約や電子領収書では印紙税が基本的に不要となるため、同じ内容の文書であっても、作成方法によって取り扱いに差が生じている現状があります。
さらに、印紙の購入・管理・貼付・消印といった一連の作業には、多くの手間とコストがかかっています。ここで企業が契約書や領収書を電子化すると、印紙税コストの削減はもちろん、保管スペースの削減や契約締結スピードの向上など、さまざまなメリットを享受できる可能性があります。このように、収入印紙の仕組みと電子化によるメリットなどを理解した上で、最適な方法を選択していくことが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
印紙が必要な契約書の種類と金額まとめ #2
契約書をはじめ、一部の文書には印紙税が課されるため、収入印紙を貼りつけ、消印しなくてはなりません。ただし、収入印紙による印紙税の納付は、必ずしも印紙税の範囲に含まれる文書に必要なわけでもありません。 同じ契約書、あるいは領収書であっても、収…
詳しくみる請負契約は印紙税・収入印紙が必要?建設工事請負契約書の軽減措置も解説
請負契約書は、印紙税の課税文書として印紙の貼付が必要です。印紙の金額は、数百円から数十万円の範囲で請負金額ごとに異なります。 この記事では、建設工事請負契約書に貼付する印紙の金額や貼付方法、印紙税の軽減措置、印紙が不要になる場合について具体…
詳しくみる譲渡契約書に印紙は必要?金額や印紙の入手方法を解説
物・権利・事業などを譲渡する譲渡契約書には、収入印紙を貼るケースがあります。印紙税法の規定を正しく理解したうえで、規定額の収入印紙を確実に貼付しましょう。印紙税を節約したい場合は、電子契約の導入をご検討ください。 本記事では、譲渡契約書に収…
詳しくみる契約書コピーの効力は?契約書の「収入印紙代」を簡単に節約できる3つの方法
「この契約書にはこの金額の収入印紙」普段、何気なく契約書に決まった額の収入印紙を貼っていませんか? 契約金額が高額であったり、同一の契約書を大量に作成したりする場合、収入印紙の額は馬鹿になりません。しかし、これらの収入印紙はちょっとした工夫…
詳しくみる工事請負契約書の収入印紙の金額はいくら?軽減措置や不要なケースも解説
工事請負契約書の収入印紙について「この金額で合っている?」「軽減措置はいつまで?」といった疑問はありませんか?本記事では、2025年の印紙税額一覧表を冒頭で分かりやすく解説。さらに、印紙が不要になる3つの例外ケースからペナルティ、実務で役立…
詳しくみる収入印紙に消印は必要?適切な押し方や印鑑の種類を解説
契約書や領収書などの文書は、印紙税法の規定に従い印紙税の課税対象になることがあります。書類に印紙を貼る場合、収入印紙を貼付した上で消印を押さなければなりません。どのように消印を行うのか、適切な押し方や使用できる印鑑の種類など、契約書作成に関…
詳しくみる