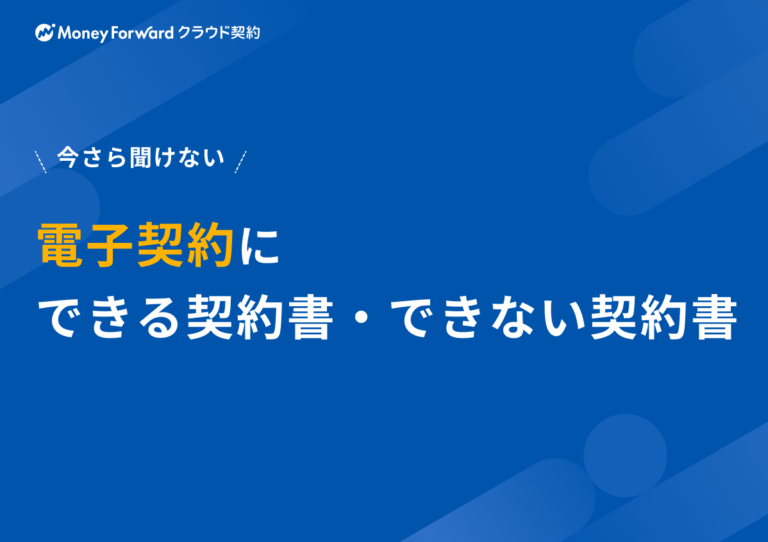- 更新日 : 2026年1月13日
【2026年最新】不動産取引の電子契約の流れは?デメリットも解説
2021年に可決したいわゆる「デジタル改革関連法」により、不動産取引の多くを電子契約化することが可能になり、2026年現在不動産取引における電子契約化は急速に進んでいます。しかし、電子契約化のためには、満たさなければならない法律の定めなどがあるうえ、紙の契約にはない特有のリスクも無視できません。
本記事では、不動産取引の電子契約化に関する法律や実際の流れを解説します。
目次
不動産取引の電子契約化はいつから?
従来、不動産契約の際には書面での契約締結が定められている書類があり、完全に電子化することは難しいと言われていました。
しかし、前述の通り2021年5月に可決したデジタル改革関連法により、それらの契約書も電子化が可能となり、不動産取引における契約書の全面電子化が2022年5月に解禁されました。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド
下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。
本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。
2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。
弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書
弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。
契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。
自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント
契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。
そもそも電子契約とは?
電子契約とは、文字通り、契約の取り交わしを電子媒体で行うことです。
前提として、契約行為は口頭のみでも成立することが可能です。しかし口約束だけでは、後になってから「言った言わない」の問題が発生する可能性が高くなります。そこで、お互いに同意した内容について明確にし記録するため、契約書を作成して署名・捺印を行います。この契約書によって、契約の当事者たちがそれぞれ同意したことを証明できるようになります。
この場合、契約書に捺印や署名がなければ、その後もし内容をめぐって争うことがあったとしても、その契約の内容は信憑性に欠けます。また、場合によっては捺印などのない書類は、後になって悪意を持って改竄することが可能です。契約書における署名・捺印はとても重要な要素だといえます。
一方で、電子契約では、紙の契約書のように物理的に捺印したり、署名したりできません。つまり、紙の契約書とは別の方法で、お互いに同意したことや改竄がなかったことについて証明をしなければなりません。そこで必要になってくるのが、電子署名の技術です。電子署名がなされた契約書は、作成者を証明することができるため、紙の契約書と同じ効力を持ちます。
電子契約について、詳しくは下記記事で解説しています。
不動産取引の電子化に関連する法律
2021年5月19日に公布されたデジタル改革関連法は、2021年9月1日に施行され、社会全体のデジタル化推進の基盤となりました。この法律に基づき、宅建業法および借地借家法の改正が行われ、2022年5月18日から不動産取引における電子契約が可能になった、という経緯があります。
宅地建物取引業法の改正
改正宅建業法により、これまで紙の書面のみとされていた以下の重要書類の電子化が可能になりました。
- 媒介契約書(第34条の2)
- 重要事項説明書(第35条)
- 売買・賃貸借契約書(第37条)
借地借家法の改正
また、借地借家法の改正により、一般定期借地契約の特約や定期建物賃貸借契約についても、電子契約が可能になりました。しかし、事業用定期借地権に関しては引き続き公正証書による締結が求められます。さらに、定期建物賃貸借契約における説明書面は、賃借人の同意を得ることで、電磁的方法(例:電子メールやオンラインプラットフォーム)で提供できるようになりました。
これらの改正により、不動産取引のデジタル化が急速に進んでいます。
電子契約できる主な不動産取引
前述の通り、「デジタル改革関連法」の成立により不動産取引においても契約の電子化が認められるようになりましたが、具体的には次の書類の電子化が認められるようになりました。
①媒介契約書
媒介契約書とは、不動産の売買や賃貸の仲介を不動産会社に依頼する際に作成する契約書です。宅地建物取引業法第34条の2により作成・交付が義務付けられており、売主(貸主)と不動産会社の権利義務関係、報酬、有効期間などを明確にします。
媒介契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいて作成され、消費者保護の観点から重要な役割を果たしています。
媒介契約には、以下の3つの種類があります。
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
- 一般媒介契約
専任媒介契約
専任媒介契約では、売主(貸主)が指定した1社のみが仲介を行います。この契約では、売主(貸主)は他の不動産業者と契約できませんが、契約期間内に自ら取引(自己発見取引)が可能です。
なお、専任媒介契約では物件情報を契約締結日から7日以内にレインズ(指定流通機構)に登録することが義務付けられています。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は専任媒介契約に似ていますが、自己発見取引はできません。取引が成立するまで、依頼者は指定された1社にのみ依頼することが求められます。
また、さらに、物件情報のレインズへの登録期限は5日以内とされており、迅速な情報共有が必要です。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業者に仲介を依頼できる契約です。この契約では依頼者は自由に業者を選び、複数の業者と同時に契約を結べます。物件情報をレインズに登録する義務はありませんが、必要に応じて任意登録が可能です。
②重要事項説明書
重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条に基づき、不動産取引で取引対象の不動産に関する重要な情報を買主(借主)に説明・提供するための法定書面です。宅地建物取引士が記名押印し、説明を行うことが義務付けられています。
ITを活用した重要事項説明(IT重説)は、賃貸取引では2017年10月から、売買取引では2021年3月からと、書面の電子化に先駆けて本格運用が開始されています。
重要事項説明書の電子化について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
③賃貸借契約書
賃貸借契約書は、不動産の賃貸借において、賃貸人(貸主)と賃借人(借主)の間での契約締結を確認する書類です。宅地建物取引業法第37条により、宅建業者が媒介・代理を行う場合には、契約が成立するまでに契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられています。
④定期借地権設定契約書
定期借地権設定契約書は、期限付きの借地権(定期借地権)を設定する際に締結する契約書です。借地借家法に基づき、土地の利用条件や賃料、契約期間(更新なし)などを明確に定めます。
定期借地権設定契約書は、以下の3種類に分けられます。
- 一般定期借地権設定契約書:50年以上の契約期間を定めたもの
- 事業用定期借地権設定契約書:10年以上50年未満で事業用建物を目的とするもの
- 建物譲渡特約付借地権設定契約書:契約終了時に建物を貸主が買い取る条件付きのもの
定期借地権設定契約書について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
なお、不動産取引において電子契約を締結する際には、相手方の同意が必要です。そのため、物件の所有者などがPCの操作などに慣れていない場合などに備えて、引き続き紙の契約書でも契約を締結できるように備えておきましょう。
マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修の契約書テンプレートを用意しています。無料で利用可能ですので、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
電子化できない不動産取引
前述の通り、不動産契約の多くは電子化できますが、一部の契約については例外となります。
例えば、事業用定期借地に関する契約については、契約書を公正証書で作成することが求められています。そのため、依然として電子化はできない契約です。その理由は、事業用定期借地権の制度が、脱法行為として利用されることを防ぐためです。
なお公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書をさします。公証人により作成されることにより、文書の成立について真正であることの強い推定(形式的証明力)が働きます。
そのほかにも「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約」および「任意後見契約書」についても、公正証書による契約書の作成が法的に求められているため電子化はできません。
ただし2025年上期に向けた公正証書のデジタル化に向けた動きが進んでおり、今後は上記の書類についても電子化できる見込みです。現在は公証役場に出頭しなければ作成できない公正証書も、ウェブ会議・電子署名を利用して作成できる予定です。これが実現されれば、大幅にコストや時間を削減することが可能でしょう。
不動産取引で電子契約を締結する流れ
不動産取引を電子契約で行うためには、いくつか実施しなければならない工程が存在します。特に、重要事項説明をオンラインで行う(IT重説)場合は、事前にその旨の同意を取引先から得ておく必要があるなど、重大な注意点があります。事前に契約の流れをイメージして、実際のフローを構築することが必要です。
以下に、不動産取引における電子契約締結の流れを紹介します。
不動産取引に関する契約書類をアップロードする
不動産取引に関する契約書類(重要事項説明書、売買契約書、賃貸借契約書など)を電子化し、電子契約システムにアップロードします。
このとき、契約書類の真正性を確保するため、PDFなどの改ざん防止機能を持つファイル形式を使用する必要があります。また、電子帳簿保存法の要件を満たすため、タイムスタンプを付与しなければなりません。
不動産業者が契約書類に電子署名をする
アップロードされた契約書類に対して、不動産業者が電子署名を行います。電子署名は、電子署名法に基づき、作成者の本人性と非改ざん性を証明するための重要な手続きであり、電子証明書を使用した電子署名や、電子契約サービスが提供する署名機能を使用するのが一般的です。
正しい方法で行われた電子署名により、契約書の作成者の同一性が確認され、電磁的記録の成立の真正が推定されます。
IT重説についての事前承諾を得る
オンラインで重要事項説明を行うIT重説の場合は、相手方の同意を得る必要があります。原則として紙の書面による同意書の取得が必要です。しかし、IT重要事項説明に関しての実施マニュアルなどでは、登録事業者及び説明の相手方が同意したことについて「証跡が残る方法」であれば、手法を問わずに同意が得られると規定されています。
オンラインで同意を検討する場合、以下のような方法が挙げられます。
- 電子署名を用いて同意書を送信・受信する
- 事業者・説明の相手方の両方が同意書ファイルへの電子署名を行う
- 登録事業者が同意書の内容を記載し、送付したメールに返信する
オンラインで重要事項を説明する
宅建士と買主による、対面での読み合わせが必要だった重要事項説明についても、オンラインで実施できるようになりました(厳密には、2013年の「世界最先端IT国家創造宣言(閣議決定)」を受けてから徐々に導入開始)。
重要事項説明をオンラインで行う場合、基本的にWeb会議システムなどを用いて行います。ただし、重要事項説明書を実際に見せながら説明する必要があるため、事前に重要事項説明書等を取引先に送りましょう。
相手方がオンラインで対応可能か確認し、重要事項説明書を事前に送付し、全て準備が整った上で実施します。
電子契約を締結する
上記までの流れで、オンラインでの重要説明の同意を取得し、準備が完了したら、電子契約サービスを利用して電子契約を結びます。
一般的な不動産契約であれば、契約に関わるのは「売主(または貸主)」「買主(または借主)」「宅建士」の三者です。電子署名を行う場合でも、非対面での契約ではなりすましのリスクがあります。そのため、電子契約サービスなどの機能で、契約当事者が本人かどうかを確認した上で電子署名を行える仕組みを導入しましょう。
契約書類を電子交付する
双方の電子署名が完了した契約書類は、各契約当事者に対して電磁的方法により交付されます。この際、契約書類は改ざん防止措置が施された状態で、各当事者が直ちに表示・保存できる形式で交付されなければなりません。
電子契約システムでは契約当事者それぞれに対して、電子契約システムから電子メールなどで契約書類が送信されます。電子契約の一連の流れはこれで完了です。
交付された電子契約書は、宅建業者は電子帳簿保存法の要件に従い、契約書類の原本を適切に保存する必要があります。
不動産取引を電子契約化するメリット
不動産取引を電子契約化するには、いくつかの必要条件がありますが、その代わりに、いくつかの大きなメリットがあります。デメリットについては後述しますが、基本的には時間も含めたコスト削減が可能となっており、利用が進められる領域であれば、積極的に活用を検討する価値はあるでしょう。
遠方でもオンラインで契約できる
電子契約となるため、インターネットを介して電子ファイルにより契約を締結できます。つまり、他県などにいる方ともオンラインで契約手続きを完結できることになります。これにより、相手方と直接会うために予定を調整し、移動するなどの物理的に必要な時間を削減することが可能です。この点は、特に相手方が遠方にいる場合には大きなメリットだといえます。
印紙税などのコストを削減できる
前述の通り、オンラインで契約締結は、対面で契約する時のように時間や場所などを相手方と話し合って調整する手間を省けます。
それに加えて、例えば遠方にいる相手方と書面でやりとりを行う場合などは、従来であれば郵送で契約書の送付などを行っていたものを、オンラインで完結できるようになるため、郵送にかかる費用や手間を削減できます。
また、電子契約書では印紙税が不要です。特に高額な不動産取引において、コスト削減を実現できることも大きなメリットです。
文書ファイルを電子化して保存できる
契約を電子化することで、契約内容や契約に付随する書類をデータで保管することができます。紙からデータにすることで、一回の契約でも、相当数の紙の削減につなげることができます。印刷用紙やインク代の節約だけでなく、ファイルや棚のスペース削減にも繋げることができ、近年、重要課題となっているSDGsの取り組みにもつなげられます。
不動産取引を電子契約化するデメリットや注意点
これまでは、不動産取引を電子契約化することによるメリットを見てきましたが、もちろんデメリットも同様に存在します。電子契約化を検討している事業者の方については、メリットだけではなく、デメリットも的確に把握しておくことが重要です。
セキュリティ対策やバックアップが必要
電子契約の場合、基本的にオンラインで情報のやり取りが発生します。オンラインの情報送受信では、当然ながらサイバー攻撃による情報流出の危険性や、重要なデータが破損してしまう危険性があるため注意は必要です。堅牢な情報セキュリティ体制の構築や、万が一破損してしまった場合のバックアップ対策などを行う必要があります。
取引先に電子契約へ同意してもらう必要も
不動産仲介の場合は、仲介業者・買主・売主の三者による取引となります。電子契約の場合、それぞれの同意が必要です。例えば、買主がPC操作に慣れていない、またはそもそもPCを持っていない場合は、電子契約はできません。取引先が契約の電子化に対応していない場合は、環境を整備してもらう必要があります。
不動産会社の業務フローの検討
紙ベースでの契約と電子契約では、業務フローが大きく変わります。そのため使用する電子契約サービスなどにあわせて、自社であらかじめ業務フローを構築する必要があります。
例えば、まず「相手方への意思確認・電⼦契約の旨の告知」はどのように行うのか、IT重要事項説明の際にはどのツールを使うのか、電子署名依頼の送信はどのように行うのかなど、あらかじめ確認し準備しておきましょう。
不動産取引に電子契約を導入した企業事例
株式会社第一住建ホールディングスでは、不動産業界特有の紙文化からの脱却を目指し、マネーフォワード クラウド契約を導入しました。
同社は、契約書の郵送や押印に伴う手間、収入印紙税の負担を課題としていましたが、電子契約の導入によりペーパーレス化を実現。また、不動産取引契約書のみならず業務委託契約書なども電子化したことで、印紙税の負担をなくし大幅なコスト削減に成功しました。
運用サポートが期待以上であったとの声
マネーフォワード クラウド契約導入の決め手になったのはリーズナブルな料金プラン、そして標準プランでワークフローを構築できることにあったといいます。
また、専任担当者による運用サポートが期待以上であり、実際の運用課題にも柔軟に対応できた点も高く評価されています。現在は大阪本社を中心に運用を進めており、今後は他拠点にも展開予定です。
同社では、電子契約の利便性が社員や取引先からも好評を得ており、不動産業界全体のDX推進や電子化促進も視野に入れています。
不動産取引の電子化による業務改善効果と関連データ
マネーフォワード クラウドが2025年5月に実施した調査(電子契約業務経験者1,563名対象)によると、電子契約システムで便益を感じられるポイントとして「費用削減」(35.6%)と「工数削減」(34.4%)が最も多く挙げられました。費用削減の詳細では「印紙税の不要化」が30.6%で最も重視され、高額取引が多い不動産業界では特に大きな削減効果が期待できます。
印紙税と契約業務の大幅な効率化を実現
不動産取引では契約金額が高額になるため、本記事で解説した事例のように印紙税の負担をなくすことで大幅なコスト削減が可能です。また、工数削減では「契約締結までのリードタイム短縮」が19.9%、「契約書の印刷・製本など手作業の省略」が21.6%で重視されており、電子契約により遠方の顧客ともオンラインで契約を完結できることで、移動時間や郵送にかかる手間が大幅に削減されます。IT重説の活用と合わせることで、契約業務全体のスピードと効率が向上します。
リスクに対処しながら、電子契約で業務効率化を
デジタル改革関連法により、不動産契約の多くをオンラインで完結できるようになってきました。導入できれば、手間やコストの面で多くのメリットがありますが、セキュリティの問題など課題も残されています。導入を検討している企業の方は、電子契約サービスをうまく利用しリスクを低減しながら、実務の中に取り込んでいきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
モニター同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
モニター同意書とは、企業が製品やサービスの評価を目的としたモニタリングに参加する方から同意を得るための法的書類です。レビュー収集や個人情報の取り扱い、写真利用など、具体的な条件を明確にすることで、事業者とモニター双方の権利を保護します。 本…
詳しくみる取材同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)
取材同意書は取材をする人と取材される人とが締結する同意書です。近年ネットやSNSが普及しさまざまな情報が発信できるようになった一方で、トラブルが発生するリスクもあるため、取材前には同意を形成しておくことが非常に重要となってきています。 この…
詳しくみる美容サロン業務委託契約書とは?例文・テンプレート、作り方を紹介
美容サロン業務委託契約書は、サロンとフリーランスの美容師やエステティシャンが締結する契約書です。法的効力を持つため、未払いトラブルや業務範囲外の請求を回避するポイントを明確にしながら作成し、レビュー・締結することが重要。この記事ではテンプレ…
詳しくみる契約締結とは?締結日の決め方や契約書作成日・効力発生日との違いも解説
契約締結とは、法的に利害関係をもつ契約内容に対して当事者が合意することを指します。紙での契約はもちろん、電子契約でも締結可能です。 本記事は契約締結とは何かを解説し、締結方法や注意点を解説します。あわせて、契約締結日、作成日、効力発生日それ…
詳しくみる賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書とは?ひな形をもとに書き方を解説
賃料不払いによる「賃貸借契約解除通知書」とは、貸主が契約解除を知らせるときに作成する文書です。賃料を払ってくれない借主と契約は続けられませんので、不払いになっているときはこれを作成することになるでしょう。 ただし解除も自由にはできません。ど…
詳しくみる契約書の法的効力とは?基礎知識から有効要件・押印との関係を解説
契約書はビジネスの約束を形にするものですが、その効力や注意点を押さえておくことで、契約に関するトラブルを未然に防ぐことができます。 企業の人事担当者や法務担当者にとって、契約書の法的効力を正しく理解することは重要です。本記事では契約書の法的…
詳しくみる