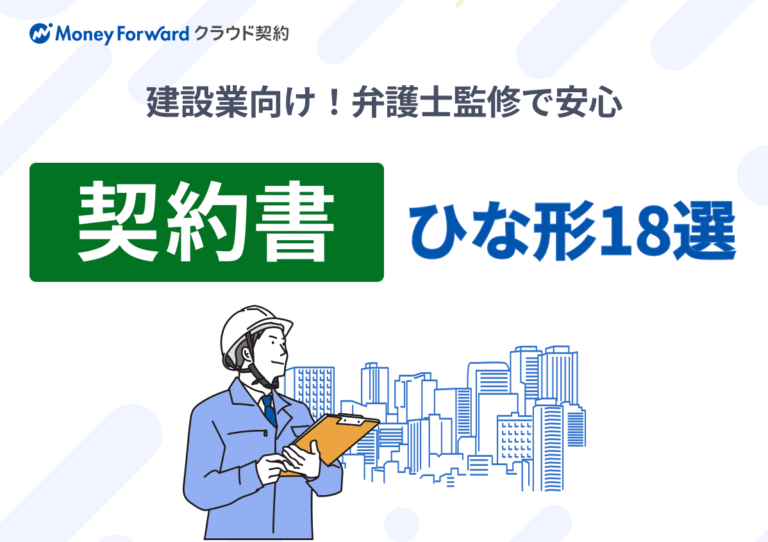- 作成日 : 2025年11月11日
電子契約におけるグレーゾーン解消制度とは?活用事例と申請の流れを解説
電子契約を導入・提供する際「自社の業界で定められた法律に違反しないだろうか」という法的な不安は大きな障壁となります。特に、法律で「書面」の交付が義務付けられている場合、電子データがこれに該当するのかは重大な問題です。
この記事では、こうした法的な不明確さ(グレーゾーン)を解消し、安心して事業を進めるための強力な仕組みである「グレーゾーン解消制度」について、電子契約に関する様々な活用事例を交えながら、その概要から申請の流れまでを分かりやすく解説します。
目次
電子契約におけるグレーゾーン解消制度とは?
電子契約の適法性について、国に直接確認し公式な回答を得られる制度活用法です。
多くの法律では、契約時に「書面」を交付する義務(書面交付義務)が定められています。電子契約がこの「書面」と見なされるかが大きな障壁でしたが、建設業や不動産業の分野で事業者がこの制度を活用し、国から「照会した法律の範囲内では適法」との公式な行政見解を得たことが大きな転換点となりました。
これにより、特に不動産分野では2022年5月から宅建業法に基づく重要事項説明書や契約書面の電子化が全面的に可能になるなど、電子契約の導入に向けた環境整備が進んでいます。つまり、電子契約の法的なリスクを解消するための強力な手段として活用されているのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
【建設業向け】契約書のひな形まとめ
工事請負契約書やリフォーム・解体・電気工事請負契約書…をはじめ、建設業で使える契約書のテンプレートをまとめた無料で使えるひな形パックです。資料内からお好きなひな形をダウンロードいただけます。
実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
そもそもグレーゾーン解消制度とはどのような制度?
グレーゾーン解消制度とは、事業者が新しいビジネスを始める際に、その事業が既存の法律に違反しないか(適法性)を、事前に国の担当省庁に確認できる「産業競争力強化法」に基づいた制度です。
この制度は、特定の業界だけのものではなく、新しい技術やサービスに挑戦するすべての事業者のために用意されています。法律の制定当時には想定されていなかった新しいビジネスモデル(ドローン配送、オンライン診療、FinTechなど)が登場した際に、事業者は法的な不安なく安心して事業をスタートさせることができます。
グレーゾーン解消制度については以下の記事でも詳しく解説しています。
なぜ電子契約でグレーゾーン解消制度が活用されるのか?
電子契約でグレーゾーン解消制度が活用されるのは、多くの業界で「書面による交付」が法律で義務付けられており、電子データがその「書面」と見なされるか不明確なケースが多いためです。
建設業法や宅地建物取引業法など、様々な法律には契約時や取引時に「書面を交付しなければならない」という規定が存在します。これらの法律が制定された時代には、現代のような電子契約は想定されていませんでした。
そのため、
- 宅地建物取引業法や建設業法といった個別の法律で定められた「書面」の要件を、PDFなどの電子ファイルが満たすことができるのか
- 電子署名法で定められた要件を満たす電子署名が、従来の押印と同等の効力を持つのか
といった点が法律の条文だけでは判断できず、解釈が分かれる「グレーゾーン」が生じていました。電子契約サービスを提供する事業者や、それを導入したい企業にとって、このグレーゾーンは大きなリスクです。そこで、自社の電子契約サービスや導入方法が適法であることを国に確認し、公式な行政見解を得るために、この制度が積極的に活用されています。
【分野別】電子契約に関するグレーゾーン解消制度の活用事例
電子契約は、業種を問わず導入が進んでいますが、契約の種類によっては「書面交付義務」が障壁となり、適法性が曖昧なケースが少なくありません。こうした法的リスクを解消するために、多くの企業がグレーゾーン解消制度を活用しています。
ここでは、経済産業省が発表した「グレーゾーン解消制度の活用事例」を参考に、行政契約・建設業・不動産業の活用事例をご紹介します。
国・地方自治体との契約における活用事例(行政契約の電子化)
国や地方自治体と契約を締結する際、従来は紙による書面契約が基本とされてきました。この点について、電子契約サービス事業者がグレーゾーン解消制度を利用し、電子署名を用いた契約の適法性を照会しました。
その結果、照会内容に応じてデジタル庁、法務省、財務省などの関係省庁から「関係法令上、電子署名等により本人確認や改ざん防止措置が講じられていれば、電子契約の利用は可能である」という趣旨の回答が示されました。これは、行政との契約に電子契約を導入できる道を開いた、画期的な事例といえます。
出典:国・地方自治体との契約における電子契約サービス提供|経済産業省
建設業における活用事例(請負契約の電子化)
建設工事の請負契約は、建設業法に基づき紙の書面での締結が義務付けられており、電子化の大きな障壁となっていました。これに対して、電子契約サービス事業者がグレーゾーン解消制度を通じて国土交通省に照会しました。
その結果、建設業法第19条および関連政省令に基づき「電子署名とタイムスタンプ、またはそれと同等の技術的措置により、契約の『見読性・本人性・原本性』が確保される場合には、電子契約も適法な契約締結と認められる」という趣旨の回答が示されました。
この判断は、建設業界の契約手続きを大きく効率化し、DX推進を後押しする重要な転換点となりました。
不動産業における活用事例(定期借家契約の電子化)
不動産分野では、借地借家法に基づき「定期借家契約」は書面による交付が必須とされ、電子化が難しい契約形態でした。そこで、電子契約サービス事業者がグレーゾーン解消制度を利用し、法務省に照会しました。
その結果、借地借家法および宅地建物取引業法の解釈として、「相手方の事前の承諾を得て、本人確認措置を講じるなど、国土交通省の示すマニュアルに沿った方法であれば、電子的に作成・交付した契約書でも法的要件を満たす」との見解が示されました。これは、不動産業界における電子契約導入を現実のものとした大きな一歩であり、実務上のインパクトも大きい事例です。
電子化の適法性を確認するグレーゾーン解消制度の申請手順
国の担当省庁への事前相談から始まり、申請書の提出を経て、国からの公式な「回答」を得る、という流れで進みます。この制度をスムーズに活用するためには、主に以下の4つのステップを理解しておくことが重要です。
ステップ1. 事前相談
まず、自社の事業を所管する省庁に、どの法律のどの部分が電子化を進める上でグレーゾーンなのかを相談します。制度に関する相談は、内閣官房に設置された政府一元窓口で受け付けています。また、経済産業省も制度の利用手引きの作成や相談支援を行っているため、どの省庁に相談すればよいか不明な場合は、まずはこちらに問い合わせることも有効です。
この事前相談は、申請全体の中でも極めて重要なプロセスです。単なる挨拶ではなく、申請が受理されるかどうか、また、的確な回答を得られるかどうかを左右するからです。相談に臨む際は、以下の点を準備しておくと円滑に進みます。
- 具体的な事業計画:どのようなサービスを、誰に、どのように提供するのかを明確に説明できる資料。
- 特定した法律と条文:どの法律の、どの条文の、どの文言(例:「書面をもって」など)の解釈に悩んでいるのかを具体的に指摘する。
- 自社の見解:なぜ自社の事業が「適法」と考えるのか、その法的根拠や理由。
- 技術的な説明資料:自社の電子署名が電子署名法第2条・第3条の要件をいかに満たすかなど、技術的な裏付けを説明できる資料。
この段階で担当者と論点をすり合わせることで、申請書の精度を高め、手戻りを防ぐことができます。
ステップ2. 申請書の提出
事前相談で明確になった論点に基づき、正式な申請書(照会書)を作成し、事業を所管する大臣宛てに提出します。この申請書は、国に法的な判断を促すための公式な文書であり、極めて具体的に記述する必要があります。
申請書には、主に以下の内容を盛り込みます。
- 事業の詳細な内容:サービスの仕組み、利用される技術、業務フローなどを、専門家でなくても理解できるよう図表なども交えて分かりやすく記載します。
- 法令解釈の論点:確認したい法律の条文を正確に引用し、その解釈がなぜ不明確(グレーゾーン)なのかを論理的に説明します。
- 照会者の見解と結論:照会者(申請企業)として、なぜその事業が適法と考えるのかを詳細に記述し「したがって、本事業は〇〇法に違反しないものと解釈されたい」といった形で結論を明確に示します。
この文書の作成には高度な法的知識が求められるため、弁護士や行政書士といった専門家の支援を受けて進めるケースもあります。
ステップ3. 省庁間の照会と回答
提出された申請書は、まず事業を所管する大臣(例:ITサービスであれば経済産業大臣)に受理されます。その後、その大臣から、照会対象の法律を所管する大臣(例:建設業法であれば国土交通大臣)へと、内容の照会が行われます。
法律を所管する大臣は、照会内容を法的に検討し、回答を作成します。産業競争力強化法では、原則として申請受理から1ヶ月以内に回答を行うと定められています(ただし、関係省庁が多岐にわたるなど複雑な事案では、理由が通知された上で期間が延長されることもあります)。
得られる回答は、単に「適法」か「違法」かだけではありません。「〇〇という技術的要件を満たす場合に限り、適法と解する」といった条件付きの肯定的な回答が示されることも多く、これが事業を展開する上での具体的な指針となります。この回答は、申請者に対して正式な書面で通知されます。
ステップ4. 回答内容の公表
事業者からの照会内容と国からの回答は、照会者の同意を前提として、原則として経済産業省のウェブサイトなどで公表されます(個人情報や事業者の競争上の利益を害する恐れのある営業秘密などは、非公開やマスキングといった調整が可能です)。これにより、申請した一社の問題解決に留まらず、同様の事業を検討している他の事業者もその法的な判断を参考にすることができます。
この公表制度には、以下のような大きな意義があります。
- 予見可能性の向上:ある事業が適法と判断されれば、それが一つの「判例」のようになり、業界全体が安心して同様の事業に取り組めるようになります。
- イノベーションの促進:法的リスクが不明確なために躊躇されていた新しい技術やサービスの社会実装を後押しします。
ただし、公表が原則であるため、事業の核心的なノウハウや他社に知られたくない機密情報を申請書に記載する場合は、非公開やマスキング(墨塗り)といった調整が可能か、事前相談の段階で担当省庁と具体的に協議することが重要です。
電子化でグレーゾーン解消制度を利用する前に知っておきたい注意点
電子化の適法性を確認できる便利な制度ですが、利用する前に知っておくべき重要な注意点が3つあります。
注意点1. 法律そのものを変える制度ではない
この制度は、あくまで現行法の解釈を確認するものであり、新しい法律やルールを独自に作ることはできません。
グレーゾーン解消制度は、現在の法律の範囲内で「自社の事業は適法か」を確認するためのものです。もし、自社の事業モデルが現行法で明確に禁止されている場合、この制度を使っても適法にはなりません。法律の改正が必要な場合は、業界団体を通じた働きかけなど、別のプロセスが必要となります。
注意点2. 申請内容と回答は原則として公表される
申請した事業計画や国の回答は、原則として経済産業省のウェブサイトで公開されるため、他社に知られたくない事業ノウハウが含まれる場合は注意が必要です。特に電子契約サービスの場合、照会書に記載した「タイムスタンプの仕組みや暗号化の仕様」といった技術的なノウハウが競合他社に知られるリスクを考慮する必要があります。
この公表は、制度の透明性を確保し、他の事業者が同様の事業を行う際の参考に供するという目的があります。どの範囲の情報までが公表されるかについては、申請前の「事前相談」の段階で担当省庁によく確認することが重要です。事業の根幹に関わる機密情報が含まれる場合は、「表現の工夫」を検討するだけでなく、照会者の同意に基づき、非公開や部分的なマスキング(墨塗り)といった対応が可能かを、事前相談の段階で必ず確認しましょう。
注意点3. 弁護士など専門家のサポートが有効
申請手続きには法的な専門知識が不可欠なため、弁護士や行政書士といった専門家の支援を受けて進めるのも有効な選択肢です。
法的な論点の整理、照会書の専門的な記述、担当省庁との折衝など、手続きには複雑なプロセスが含まれます。経験豊富な専門家に依頼することで、論点がずれることなく、スムーズかつ確実に手続きを進めることが期待できます。初めて制度を利用する場合は、まず専門家へ相談することをおすすめします。
電子契約でグレーゾーン解消制度を活用する際のQ&A
Q. 誰でも申請できますか?
A. はい、原則として法人・個人事業主を問わず、誰でも申請可能です。最も重要なのは、具体的な事業計画があることです。アイデア段階の漠然としたものではなく「誰に」「何を」「どのように」提供するのかが明確になっている事業が対象となります。
Q. 申請に費用はかかりますか?
A. 国への申請自体に手数料はかかりません。ただし、申請書の作成には高度な法的知識が求められるため、弁護士や行政書士といった外部の専門家の支援を受けて進めるケースも少なくありません。その場合、専門家への相談料や依頼費用が別途発生します。
Q. 回答に法的拘束力はありますか?
A. 回答は、裁判所の司法判断を直接拘束するものではありません。しかし、その法律を所管する省庁の公式な見解であるため、非常に重い意味を持ちます。回答に従って事業を行う限り、行政から指導を受ける可能性は極めて低いと言え、事業者は安心して事業を推進するための強力な根拠とすることができます。
法的な不安を解消し、安心して電子契約を導入するために
今回は、電子契約の導入・提供における法的な不安を解消するグレーゾーン解消制度について解説しました。
この制度は、建設業や不動産、人材派遣など、幅広い業界で電子契約の普及を後押しする重要な先例が示されてきました。自社で取り扱う契約書が法律で書面交付を義務付けられている場合でも、この制度の活用事例を調べることで、電子化への道筋が見えるかもしれません。
新しい技術やサービスを安心して社会に実装していく上で、グレーゾーン解消制度は事業者にとって心強い味方と言えるでしょう。今後は契約の電子化だけでなく、特にメールやクラウドサービスで請求書や領収書といった「電子取引」データをやり取りする事業者にとっては、電子帳簿保存法に準拠したデータ保存への対応も重要となるため関連法制度全体の理解を深めていくことが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
代理店契約書のリーガルチェックのポイントは?確認事項や注意点を解説
代理店契約は、自社の商品やサービスを他社に販売・提供してもらう際に結ぶ契約です。契約の構造や条項の内容によっては、自社にとって不利な義務やリスクを抱える可能性があるため、契約書のリーガルチェックが欠かせません。 この記事では、チェックすべき…
詳しくみる不動産賃貸は電子契約もOK!書類の準備や契約の流れ、保管方法を解説
不動産賃貸は電子契約が可能です。宅地建物取引業法の改正により電子化が可能になり、賃貸契約に関する一連の流れをオンラインで完結できるようになりました。これにより、不動産業賃貸の業務を効率化できます。 本記事では、不動産賃貸で電子契約できる書類…
詳しくみる小売業で電子契約は導入できる?メリットや企業事例、サービスを選ぶポイントも
小売業における電子契約導入は、業務効率化やコスト削減に有効な手段です。多岐にわたる契約業務を抱える小売業にとって、電子契約は多くのメリットをもたらす機会となるでしょう。本記事では、電子契約の基本から、小売業で主な対象となる契約書類や導入によ…
詳しくみる電子契約サービスを乗り換える方法・流れは?注意すべきポイントも解説
電子契約サービスの選択肢が増える中で、より自社に適したサービスへの乗り換えを検討する企業が増えています。電子契約サービスの乗り換えには、適切な手順と注意点の把握が不可欠です。 本記事では、電子契約サービスを乗り換える方法や流れ、注意するべき…
詳しくみる電子契約の当事者型と立会人型の違いは?メリットや選ぶポイントも解説
電子契約では、契約当事者が電子署名を付与する「当事者型」と、第三者である事業者が電子署名を付与する「立会人型」の2種類があります。電子署名は契約書の信頼性に関わる重要な要素だけに、どちらを使えばいいかお悩みの方もいるかもしれません。 今回は…
詳しくみる電子契約で内部統制を強化する方法を解説
電子契約サービスは契約業務の効率性を高め、企業のコンプライアンスとリスク管理の強化といった内部統制の強化に寄与します。 この記事では、電子契約サービスが企業の内部統制に役立つ理由や導入するメリット、必要な機能について解説します。電子契約サー…
詳しくみる