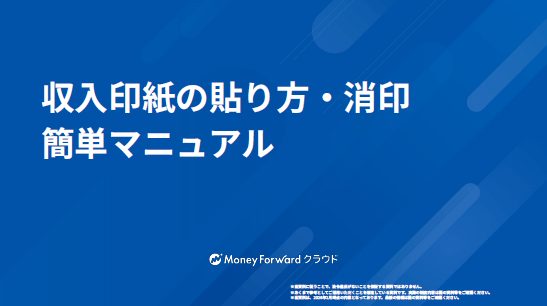- 更新日 : 2026年1月28日
収入印紙の正しい貼り方は?2枚以上ある場合や割印、のりの使い方も解説
契約書や領収書などには、一定の金額以上の取引で収入印紙の貼付が必要です。場合によっては、2枚以上の複数枚を貼付しなければならないこともあります。
この記事では収入印紙の正しい貼り方や、貼る収入印紙の金額、収入印紙を間違えて貼ってしまった場合の対処法などについて解説していきます。
目次
そもそも収入印紙とは
収入印紙とは、契約書や領収書などの一定の課税文書に対して、税金を納めるために貼付が必要な証票のことです。この課税文書に対して課せられる税金を印紙税といい、どのようなものが課税文書に該当するかは印紙税法により定められています。契約書や領収書の他、約束手形や株券、保険証券などの取引に関するものは課税文書に該当し、収入印紙の貼付が必要なことがあります。収入印紙は通常の切手と同じで、郵便局やコンビニで購入できます。見た目も通常の切手と似ていますが、切手は郵便料金の支払いのために貼るもので、収入印紙は国税の納付のために使用するという違いがあります。
また、収入印紙とよく似た言葉に「収入証紙」というものがあります。収入証紙は、地方自治体に対して手数料を払う際に使用されるものです。
収入印紙が必要な契約書・領収書
収入印紙が必要な契約書は印紙税法に定められており、具体的には請負契約書や不動産の譲渡に関する契約書などが該当します。
一方で、建物の賃貸契約や会社と従業員との雇用契約書、金額が1万円未満の契約書などは印紙税法の課税文書には該当しないため、収入印紙の貼付は不要です。
領収書は原則として金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要です。
ただし、クレジットカードでの支払いであることが明記されている場合や、紙ではなくPDFなどで作成した領収書をメールで送付した場合などは、収入印紙の貼付が不要とされています。
【収入印紙が必要な契約書】
| 分類 | 文書の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 | 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など |
| 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 | 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など | |
| 消費貸借に関する契約書 | 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など | |
| 運送に関する契約書 | 運送契約書、貨物運送引受書など | |
| 第2号 | 請負に関する契約書 | 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
収入印紙の金額
実際に貼付が必要な収入印紙の金額は、印紙税法別表第1によって以下表のように定められています。
第1号、第2号の分類は、前章を参照してください。
【第1号文書】
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
※契約金額の記載のないものは200円
【第2号文書】
| 請負金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
※契約金額の記載がないものは200円
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド
電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。
社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
収入印紙の正しい貼り方
収入印紙の貼り方は、基本的には普通の切手と同様です。
ただし印紙を貼る位置にやや注意が必要な他、割印(消印)を押す必要があります。
収入印紙を貼る位置
収入印紙を貼る位置について、法律上は特に定められていません。必ずここに貼らないといけないという決まりはありませんが、見えやすくかつわかりやすい位置に貼るようにしましょう。
契約書の場合は通常、左上に貼ることが一般的です。複数枚にわたる契約書の場合は、1枚目に貼付します。
領収書の場合は、収入印紙の貼付欄があればその枠内に貼ります。もし貼付欄がない場合は、領収書の余白部分などわかりやすい場所に貼りましょう。
割印の押し方
収入印紙は、ただ貼っただけでは印紙税を納付したことにはなりません。貼付した収入印紙には割印という印鑑を押す必要があります。
割印とは、収入印紙の再利用など、不正利用防止のために押す印鑑です。契約書や領収書などの課税文書と収入印紙にまたがるように押します。
また、割印とよく似た言葉に消印という言葉があります。割印は名前の通り、2つの文章を割るように押すことから慣習的に使われてきた言葉です。
一方で消印は、印紙税法で使われる言葉で印紙が使用済みであることを明らかにするために押す印鑑のことです。
この2つの言葉は、慣習的に使われているか法律上使われている言葉かの違いのため、どちらの呼び方でも特に大きな問題はありません、この記事では、割印(消印)として表現しています。
なお、一般的には割印(消印)は印鑑を押しますが、印鑑が手元にない場合などはサインをすることでも可能です。その場合は、消えないインクを使ったボールペンで、誰が割印を行ったのかわかるようにサインした人の名前を記します。また、通常の割印(消印)を押すのと同じように印紙と書類に重なるように行う必要があります。
のりを使用する場合の注意点
収入印紙の裏面には乾燥したのりが付いています。実際に貼付する際は、裏面を水などで濡らして貼ります。
このときの注意点は、少量の水で濡らすことです。多量の水で濡らすと印紙がふやけて破れてしまったり、貼れなくなったりしまうため、濡らす際は、少量の水を使うようにしましょう。
すでに塗布されているのりでは不安な場合は、裏面にスティックのりなどを付けて貼る方法もあります。液状タイプののりを使う場合は、下敷きにする紙と印紙がくっつかないよう、塗りすぎには注意しましょう。
なお、舌で舐めて唾液で濡らすという方法をとることもありますが、衛生面などの点からはあまりお勧めできません。
収入印紙が複数枚ある場合の貼り方
貼付する収入印紙の金額が大きくなった場合は、1つの書類に2枚以上の収入印紙が必要となることがあります。このような場合はいくつか注意すべき点があります。
複数の印紙を貼る位置
1つの書類に2枚以上の収入印紙を貼る場合は、通常左右、または上下に並べて貼ります。
印紙を貼る位置は法律上決められていないとはいえ、バラバラに貼ってしまうと見た目も悪く取引の相手方にも失礼です。
複数の印紙が貼ってあることが一目でわかるように左右、または上下に並べて貼りましょう。
それぞれの収入印紙に割印を押す
複数枚の印紙を貼付した場合は、それぞれの収入印紙に割印(消印)を押すか2枚の印紙にまたがって押す必要があります。
収入印紙は、貼っただけでは印紙税を納付したことにはならないため、貼付した収入印紙にはすべて割印(消印)を押すようにしましょう。
収入印紙の貼り方を間違えた場合の対処法
収入印紙を間違えて貼ってしまうと、場合によっては交換や還付を受けられません。万が一、貼り方を間違えた場合は、以下のように対処しましょう。
収入印紙を別の書面に貼った場合
白紙の用紙や封筒などに間違えて収入印紙を貼ってしまった場合は、印紙の交換が可能です。この場合、用紙から剥がしたり切り離したりしてしまった場合は交換できなくなるため注意しましょう。
収入印紙の交換は、印紙を販売している郵便局で行うことができます。万が一、間違えて収入印紙を貼ってしまった場合は、印紙を剥がしたりせず、そのままの状態で郵便局の窓口に持参しましょう。
収入印紙の金額を間違えた場合
収入印紙を本来の金額よりも多く貼付してしまった場合や、本来は課税文書ではなく収入印紙の貼付が不要であるにもかかわらず間違って貼ってしまった場合は、超過した金額について還付を受けることができます。
このような場合は、「印紙税過誤納付確認申請書」と一緒に過大に貼付した書類、または誤って貼付した書類を税務署に提出します。審査の結果、還付が認められれば3カ月程度で還付されます。
ただし、還付は文書作成から5年以内となっているため、できるだけ早く還付の手続きを行うことが必要です。
なお、交換する場合と同様に、印紙を剥がしたり切り離したりしてしまうと還付が受けられなくなるため、必ず貼ったままの状態で税務署の窓口に提出しましょう。
一方で、収入印紙を貼付したものの金額が本来必要な金額に満たない場合は、不足分の印紙を追加で貼付する必要があります。
手順としては、不足している金額の印紙を、すでに貼付済みの印紙の横などに貼り、割印(消印)を行うことで対処可能です。
収入印紙を貼り忘れたらどうする?
収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、過怠税というペナルティが科されます。過怠税とは、本来納付しなければならない印紙税の金額に加えて、さらにその2倍の金額が徴収されることです。したがって、合計すると、本来納付する印紙税の3倍の金額を納付することとなります。
ただし、これは税務署による税務調査の際に貼り忘れが発覚した場合です。収入印紙の貼り忘れに気づき自主的に申し出た場合は、本来の金額の1.1倍の金額のペナルティに軽減されます。
後から収入印紙の貼り忘れに気がついた場合は、必ず、自主的に税務署へ申し出ましょう。
また、収入印紙を貼っていたとしても、割印(消印)が押されていなかったり、必要な印紙の金額に満たなかったりする場合は、印紙税を納付したことにはならないため、ペナルティが科されることがあります。
収入印紙は必要な金額を正しく貼り、割印(消印)を必ず押すようにしましょう。
契約金額が大きくなれば、必要な印紙の金額も高くなり、印紙を貼り忘れた場合の過怠税の金額も大きくなります。収入印紙の貼り忘れには注意が必要です。
収入印紙は正しい金額を正しい方法で貼ることが重要
収入印紙は、作成された文書が課税文書に該当する場合に、必ず貼付が必要です。
法律上、印紙の貼り方は特に定められていませんが、わかりやすい位置に貼り、割印(消印)を押す必要があります。
万が一、印紙を貼り間違えた場合や、多く貼ってしまった場合は、交換や還付を受けることができます。一方、印紙の貼り忘れは過怠税として2倍の金額のペナルティが科されることがあるため、必要な金額の収入印紙を正しく貼るようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
基本契約書の印紙税200円と4000円の違いは?契約書や領収書の金額一覧、貼らなくていい場合も解説
ビジネスで使う契約書や領収書には、4000円または200円の収入印紙が必要になるケースがあります。特に基本契約書では、金額に20倍もの違いがあるため、この違いを正しく理解しておくこ…
詳しくみる機密保持契約書に印紙は不要?必要な場合や秘密保持契約との違いを解説
機密保持契約書は、印紙税法の課税文書に該当しないため、印紙を貼る必要はありません。印紙なしが基本です。しかし、印紙が必要となる場合もあるため、注意してください。どんな場合に印紙が必…
詳しくみる秘密保持契約書(NDA)に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
秘密保持契約書(NDA)には、原則として収入印紙(印紙)が不要です。ただし、文書の記載内容次第で課税文書として印紙を貼らなければならないことがあります。 印紙を貼る場合にいくら必要…
詳しくみる建物賃貸借契約書に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
建物賃貸借契約書に印紙を貼る必要があるかどうか、わからないという方も多いのではないでしょうか。原則として印紙は不要です。本記事では、建物賃貸借契約書に印紙が不要である理由や印紙が必…
詳しくみる株式譲渡契約書に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
企業買収時の株式譲渡契約書に金額を受領した旨の記載がある場合、収入印紙が必要です。貼る場所は正本・副本をまたがって契約書の上部に、どちらが印紙税を負担するかについては基本的に折半で…
詳しくみる労働者派遣基本契約書に印紙は不要?必要な場合はある?ルールを解説
労働者派遣基本契約書には、印紙を貼付する必要はありません。これは印紙税法に基づくもので、労働者派遣契約書が印紙税の対象である第7文書「継続的取引の基本となる契約書」や、第2文書の「…
詳しくみる