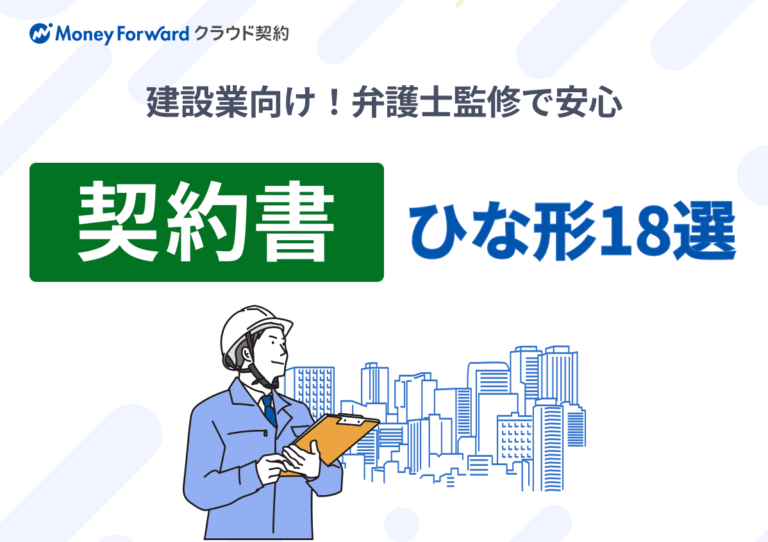- 作成日 : 2025年11月11日
建設業法第19条第3項とは?電子契約を導入するために必要な承諾と書面交付義務を解説
建設業界でも導入が進む電子契約ですが、建設業法第19条第3項では、契約書を電子化する際に特別な定めがあることをご存知でしょうか。この条文は、建設工事の請負契約を書面で交付する原則を定めており、電子化するには相手方からの「承諾」が不可欠です。本記事では、建設業法第19条第3項の概要から、適法に電子契約を導入するための具体的な手順、そして導入するメリットや注意点まで、人事労務の初心者がつまずきやすいポイントを分かりやすく解説します。
目次
電子契約に関わる建設業法第19条第3項とは?
建設工事の請負契約で電子契約を利用する場合、法律で定められた書面での交付に代えるためには、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない、と定めた条文です。この承諾がないまま一方的に電子契約を送付しても、法律上の交付義務を果たしたことにはなりません。
建設業法第19条の全体像
建設業法第19条は、建設工事の請負契約における当事者の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐことを目的として、契約内容の書面化と相互交付を義務付けている法律です。
具体的には、同条の第1項で工事内容や請負代金の額といった法定の15項目を記載した契約書を作成し、署名又は記名押印をして相互に交付することが義務付けられています。そして、第3項でこれらの書面交付に代わる電子的措置(電子契約)のルールを定めている、という構成になっています。これは、口約束による「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、公正な取引関係を確保するための重要な規定です。
第3項が定める「承諾」の重要性
建設業法第19条第3項が定める「承諾」は、電子契約を有効に成立させるための、極めて重要な法的要件です。
通常の業務委託契約などでは、当事者双方の意思が合致(合意)すれば契約は成立します。電子署名は、その合意が本物であることを証明し、契約の証拠力を高めるために利用されるのが一般的です。しかし建設業においては、電子署名を行う以前に、「契約内容を紙ではなく電子データで受け取ること」について、相手方から明確な承諾を得る必要があります。
この「承諾」の証明がなければ、たとえ電子署名が完了していても、法律で定められた書面交付義務を果たしていないと見なされるリスクがあります。そのため、承諾を得た事実をメールや同意書などの形で記録・保管しておくことが不可欠です。
出典:建設業法 | e-Gov 法令検索
出典:建設業法令遵守ガイドライン(第11版)|国土交通省
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
【建設業向け】契約書のひな形まとめ
工事請負契約書やリフォーム・解体・電気工事請負契約書…をはじめ、建設業で使える契約書のテンプレートをまとめた無料で使えるひな形パックです。資料内からお好きなひな形をダウンロードいただけます。
実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
建設工事の請負契約で電子契約を導入するメリットは?
建設工事の請負契約で電子契約を導入する最大のメリットは、コスト削減、業務効率化、そしてコンプライアンス強化の3つです。特に、契約金額が大きくなる建設業界では、印紙税が不要になる経済的メリットは計り知れません。
メリット1. 大幅なコスト削減
電子契約を導入すると、契約書にかかる印紙税が不要になるほか、紙の印刷・製本・郵送といった物理的なコストを大幅に削減できます。システムの利用料は発生しますが、それらを考慮しても企業全体のコスト削減に大きく貢献します。
建設工事の請負契約書は、印紙税法上の課税文書にあたり、契約金額に応じて高額な収入印紙の貼付が必要です。しかし、電子契約は課税文書に該当しないため、印紙税が非課税となります。
例えば契約金額が1億円超5億円以下の工事であれば、本来10万円の印紙税が必要ですが、現在は軽減措置が適用されており6万円となります。電子契約であれば、この6万円が節約可能です(※この軽減措置は2027年3月31日作成分までが対象)。このほか、紙代、インク代、郵送費、書類保管用のキャビネット費用なども削減可能です。
メリット2. 契約業務の大幅な効率化
電子契約は、契約書の作成から押印、送付、締結、保管までの一連のプロセスをオンラインで完結させ、業務時間を劇的に短縮します。
従来の紙契約では、印刷・製本→押印→郵送→相手方の押印・返送→保管という流れで、締結までに数日から数週間かかることも珍しくありませんでした。電子契約サービスを活用すれば、これらの作業をすべてオンライン上で完結できます。
締結までの時間は、相手方の確認状況や社内の承認フローにもよりますが、紙の契約書に比べて大幅に短縮されることが一般的です。契約進捗もシステム上で可視化でき、契約書の検索も容易になるため、書類管理の手間も削減されるでしょう。
メリット3. コンプライアンスとセキュリティの強化
電子契約サービスを利用することで、契約の締結履歴が正確に記録され、改ざんリスクを低減し、内部統制やコンプライアンスを強化できます。
多くの電子契約サービスは、誰が・いつ・何に同意したかというログ(監査証跡)を自動で記録します。また、電子署名やタイムスタンプ技術により、契約書が作成された時点から改ざんされていないことを証明できます。これにより、契約の真正性が担保されるだけでなく、契約書の紛失や閲覧権限のない者によるアクセスといったセキュリティリスクも防ぐことができます。
建設業法第19条第3項に沿って電子契約を導入する手順は?
適法に電子契約を導入するには、相手方からの承諾取得、システムの選定、社内ルールの整備というステップを順番に踏むことが重要です。特に最初の「承諾」のプロセスを確実に行うことが、コンプライアンスの鍵となります。
ステップ1. 相手方(発注者または受注者)からの承諾を得る
最初に、契約の相手方に対し、請負契約の締結を電子的な方法で行うことについて承諾を得ます。この承諾は、電子契約書を送付するなど、電子的な措置を実施する前に取得する必要があります。オンラインの手続き上、先に電子交付への承諾を得てから契約内容の確認や締結に進む、というフローが確保されていれば問題ありません。なお、相手方は一度行った承諾を撤回することも可能です。
承諾を得る方法としては、以下のようなものが考えられます。
- メールでの確認:「今後の建設工事請負契約は、電子契約システム〇〇を利用して締結することに同意いただけますでしょうか」といった文面で相手方に送り、同意する旨の返信をもらう。
- 基本契約書での包括的同意:継続的な取引がある場合に、基本契約書で電子契約利用の同意を得る方法。ただし、単に「電子契約を利用できる」と定めるだけでなく、利用する電子契約サービスの名称や、メール等の具体的な方法、ファイルの形式(PDFなど)を明示した上で承諾を得る必要がある。利用するシステム等を変更する際は、改めて承諾を得る。
- 同意書の取得:電子契約の利用に関する専用の同意書を作成し、相手方に署名・押印してもらう。
どの方法であっても「いつ」「誰が」「何に」同意したかが明確にわかる形で証拠を保管することが極めて重要です。
ステップ2. 電子契約サービスの選定
次に、電子署名法などの関連法規に対応した、信頼性の高い電子契約サービスを選定します。建設業の取引で利用する上で、特に以下の点を確認しましょう。
- 法的有効性:電子署名法が定める要件を満たし、契約の証拠力を担保できるかどうか。特に、契約当事者本人が署名する「当事者型」か、サービス事業者が介在する「事業者署名型(立会人型)」か、その上で本人確認はどのレベルまで行われるか、といった点も重要。
- セキュリティ:通信の暗号化、不正アクセス防止策、データのバックアップ体制などが万全か。
- 保管機能:電子帳簿保存法の要件を満たした検索・保管が可能か。建設業の契約書は、建設業法上、原則5年間の保存が義務付けられている(新築住宅の建設工事に関するものは10年間)。安全に長期間データを管理できることが重要。
- 操作性:自社だけでなく、契約相手にとっても使いやすいシステムか。
ステップ3. 社内規定の整備と周知
続いて、電子契約の利用に関する社内ルール(規定)を整備し、関係者に周知徹底します。
規定に盛り込むべき内容としては、以下のような項目が挙げられます。
- 電子契約の対象となる契約の種類
- 相手方から承諾を得るための具体的な手順と記録方法
- 電子契約システムの利用方法と権限設定
- 作成した電子契約書の保管・管理方法
これらのルールを明確にすることで、担当者による運用のばらつきを防ぎ、内部統制を確保します。
ステップ4. 電子契約の締結と保管
最後に、整備した手順に従い、実際に電子契約を締結します。選定した電子契約サービス上で契約書データ(PDFなど)をアップロードし、相手方に送信します。相手方が内容を確認し、電子署名を行えば契約締結は完了です。
締結済みの電子契約書は、電子帳簿保存法における「電子取引」データとして、法律の要件に従って保管する必要があります。具体的には、改ざん防止措置を講じ、「取引年月日・金額・取引先」で検索できる状態にしておくことなどが求められます。いつでも検索・表示できるように、工事名、契約相手、契約日などの情報と紐づけて管理しましょう。
電子契約を導入する際に特に注意すべき点は?
建設業法で特に重要となる「承諾の証拠保管」を徹底すること、そしてITに不慣れな取引先への丁寧な説明と配慮が、導入をスムーズに進める上で不可欠な注意点です。
承諾を得た証拠を必ず保管する
最も重要な注意点は、相手方から電子契約に関する承諾を得た証拠(メールや同意書など)を、締結した契約書データと紐付けて保管することです。
万が一、後から「電子での交付には同意していない」と主張された場合、この承諾の証拠がなければ、建設業法第19条第3項の違反を問われる可能性があります。契約の有効性自体が争点になることもあるため、承諾の記録は契約書そのものと同じくらい重要だと認識し、厳重に管理してください。
取引先への配慮と丁寧な説明
電子契約はまだすべての事業者に浸透しているわけではありません。特に、ITツールの利用に慣れていない事業者もいることを想定し、導入のメリットや操作方法、セキュリティについて丁寧に説明することが大切です。
一方的に電子契約への切り替えを要請するのではなく、「印紙税が不要になる」「手続きが早くなる」といった相手方にとってのメリットを伝え、理解を求める姿勢が円滑な移行の鍵となります。必要であれば、操作方法に関する簡単なマニュアルを用意するなどの配慮も有効です。
もし建設業法第19条に違反してしまった場合のリスクとは?
建設業法第19条の義務に違反しても、直ちに罰金刑といった刑事罰はありません。しかし、監督処分や過料、経営事項審査の減点、契約トラブルの発生といった、事業の根幹に関わる重大なリスクが伴います。
監督処分(指示・営業停止など)
法令違反があった場合、国土交通大臣や都道府県知事から監督処分を受ける可能性があります。最初は業務改善の「指示」ですが、違反を繰り返したり内容が悪質だったりする場合には、「営業停止処分」や、最も重い「建設業許可の取消処分」に至ることもあります。
経営事項審査(経審)での減点
公共工事の入札に参加する建設業者が受ける経営事項審査(経審)では、法令遵守の状況が評価項目の一つです。建設業法違反が発覚すると、この評価が減点される可能性があります。評点が下がると、入札で不利になり、事業機会の損失に直結します。
契約の有効性が問われるトラブル
法律で定められた手続き(承諾など)を経ずに締結した電子契約は、後日、相手方から契約の有効性を争われる可能性があります。「言った・言わない」といった紛争に発展し、訴訟になった場合に自社が著しく不利な立場に置かれるなど、深刻な経営リスクの原因となります。
建設業法第19条第3項を遵守し、安全な電子契約へ移行しよう
本記事では、建設業法第19条第3項の規定と、それに基づいた電子契約の導入方法について解説しました。
建設工事の請負契約を電子化する際は、契約を締結する前に必ず相手方の「承諾」を得て、その証拠を保管することが法律で定められています。この重要なポイントを確実に押さえ、適切な手順を踏むことで、コンプライアンスを遵守しながら、コスト削減や業務効率化といった電子契約の大きなメリットを享受できます。本記事を参考に、安全でスムーズな電子化への第一歩を踏み出してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
消費者契約法とは?契約の取消権が有効なケースや最新の改正を簡単に解説
消費者契約法とは消費者と事業者間の情報量や交渉力の格差を是正し、消費者の利益を守るための法律です。一般消費者を相手方にサービスを展開している企業の方は、消費者契約法を正確に把握して…
詳しくみるリーガルチェックを外注するメリットは?費用や失敗しない選び方まで徹底解説!
新しい取引先との契約書、ウェブサイトに掲載する利用規約、新規事業の適法性…ビジネスのあらゆる場面で法的リスクは潜んでいます。そのリスクを事前に洗い出し、問題を未然に防ぐ手続きがリー…
詳しくみるChatGPTによるリーガルチェックの方法は?契約書作成に使えるプロンプトも紹介
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIを活用したリーガルチェックが、多くの企業で注目されています。簡単な指示(プロンプト)で契約書の要約やリスクの洗い出しができるため、法務部門…
詳しくみる電子契約の本人確認とは?方法やなりすましの原因と対策を解説
電子契約が普及する中で、本人確認は企業にとって極めて重要な課題となっています。紙の契約書では、署名や捺印による本人確認が一般的でしたが、電子契約ではデジタル技術を利用して信頼性を確…
詳しくみる契約書に電子署名をする方法は?PDFやWord、スマホの場合を解説
契約書への電子署名は、PDFソフトやWord・Excel、電子契約サービスを利用することで可能です。電子署名とは、契約データへ電磁的に署名することを指します。本記事では、スマートフ…
詳しくみるPDFに無料で電子署名する方法は?やり方や手順、確認方法、注意点を解説
電子契約などのPDFファイルには、電子署名を行うことが推奨されます。無料で電子署名をしたいときは、Adobe Acrobat Reader、無料のオンラインツール、電子契約サービス…
詳しくみる