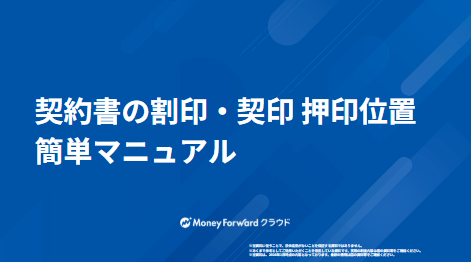- 更新日 : 2026年1月28日
割印とは?正しい押し方や位置、失敗した場合の対処法などを解説
割印とは、独立した複数の文書にまたがって印鑑を押し、それらの文書の一貫性や関連性を証明する行為です。例えば、契約書とその控え(写し)の2部にまたがって押すことで、両者が同一の取引に基づくものであり、改ざんされていないことを示します。
今回は、割印の正しい位置や押し方、契印・訂正印といった他の押印との違い、失敗した場合の対処法から、電子契約の実務まで詳しく解説します。
目次
割印とは?
割印とは、独立した複数の文書にまたがって印鑑を押すことを指します。読み方は「わりいん」です。
複数の関連文書に割印を施すことで、それらが同一の取引や合意に基づいていることを明確にします。例えば、契約書とその控えの両方にまたがるように押すことで、両者の内容が同一であることを示せます。
また、割印が押された文書は、法的な争いが発生した際に、文書の真正性を証明する手段として機能することもあります。関係者それぞれが割印を押すことで、文書が関係者間で確認された証拠になります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド
下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。
本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。
2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。
弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書
弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。
契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。
自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント
契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。
割印と混同されやすい押印との違いは?
割印と混同されやすい押印がいくつかあります。それぞれの目的と使い分けを明確に解説します。
消印(けしいん)
消印とは、収入印紙が使用済みであることを証明するために押す印鑑のことで、印紙税法で定められた義務です。
収入印紙と契約書などの文書本体にまたがるように押します。この行為は商習慣上「割印」とも呼ばれることがありますが、法的には「消印」として区別されます。
止印(とめいん)
止印とは、契約書などの文書の末尾に余白がある場合に、後から不正に文章が書き足されるのを防ぐために押す印鑑です。「ここで文書は終わりです」ということを証明します。
文書の最後の文字のすぐ後ろ(末尾)に押します。この際、署名・捺印に使用したものと同じ印鑑を使用するのが一般的です。
止印を押す代わりに、文書の末尾に「以下余白」と記載することでも、同様の効果が得られます。実務上、必ずしも押さなければならないものではありません。
訂正印(ていせいいん)
訂正印は、契約書などの文書に記載された内容を修正・訂正するために使用する印鑑です。
修正したい箇所に二重線を引き、その上から押印し、正しい内容を記載します。通常、契約書に署名・捺印した当事者全員の訂正印が必要です。
捨印(すていん)
捨印とは、契約書の余白にあらかじめ印鑑を押しておき、軽微な修正があった際に文書を訂正できるようにするものです。
捨印の横に「◯文字追加(削除)」などと記入することにより、相手方に訂正印をもらい直す手間を省略できます。ただし、意図しない修正に利用されるリスクもあるため、安易な押印は避けるべきです。
契印(けいいん)
契印は、1つの文書(契約書など)が複数ページにわたる場合に、そのページの連続性を確認するために用いられます。
ページの見開き部分(製本テープを貼った場合は製本テープと本文)にまたがるように押します。使用する印鑑は、署名・捺印に使用したものと同じ印鑑を使用するのがルールです。
割印を押す主な書類は?
割印は、特定の文書に信頼性と正当性を付与する重要な役割を担います。ここでは、どのような書類に割印を押すべきか、そしてそれがなぜ必要なのかについて説明します。
契約書
契約書は、割印を押すことが最も一般的な文書の1つです。契約の正本とコピー(控え)の両方に割印を押すことで、文書の一貫性と改ざん防止が保証されます。これにより、契約が法的に実施される過程で、文書の真正性が疑われることがありません。
- 不動産取引の契約書
- 大規模な商取引に関する契約書
- 雇用契約など、長期にわたるサービス提供の契約書
会社の重要文書
企業が内外に発信する重要な文書にも割印が用いられます。これには、会社の定款、取締役会の議事録、株式譲渡契約などが含まれます。これらの文書に割印を押すことで、その正確性と公式な承認が保証されます。
- 会社の定款
- 株式譲渡契約書
- 取締役会や株主総会の議事録
公的書類
公的機関や法的手続きで必要とされる文書にも、割印が求められることがあります。これには、裁判所の提出書類や公的な証明書が含まれます。割印は、これらの文書が正式なものであることを示すために重要です。
- 裁判所への提出書類
- 法的な証明書や許可書
その他の文書
割印は、その他多くの場面で利用されることがあります。例えば、大学からの学位証明書や医療関係の重要な文書、さらには個人間の重要な合意文書に至るまで、多岐にわたります。
- 学位証明書
- 医療記録
- 個人間の貸借書
割印の正しい押し方と位置は?

割印の押し方や位置に、法律上の厳密な定めはありませんが、実務上の慣習(マナー)が存在します。ここでは、具体的なケース別に正しい位置と押し方を詳しく解説します。
契約書(2通)の原本と写し
最も基本的なケースです。契約当事者(甲と乙)が2通の契約書(原本と写し、または当事者保有分)に割印を押します。
- 正しい位置:2通の契約書を縦または横に少しずらして重ね、両方の書類にまたがるように押します。慣習として、契約書の上部(天)の余白に押すことが多いです。上部でなくても、両方にまたがる場所であれば問題ありません。
- 押し方:契約の当事者全員(甲乙双方)が、それぞれ割印を押す必要があります。一般的には、契約書に署名・捺印した印鑑と同じ印鑑を使用します。
契約書(3通以上)
3社間契約(甲・乙・丙)などで、契約書が3通以上になる場合の押し方です。
- 正しい位置:すべての契約書(3通)を重ねた状態で、縦または横に少しずつずらします。
- 押し方:すべての契約書に印影がまたがるように、当事者全員(甲・乙・丙)が印鑑をしっかりと押します。3通の書類の上部(天)を、階段状になるように少しずつずらして重ねると押しやすくなります。
ただし、書類が厚く、一度にすべての文書に明瞭な印影を残すことが難しい場合があります。その場合は、「1枚目と2枚目」「2枚目と3枚目」というように、2通ずつの組み合わせで順次、割印を押していく方法もあります。
領収書と控え
領収書とその控えに割印を押すことは、取引の正当性と双方の合意を確認するために重要です。
- 正しい位置:領収書と控え(ミシン目などで切り離す場合)を重ねた状態で、両方(切り取り線)にまたがるように割印を押します。
- 押し方:領収書を発行する側(代金を受け取った側)が押します。受領側(代金を支払った側)が押す必要はありません。
収入印紙
収入印紙の割印(消印)は、印紙税法で定められた義務であり、押し方には明確なルールがあります。
- 正しい位置:契約書や領収書などの書類本体と、貼付した収入印紙の彩紋(模様部分)とにまたがるように押します。押す位置は特に決められていませんが、収入印紙の右側に押すのが一般的です。
- 押し方:印紙の再利用を防ぐため、印紙と文書本体の両方にかかるよう、判別できるように(=判明に)押す必要があります。印紙だけに押したり、書類だけにはみ出したりした場合は無効となるため注意が必要です。
参考:印紙の消印の方法|国税庁
割印に使用する印鑑の種類は?
割印に使用する印鑑は、その文書に捺印した印鑑をそのまま用いるのが一般的です。ただし、文書の重要性に応じて使い分けられます。
実印
実印は、個人が登録することができる最も正式な印鑑です。通常、不動産の売買や高価な取引に使用され、法的な効力を持つ重要な文書に押されます。
実印は、その所有者だけが使用することが許されており、個人の身元確認としての役割も果たします。割印として実印を使用する場合、その文書への信頼性が非常に高くなるでしょう。
銀行印
銀行印は、主に金融機関での取引に使用される印鑑です。実印ほどの信頼性はありませんが、個人を特定する役割を持ちます。
割印として銀行印を使うことは少ないですが、小規模なビジネス取引や内部文書で使用されることがあります。
認印
認印は、日常的な文書に使用される最も一般的な印鑑です。サイズや形状に特に決まりはなく、個人のものから企業の簡易な印まで多岐にわたります。
割印としては、認印が最も頻繁に使用される印鑑です。特に、社内文書や一般的な書類の割印に適しており、手軽に使用できるため、多くの企業や個人に広く普及しています。
割印専用の印鑑
通常の印鑑よりも印章が縦長になっている割印専用の印鑑も存在します。印章が縦長なので、複数枚の文書にまたがって割印を押しやすく作られています。
割印をきれいに押すためのコツは?
割印、特に複数枚にまたがる押印は失敗しやすいものです。ここでは「押印ミス」や「かすれ」を防ぐためのコツを、チェックリストと手順で深掘りします。
準備編|押印前のチェックリスト
- 平らな場所を確保する:押すときに凸凹のある場所は避けます。必ず平らな机の上などで押しましょう。
- 印鑑マット(捺印マット)を用意する:印影を鮮明にするには、印鑑マットの使用が最も効果的です。ゴムや合皮などの適度な弾力がある素材が、印影を鮮明にします。
- 朱肉の状態を確認する:朱肉が乾燥していたり、逆にインクが多すぎたりしないか確認します。印鑑全体に朱肉が均等に付くように意識します。
- 印鑑の上下を確認する:印鑑の持ち方も重要です。上下を間違わないよう、印の上部にある「アタリ」を確認します。
実践編|きれいな押印のステップ
- 朱肉を付ける:朱肉を強く叩きつけず、印面全体に均等に、軽くポンポンと朱肉を付けます。
- 書類をセットする:割印を押す書類(2枚以上)を、印鑑マットの上に平らに置きます。
- 書類をずらす:契約書の1枚目を開いて重ねるなどして 、割印を押す位置(通常は上部)を決め、上下または左右にずらします。
- 印鑑を持つ:印鑑を親指、人差し指、中指で支えるように持ちます。
- 押印する:印面の上下(アタリ)を確認し 、押したい位置に印鑑を垂直に当て、均等な圧力で「の」の字を書くようにゆっくりと体重をかけます。
- 印鑑を離す:押印したら、真上にそっと持ち上げます。
応用編|3部以上・厚い書類のコツ
3部以上の書類は段差が大きくなり、かすれやすくなります。
- 段差を減らす:割印を押す部分(上部)以外に、同じ高さになるように不要な紙(コピー用紙など)を挟み、段差をできるだけ平らにします。
- 重ね方(1枚目を重ねる):契約書の1枚目を開いて重ねる(1枚目と2枚目の表紙同士を重ねる)と押しやすくなります。
- 縦長印鑑の使用:このケースこそ、印章が縦に長い割印専用の印鑑が役立ちます。
割印の位置や押し方に失敗した場合の対処法は?
割印に失敗しても、修正液や二重線での訂正は絶対にしてはいけません。正しい対処法を解説します。
印影が不鮮明な場合
印影の確認が困難なほど不鮮明な場合は、失敗した印影の隣など、別の位置に改めて割印を押します。
失敗した割印に訂正の措置(二重線など)を施す必要はなく、そのままで構いません。多少かすれている程度で、誰の印鑑か判別できるのであれば、押し直す必要はありません。
不適切な位置で押した場合
割印を押す位置に厳密な決まりはないため、印影が明確であれば、あまり気にする必要はありません。
どうしても気になる場合は、適切な位置に改めて割印を押し直せば足ります。失敗した印影は放置して構いません。
誤った印鑑を使用した場合
割印に使用する印鑑に法律上の決まりはないため、当初の予定とは異なる印鑑を使用しても、直ちに問題となることはありません。
どうしても当初予定していた印鑑に改めたい場合は、別の位置に改めて正しい印鑑で割印を押します。この場合も、失敗した割印に訂正の措置は不要です。
割印と契約の法的効力は?
割印は、契約書の真正性や不可分性を保証するために用いられますが、法的には契約の成立条件ではありません。割印がないという事実は、契約の有効性に直接的には影響しません。
参考:押印についてのQ&A
割印の法的な役割
割印がない場合でも契約は有効ですが、以下の理由で重要な役割を持つとされます。
- 信頼性の向上:割印を押すことで文書の信頼性が向上し、それにより契約当事者間の信用が築かれやすくなります。
- 証拠としての価値:法的な争いが発生した場合、割印が押された文書はその真正性を証明する強力な証拠となり得ます。
割印なしでの契約例
- 口頭契約:多くの簡単な取引では、口頭での合意のみで契約手続きを進めます。例えば、日常の商取引やサービスの提供において、特に公式な書類は必要とされません。
- 電子契約:電子メールやオンラインフォームを通じた合意も、割印が押されない形式の1つです。これらはデジタル署名やその他の電子認証方法によって、契約の成立を確実にします。
電子契約における割印の取り扱いは?
電子契約では、物理的な割印は押されません。
その代わり、デジタル署名やタイムスタンプなどの電子認証方法によって、契約の成立と非改ざん性(真正性)を確実にします。これらが従来の割印や契印の役割を果たします。
割印を押した後の契約書の取り扱いは?
割印を押した後の契約書の取り扱いは、その証拠力を維持するために重要です。
押印後の契約書の保管方法
割印や契印、署名捺印が完了した契約書の原本は、当事者双方が1通ずつ(または原本と写しを)保有します。
保管の際は、湿気や直射日光を避け、鍵のかかるキャビネットや金庫など、安全で改ざんや紛失のリスクがない場所に保管してください。
紛争時における割印の証拠力
裁判などの紛争において、契約書の「真正な成立」が争われることがあります。その際、割印は「契約書が2通同時に作成され、内容が同一であること」を証明する有力な証拠となります。
割印がない場合、一方の当事者が「私が持っている写しは、相手が持つ原本とは内容が異なる」と主張した際、反論が難しくなる可能性があります。割印は、こうしたリスクを防ぐ役割を担います。
割印に関するよくある質問(FAQ)
最後に、割印に関するよくある質問とその回答をまとめました。
割印はシャチハタでもいいですか?
法律上は可能ですが、実務上は避けるべきです。
シャチハタは誰でも容易に入手でき、印影が変形しやすいため、本人が押したという証明性に欠けます。 金額が大きな契約書や重要な事項を定めた契約書の場合には、契約書に押した印鑑と同じ印鑑(実印や銀行印、認印)で割印を押すのが一般的であり、ビジネスマナーとしても推奨されます。
割印を押す順番(甲乙丙)は決まっていますか?
割印を押す順番に、法的なルールや厳密なマナーはありません。
ただし、実務上、契約書の上部(天)に割印を押す場合、発注者である甲が上に押し、その両脇や下に乙、丙が押すといった慣習が見られることもあります。 重要なのは、当事者全員(甲・乙・丙)が、すべての書類にまたがるように押すことです。
割印専用の印鑑を作る際のポイントは?
割印専用の印鑑の要件は、法律上特に決められていません。作成する際のポイントは以下の通りです。
- サイズ:複数枚に押しやすい縦長の形が一般的です(例:横12〜15mm、縦30〜36mm)。
- 刻印内容:会社名を入れるのが一般的です。「株式会社〇〇之割印」とすることもあります。
- 書体:篆書体(てんしょたい)や古印体(こいんたい)などが一般的です。
割印を正しく押すことで契約書の信頼につながる
割印は、法律で決められた押し方やルールがあるわけではありませんが、文書の連続性や関連性を明らかにするという役割があります。
割印がなくても契約書自体は有効ですが、割印を正しい押し方で押すことによって契約書の信憑性を高められます。
割印に使用する印鑑には、特に条件などの決まりはありませんが、契約書に押印された印鑑を使用するのが一般的です。また、法人の場合は必要に応じて割印専用の印鑑の作成なども検討するとよいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
原状回復費用の請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
原状回復費用の請求書とは、賃貸借契約の終了時に、賃貸人が賃借物件を原状回復させるために工事などして要した費用を賃借人に請求するための書類です。企業がオフィスを借りる場合や工事による…
詳しくみる人材派遣での個別契約書の書き方・記載項目を解説!
人材派遣を行う際に必要な派遣契約書の一つに「個別契約書」があります。個別契約書は、労働者派遣法で記載項目が細かく定められています。個別契約書はどのように作成し、いつ取り交わせばよい…
詳しくみる不動産死因贈与契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
不動産死因贈与契約書とは、贈与者の死亡により不動産贈与の効力が生じる契約書のことです。口約束でも贈与契約は成立しますが、トラブルを回避するためにも契約書を作成しておくほうがよいでし…
詳しくみる譲渡承認取締役会とは?手続き・メリットから議事録の記載事項まで徹底解説
中小企業の株式譲渡で重要な役割を果たすのが、会社の承認機関です。取締役会設置会社では「譲渡承認取締役会」がその中心となりますが、手続きは複雑で、承認・不承認いずれの場合も法的な知識…
詳しくみる転抵当権設定契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
転抵当権設定契約書は、抵当権に対してさらに抵当権を設定する際に締結する契約書です。転抵当権の特徴を踏まえつつ、必要な事項を適切に定めた契約書を作成しましょう。本記事では、転抵当権設…
詳しくみる商品売買代金請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
商品売買代金請求書とは、売買契約において、買主が期日までに代金を支払わない場合に、買主に対して送付する書類です。この記事では、商品売買代金請求書とは何かについて基本的な知識を説明す…
詳しくみる