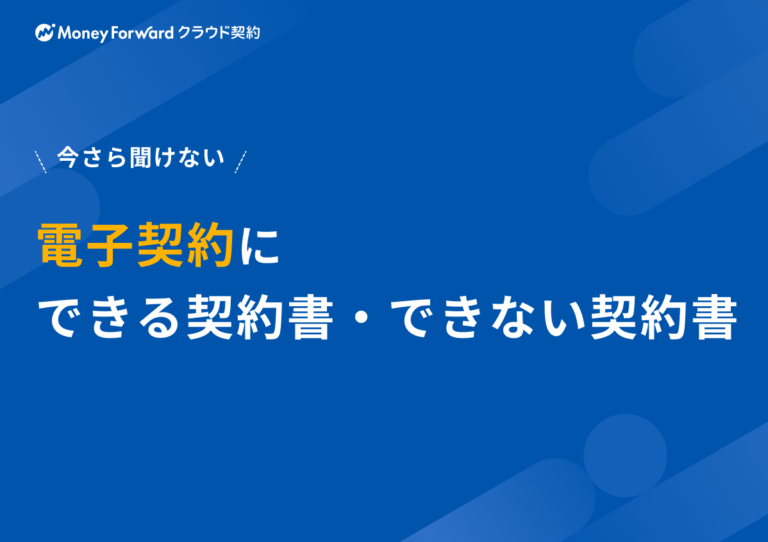- 更新日 : 2025年3月6日
海外での電子契約の普及状況は?法的有効性についても解説!
現在、日本では電子契約が普及しつつあります。海外の企業と取引を行っている日本企業は、その取引に電子契約が使えるのか気になるかもしれません。今回は海外における電子契約の普及状況や、導入することで得られるメリット、電子契約を導入する上で理解しておきたいリスクなどについて解説します。
海外での電子契約の普及状況は?
海外には日本よりも電子契約の普及が進んでいる国があり、社会保障や納税などのデジタル化が進んでいる国(エストニアなど)もあります。電子契約の導入に積極的な国々と比べると、日本は電子契約を含む「デジタル化」が遅れているといわれていますが、近年は日本でも国や民間企業が電子契約の普及を進めるようになりました。それに伴って法律が整備され、さまざまな電子契約サービスが登場しています。
海外における電子契約は、電子契約サービスを導入して行われるケースが多いようです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
導入で失敗したくない人必見!電子契約はじめ方ガイド
電子契約のキホンからサービス導入の流れまで、図解やシミュレーションを使いながらわかりやすく解説しています。
社内向けに導入効果を説明する方法や、取引先向けの案内文など、実務で参考になる情報もギュッと詰まった1冊です。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
海外での電子契約の法的有効性は?
海外では、すでに電子契約に関する法律が整備されている国と、そうでない国があります。電子契約の法整備が進んでいる国でも、その要件は国によって異なります。そのため、日本企業が海外企業との取引に電子契約を用いる場合は、取引先の国の法律をよく調べる必要があります。その場合は取引先の国だけでなく、日本の電子契約に関する法律の要件も満たさなくてはなりません。また、電子契約に関する法律が整備されていない国もあり、その場合は電子契約を行えません。
海外取引に電子契約を用いるメリットは?
海外取引に電子契約を用いることの最大のメリットは、輸送コストを削減できることでしょう。
書類を送る際、それを返送してもらう際に輸送コストがかかりますが、電子契約ではこのようなコストがかかりません。また、海外企業との書類のやりとりでは、確実に相手に届くのか、確実に自分に返送されるかといった心配もあるでしょう。電子契約であれば、そういった心配も不要です。
ビジネスのスピードアップも期待できます。海外企業との取引では、書類の輸送に多くの時間を要するためです。電子契約であれば即座に契約書のデータが相手に届くため、タイムラグがありません。それによって、契約にかかる時間を大幅に短縮できます。
海外取引に電子契約を用いるリスク・デメリットは?
海外企業との取引に電子契約を導入することには、リスクやデメリットもあります。
まず、取引相手の国の電子契約に関する法律に関する問題です。前述のとおり、国によって電子契約の要件は異なります。要件には技術的なものや、国や地域における商習慣が反映されたものがあり、さまざまな規制が設けられています。日本の電子契約に関する法律の要件だけでなく、相手国の法律の要件も満たさなければならず、その調査に時間がかかるケースも少なくありません。
海外の法律が、日本の法律よりも複雑である場合が多いことも問題です。日本では法律は国が定めますが、海外では国よりも小さい行政単位で法律が定められているところも少なくありません。例えば、アメリカ合衆国の法律は、連邦法と各州法で構成されています。そのため、調査が必要な電子契約の法律も取引相手の国だけでなく、州法なども調査する必要があるのです。
海外取引にも電子契約は使える!一方で調査は重要
欧米諸国は日本よりも電子契約が普及しているといわれますが、日本企業が海外企業との契約に電子契約を用いる場合は、相手国の電子契約に関する法律をよく調べる必要があります。調査を怠ると契約が無効になったり、トラブルに繋がったりするおそれがあるため、時間をかけてしっかり調査を行いましょう。
よくある質問
海外企業と電子契約はできる?
海外企業との電子契約は基本的に可能です。海外では日本よりも電子契約の法整備が進んでいるといわれていますが、そうでない国もあります。そのような国の企業との契約には、電子契約を用いることができません。詳しくはこちらをご覧ください。
海外企業と電子契約を行う場合の注意点は?
まず、相手国において電子契約に関する法整備がなされていることを確認します。その上で、日本における電子契約の法整備とうまく合致するかどうかを確認しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
契約書をペーパーレス化する方法と進め方を解説
契約書を電子化すれば職場のペーパーレスが進み、保管や管理がしやすくなります。ただ法整備が進んでいる段階で移行期にある企業も多いため「全部ペーパーレスにしてもよいのか」という不安を持…
詳しくみる契約書管理を電子化するメリットや方法は?注意点も解説!
今、従来の紙の契約書に代わって電子契約を導入される企業や個人事業主の方が増えてきています。契約を電子化することでさまざまなメリットが得られます。とりわけ契約管理の点においては非常に…
詳しくみる中小企業で電子契約が必要な理由は?導入方法やおすすめサービスを紹介
「契約」と聞くと、分厚い紙の束に印鑑を押し、収入印紙を貼るといった作業を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、中小企業を取り巻くビジネス環境は目まぐるしく変化しており、…
詳しくみる電子署名は改ざんできる?改ざん手口や改ざん防止セキュリティを解説
テレワークの普及やDX推進の流れを受け、契約業務においても電子契約システムと「電子署名」の利用が急速に広がっています。特に、タブレットなどに手書きでサインする手軽な電子サイン(手書…
詳しくみるリーガルチェックを弁護士に依頼するメリットは?費用相場から依頼方法まで徹底解説
リーガルチェックは、契約書や利用規約といった法的文書に潜むリスクから事業を守るための重要なプロセスです。この記事では、なぜリーガルチェックが不可欠なのか、そしてなぜ専門家である弁護…
詳しくみる長期署名とは?電子署名の有効期限を10年以上延長する方法を解説
長期署名とは電子契約・電子署名を適切に長期間管理するために、タイムスタンプを付与して有効期間を延長する仕組みのことです。この記事では長期署名の基本情報、利用方法、注意点などについて…
詳しくみる