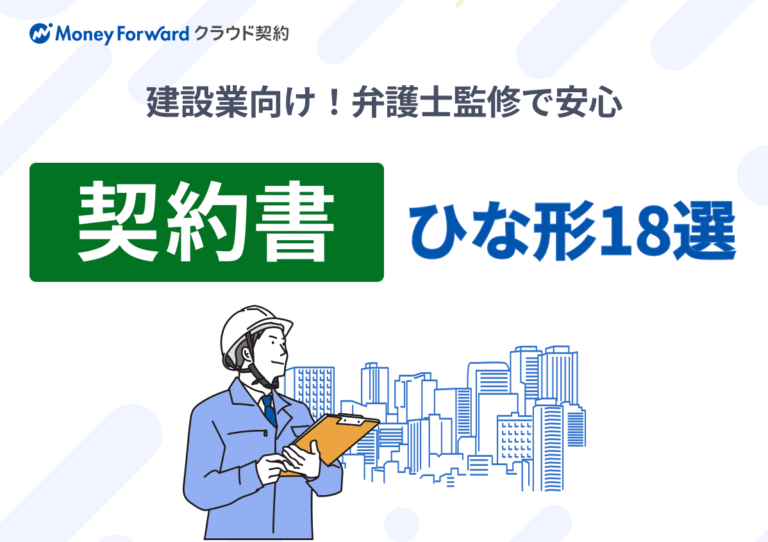- 作成日 : 2025年11月11日
建設業の電子契約に承諾書はなぜ必要?建設業法が定める義務と取得方法を解説
建設業界においても、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せ、業務効率化やコスト削減の観点から「電子契約」への関心が高まっています。しかし、建設工事の請負契約を電子化する際には「建設業法」が定める特有のルールを遵守する必要があります。その中でも特に重要なのが、契約の相手方(注文者)から「電子契約利用承諾書」を事前に取得することです。
本記事では、なぜ承諾書が必要なのか、その法的根拠から具体的な取得方法、注意点までを専門家の視点で分かりやすく解説します。
目次
電子契約の承諾書は必須?建設業法が求める「事前承諾」の意味
建設工事の請負契約を電子化するには、事前に相手方の「承諾」を得ることが建設業法で義務付けられています。これは、ITに不慣れな注文者を一方的な電子契約から保護するためのルールです。
重要なのは、特定の「承諾書」という書式が必須なのではなく、承諾を得るという行為そのものです。承諾は書面やメールなどで得ることができ、その前に利用する電子契約システムの種類や内容を相手に示す必要があります。この承-諾の記録が、後のトラブルを防ぐ重要な証拠となります。
もし事前承諾なしに電子契約を結んだ場合、書面交付義務を定めた建設業法第19条違反と見なされ、監督処分の対象となるリスクがあります。ただし、これは行政上の手続き違反であり、契約そのものが民法上ただちに無効になるわけではない、という点も知っておきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
【建設業向け】契約書のひな形まとめ
工事請負契約書やリフォーム・解体・電気工事請負契約書…をはじめ、建設業で使える契約書のテンプレートをまとめた無料で使えるひな形パックです。資料内からお好きなひな形をダウンロードいただけます。
実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
そもそも建設工事の請負契約は電子契約で締結できる?
前述の通り、法律で定められた「相手方の承諾」などの要件を満たせば、建設工事の請負契約も電子契約で締結することが可能です。
その根拠は、2001年(平成13年)に改正された建設業法にあります。もともと建設業法第19条第1項では、契約の当事者が「署名又は記名押印をして相互に交付」することが義務付けられており、書面での契約締結が原則とされていました。
しかし、情報化社会の進展に伴い同条第3項が追加され、注文者(発注者)の承諾を得た上で、一定の技術的基準を満たす電磁的方法(電子契約など)を用いることが例外的に認められるようになりました。
この法改正により、建設業界でもペーパーレス化の道が開かれ、収入印紙代や郵送費の削減、契約締結までの時間短縮といった電子契約のメリットを享受できるようになったのです。こうした電子化の動きは民間工事だけでなく公共工事にも広がっています。特に国の直轄工事などでは電子入札がほぼ100%定着し、電子契約も高い水準で普及していますが、地方自治体、特に市区町村レベルでは導入状況に差が見られるのが現状です。
電子契約の要件については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
電子契約承諾書には何を書くべきか?
建設業法(施行規則第13条の5)は、相手方の承諾を得る前に、事業者が示すべき事項を法的に定めています。これに加え、実務上のトラブルを防ぐために明確にしておくべき推奨項目があります。
承諾前に相手方へ示すべき種類・内容
法律が事業者に義務付けているのは、以下の2点を相手方に示すことです。
- 電磁的措置の種類(例:〇〇という電子契約サービスを利用する、など)
- ファイルへの記録の方式(例:PDF形式で記録する、など)
トラブル防止のために追加すべき推奨項目
上記の必須要件に加え、以下の項目も書面やメールで明確に合意しておくことで、「言った言わない」といった実務上のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 対象となる工事案件名
- 承諾の意思表示を求める明確な文言
- 承諾した日付
- 注文者の氏名・名称
- 電子交付を行うメールアドレスや担当者
電子契約利用の承諾書(同意書)はどのように取得する?
相手方からの承諾は、書面、電子メール、または電子契約システム上の機能など、承諾の意思が記録として残る方法で取得します。
国土交通省の「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」でも特定の方法に限定されてはおらず、実務上は複数の方法が認められています。円滑に承諾を得るための具体的なステップと方法を見ていきましょう。
ステップ1. 相手方への事前説明と合意形成
まず最も重要なのは、なぜ電子契約を導入したいのか、相手方にとってどのようなメリットがあるのか(例:手続きの迅速化、書類保管の負担軽減など)を丁寧に説明し、理解を得ることです。操作に不安がある相手方には、利用する電子契約サービスの使い方を簡単にレクチャーするなど、丁寧なサポートを心がけましょう。
ステップ2. 承諾の取得
相手方のITリテラシーや状況に合わせて、最適な承諾の取得方法を選択します。主な方法には、以下の3つがあります。それぞれの特徴を比較しました。
| 取得方法 | メリット・デメリット | おすすめの場面 |
|---|---|---|
| 書面 | 【メリット】 最も丁寧で確実性が高い
【デメリット】
|
|
| 電子メール | 【メリット】
【デメリット】
|
|
| 電子契約サービス | 【メリット】
【デメリット】
|
|
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
方法1. 書面で承諾書を取得する
「電子契約利用承諾書」というタイトルの書面を作成し、必要事項を記載の上、相手方に署名または記名押印をしてもらいます。最も確実で丁寧な方法です。特に、今後の継続的な取引全体で電子契約を利用したい場合は、最初に包括的な承諾書を取り交わしておくのが効率的です。
方法2. 電子メールで承諾を得る
承諾を依頼するメール本文に、どの契約をどの電子契約サービスで締結したいのかを明記し、相手方に同意する旨を返信してもらうことで、承諾の記録を残します。個別の契約ごとに承諾を得る場合など、迅速に対応したい場合に有効な方法です。
【メール文例:承諾を依頼する場合】
件名:【株式会社〇〇】工事請負契約の電子化に関するご承諾のお願い 株式会社△△ 〇〇様 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 株式会社〇〇の〇〇です。 この度、弊社では契約業務の迅速化と効率化のため、電子契約サービス「〇〇サイン」を導入いたしました。 つきましては、先日お打ち合わせいたしました「〇〇邸新築工事請負契約」につきまして、同サービスを利用した電子契約にて締結させていただきたく、ご承諾いただけますでしょうか。 本メールへの返信にてご承諾の旨をお知らせいただけましたら幸いです。 大変お手数ではございますが、以下のいずれかをコピー&ペーストしてご返信ください。 【承諾します】「〇〇邸新築工事請負契約」の電子契約での締結に承諾します。 【承諾しません】 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
方法3. 電子契約サービス上の同意取得機能を活用する
近年の電子契約サービスには、契約書を送信する前に、相手方が電子契約の利用に同意するチェックボックスをクリックしなければ先に進めない機能が搭載されているものがあります。
この機能は承諾記録の一方法となり得ますが、ただチェックさせるだけでは不十分な場合があります。建設業法施行令で定められた、利用する電子契約システムの種類や記録方式といった「電磁的措置の種類・内容」を相手方が確認した上で同意する、というプロセス全体の設計が不可欠です。
承諾書取得と電子契約導入において注意すべき6つのポイント
1. 技術的基準を満たすシステムの選定
相手方の承諾を得るだけでなく、利用する電子契約システムが建設業法施行規則で定められた、以下の技術的基準を満たしていることが必須です。
- 見読性:PC等で明瞭に確認・印刷できること
- 原本性:改ざんされていないことを確認できること
- 本人性:契約当事者本人が締結したことを確認できること
信頼できる事業者が提供する電子契約サービスを選びましょう。
2. 法律で定められた電子交付の方式の理解
相手方の承諾を得る際には、どのような「方式」で契約書を電子交付するのかを明確に伝えることが望ましいです。建設業法施行規則(第13条の4第1項)では、主に以下の方式が定められています。
- 第1号イ:電子メールを利用する方法
- 第1号ロ:ファイル転送サービスやクラウドサービスなどを利用する方法(非対面)
- 第1号ハ:対面でクラウドサービスなどを利用し交付する方法
- 第2号:コンパクトディスク等の電磁的記録媒体を交付する方法(CD-ROMやUSBメモリなど)
実務上は、電子メールやクラウドサービスを利用する方法(第1号イ・ロ・ハ)が広く利用されていると考えられます。これらを正しく理解し、どの方式を利用するのかを事前に明確にしておくことが重要です。
3. 社内運用のルール化と周知徹底
電子契約は、導入するだけで自動的に効率化されるわけではありません。
- 誰が承諾書を取得し、どこに保管するのか
- 誰が契約書を作成し、送信するのか
- 操作方法がわからない社員へのサポート体制
上記のようなルールを明確に定め、関係者全員に周知徹底することが、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな運用を実現する鍵となります。
4. 相手方への丁寧な配慮
自社にとっては業務効率化につながる電子契約も、取引先にとっては新たな負担になる可能性があります。導入を一方的に進めるのではなく、事前に丁寧な説明を行い、必要であれば操作方法のサポートを行うなど、相手方の立場に立った配慮が、良好な取引関係を維持する上で不可欠です。
5. 承諾書の適切な保管
取得した承諾書は、関連する契約書本体と紐づけ、契約書と同じ法定期間(原則として目的物の引渡しから10年間)保管する必要があります。
その理由は、承諾書が建設業法を遵守した証拠であり、紛失すると契約の有効性や法令遵守の証明が困難になるためです。
保管期間は案件によって5年または10年と異なります。建設業法で定められた主な期間は以下の通りです。
- 原則:5年間 (帳簿および事業に関する図書)
- 10年間となる主なケース:
- 新築住宅の建設工事に関するもの
- 営業に関する図書(工事内容の図面など)
承諾書もこれらに準じるため、自社の案件がどの期間に該当するかを確認することが重要です。
- 保管方法:
いずれの形式であっても、契約書と承諾書が離ればなれにならないよう、紐づけて管理するルールを徹底することが重要です。
6. セキュリティ対策の徹底
電子契約は利便性が高い一方、なりすましによる不正契約や情報漏洩といったリスクも伴います。
- 利用する電子契約サービスのセキュリティ強度
- 自社のアクセス管理やパスワードポリシーの徹底
- フィッシング詐欺などに関する社員への注意喚起
これらのセキュリティ対策を講じることで、安心して電子契約を利用できる環境を整えることが不可欠です。
建設業法を守り、契約書の電子化を円滑に進めるために
建設業法のもとで電子契約を導入する際、注文者からの事前承諾書の取得は、避けて通れない法的な手続きです。この記事で解説したように、相手方への丁寧な説明から始まり、適切な方法(書面、メール、システム機能)での承諾取得、そして必須項目と推奨項目を盛り込んだ承諾書の作成が重要となります。
さらに、取得した承諾書は契約書本体と同様に、法定期間中、適切に保管する義務も忘れてはなりません。
これらは単なる形式的な作業ではなく、取引相手を保護し、信頼関係を築きながら将来の紛争リスクを回避するための、攻めと守りを兼ね備えた重要なプロセスです。一つひとつの手順を適切に踏むことで、建設業法を遵守しながら、真に効率的で安全な契約業務を実現しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
レベニューシェア契約書のリーガルチェックのポイントは?確認事項や注意点を解説
レベニューシェア契約は、売上に応じて報酬を分配する成果報酬型の契約であり、IT業界や新規事業分野を中心に活用が進んでいます。固定報酬ではなく、事業成果に連動した支払いが特徴で、受発…
詳しくみる電子契約の文書管理はどうする?ルールや一元管理の方法を解説
電子契約書を管理する際には、さまざまなルールがあります。企業の法務担当者としては、それらのルールを把握して適切に管理しなければなりません。 本記事では、電子契約の文書管理の要件や重…
詳しくみる注文書や注文請書は電子契約にできる?電子化のメリットや保存要件も解説
注文書や注文請負書はさまざまな方法で電子化が可能です。電子帳簿保存法の改正やコロナ禍をきっかけにデジタルへの移行を試みているものの、よく分からないとお悩みの方も多いでしょう。 この…
詳しくみる不動産賃貸は電子契約もOK!書類の準備や契約の流れ、保管方法を解説
不動産賃貸は電子契約が可能です。宅地建物取引業法の改正により電子化が可能になり、賃貸契約に関する一連の流れをオンラインで完結できるようになりました。これにより、不動産業賃貸の業務を…
詳しくみる電子契約は訂正できる?訂正方法や覚書の書き方を解説
電子契約の導入が進む現代において、締結後の契約内容の誤りや変更の必要性は誰にでも起こり得る問題です。紙の契約書とは異なり、電子契約には特有の訂正ルールが存在します。 この記事では、…
詳しくみる誓約書にも電子契約を利用できる?電子化する方法やメリット・デメリットも解説
誓約書とは、当事者が遵守すべき事項を文書に記した書類です。誓約書でも電子契約の利用ができます。電子契約を利用することで、コストを削減や業務効率化が実現可能です。 本記事では、誓約書…
詳しくみる