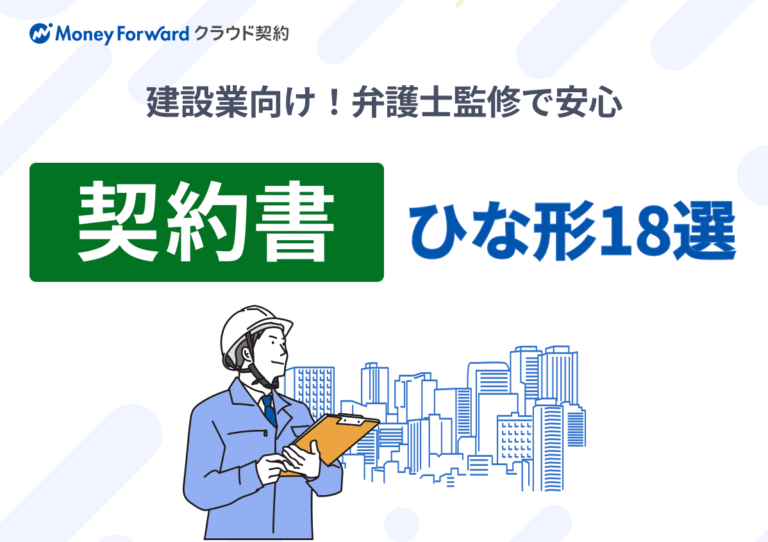- 更新日 : 2025年12月2日
建設業法でも電子契約は利用可能!国土交通省のガイドラインをもとに導入方法を解説
建設業でも電子契約の利用は可能です。国土交通省のガイドラインにより、建設業法における電子契約の技術的要件や適法性が明確化されました。本記事では、電子契約を導入するための手順や注意点、利用できる契約書の種類、システム選定時の確認ポイントなどをわかりやすく解説します。
目次
建設業法改正で電子契約が利用可能に
建設業における契約書の電子化は、2001年の法改正を皮切りに段階的に進められてきました。特に近年では、クラウド型電子契約サービスの法的な位置づけが明確化されたことで、建設業界でも電子契約の実務利用が本格化しつつあります。
2001年 工事請負契約書が電子契約に対応
2001年(平成13年)の建設業法改正により、契約書を紙で交わす従来の方法に加え、電子媒体による締結も可能となりました。法改正によって、新たに建設業法第19条第3項が新設され、電子契約の導入には「見読性」と「原本性」が技術的に確保されていること、さらに相手方の事前承諾を得ていることが条件とされました。
この改正により、電子契約の法的根拠は整った一方で、当初は技術的要件を満たすシステムの導入自体が困難であったことや、業界慣行の影響もあり、すぐには普及に至りませんでした。
2018年 グレーゾーン解消制度によりクラウド型電子契約システムの適法性が明確化
その後、大きな転機となったのが、2018年に行われた「グレーゾーン解消制度」に基づく確認です。これは、企業が新たな事業活動に取り組む際、現行法がどう適用されるか不明な部分について、事前に所轄官庁へ確認できる制度です。
同年、電子契約サービスを提供する事業者がこの制度を活用し、クラウド上で運用される電子契約システムについて、建設業法における適法性を経済産業省から確認を取りました。これにより、クラウド型の電子契約が合法であると明確化され、建設業界における実務活用が一気に浸透しました。
2020年〜2022年 本人確認方法の明確化で電子契約の実務運用が加速
2020年には、建設業法施行規則の一部が改正され、電子契約の技術的要件として「本人性の確保」が新たに加えられました。これは、契約の相手方が真正な当事者であることを技術的に担保する必要があることを意味しており、単なる電子的なやり取りではなく、契約の正当性を支える重要な要素として位置づけられています。
わずか数年後、2022年に再びグレーゾーン解消制度を通じて、本人確認の方法についての国の見解が示されました。詳しくは後述しますが、電子証明書を用いた方法などが「本人性の確保」に該当すると認められるようになりました。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
【建設業向け】契約書のひな形まとめ
工事請負契約書やリフォーム・解体・電気工事請負契約書…をはじめ、建設業で使える契約書のテンプレートをまとめた無料で使えるひな形パックです。資料内からお好きなひな形をダウンロードいただけます。
実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由
多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。
送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。
電子契約サービス比較マニュアル
日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。
電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。
電子契約導入後のよくある悩み3選
電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。
電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。
国土交通省の「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する技術的基準に係るガイドライン」とは
建設業法では、2001年の法改正により、電子契約が一定の条件のもとで認められるようになりました。これに伴い、国土交通省は「建設業法施行規則第13条の2第2項」で定められた技術的要件を具体化するため、「技術的基準に係るガイドライン」を策定しています。
このガイドラインは、建設工事における電子契約の安全性と信頼性を確保するための基準として、電子契約を導入する事業者が準拠すべき項目を示したものです。契約当事者間のトラブル防止や、長期間の契約管理における法的安定性の確保を目的としています。
見読性の確保
電子契約における見読性とは、電磁的に記録された契約内容が、必要なときに即座に画面表示または紙面出力などで確認できる状態にあることを意味します。
ただデータが保存されているだけでは不十分で、視認しやすい形式でなければなりません。また、契約関連の情報を容易に検索・抽出できる機能も推奨されています。
原本性の確保
建設業においては、契約金額が大きく、期間も長期にわたるケースが多いため、契約書の「原本性」が特に重視されます。電子契約においては、公開鍵暗号方式による電子署名や、第三者機関が発行する電子証明書の添付が推奨されており、これにより改ざんの有無や発信者の真正性を技術的に担保します。
また、契約記録を改ざんできない状態で保存し、必要に応じて第三者の証明を受けられる体制整備も望まれます。こうした措置によって、紙の契約書と同等の信頼性を実現しています。
本人性の確保
2020年の改正で追加された「本人性の確保」は、契約を締結する相手が本当にその人物や企業であることを確認するための技術的手段のことです。なりすましや不正な契約リスクを防ぐことが可能になります。
ただし、導入当初は具体的な確認方法が明確ではなく、実務上の混乱もありました。そこで2022年にグレーゾーン解消制度を通じて、複数の本人確認方法が国により正式に認められるようになり、IDとパスワードの組み合わせに加え、電子証明書、タイムスタンプ、印影イメージなどを活用することで、複数の選択肢が現場に提供されることとなりました。
これらの基準は、建設業における電子契約を安全かつ確実に運用していくための土台となるものであり、導入時にはガイドラインの全容を把握したうえで、対応するシステムの選定や社内体制の整備を行うことが求められるでしょう。
国土交通省の「建設工事の電子契約についての解説」とは
国土交通省は、建設業界における電子契約の理解促進と円滑な導入を支援するため、「建設工事の電子契約についての解説」という資料を公開しています。
この文書は、前述の「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する技術的基準に係るガイドライン」の内容を、より実務的かつ具体的に解説したものです。
実務上、目を通しておきたい解説書の1つ
「建設工事の電子契約についての解説」では、ガイドラインに記載されている技術的要件を中心に、電子契約を導入するうえで事業者が理解すべきポイントを丁寧に整理しています。例えば、どのような場合に電子契約が認められるのか、クラウド型システムを使う場合にどんなリスクが想定されるかといった、現場で生じやすい疑問にも配慮した内容です。
また、実際の契約プロセスを踏まえた「運用面での留意点」や「契約の保存義務」「証明方法」についても言及されており、運用・管理面の注意点にも踏み込んでいます。
電子契約導入を検討している事業者は、国土交通省のガイドラインとあわせて必ず目を通しておきたい解説書です。
建設業で電子契約が利用できる主な契約書
建設業界でも、法改正やガイドラインの整備により、さまざまな契約書で電子契約の利用が可能となっています。特に国土交通省の技術的基準を満たしたシステムを利用すれば、書面交付を前提とした契約書類も電子化できるようになりました。ここでは、建設業で実際に電子契約が導入されている主な契約書の種類をご紹介します。
工事請負契約書
工事請負契約書は、元請業者と発注者との間で締結される、建設工事の実施に関する最も基本的な契約書です。2001年の建設業法改正以降、電子契約でも交わすことが可能となっており、現在では多くの企業でクラウド型電子契約サービスが活用されています。電子化することで、契約締結までのスピード向上や印紙税の削減などが期待できます。
工事請負契約書ついて詳しくはこちら
工事下請基本契約書
工事下請基本契約書は、元請業者と下請業者との継続的な取引関係を明確にするための契約書です。単発の工事ごとに契約するのではなく、取引の大枠をあらかじめ定めておくもので、こちらも電子契約が利用可能です。電子化により、双方の確認・保存が容易になるほか、契約書の紛失リスクも減らせます。
工事下請基本契約書について詳しくはこちら
売買契約書
建設資材や機器の購入にあたっては、売買契約書が必要になります。例えば、建材業者や設備メーカーとの間で交わされる契約書も、現在では電子契約で締結することが可能です。紙の契約書に比べて手続きが効率化され、契約状況の管理も一元化できるでしょう。
売買契約書について詳しくはこちら
賃貸借契約書
建設機材や土地、仮設事務所などの賃貸借に用いられる契約書も、一定の要件を満たすことで電子契約が利用可能です。特に、短期間の貸借契約が多い建設業では、電子契約によって書類管理の煩雑さが軽減されるという利点があります。
賃貸借契約書について詳しくはこちら
注文書
注文書は、工事や資材の発注に際して発行される文書で、取引の根拠となる重要な資料です。従来はFAXや郵送でやり取りされていましたが、近年では電子化が進んでおり、クラウド上での発行・保管が一般的になりつつあります。電子契約システムを利用することで、タイムスタンプによる証拠力の強化や、発注・受領の自動化も実現可能となりました。
注文書について詳しくはこちら
建設業で電子契約を導入するメリット
建設業における電子契約の導入は、業務効率の向上やコスト削減など、さまざまな面で大きなメリットをもたらします。特に契約書の量が多く、金額も大きい傾向にある建設業界にとっては、従来の紙ベースの運用から電子契約に切り替えることで、多くの負担を軽減できる可能性があります。
契約締結までの業務を効率化できる
電子契約を導入することで、契約書の印刷、製本、押印、保管といった一連の煩雑な作業が不要になります。契約書をクラウド上で共有・締結できるため、関係者の確認作業もスムーズに進みます。従来は数日かかっていた契約締結作業が、最短で即日完了することも可能となり、社内外のやりとりのスピードも大きく改善されるメリットがあります。
印刷・郵送・保管コストを削減できる
電子契約の導入により、印刷費や郵送費がかからなくなるだけでなく、契約金額に応じて課税される印紙税も不要になります。例えば、1件の工事請負契約で数万円単位の印紙税が発生するケースでは、電子契約への切り替えによりこれをまるごと削減できます。
また、紙の契約書を物理的に保管するスペースや管理コストも不要になるため、長期的に見て経費削減効果は非常に高いといえます。
契約書の改ざんや紛失のリスクがなくなる
電子契約では、電子署名やタイムスタンプによって、契約締結後の改ざんが行われた場合にすぐに検出できます。また、契約書はクラウド上にデータとして保管されるため、紙の契約書のように紛失や劣化のリスクがありません。
さらに、閲覧履歴の記録も可能なため、誰がいつ契約書にアクセスしたかが明確になり、内部統制やコンプライアンス面でも優れた効果を発揮します。
取引先からの信頼性が向上する
電子契約は、安全性や透明性が高いため、取引先に対しても大きな安心感を与えられます。電子署名によって本人確認がなされ、文書の真正性が担保されていることから、契約内容が正確であるという信頼を得やすくなります。
特に、重要度の高い契約においては、こうした信頼性が企業の信用力にも直結するため、ビジネスパートナーとの関係構築にも好影響をもたらすでしょう。
建設業で電子契約を導入する方法
建設業で電子契約を導入するためには、いくつかの段階を踏む必要があります。事前準備を整えたうえで、適切な契約書やシステムを選定し、取引先との同意を得ることが重要です。
電子契約の対象となる契約書を確認する
まずは、電子契約を導入する対象の契約書を明確にしましょう。上述したように、工事請負契約書や下請基本契約書、注文書など、建設業で多く利用される契約書の中には電子契約に対応しているものが多くあります。
ただし、契約書の種類や内容によっては、電子契約が法的に認められない場合もあるため、国土交通省のガイドラインや関連法令を確認することが重要です。
電子契約システムを導入する
電子契約をスムーズに進めるには、建設業法に準拠した電子契約システムの導入が欠かせません。システムは、操作性やセキュリティ、法令対応などの観点から選定する必要があります。
例えば、本人確認機能やタイムスタンプ機能、文書改ざんの防止策が備わっているものを選ぶと安心です。また、クラウド上でのデータ保存や署名履歴の記録が可能なものを選ぶことで、業務効率の向上にもつながります。
取引先の事前承諾書・同意書を取得する
電子契約の実施にあたっては、取引先からの事前承諾を得ることが必要です。電子契約を導入している旨や、対象となる契約書の範囲、電子化に対する同意を文書で取り交わすことで、未然にトラブルを防止することが大切です。必要に応じて「電子契約利用承諾書」などの書式を用意し、署名・合意を取得しましょう。
必要に応じてマニュアルを作成・共有する
社内外で電子契約を円滑に運用するためには、操作方法や手順をまとめたマニュアルを作成し、関係者と共有することが有効です。特に、現場の担当者がシステムを正しく使いこなせるよう、実際の画面を用いた説明やフロー図などを用いてわかりやすくまとめることが求められます。また、社内規定や承認フローの見直しもあわせて検討しておくと、よりスムーズな導入が可能になるでしょう。
建設業の電子契約システムを選ぶときのポイント
建設業において電子契約を導入する際、使用するシステムの選定は非常に重要です。システムの選び方次第で、業務効率や法令対応、セキュリティの確保に大きな差が生まれます。ここでは、建設業の実務に適した電子契約システムを選ぶためのポイントを解説します。
建設業法の技術的基準を満たしているか
建設業で電子契約を行う場合には、建設業法施行規則第13条の2第2項で定められた技術的基準を満たすことが前提となります。見読性、原本性、本人性の3つの技術的要件が求められるため、これらを確実に担保できるシステムであるかを確認しましょう。国土交通省が公表しているガイドラインに準拠しているかどうかも、判断材料になります。
電子帳簿保存法に対応しているか
契約書は長期にわたり保存が必要となる書類の1つです。電子契約を行った文書も、電子帳簿保存法に基づいた保存体制を構築しておく必要があります。
電子帳簿保存法とは、帳簿書類を電子データとして保存することを認め、その際の保存要件を定めた法律です。契約書の真正性や保存性が担保されており、税務署への提出や監査時にも問題なく対応できるシステムを選ぶことを心がけてください。
既存システムとの連携ができるか
電子契約は契約業務だけで完結するものではなく、社内の他の業務システムと連携させることで一層の効率化が期待できます。例えば、文書管理システムや会計ソフト、工程管理ツールなどと連携することで、契約に関連する一連の業務フローを自動化できます。API連携の有無やカスタマイズの柔軟性も確認しておきたいポイントです。
取引先がスムーズに利用できるか
電子契約は双方の合意があってこそ成立するため、相手方の使いやすさも重要な選定基準に含まれます。アカウント登録が不要であったり、スマートフォンからも操作できたりするなど、相手に負担をかけずに署名を行える仕様であれば、導入後のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。
セキュリティ対策が万全か
建設業では、契約金額が高額になりやすく、機密性の高い情報も扱うため、情報漏えいや不正アクセスに対する対策は必須です。データの暗号化、アクセス権限の細分化、多要素認証などのセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。さらに、国内外のセキュリティ認証を取得しているサービスであれば、より信頼性が高いといえます。
建設業における電子契約導入の効果と関連データ
マネーフォワード クラウドが2025年5月に実施した調査(電子契約業務経験者1,563名対象)によると、電子契約システムで便益を感じられるポイントとして「費用削減」(35.6%)と「工数削減」(34.4%)が最も多く挙げられました。費用削減の内訳では「印紙税の不要化」が30.6%で最も重視され、契約金額が大きい建設業界では特に大きな削減効果が期待できます。
印紙税削減と契約業務の効率化を両立
工数削減では「契約書の印刷・製本など手作業の省略」が21.6%、「契約締結までのリードタイム短縮」が19.9%で重視されており、本記事で解説した建設業における電子契約導入により得られる効果と一致しています。建設業では工事案件ごとに高額な契約を締結するため、電子化により印紙税が不要になることで大幅なコスト削減が実現できます。また、印刷・製本・郵送といった作業が不要になり、契約締結までのスピードが向上することで、工事着工までのリードタイムも短縮されます。
電子契約の導入はガイドラインと実務に沿って慎重に進めよう
建設業における電子契約の導入は、業務効率化やコスト削減につながるだけでなく、コンプライアンス強化や取引先との信頼関係の構築にも貢献します。しかし、その運用には建設業法や国土交通省のガイドラインへの適合が求められ、技術的基準や本人確認の手続き、事前承諾の取得など、多くの注意点があります。
導入にあたっては、どの契約書が電子契約に適しているかを確認し、自社と取引先双方にとって使いやすく、かつ法的要件を満たすシステムを選ぶことが重要です。今回の記事を参考に、建設業の実情に即した形で、安心・安全な電子契約環境を整えていきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
建設業で電子契約は利用できる!メリットや注意点、保存について解説
電子契約には多くのメリットがあり、公共工事を含む建設業でも導入が盛んです。この記事では、建設業における電子契約の法的根拠や、グレーゾーン解消制度がどのように関係しているのかに加えて…
詳しくみる電子契約を変更契約するには?書面と電子の変更方法について解説
ビジネスにおいて、一度締結した契約について、後から内容を変更したいという状況は決して少なくありません。特に近年、多くの企業で導入が進んでいる電子契約においても、こうした変更の必要性…
詳しくみるクラウド型の契約書管理システムのおすすめは?メリット、デメリットや比較ポイントを解説
契約書管理をクラウド上で行うと、法改正に自動で対応できる、管理コストを抑えられる、リモートアクセスができるなどのメリットがあります。料金体系・操作性・機能・サポート・セキュリティな…
詳しくみる中小企業のためのリーガルチェックガイド|費用から無料相談、社内でのやり方まで解説
中小企業の経営において、リーガルチェックは事業の成長を守るための重要なリスクマネジメントです。「法律は難しくてよく分からない」「費用がかかりそう」といった理由で、後回しにされがちで…
詳しくみる電子契約の後文・文言の書き方は?ひな形の変更方法や文例を解説
後文(こうぶん)とは、契約書や電子契約の末尾に記載された文章を指します。後文には、契約当事者の情報や契約の成立日、契約締結や保管の方法などが記載されています。電子契約の場合、紙の契…
詳しくみる覚書は電子契約にできる?締結の流れやメリットを解説
契約締結段階で相手方と交わす覚書は、電子契約で行うことができます。紙の書面でやり取りするのと比べて、印刷や郵送などの工程が必要なく、作業時間やコストの削減につながる点がメリットです…
詳しくみる