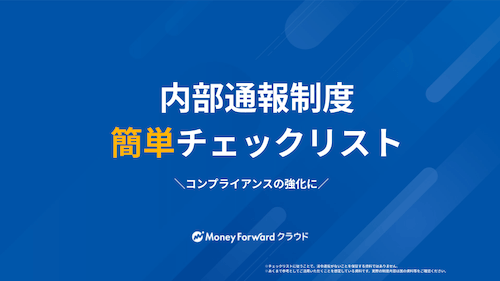- 更新日 : 2025年3月13日
内部通報制度とは?公益通報者保護法の概要や事業者が行うべき対応を解説
内部通報制度とは、従業員や役員などが企業内の不正行為を通報できる窓口を設置し、公益通報した者を守ることで、不正行為の通報を促す制度です。公益通報者保護法の改正により、301人以上の会社では制度を設けることが義務化されました。本記事では、内部通報制度の概要や適切に機能させるポイント、求められる対応などを解説します。
目次
内部通報制度とは
内部通報制度とは、企業内の不正行為などの通報を促すために、従業員や役員などが不正行為を通報できる窓口を設置し、公益通報した者を守る制度です。
企業内の不正行為を通報する従業員などを「公益通報者」といいます。また、内部通報制度の対象となるのは、「通報対象者事実」に該当する場合です。それぞれの定義を解説します。
公益通報者の定義は?
公益通報者の定義は、以下のとおりです。
- 労働者:使用者に関する通報が対象
- 派遣労働者:派遣先事業者に関する通報が対象
- 請負契約などを結んだ業務従事者:発注者にあたる事業者に関する通報が対象
- 役員:役員として所属する事業者に関する通報が対象
なお、労働者・派遣労働者・請負契約などを結んだ業務従事者については、それぞれ退職もしくは業務に従事した後1年以内の者も含めます。
通報対象事実の定義は?
通報対象事実の定義は、以下のとおりです。
- 犯罪行為
- 過料対象行為
- 上記2つにつながる恐れのある行為
犯罪行為とは、公益通報者保護法・政令によってリストアップされた、約460の法律のいずれかに違反するものを指します。また、過料対象行為とは、公益通報者保護法が定めた法令により、過料の対象とされている行為のことです。過料は、法律に違反したペナルティとして支払う金銭です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド
下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。
本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。
2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。
【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選
法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。
法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。
AI契約書レビュー導入で”失敗”しないための秘訣 ワンストップ法務DXで実現する業務効率化とコスト削減
AI契約書レビューの導入は、法務業務の効率化の第一歩に過ぎません。ツールを単体で使っても、「運用が定着しない」「投資対効果が見えにくい」といった課題が残ることが少なくありません。
本資料では、AIレビューの価値を最大化する「ワンストップ法務DX」戦略を解説します。弁護士費用の最適化や業務の属人化解消など、法務部門全体の業務効率化とコスト削減を実現する秘訣を、ぜひダウンロードしてご覧ください 。
公益通報者に認められる権利
公益通報を促すためには、公益通報者が社内の不正行為を通報したことで、会社から報復を受け、解雇や降格などにあうのを防がなければなりません。会社は、公益通報者に対する、以下のような不利益な取扱いを禁止しています。
- 労働者の解雇
- 派遣元事業主との派遣契約の解除
- 上記以外の、事業者による不利益な取扱い
役員については、公益通報をしたことを理由として解任された場合、会社に対し解任によって発生した損害賠償の請求が可能です。
事業者や法務担当者に求められる対応
従業員が301人以上の会社の場合、事業者には社内に公益通報制度を整備する義務が課せられます。
従業員が301人以上の会社が、社内に公益通報制度を整備しないまま放置すると、公益通報者保護法違反に該当します。場合によっては行政からの指導、勧告を受け、それにも従わない場合には20万円以下の過料の制裁を受けるなどのペナルティを受ける可能性があることを押さえておきましょう。
社内の内部通報制度を機能させるためには、法務担当者がその重要な役割を担います。法務担当者の主な業務は、以下のとおりです。
- 内部通報の受付および対応方針の決定
- 通報対象事実に関する調査
- 是正措置・再発防止策の実施
- 関連する社内規程の制定および改定
- 社外窓口との連絡
- 社内への周知および教育
内部通報制度を適切に機能させるためのポイント
内部通報制度を適切に機能させるためのポイントは、主に以下の4点です。
- 調査における独立性を確保する
- 利益相反のリスクを避ける
- 通報者の保護および不利益な取扱いの禁止を徹底する
- 社内・社外の両方の窓口を設置する
各ポイントを解説します。
調査における独立性を確保する
内部通報制度を適切に機能させるには、調査における独立性を確保することがポイントです。調査は、客観的な立場から実施する必要があり、他の役員や従業員の意向によって対応が左右されることを防がなければなりません。
内部通報の担当者に十分な権限を与えるとともに、情報統制を厳密に行うなどの対応が不可欠です。
利益相反のリスクを避ける
不正行為の疑いがあるとされた当事者を、通報対象事実の調査などの業務に関与させることは避けなければなりません。利益相反による癒着が生まれ、適切な調査結果を得ることは困難になるでしょう。
調査などの業務から外す必要があるのは、当事者だけではありません。上司や同僚などの、近い関係にある者も、調査などに関わることを防ぐ必要があります。
通報者の保護および不利益な取扱いの禁止を徹底する
公益通報者を保護し、不利益な取扱いの禁止を徹底することは、内部通報制度の基本であり、もっとも重視しなければならないポイントです。
特に経営陣などの不正行為については、行為者をかばい公益通報者を暗に責めるような雰囲気になることもあります。法務担当者は、行為者が誰であっても公益通報者の保護を徹底することを周知し、ルールが厳格に運用されるように努めなければなりません。
社内・社外の両方の窓口を設置する
社内窓口のみでは、経営陣からの介入や利益相反の排除を行うことに限界があることも少なくありません。内部通報窓口の独立性を高め、さらに不正行為の抑止力を高めるには、社外窓口もあわせて設置することが有効です。社外窓口は、外部弁護士に依頼して設置する方法が一般的といえるでしょう。
事業者が知っておきたい直近の公益通報者保護法改正
2022年6月1日より、公益通報者保護法が改正され、施行されています。この改正により、常時使用する労働者数が301人以上の事業者は、内部通報に適切に対処するための体制整備が義務化されました。なお、労働者が300人以下の場合は努力義務が課せられています。
同改正ではこのほかにも、内部調査に従事する者の情報の守秘義務や、行政機関や報道機関などへの通報を理由とした解雇を無効とする要件の、緩和などが定められました。
参考:消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要
参考:e-Gov法令検索 公益通報者保護法
内部情報制度の概要と必要な対応を理解しよう
内部通報制度とは、企業内の不正行為などの通報を促すことを目的に、従業員や役員が不正行為を通報できる窓口を設置し、通報した者を守る制度です。近年、コンプライアンスへの意識が高まっており、不正行為の早期発見・是正が求められます。
公益通報者保護法の改正によって、従業員301人以上の会社は、社内に公益通報制度を設けることが義務化されました。従業員300人以下の会社であっても、自主的に制度を規定しておくことの意義は大きいと考えられます。本記事を参考に、内部通報制度の概要や必要な対応について、理解を深めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
派遣契約とは?業務委託との違いや3年ルールについて解説
派遣契約とは、派遣会社に雇用される労働者を別企業で労働させる形式の契約です。通常の雇用契約とは異なる法律によって契約をする必要があります。 今回は、派遣契約の基本的な説明をした上で…
詳しくみる2020年施行の実用新案法改正とは?概要や事業者への影響を解説
2020年4月から施行された改正実用新案法により、実用新案権侵害の損害賠償に関するルールが見直されました。同時期に施行された特許法の改正と同じ内容です。本記事では2020年4月施行…
詳しくみる利用規約とは?テンプレートをもとに作り方や例文、同意ボタンの注意点などを解説
利用規約とはサービス提供者の権利義務や、利用者がサービスを利用するにあたって遵守しなければならない内容などを定めたものです。 特にWebやアプリなどでサービスを提供する場合は、サー…
詳しくみる履行不能と契約解除の関係は?解除の要件や通知方法、注意点を解説
契約において債務の履行が不可能となる「履行不能」は、解除や損害賠償の可否、通知方法など、企業法務にとって実務上の重要な論点になります。不可抗力による履行不能と債務者の責任による履行…
詳しくみる新リース会計基準でサブリースはどうなる?会計処理や事業者への影響を解説
新リース会計基準の適用によって、サブリースの扱いはこれまでと大きく変わります。今後は資産や負債の計上が必要となるため、会計処理が大きく変わることに不安を感じることもあるかもしれませ…
詳しくみる広告審査とは?具体的な業務フローや関連する法律を解説
企業が広告を掲出する際には、表現や内容が適切かどうかについて広告審査を行う必要があります。景品表示法・消費者契約法・薬機法・健康増進法・金融商品取引法など、適用される法律の内容を踏…
詳しくみる