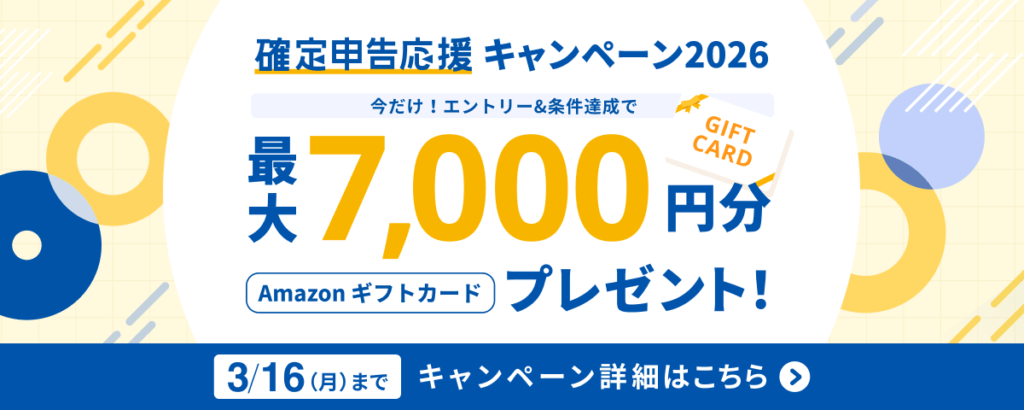- 更新日 : 2025年11月20日
青色申告の節税術は?メリットや法人化との違いを解説
事業を始めたばかりの個人事業主にとって、できるだけ税金の負担を抑えたいというのは共通の悩みです。そんなときに強い味方となるのが「青色申告」という制度です。帳簿の作成や申請手続きには一定の手間がかかるものの、最大65万円の特別控除をはじめ、赤字の繰越、家族への給与を経費にできる仕組みなど、節税に直結するさまざまな優遇措置が用意されています。
本記事では、青色申告の基本から、節税メリット、法人化との節税効果の違いなどを解説します。
目次
青色申告とは
青色申告は、一定の帳簿を作成・保存し、正確な所得申告を行うことで節税効果を得られる制度です。特に個人事業主にとって、正しく活用することで税負担の軽減に大きく貢献します。
青色申告の対象と基礎的な仕組み
青色申告が適用されるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある個人事業主であり、給与所得のみの会社員などは対象外です。対象となるのは、個人事業主です。帳簿としては、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などを作成し、これを基に確定申告を行います。帳簿付けには一定の手間がかかりますが、その分税制上の優遇措置が設けられており、白色申告にはない節税効果を期待できます。
なかでも代表的な優遇が「青色申告特別控除」で、一定の条件を満たせば所得から最大65万円を差し引くことが可能です。複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付が必要となりますが、控除額が大きいため節税効果は高くなります。要件を満たさない場合でも10万円または55万円の控除が受けられる仕組みとなっており、青色申告のメリットのひとつとなっています。
白色申告との違い
白色申告は届出不要で簡易な手続きが可能ですが、節税面での優遇はほとんどありません。たとえば家族従業員への給与は、年間で次のいずれか少ない金額しか控除されません。
- 事業主の配偶者:86万円、配偶者以外:一人につき50万円
- 控除前の事業所得等の金額を(専従者数+1)で割った金額
これに対して青色申告では、事前に届出をすれば家族への給与全額を必要経費に算入でき、所得を効果的に圧縮できます。(ただし、青色事業専従者となるためには一定の要件があります。)
また、事業で生じた赤字についても、白色申告では翌年以降に繰り越しができないのに対し、青色申告では最長3年間繰越可能です(ただし、白色申告でも変動所得の損失額や被災した事業用資産の損失額、雑損失については最大3年間の繰越控除が可能です。)。
このように、青色申告は手続きの労力と引き換えに、幅広い節税の選択肢が得られる制度です。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
この記事をお読みの方におすすめのガイド・お知らせ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
今だけ!確定申告 応援キャンペーン2026
青色申告をされる方に当サイトでご案内中!今だけ&お得な「確定申告応援キャンペーン2026」を実施しております。
まずは無料登録だけしてみて、その後キャンペーンに応募する形でも問題ございません。ぜひお気軽にお試しください。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
青色申告を利用するための条件
青色申告を受けるには、所定の手続きと帳簿整備が求められます。要件を満たして初めて特別控除などの節税メリットが得られるため、制度申請前に手順を正しく理解しておきましょう。
所得税の青色申告承認申請書の提出
青色申告を行うには、最初に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。この申請書は、青色申告を開始する年の3月15日までに提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以降に新たに開業した場合には、開業日から2か月以内の提出が認められています。期限を過ぎるとその年は青色申告が認められず、白色申告となってしまうため注意が必要です。
この申請書には、申告者の基本情報のほか、事業の種類や帳簿の記帳方式などを記載します。申請書の様式は国税庁の公式サイトから入手でき、郵送やe-Taxによる提出も可能です。
複式簿記と帳簿の作成・保存
青色申告の特典を受けるには、日々の取引を「正規の簿記の原則」に基づき記帳する必要があります。これは一般的に複式簿記の形式を指し、仕訳帳から転記した現金出納帳や仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿を使って、正確に取引を記録・整理することが求められます。帳簿は日々記帳し、年度末には貸借対照表と損益計算書を作成することで、所得状況を明確に示す必要があります。
これらの帳簿と財務書類は、翌年の確定申告書に添付し、原則として3月15日までに税務署に提出します。帳簿及び決算関係書類・現預金取引関係書類の保存期間は原則7年間とされており、青色申告者には帳簿保存義務も課せられます。帳簿作成が面倒に思えるかもしれませんが、クラウド会計ソフトなどを活用すれば、記帳作業を効率化することも可能です。
期限内申告が特別控除の条件
青色申告を行う最大のメリットの一つである「青色申告特別控除」は、確定申告書と必要な添付資料を期限内に提出することが条件です。特別控除には10万円・55万円・65万円の3区分がありますが、最大65万円控除を得るためには、複式簿記で記帳し、かつe-Taxで申告するか電子帳簿保存を行っている必要があります。これらの条件を満たさない場合、控除額は55万円または10万円に減額されます。
また、たとえ還付目的の申告であっても、提出が法定期限を過ぎていれば青色申告特別控除については対象外となります。青色申告の効果を最大限に得るには、帳簿の整備とあわせて、申告期限の管理も忘れないようにしましょう。これらの準備を正しく行うことで、青色申告ならではの節税効果をしっかりと享受できます。
青色申告の節税メリット
青色申告は正しく活用すれば、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の負担も抑えられ、個人事業主にとって有利な制度です。ここでは青色申告によって得られる節税メリットを紹介します。
青色申告特別控除で所得を減らせる
青色申告で最も知られている特典が先述の「青色申告特別控除」です。これは、確定申告時に所得金額から最大65万円(または55万円、10万円)を差し引ける制度です。この控除は所得税・復興特別所得税のほか、住民税や国民健康保険料にも影響します。たとえば青色申告特別控除前の合計所得300万円の方が65万円の青色申告特別控除を適用した場合、所得税(税率5%~)と住民税(税率10%)だけで見ても、単純計算で年間約97,500円(所得税32,500円+住民税65,000円)の税負担が軽減されます。実際には国民健康保険料も減額されるため、メリットはさらに大きくなります。10万円控除でも節税効果はありますが、65万円の所得控除を受ける方が圧倒的に有利です。
赤字を繰り越して将来の黒字と相殺できる
青色申告では、事業で生じた赤字(純損失)を翌年以降最大3年間繰り越せます。これを「純損失の繰越控除」と呼びます。たとえば初年度に100万円の赤字が出て、翌年に250万円の黒字が出た場合、翌年の課税所得は差額の150万円に圧縮されます。(ただし、初年度の確定申告において損失申告をして赤字を繰越した場合に限ります。)この差によって、所得税だけでも77,500円もの節税効果が得られると試算されています。
白色申告では、上記のような「純損失」による赤字の繰越は原則認められません。青色申告を選んでおけば、将来の利益に備えて税負担を抑える選択肢が広がります。
家族への給与を経費にできる
青色申告では、「青色事業専従者給与」の制度を使えば、配偶者や子どもなど家族に支払った給与を必要経費として全額計上することが可能です。条件としては、事前に税務署に届出を行い、実際に事業に従事していること、給与が相当な水準であること等が求められます。
白色申告では、先述のように配偶者で86万円、その他の親族で50万円までの定額控除しか受けられません。青色申告を選ぶことで、家族の協力に対する正当な対価を費用として処理でき、課税所得を大きく抑えられます。
貸倒引当金で未回収リスクに備える
売掛金の多い事業では、将来的に回収不能となるリスクがあります。青色申告者は、そのリスクに備えて貸倒引当金を設定し、経費として計上することが認められています。期末時点の売掛金残高の5.5%までを必要経費として計上できるため、事前に税負担を軽減することが可能です。これを「一括評価」の貸倒引当金と言います。
一方、白色申告では一括評価の貸倒引当金の計上はできません。
(しかしながら、白色申告でも、例えば更生計画認可が決定した等の売掛金や貸付金については、貸倒引当金の設定は認められます。これを「個別評価」の貸倒引当金と言います。)
したがって、各種の引当金を計上でき、予防的に対応できる青色申告は、資金繰りや経営の安定を重視する事業者にとって有効な制度といえるでしょう。
少額減価償却資産の特例で設備投資を一括経費化できる
青色申告には、設備投資に関する節税策も用意されています。通常、10万円以上の資産は原則として減価償却処理を行いますが、青色申告者で一定の条件を満たす場合、1個30万円未満の資産については購入した年に全額を必要経費に計上することが可能です。
これを「少額減価償却資産の特例」といい、年間300万円までを上限として適用されます。たとえば利益が大きく出そうな年に、この制度を活用してパソコンや備品などの購入を集中させれば、その年の利益を圧縮でき、税負担を減らせます。
この制度は時限立法(租税特別措置法)ですが、都度更新されています。適用する場合には念のため確認しましょう。活用を検討している場合は、制度の期限や要件を必ず確認しておきましょう。
青色申告と会社設立(法人化)はどちらが節税になる?
事業を行うにあたって、個人のまま青色申告で進めるか、法人化して節税を図るかは、所得額や事業の将来性に応じて検討する必要があります。それぞれに異なる節税効果があり、最適なタイミングでの判断が求められます。
所得が増えると法人化の方が有利になることもある
青色申告には多くの節税メリットがありますが、一定以上の所得になると法人化の方が税負担を抑えられる可能性があります。一般的に、個人事業主の年間所得が800万円を超えると、法人化を検討すべき目安とされています。これは、個人の所得税が累進課税であるため、所得が上がるほど税率も高くなる一方、法人税は一定の税率が適用されるためです。
たとえば個人で所得が900万円の場合、所得税率は33%に達します。対して法人税では、中小企業の場合800万円以下の所得に対して約15%、それを超える部分についても約23.2%の税率にとどまります。そのため、所得が高くなるほど法人の方が有利になる傾向があります。
法人化すると節税項目が拡大する
法人化のメリットは、税率だけにとどまりません。法人では、代表者に支払う役員報酬や将来の役員退職金を損金(所得税における必要経費)として計上することが可能です。これにより、個人にとっての所得を分散させる形になり、全体の税負担を抑えることにつながります。
資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として最長2年間は消費税の納税が免除されます。(ただし、インボイス発行事業者として登録した場合や、1年目の上半期の課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、この限りではありません。)
これにより、創業初期のキャッシュフローを改善しやすくなるという利点があります。経費にできる範囲も広がり、法人用のクレジットカードや通信費なども会社経費として処理しやすくなります。
法人化には新たなコストと義務もある
ただし、法人化にはデメリットや追加のコストも存在します。まず、法人になると健康保険や厚生年金への加入が義務化され、社会保険料の負担が発生します。これは個人事業主の国民健康保険と比べて高額になる場合もあります。
さらに、法人を設立するには登記費用や定款認証費用などの初期費用が必要であり、法人維持には毎期の決算報告や税務申告など、個人事業よりも煩雑な事務処理が求められます。顧問税理士を必要とするケースも多くなり、事務負担や専門家報酬も考慮すべき要素となります。
節税効果の比較は段階的に判断することが賢明
青色申告による節税効果は十分に大きく、事業の初期段階ではまず個人事業主としての運営で十分なケースも多くあります。帳簿付けや申告ルールを守れば、多くの優遇措置が得られるため、最初から法人化するよりも実務的な負担は軽くなります。
そのうえで、所得が増加し、将来的に安定した売上や利益が見込まれるようになってから法人化を検討するという流れが合理的です。節税だけを目的に性急に法人化を進めるのではなく、現在の利益水準や事業の方向性を踏まえて、税理士など専門家に相談しながら最適なタイミングでの判断を行いましょう。
マネーフォワード クラウド開業届は、開業を検討されている方に役立つ「開業時に決めることチェックリスト」を無料で用意しております。
このチェックリストは、開業前にやっておくことをリストアップし、初心者の方にも分かりやすくまとめています。個人事業主か法人(株式会社など)か事業形態に悩まれている方にもおすすめの資料です。 一つひとつ確実にクリアしていくことで、スムーズに事業をスタートできます。
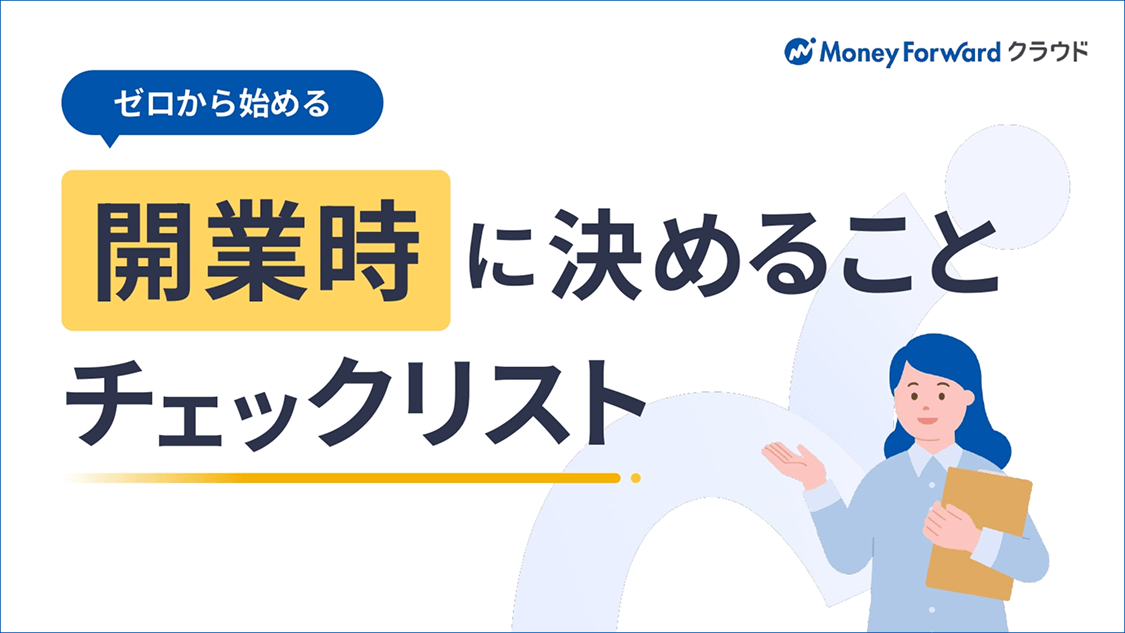
青色申告における電子帳簿保存法対応と控除の関係
青色申告では、正確な帳簿の作成が節税の前提となりますが、近年は「電子帳簿保存法」との関係が強まっています。青色申告特別控除65万円を受けるためには、電子帳簿の保存または電子申告への対応が不可欠です。
青色申告と電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などの国税関係書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。令和4年(2022年)の改正により、事前承認制度が廃止され、制度の利用がより柔軟になりました。これにより、青色申告を行う個人事業主も、要件を満たせば帳簿・決算書・請求書などを紙ではなく電子データのまま保存できるようになります。
ただし、電子帳簿保存を行う場合には、保存要件として「真実性の確保(改ざん防止)」と「可視性の確保(見やすさ)」を満たす必要があります。電子データにタイムスタンプを付与したり、検索機能を確保したりといった技術的な対応が求められます。
控除65万円の適用には電子保存・電子申告が必要
青色申告特別控除の最高額である65万円を適用するには、従来の「複式簿記による記帳+決算書提出」に加え、「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存の実施」が必要となります。これらの条件のいずれも満たさない場合、控除額は55万円にとどまります。
たとえば、複式簿記で帳簿をつけていても、必要書類を添付の上、書面で申告し、帳簿も紙で保存している場合は55万円の控除にしかなりません。一方で、e-Taxで申告するか、訂正・削除履歴の確保など国税庁の定める要件を満たす『優良な電子帳簿』として帳簿をデータで保存していれば、65万円控除が認められます。
そのため、青色申告による節税効果を最大限に活用したい場合は、電子帳簿保存への対応やe-Taxでの申告体制を整えることが大きなポイントになります。
青色申告を活用して、着実に節税を実現しよう
青色申告は、個人事業主にとって有利な節税制度です。特別控除をはじめ、青色欠損金の繰越、家族への給与の経費化、設備投資の即時償却など、幅広い優遇措置が用意されています。制度の利用には事前の申請や帳簿作成、期限内申告など一定のルールがありますが、要件を満たして運用すれば、節税効果は大きくなります。将来的に法人化を検討する場合でも、まずは青色申告をしっかり活用して、堅実な経営と納税管理の基盤を整えていきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所得税の青色申告決算書とは?書き方・種類・提出方法などについて解説!
「青色申告決算書」とは、青色申告の場合に確定申告書に添付して提出する書類です。青色申告決算書には、一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類があります。なお、現金主義用は…
詳しくみる青色申告とは?やり方・対象者を初めてでもわかりやすく解説【個人事業主・フリーランス必見】
会社から独立してフリーランス(個人事業主)となった場合、原則として毎年確定申告を行う必要があります。(※所得が一定以下など、申告が不要となるケースもあります。)確定申告の方法には青…
詳しくみる青色申告特別控除で10万円控除を受ける要件とは?帳簿や書類について解説
青色申告特別控除とは、青色申告だけに認められるメリットです。控除額は最大65万円で、作成する帳簿や申告方法により65万円のほかに55万円、10万円の控除額が用意されています。 65…
詳しくみる青色申告は開業届と青色申告承認申請書の提出が必要!流れや注意点を解説
新たに事業を開始した場合、税務署へ開業届を提出することが必要です。また、税金計算上で有利な取扱いができる青色申告制度を利用したい場合は、青色申告の申請を行い、承認を受けなければなり…
詳しくみる農業の確定申告で青色申告を選ぶべき理由や白色申告との違いは?兼業農家も必見!
農業で生計を立てている農家の所得(収入から経費を差し引いたもの)は、所得の種類でいうと事業所得にあたります。事業所得については青色申告制度を利用でき、青色申告特別控除を受けることが…
詳しくみる【個人事業主向け】青色申告をするメリットは?白色申告との違いとあわせて解説【個人事業主向け】
個人事業主が確定申告をする方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は白色申告に比べて、特別控除が受けられることや青色事業専従者給与を必要経費に算入できる(※届出・要…
詳しくみる