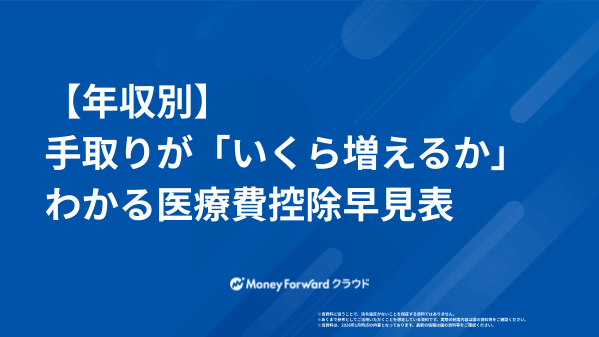- 更新日 : 2026年1月16日
過去の確定申告書の控えを閲覧したい! 紛失して再発行するには?
過去の所得を知りたい場合や、確定申告書の控えを無くしてしまった場合は、確定申告書を提出した税務署に所定の手続きを行うことで、過去の所得情報を入手することができます。
この記事では、過去の申告書を閲覧する閲覧請求の手続きと申告書の再発行である開示請求の手続きについて、詳しく解説していきます。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
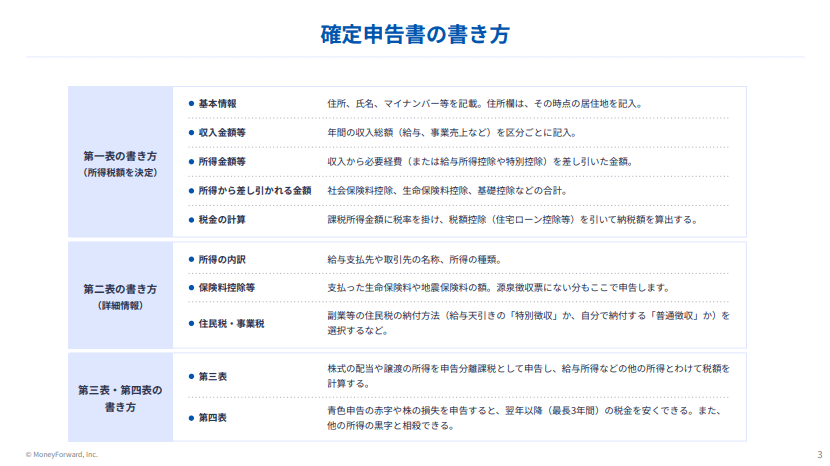
目次
過去の申告書への手続きは3つ!閲覧請求、情報取得と開示請求
過去に提出した確定申告書の情報を知るには、以下の3つの手続きがあります。
閲覧請求
納税者本人または代理人が、税務署の窓口で過去に提出した申告書を閲覧することができます(e-Taxにより提出された申告書も閲覧可)。代理人が閲覧する場合は、委任状が必要になります。閲覧の際にはメモ、写真撮影が可能です。閲覧請求では、紙面の申告書控えをもらえません。
申告書等情報取得サービス
確定申告書等を紙で提出している場合であっても、「申告書等情報取得サービス」で、e-Taxを通じて過去分の申告書等をPDF形式で取得する方法があります。マイナンバーカードが必要となりますが、手数料はかかりません。このサービスでは令和2年以降の直近3年分の、所得税の確定(修正)申告書、青色申告決算書、収支内訳書のみが対象となります。
開示請求
納税者本人または代理人が、郵送または窓口で「保有個人情報開示請求書」を提出し、後日、確定申告の控えを受け取ることができます。所得証明などで申告書の控えが必要な場合の手続きです。
閲覧請求は窓口で行うためすぐに対応してもらえますが、開示請求は確定申告の控えを受け取るまでにある程度の日数(2週間から1カ月が目安)がかかってしまいます。
「申告書」には確定(納税)申告書のほか修正申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書を含みます。
参考: 申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁、申告書等の情報の取得について|国税庁、開示請求等の手続|国税庁
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
閲覧請求の手順
閲覧請求では、確定申告書の控えを発行してもらえませんが「申告書等閲覧申請書」を窓口に提出することで、当日その場で申告書を閲覧することができます。
閲覧請求の流れは以下の通りです。
- 確定申告書を提出した税務署で「申告書等閲覧申請書」を提出する
※代理人が提出する場合は上記に加えて「委任状」が必要です - 申告書を閲覧する
納税者本人が閲覧請求をする際に必要なものは以下の通りです。
- 申告書等閲覧申請書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど)
代理人が閲覧請求をする際に必要なものは以下の通りです。
- 申告書等閲覧申請書
- 委任状
- 印鑑登録証明書(委任状の実印に対するもの)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど)
代理人が閲覧請求をする場合は、納税者本人(委任者)による委任状が必要になります。
この委任状に納税者本人の実印(届出印)が必要であり、この印鑑に対する印鑑登録証明書が必要です。印鑑登録証明書は申請日前30日以内に発行されたものに限られます。
閲覧は原則として書き写しによりますが、閲覧時の写真撮影が可能になりました(デジカメ、スマホ、タブレット又は携帯電話などが利用可)。ただし撮影した画像データを所得証明のために使用することはできません。
当然のことながら、撮影した画像データの取り扱いには十分に注意しましょう。
申告書等情報取得サービスの手順
令和4年5月から開始されたサービスで、e-Taxにログインし、申請を行うことにより直近3年分(令和2年分以降のもの)の申告書をPDFファイルでダウンロードできます。
申告書等の情報取得についての流れは以下の通りです。
- パソコンやスマホなどからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成して送信する
※「申告書等の閲覧を申請する」→「所得税申告書等情報の閲覧」 → 対象年度などを選択 → 電子署名の付与 → 送信 - e-Taxのメッセージボックスに返信が届いたら、添付されたPDFファイルをダウンロードする
申告書等の情報取得で取得できる情報は以下の通りです。
申告書等の情報取得に必要なものは、以下の通りです。
- パソコン、スマホ、タブレット等
- マイナンバーカード
マイナンバーカードは電子署名をするために必要となります。また、代理人や相続人による代理申請はできません。
便利な点としては、紙で確定申告書を提出した場合であってもPDFファイルが取得できるところです。申請後は数日後に閲覧、ダウンロードが可能となります。
参考:
申告書等の情報の取得について|国税庁
紙で申告した方もe‐Taxで所得税申告書等のPDFファイルを取得できます|国税庁
申告書等情報取得サービスの手順はどのようになりますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
開示請求の手続き
開示請求は申告書の控えを再発行してもらう手続きです。
閲覧請求とは違い、申告書の控えを入手することができますが、ある程度の日数(2週間から1カ月が目安)がかかってしまいます。
開示請求の流れは以下の通りです。
- 確定申告書を提出した税務署の窓口または郵送で「保有個人情報開示請求書」を提出する
※代理人が税務署の窓口で提出する場合は上記に加えて「委任状」が必要です - 後日、開示の可否の通知が届く
- 後日、税務署の窓口または郵送で申告書の控えを受け取る
注意点として「保有個人情報開示請求書」は2種類あり、開示する個人情報の内容が保有個人情報か特定個人情報かで違ってきます。保有個人情報と特定個人情報の違いは、マイナンバーの記載の有無です。マイナンバーの記載がある申告書を希望する場合は、特定個人情報用の「保有個人情報開示請求書」を提出しましょう。
さらに、「保有個人情報開示請求書」を提出する際は、再発行を希望する申告書の件数で手数料がかかります(1件につき300円)。
次に開示の可否の通知は、可能な場合は「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」が届きます。不可の場合は「保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)」が届きます。
次に、申告書の受取方法は自分で窓口受取か郵送かを選択することができます。
最後に納税者本人が窓口で開示請求を行う際に必要なものは以下の通りです。
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書
- 手数料分の収入印紙または現金(件数×300円)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど)
また、代理人が窓口で開示請求を行う際に必要なものは以下の通りです。
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書
- 委任状(特定個人情報に係る開示請求用、依頼者の実印要)
- 印鑑登録証明書(委任状の実印に対するもの)
- 手数料分の収入印紙または現金(件数×300円)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなど)
代理人が開示請求をする場合は、納税者本人(委任者)による委任状が必要になります。
この委任状に納税者本人の実印(届出印)の押印があるため、この印鑑に対する印鑑登録証明書が必要です。印鑑登録証明書は申請日前30日以内に発行されたものに限られます。
なお、印鑑登録証明書に換えて委任者本人の運転免許証または個人番号カード(通知カードは不可)等のコピーを委任状に添付することもできます。
最後に補足として、どうしてもマイナンバーの記載がない申告書を取得したい場合は、本人または法定代理人が開示請求を行う必要があるため注意が必要です。
所得証明で気を付けること
源泉徴収票などの所得証明書類がない方は、別途、所得証明を請求する方法があります。しかし、過去分の確定申告書の控えを求められるケースも多々あります。
確定申告書を所得証明に使用する場合は、税務署の受付印がある申告書の控えを保存するように気を付けましょう。e-Taxの場合には電子申請等証明書を残しておきましょう。
確定申告書を郵送で提出する場合は、申告書控えと返信用封筒を同封して提出することで、税務署の受付印がある申告書の控えにすることができます。
住宅ローンや審査の厳しい融資を検討している場合は、特に気を付けましょう。
過去の確定申告書を閲覧等するサービスは3通り!
過去に提出した確定申告に対する、閲覧請求と情報取得そして開示請求について解説しました。
閲覧請求は、税務署の窓口に行った当日に対応してもらえる手続きです。情報取得は、e-Taxで申請を行い、申告書をPDFファイルでダウンロードする新しいサービスです。開示請求は、確定申告書を再発行してもらうため、2週間から1カ月程度かかってしまう手続きです。
特に、開示請求をする場合は、期日までに余裕をもって事前に備えておくことが重要です。
参考:
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁、申告書等閲覧申請書
申告書等の情報の取得について|国税庁
保有個人情報開示請求書 様式1 本人及び法定代理人|国税庁
保有個人情報開示請求書 様式2 本人、法定代理人、任意代理人|国税庁
はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法
確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。
個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。
①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。
②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。
③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。
追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える
有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料
マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典


マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
過去に提出した確定申告書の情報を知るには?
閲覧請求、情報取得、開示請求の2つの手続きが必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
閲覧請求の手順は?
確定申告書を提出した税務署で「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告書を閲覧できます。詳しくはこちらをご覧ください。
所得証明で気を付けることとは?
源泉徴収票などの所得証明書類がない方は、確定申告書の控えが所得証明になることです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
さんきゅう倉田が「国税庁チャットボット」と格闘してみた
確定申告シーズン到来。複雑な申告手続きに頭を悩ませている方も多いと思います。かといって、税理士さんに相談するほどお金に余裕があるわけではないし、税務署に聞きに行くのは恐ろしい。 そ…
詳しくみる「住民税は2年目から」は本当?新卒会社員が知っておきたい税のしくみ
給与所得者の場合、住民税は前年の給与所得に対して課税され、その年の6月から翌年の5月にかけて給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。 したがって、前年の給与所得がない入社…
詳しくみる新社会人の疑問「東京都の住民税額は区によって違う?」「新卒1年目は住民税ない?」
新年度が近づいてきました。この春から新社会人になる方は期待半分、不安半分といったところでしょうか。これからは自分でお金を稼ぎ、資産管理をしなければなりませんが、金融や税金の知識がな…
詳しくみるこれを見れば全てわかる!個人事業主の〇〇は経費にできる?
個人事業主の方が生活や事業で使った費用は、どこまで経費として計上できるのでしょうか? 家賃や生活にかかるお金など、これって経費にできるの?と疑問に感じるものも多いかと思います。 特…
詳しくみるフリーランスが知るべき住民税の基本。元会社員なら「何月に退職したか」がポイント
会社員なら、住民税は基本的にお給料から天引きされます。会社が本人に代わって納税してくれるのであまり気にすることもありません。 一方、フリーランスは当然自分で支払わないといけません。…
詳しくみる「競馬は二重課税」と批判再燃 税理士に聞く「馬券と税金」の不思議なカラクリ
「正直がバカを見る制度」と言われても仕方ないのでしょうか。 先日、競馬や競輪などの公営ギャンブルで当たった1,000万円以上の高額払戻金について、会計検査院が調査したところ、約8割…
詳しくみる