- 更新日 : 2025年1月28日
個人事業主が消費税を払えないとどうなる?リスクと対処法を解説
個人事業主になると、納めなければならない税金の種類が増え、資金繰りの難しさに直面することも珍しくありません。
個人事業主のなかには、消費税を払えない状況に直面している方もいるのではないでしょうか。この記事では、消費税を支払えない場合に伴うリスクや、対策方法、相談先について解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
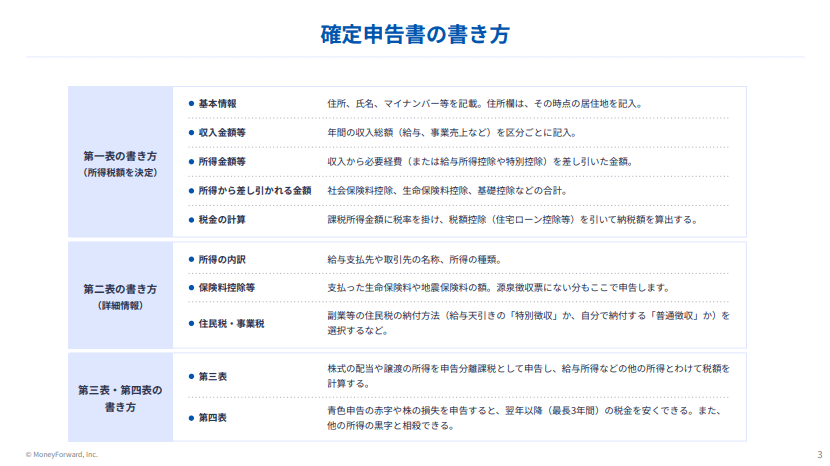
目次
個人事業主が消費税を払えないとどうなる?
消費税を支払えないとさまざまなリスクが発生します。元々の税額に延滞税が加算されたり、身の回りの財産を差し押さえられる強制徴収などに発展する可能性も知っておきましょう。
延滞税がかかる
納付期限をすぎると延滞税が課せられ、元々定められていた税額と併せて納付しなければなりません。延滞税は、納付期限の次の日から発生し、延滞すればするほど税額が増えていきます。
延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月経過以降になると、延滞税の割合がさらに上がることを覚えておきましょう。
- 納付期限の翌日から2ヶ月以内の期間:原則年率7.3%※延滞税特例基準割合+1%と比較し低い方を適用
- 納付期限の翌日から2ヶ月経過以降の期間:原則年率14.6%※特例基準割合+7.3%のいずれか低い方を適用
督促状が送られてくる
税金の滞納が続いている場合は、支払いを促す内容の督促状が送られてきます。
国税通則法の37条では、納税者が納付を完了していない場合、納付期限から50日以内に督促状が発されるとされています。
また、督促状の形式も封書やはがきなどさまざまですが、記載されている内容は同じです。
差し押さえなどの強制徴収
督促状が発された日から10日以内に支払いができない場合は、財産の差し押さえが可能な状態になり、不動産や給与、預貯金などを対象に強制徴収が行われます。差し押さえの対象となる財産は、「金銭的価値を有すること」が条件です。
財産の差し押さえまで発展すると、ある日いきなり生活費がなくなることも考えなければなりません。最悪の事態を避けるためにも、督促状が届いた時点で事態の重さを受け入れ、対応するのがいいでしょう。
加算税の種類
加算税とは、正しい税額ではない内容を申告した場合に課税されるペナルティの一種で、以下の4種類に分かれています。
| 名称 | 課税要件 |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告・更正があった場合 |
| 無申告加算税 |
|
| 不納付加算税 | 源泉徴収等による国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合 |
| 重加算税 | 仮装隠蔽があった場合 |
参照:加算税の概要|財務省
自分で申告内容の誤りに気づいた場合、税務署から指摘を受ける前に申告すれば税率が軽減されます。
これらの加算税の賦課決定を受けた人は、賦課決定通知書が発された日の翌日から1月以内に加算税を納付しなければなりません。また、重加算税のうち2024年(令和6年)1月1日以降に法定申告期限が到来するものについては、最大加算税が20%から30%に引き上げられた点にも注意が必要です。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
個人事業主が消費税を払えない時はどうする
ここからは、消費税を払えない場合の相談先や対応方法、支払いの猶予が認められるケースについて解説します。
税務署に相談する
前述した通り、税金を滞納するとさまざまなリスクが発生します。事業をする上で資金繰りがうまくいかなくなり、消費税を払えなくなる可能性も出てくるでしょう。その場合は、早めに所轄の税務署に相談してください。
所轄の税務署がわからない場合は、国税庁のこちらのページを参考にお近くの税務署を調べ、直接税務署に直接出向くか、電話で問い合わせをしましょう。
相談する際は、納税の意思があることを伝えた上でアドバイスを受けることが大切です。早めに税務署に相談し、対応方法について助言をもらいましょう。
消費税の支払い猶予が認められる例
消費税を期限までに支払えない場合、税務署に申請することで受けられる「猶予制度」が存在します。この制度は、原則として1年以内の期間に限り、分割して納付できるようになるというものです。以下の条件に該当する場合は、猶予制度の利用を検討しましょう。
- 納税者ご本人がその財産について、災害等を受け、又は盗難に遭った。
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった。
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした。
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
ほかにも、猶予制度を受けるためには、「申請があること」「原則として、担保の提供があること」なども含まれます。
個人事業主が消費税を払わなくてもよい場合
個人事業主が消費税を払わなくていいケースは以下のようなものがあります。
基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円以下
免税事業者か課税事業者の判断は、基準期間と特定期間の課税売上高で決まります。あらためて説明すると、個人事業主における基準期間と特定期間の違いは以下の通りです。
- 基準期間:その年の前々年
- 特定期間:その年の前年の1月1日〜6月30日までの期間
また、免税事業者でいるためには以下の2つの条件をどちらも満たさなければなりません。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 特定期間の課税売上高か給与等支払額のいずれかが1,000万円以下であること
2に関しては、課税売上高か給与等支払額どちらかが1,000万円以下であれば要件を満たしたことになります。
開業から2年間
個人事業主の場合、開業から2年間は免税事業者となり、消費税の納税は免除されます。個人事業主が課税事業者になるには、課税期間の基準期間(前々年の1月1日から12月31日まで)の課税売上高が、1,000万円を超える場合に限られます。
前々年の実績をもとに算出されているため、前年・前々年に売上のない開業から2年間は消費税が免除されるという仕組みです。
消費税の免税事業者
免税事業者は、消費税の納税義務がありません。前述の通り、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者になる必要があります。
消費税が10%の場合、仮に110万円の売上があったら、10万円は消費税という計算になります。課税事業者は10万円分を納税しなければなりません。一方、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば納税する必要がないのです。
適格請求書発行事業者に登録していない場合
個人事業主が適格請求書発行事業者へ登録すると課税事業者になります。適格請求書(インボイス)を交付するためには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。
登録自体は任意ですが、登録している場合は消費税の免除がされないことを覚えておきましょう。
個人事業主が消費税を多く払いすぎた場合
課税事業者の個人事業主は、支払った消費税が受け取った消費税より多い場合、要件を満たせば消費税が還付されます。免税事業者の方は消費税を納税していないので対象ではありません。
消費税の計算方法には、「原則課税方式・簡易課税方式・2割特例」の3つありますが、還付の対象は「預かった消費税 ー 支払った消費税」の式で計算される原則課税方式の場合のみです。
還付を受け取るまでの方法は以下の通りです。
- 消費税還付の申告書を作成する
- 消費税の還付申告についての明細書を作成する
- 申告期限内に税務署長へ必要書類を提出する(還付申告は任意のため、期限後申告であってもペナルティは生じない)
- 還付金を受け取る
申告期限は、個人事業主と法人で違います。法人が「課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内」なのに対し、個人事業主は「翌年3月31日」なので、混同しないように注意しましょう。
個人事業主が支払う税金の種類
個人事業主が払う税金の種類は数種類あります。自分の状況に合わせて該当する税金を把握しておきましょう。
1.所得税
所得税とは、個人の課税所得にかかる国税です。課税所得の金額は、「収入-経費-所得控除」の計算式をもとに算出されます。所得控除とは、納税者個人の事情を考慮し、所得から定められた項目の金額を差し引ける制度のことで、医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除など15種類あります。
算出した課税所得に税率を適用したものが所得税です。所得税の金額は以下の表の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円~194万9,000円 | 5% |
| 195万円~329万9,000円 | 10% |
| 330万円~694万9,000円 | 20% |
| 695万円~899万9,000円 | 23% |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% |
| 4,000万円~ | 45% |
2.住民税
住民税とは、居住する地域に納める地方税です。納められた税金は、各地方自治体で住民が受けられる、消防・社会福祉・学校教育などの行政サービスを維持するために使われています。
住民税は、都道府県に納める「道府県民税(都民税)」と、市区町村に納める「市町村民税(特別区民税)」で構成されています。住民税には、個人住民税と法人住民税の2つがあり、個人事業主が払うのは個人住民税です。
また、住民税の額は、所得金額にかかわらず一定額の「均等割」と、前年(1月1日〜12月31日)の所得金額に税率を掛け合わせて算出する「所得割」の2つで構成されています。居住地域によって税率が異なるので、詳細を知りたい場合は各自治体に確認しましょう。
3.消費税
消費税とは、ものやサービスを購入した際に納める国税です。消費税が発生する取引のなかには、地方消費税も含まれています。
個人事業主が納税義務を負う必要があるのは、売上が規定額を満たし、課税事業者になった時です。前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合、もしくは、前年の上半期の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者になり消費税を支払わなければなりません。
参考:消費税のしくみ|国税庁
4.個人事業税
個人事業税とは、地方税法によって定められている70の法定業種に該当する事業を営み、事業所得が290万円以上の個人事業主に課税される地方税です。
漫画家・ライター・プログラマーなど一部の業種以外は、ほとんど法定業種に含まれています。また、税率は都道府県ごとに違い、業種によっても異なります。東京都の場合、第1種事業(5%)、第2種事業(4%)、第3種事業(各種士業は5%・あんまやマッサージなどその他の医業に類する事業は3%)と分かれています。
参考:個人事業税|東京都主税局
5.国民健康保険税
国民健康保険税とは、個人事業主が加入する国民健康保険料です。国民健康保険税は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料」で構成されており、全世帯が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて計算される「所得割」を合算した額が課税されます。
6.固定資産税・都市計画税
固定資産税は、固定資産(住宅・店舗・倉庫・土地など)を持っている場合に課せられる地方税です。お住まいの市町村に納税し、納められた税金は公共の道路や公園の整備などに使われます。(東京都23区内の場合は、東京都に都税として納税する)
都市計画税とは、都市計画法で指定されている「市街化区域(街の整備が進んでいる、またはこれから整備される計画のある区域)」に、家屋や土地を保有している場合に課せられる税金です。この区域に不動産を保有していると、固定資産とは別に都市計画税がかかります。
固定資産税の課税標準額に税率を掛けて税額が算出されます。
参考:固定資産税|総務省
参考:都市計画税|総務省
消費税が払えないとわかった時点で税務署に相談しよう
個人事業主が消費税の支払いが滞ってしまった場合、延滞税の加算や財産の差し押さえなど、大きなリスクに発展してしまいます。万が一、消費税が払えないとわかった時は速やかに税務署に相談し、納税の意思があることを伝えた上で対処法の助言をもらいましょう。
個人事業主は、納める税金の種類が多いのも特徴です。消費税のほか、所得税や固定資産税など、発生する税金の種類を日頃から把握し適切に管理しましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
賃上げ促進税制の個人事業主向けガイド!税金の控除や改正を解説
賃上げ促進税制とは、賃上げを実現した法人・個人事業主の法人税・所得税を優遇する制度です。2024年度の税制改正により要件などが見直されたため、この機会に理解を深めましょう。 この記…
詳しくみる【個人事業主向け】出金伝票の書き方とは?勘定科目や注意点、保存について解説
個人事業主は、事業を行ううえで必要な出費があった際に出金伝票を書く場合があります。出金伝票は現金を支出したときに記載する伝票で、勘定科目と支出額を記載することで、事業に必要な支出の…
詳しくみる家内労働者とは?個人事業主との違いや税務・確定申告の注意点を解説
企業に属さず自宅で作業を行う「家内労働者」は、外から見ると個人事業主と似た働き方に見えるかもしれません。しかし実際には、法律上・税務上での取り扱いや制度面で明確な違いがあります。 …
詳しくみる薬代は経費になる?個人事業主が知っておくべき申告のルールや控除を解説
個人事業主が薬局で購入した薬代や衛生用品の費用を経費にできるのかは、多くの人が疑問に感じるポイントです。その答えは「場合による」であり、支出の内容や目的によって取り扱いが異なります…
詳しくみる個人事業主の報酬未払いはどう回収する?対応方法や確定申告の注意点を解説
フリーランスや個人事業主として活動していると、納品後に報酬が支払われない「未回収トラブル」に直面することがあります。こうした未回収の報酬は、事業の資金繰りに直接影響を与えるだけでな…
詳しくみる個人事業主が業務改善助成金を活用するには?要件・助成額・申請の流れを解説
個人事業主にとって、従業員の雇用や設備投資は事業運営の大きな課題です。そんな中、厚生労働省が実施する「業務改善助成金」は、従業員の賃上げと生産性向上を支援する制度として注目されてい…
詳しくみる



