- 更新日 : 2026年1月23日
個人事業主が何年も確定申告してないとどうなる?ペナルティや対処法を解説
個人事業主で、何年もの間確定申告をしていない人もいます。納めるべき所得税がある場合は、確定申告の提出が必要です。実際に確定申告をずっとしていなかった場合、どのような問題が発生する可能性があるのでしょうか。何年も確定申告をしていない個人事業主へのペナルティや対処法を解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
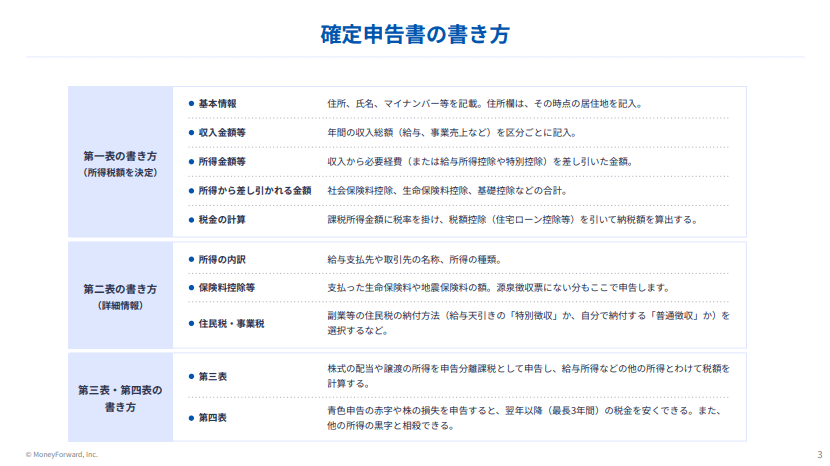
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主が何年も確定申告してないとどうなる?
個人事業主として開業したものの、何年も確定申告をしていないケースも存在します。そもそも、確定申告が必要かどうかわからないという場合もあるでしょう。何年も確定申告をしない場合、どのような問題が発生する可能性があるのでしょうか。主な問題点を紹介します。
各種控除が受けられない
所得税の計算には、所得金額から差し引ける「所得控除」や所得税額から直接差し引ける「税額控除」があります。これらは、申告者の状況などを加味して設けられている項目です。
個人事業主でも、業務委託元から所得税の源泉徴収を受けていたり、個人事業以外の所得で源泉徴収を受けていたりする場合は、確定申告をしないことで各種控除(所得控除や税額控除)を適用できないデメリットがあります。結果として、本来よりも多く所得税を納めてしまっている可能性があります。
住民税の申告が必要になる
住民税の申告とは、1月1日時点で住民登録をしている自治体に対して、前年度の所得を申告する手続きです。住民税の申告は、収入がなかったり、赤字により所得が発生していなかったりする場合でも必要です。
ただし、所得税の確定申告書を提出する人や公的年金等の雑所得のみの人などは、住民税の申告対象から除外されています。所得税の確定申告をすることで、住民税の申告も完了するためです。確定申告をしない場合は、住民税の申告が必要です。申告をしない場合は、国民健康保険料が正しく算定されないなどの問題が発生します。
青色申告特別控除が受けられない
所得税の確定申告において、青色申告を選択している事業者は、青色申告特別控除の特典を受けられます。青色申告特別控除は、不動産所得または事業所得が生じる事業を営む事業者が適用できる制度です。
不動産所得または事業所得の金額から、最大55万円(電子申告または電子帳簿保存の要件を満たす場合は最大65万円)を差し引いて所得の計算ができます。帳簿付けにおいて現金主義を採用している場合は、最大10万円の控除を受けられます。
青色申告特別控除の要件は、青色申告をしていることです。確定申告をしていない場合は、適用の対象外となります。
無申告加算税、延滞税、重加算税などの追徴課税がある
行政制裁として、申告義務が適正に行われなかった場合には、加算税が課されることがあります。
本来納めるべき所得税があるにもかかわらず、申告期限までに確定申告をしなかったときに課されるのが「無申告加算税」です。本税(本来納めるべき税金)に対して、5~30%の加算を受けます。仮装隠ぺいがあるなど悪質な場合は、無申告加算税に代えて40%の重加算税を課されることがあります。
延滞税は、税金が期限までに納付されない場合に課される利息のようなものです。納めるべき税金があるにもかかわらず確定申告をしないときは、上記の加算税に加えて、延滞税も加算されます。
国民健康保険の軽減が受けられない
国民健康保険に関して、所得が少ない世帯に関しては、2割、5割、または7割の軽減措置が設けられています。いずれも、法令により定められた所得基準を下回る世帯が適用できる制度です。
確定申告を行わないでいると、所得不明の状態となることから、国民健康保険料を正しく計算できません。実際に基準を下回っていたとしても、自治体側で所得を把握できないため、国民健康保険料の軽減を受けられません。
給付金や助成金が受けられない
個人向けの給付金や助成金、手当については、非課税など、所得金額が支給の判定基準になっているものがあります。所得を基準にした給付金などについては、国民健康保険料の軽減措置と同じく所得不明という理由で受けられない可能性があります。
社会的信用が低下する
確定申告をしないと、所得不明になるため、所得証明書を取得できません。取引や手続きなどで所得証明書の提出を求められた場合、提出できないことで、社会的信用が低下してしまうおそれがあります。
銀行融資が受けられない
確定申告をしないと確定申告の控えなども手元にないことになるため、公的に所得を証明できなくなります。所得不明であることから、金融機関も融資額の回収可能性などを判断できず、融資の申込みをしても受けられない可能性があります。
賃貸契約や住宅ローン契約を結べない
確定申告をしないと収入や所得を証明できる材料がありません。銀行融資が受けられない理由と同じ理由で、不動産の賃貸契約や住宅ローンの契約を結べない可能性があります。
刑事責任を問われる可能性がある
確定申告を正当な理由なしに提出しないでいると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。また、悪質な脱税と疑われ、強制調査により有罪になった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
個人事業主の無申告者はどのくらい?
国税庁の「令和6事業年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税無申告者の調査状況は4,812件(前年は5,274件)、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円(前年は2,590万円)でした。追徴課税の総額は252億円(前年は220億円)となっています。
一方、消費税の追徴課税に関して、令和6事業年度は165億円(前年は214億円)となっています。
個人事業主が何年も確定申告をしていないとなぜバレる?
何年も確定申告をしてこなかった個人事業主が、あるきっかけで無申告だったことが税務署にバレるケースがあります。無申告が発覚する主なパターンを紹介します。
取引先の支払調書で発覚するケース
支払調書とは、報酬の支払者が税務署に提出する法定調書の一種です。報酬・料金・契約および賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などがあります。支払調書は、取引先と無申告の個人事業主との報酬の受け渡しを裏付ける書類です。取引先から税務署に提出される支払調書と対象者の所得との整合性が取れず、無申告が発覚することがあります。
国税局や税務署の税務調査で発覚するケース
税務署や国税局は、法人や個人事業主の一部について税務調査を実施しています。税務署や国税局が、実際に保管されている帳簿などの書類を確認して、不正などがないか確認する手続きです。直接的に税務調査を受けなかったとしても、取引先経由で税務調査を受けることになり、無申告が発覚するケースがあります。
第三者の税務署への告発で発覚するケース
国税庁のホームページには、匿名で情報を提供できるページがあります。取引先などを経由していなくても、第三者からの情報提供で無申告が発覚するケースがあります。
個人事業主の確定申告に時効はない?
確定申告には、時効があります。一般的な期間は、3年もしくは5年です。悪質な場合は、時効が7年に延長されます。時効になった場合、過去にさかのぼって無申告の税金は課されないことになりますが、時効になる可能性はほとんどないとされています。つまり、確定申告が無申告の状態にある場合は、早期に申告をすることが重要です。
個人事業主の年収が160万円以下や赤字の場合は?
「160万円の壁」という言葉がありますが、これは給与所得者に該当する場合に関係のある言葉です。アルバイトやパートなどで年間の収入が160万円以下の場合、所得税が発生しないことになります。給与所得控除の下限65万円+基礎控除額95万円の合計が160万円になるためです。
ただし、160万円の壁が適用されるのは、給与所得者に限った話です。事業所得などに該当する個人事業主については、160万円の壁はありません。関係してくるのは基礎控除95万円です。事業所得のある個人事業主については、160万円ではなく、事業所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が基礎控除を下回る95万円以下、もしくは基礎控除以外の所得控除の合計額が所得金額を上回る場合に、確定申告をしなくても済みます。
なお、基礎控除以下で所得金額が0円になる場合、または事業所得が赤字になる場合で、納めるべき所得税額がない場合は、確定申告の必要性はありません。ただし、青色申告を選択している場合は、確定申告をしないことで赤字の翌年以降の繰り越し控除ができなくなるため、注意しましょう。
個人事業主が何年も確定申告してない場合の対処法
個人事業主が何年も確定申告をしてこなかった場合の対策について解説します。
税務署に自主的に相談する
確定申告が必要であるにもかかわらずしなかった場合の罰則として、無申告加算税があると説明しました。無申告加算税は、税務署からの調査の通知を受ける前または受けた後に、自主的に期限後申告をした場合は低い加算割合が適用されます。税務調査を受けることで多額の追徴課税を課されないようにするためにも、無申告の状態に気付いた時点で、税務署に自主的に相談することをおすすめします。
税理士に相談する
確定申告をしようと考えていても、どのようにすればよいかわからない場合は、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士に依頼することで、確定申告に対する不安を取りのぞけるほか、正確な申告を期待できます。
過去分の確定申告をする
確定申告のやり方自体に不安がない場合は、自主的に過去にさかのぼって無申告の時期から確定申告をする選択肢もあります。過去分をまとめてする場合は計算ミスなども生じやすくなるため、確定申告ソフトなどを活用するとよいでしょう。
何年も確定申告をしていない個人事業主は早急な対策が必要
個人事業主で、何年も確定申告をしていないケースもあります。ただし、赤字が続いていたり、所得が極端に低い時期が続いていたりするなどで納めるべき所得税がない場合は、問題ありません。しかし、納めるべき所得税があるにもかかわらず無申告の状態が続くと、さまざまな問題が生じる可能性があります。確定申告が必要な個人事業主については、税務署に相談するなど早急な対策が必要です。
個人事業主の確定申告は以下の記事で解説しています。この記事を読んで確定申告をする人は参考にしてください。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主の黒ナンバーに任意保険は必要?補償内容・費用・選び方を解説
黒ナンバーを使って軽貨物運送事業を行う個人事業主にとって、任意保険の選び方は事業継続の重要なポイントになります。本記事では、黒ナンバーの基本から任意保険の必要性、補償内容の選び方、…
詳しくみる消費税と所得税は二重課税になる?個人事業主が誤解しやすい税の仕組みを解説
個人事業主の間でしばしば疑問に上がる「消費税と所得税の二重課税」問題。売上に含まれる消費税まで所得税の対象になっているのでは、と不安を感じたことはありませんか? 本記事では、消費税…
詳しくみる個人事業主とは?定義やメリット、開業方法・フリーランスとの違いを解説
個人事業主とは、法人ではなく個人で事業を営む自営業者を言います。個人事業主として事業を新たに開始した場合、原則として1ヵ月以内に管轄の税務署へ開業届を提出する必要があります。 この…
詳しくみる個人事業主は住宅ローンの審査に通らない?通りやすくなるポイントも解説
個人事業主は収入の安定性が低いと見られる可能性があるため、住宅ローンの審査が厳しいと言われているのが現状です。 本記事では、個人事業主が住宅ローンに通りにくいと言われている理由や金…
詳しくみる個人事業主の所得税が0円になるのはどんなとき?所得税額の計算方法や確定申告について解説
事業の赤字が膨らんだ場合など、個人事業主の所得税が0円になることがあります。所得税が発生しない場合であっても、確定申告は必要になるのでしょうか。個人事業主の所得税や住民税、個人事業…
詳しくみる個人事業主の厚生年金の代わりは?種類や節税、確定申告の手続きを解説
個人事業主は厚生年金には加入できません。厚生年金は会社員のための制度であるためです。ですが、代わりとなる制度が多く用意されているため、活用することで年金の不安を解消できるでしょう。…
詳しくみる



