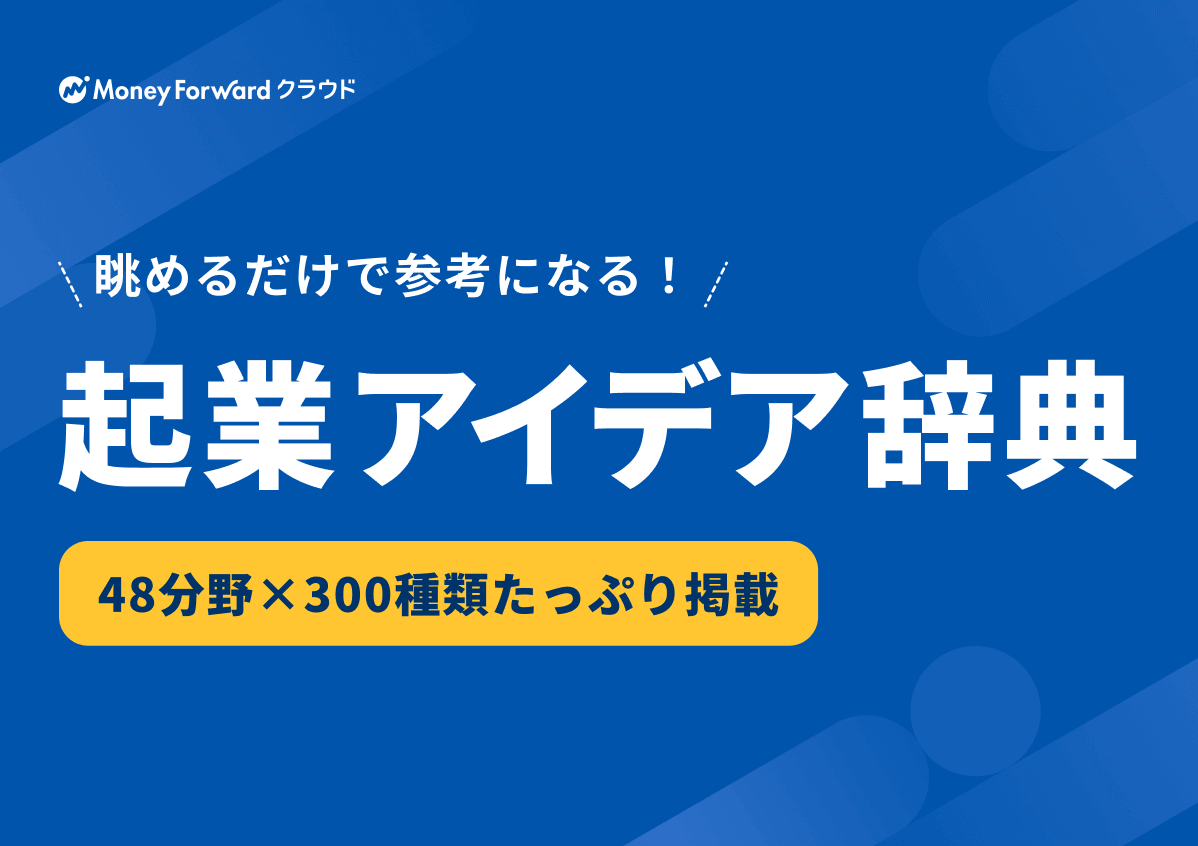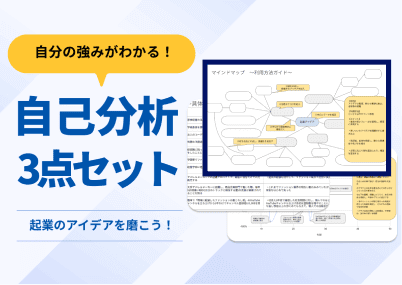- 更新日 : 2025年2月27日
副業で家賃や光熱費は経費にできる?按分計算や確定申告についても解説!
サラリーマンの方で事業所得や不動産所得、雑所得などの副業があり一定の要件に該当した場合、給与所得と副業の所得を合算し、所得税を納付しなければなりません。副業の所得を計算する過程で家賃やパソコンの経費、水道光熱費等を必要経費にすることはできるのでしょうか?
今回は、副業について青色申告ができるか?必要経費を割合で按分する方法は?などについて解説します。
目次
副業の売上・経費入力や、申告書の作成から申告作業まで、1つで完結するのが「マネーフォワード クラウド確定申告」。家計簿感覚で簡単に使えるので、初めての方にも多くご使用いただいています。
スマホのほうが使いやすい方は、アプリからも副業の確定申告が可能です。

副業で家賃や光熱費は経費にできる?
家賃や光熱費を経費にできるかについて解説する前に、まずは「必要経費」とは何かについて説明します。
そもそも経費とは?
「必要経費」という呼び方は所得税法上の名称であり、所得を計算するにあたって、収入を得るために必要な経費として収入金額から控除することが認められるものです。法人でいうところの「費用」に該当します。
所得税計算の基礎となる「所得金額」を求める計算式は以下の通りです。
所得金額が少なければ少ないほど、納付する所得税は当然少なくなります。したがって、所得金額を抑えるためには「必要経費」が多ければ多いほどよい、ということになります。
しかし、必要経費とするためには「収入を得るために要した支出であること」が前提となります。支出すれば何でも必要経費になるというわけではないのです。必要経費とするためには収入金額との紐づけが必要になります。
経費が認められる所得とは?
一言で「必要経費」といっても、副業の所得区分によって必要経費となるものが異なります。副業から得ることが多い次の所得について、必要経費となるものを挙げてみましょう。
事業所得
事業所得の場合、必要経費となるものは多岐に渡ります。
- 販売商品の仕入代金
- 営業車両のガソリン代、車検費用、自動車税など
- 事業所の電気代、水道代、ガス代など
- 従業員を雇用した場合の人件費
いずれの経費も「収入を得るために支出したもの」でなければなりません。
雑所得
雑所得の必要経費も、事業所得と同様に多くの種類があります。
- 雑所得を得るために使うパソコンや通信機器
- ネットで商品を販売した際にかかった手数料
- 10万円以上の備品にかかる減価償却費
- 文房具やコピー用紙などの事務用品
副業が事業所得と雑所得のいずれに該当するのかといった明確な線引きはありません。しかし、「所得を得るために要した支出」という部分は事業所得と同じです。
不動産所得
不動産所得は、アパートや駐車場などの不動産を賃貸し収入を得るものです。
- 土地や家屋にかかる固定資産税
- アパートの修繕費用
- 管理を不動産業者に委託している場合の管理手数料
- 建物にかかる火災保険料
収入を得る対象が土地や家屋であるため、必要経費にできる支出は土地や家屋にかかるもののみ、と事業所得や雑所得と比べて限定されてきます。
副業の記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
起業アイデア辞典300選!
「いつか起業したいけれど、自分に何ができるか分からない」そんなあなたにぴったりの厳選300アイデアを公開!
スキルを活かす仕事から未経験OKなものまで、市場の需要や収益性を網羅しました。パラパラと眺めるだけで、あなたに最適な起業方法のヒントが見つかるはずです。
起業アイデアを磨く!自己分析3点セット
「やりたいことはあるけれど、ビジネスとして成立するか不安」という方へ。
自分の強み・価値観・市場ニーズを掛け合わせ、唯一無二のアイデアに昇華させる自己分析メソッドを3つのシートにまとめました。
経営スキル習得の12か月ロードマップ
「経営を学びたいが、何から手をつければいいか分からない」と悩んでいませんか?
本資料では、財務・マーケティング・組織作りなど多岐にわたる経営スキルを、12か月のステップに凝縮して体系化しました。
1から簡単に分かる!起業ロードマップ
起業に興味はあるけれど、複雑な手続きや準備を前に足踏みしていませんか?
準備から設立までの流れを分かりやすく図解しました。全体像をひと目で把握できるため、次に何をすべきかが明確になります。
副業で経費に計上できる費用は?
では、副業で経費に計上できるものをいくつか列挙してみましょう。
家賃
貸店舗を賃借して副業を行う場合や、賃貸している自宅の一部を副業で使用している場合があります。事業所は収入を得るための拠点となります。したがって、事業所にかかる家賃は必要経費とすることが認められます。
ただし、賃貸物件の一部だけを副業で使用しているようなケースでは、家賃の全額を必要経費とすることはできません。次章で解説する「按分計算」が必要になります。
水道光熱費・通信費
副業でパソコンや事務機器を使うためには電気や通信環境が必要です。また、副業を行うにあたって水回りやトイレといった設備が必要になることもあり、水道を使うこともあるでしょう。電気料金や水道料金、通信費は販売商品と異なり直接的ではありませんが、収入を得るために間接的に必要になる支出です。したがって副業の必要経費として認められます。
パソコンの購入費用
今やパソコンやタブレットといったアイテムは、ビジネスの必需品であるといっても過言ではありません。パソコンやタブレットの購入費用は高額になりがちですが、所得税法では取得価額が「10万円未満」のものは消耗品として必要経費とすることができます。また、10万円以上の購入費用についても、減価償却という方法で期間経過に応じて必要経費とすることができます。
マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。
税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。
家賃や光熱費を経費にするには按分計算が必要!
支出した経費が、全額副業で収入を得るためにかかったものであれば問題はありません。しかし、経費のうち一部でもプライベート部分が含まれている場合には、プライベート部分を控除しなければなりません。これを「按分計算」と呼びます。
按分計算とは?
例えば、10万円の経費を支出したとします。このうち、3万円相当額がプライベートにかかるものであった場合、10万円全額を副業の必要経費とすることはできません。
10万円からプライベート部分の3万円を差し引いた残り7万円だけが必要経費として認められます。これが「按分計算」です。
按分計算について詳しく知りたい方は、以下のサイトを参照してください。
按分計算の割合は?
「按分計算」をするためには、副業とプライベート部分を分けるための「基準」が必要となります。例えば消耗品を2個購入し、1個を副業で使い1個をプライベートで使うようなケースであれば「按分計算」は簡単です。しかし、家賃や水道光熱費のように、目に見える形で明確に按分することが困難な経費もあります。
このような場合には、経費の按分基準として「使用割合」を使うのが一つの方法です。
自宅アパートの一部を副業の事務所として使用する場合には「アパート全体の床面積のうち事務所として使用している部分の床面積」の割合で按分することができます。また、水道光熱費については、24時間のうち、事務所を使用している時間の割合だけを必要経費とするか、使用頻度に応じて按分するのも方法です。
いずれにしても、按分する基準は明確にしておかなければならず、税務署に対して説明できるようにしておく必要があります。
経費計上で副業の所得が20万円以下になれば確定申告しないでよい?
本業であるサラリーマンの給与所得以外の副業で、副業の所得金額が20万円以下になると確定申告が不要になる制度があります。これが「申告不要制度」です。
先にも解説しましたが、所得金額は収入金額から必要経費を差引きすることで計算されます。したがって、必要経費を計上して所得金額を20万円以下に抑えることができれば、確定申告の手続きが不要になります。
ただし、この「申告不要制度」は、本業である給与所得で「年末調整をしていること」が前提になります。何らかの事情で会社で年末調整をしていない場合には、副業の所得金額を問わず、確定申告が必要になりますので注意してください。
なお、確定申告について詳しく知りたい方は、以下のサイトを参照してください。
副業で青色申告を選択して節税する方法も!
所得税法には「青色申告制度」というものがあります。事業所得や不動産所得の計算を、正規の簿記の原則に従った「複式簿記」により行った場合、さまざまな税法上の特典を受けられる制度です。
青色申告の大きな特典としては、計算した所得から最大で65万円控除(e-Tax等を使った電子申告の場合)することができるというものです。これを「青色申告特別控除」と呼びます。
青色申告には、その他にも以下のような税法上の特典があります。
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金の計上
- 純損失の繰り越し(最大3年間)
- 30万円未満の固定資産の全額必要経費計上
なお、副業が雑所得に該当する場合には青色申告の適用はありませんので注意してください。
青色申告について詳しく知りたい方は、サラリーマン・会社員の青色申告の条件 メリットや副業時の注意点も を参照してください。
副業の確定申告では必要経費の計上を忘れずに
副業の確定申告は、できるだけ所得金額を抑えたいところです。収入を得るために支出した経費は、探してみれば意外とあるものです。ご自身が支出した経費のなかで、副業のために支出したと考えられるものがあれば、金額の多寡、割合の大小を問わず、按分計算で必要経費に計上してみてはいかがでしょうか。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
副業で家賃や光熱費は経費にできる?
副業で収入を得るために支出した部分は経費として認められます。詳しくはこちらをご覧ください。
経費計上で副業の所得が20万円以下になれば確定申告しないでよい?
原則として確定申告は不要ですが、給与所得で年末調整をしていることが前提です。詳しくはこちらをご覧ください。
青色申告ができる副業は?
事業所得と不動産所得に限られます。雑所得は青色申告ができません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
副業の確定申告の関連記事
新着記事
メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説
メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…
詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説
本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…
詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説
未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…
詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説
米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…
詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説
個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…
詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説
新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…
詳しくみる