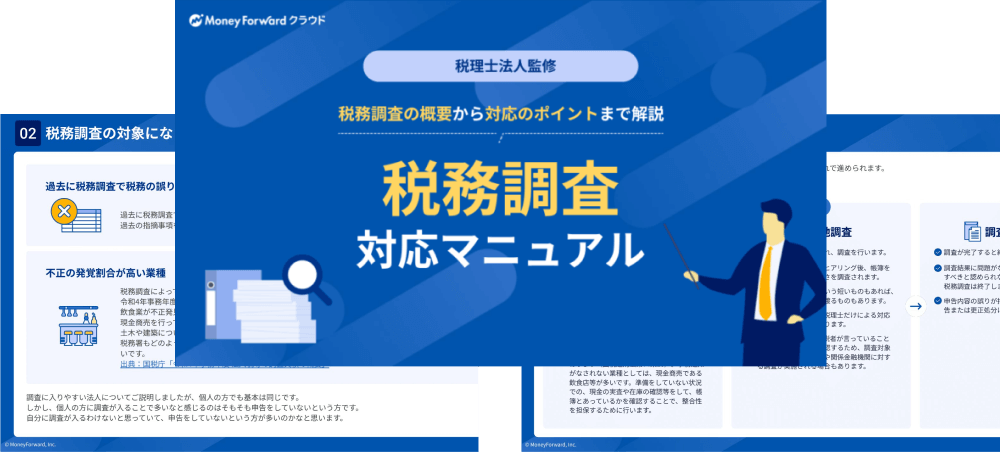- 更新日 : 2025年10月28日
個人事業主が提出すべき法定調書は?種類・期限・確定申告との関係を解説
事業活動を行う中で、誰かに報酬や給与を支払ったことがある個人事業主であれば、「法定調書」という言葉に触れたことがあるかもしれません。法定調書は税務署に支払内容を報告するための書類であり、法人だけでなく個人事業主にも提出義務が生じる重要な税務手続きです。
本記事では、法定調書の仕組みや対象となる支払い、提出方法や確定申告との関係、記載ミスがあった場合の修正方法などを解説します。
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

法定調書とは?個人事業主にも関係ある?
法定調書は税務署への支払記録を報告する制度で、法人だけでなく個人事業主にも関係しています。支払った金額や相手の情報を税務署に提出し、税務監査や申告内容の確認に役立てられます。
法定調書は支払内容の記録
法定調書とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法などの法律に基づき、税務署への提出が義務付けられた支払内容の記録書類のことです。2025年時点で、国税庁によると60種類以上の法定調書が存在しており、報酬・料金に関するものだけでも多数が含まれています。これらの書類を通じて税務署は支払われた金銭を把握し、受け取った側の申告内容との照合に使われます。不一致があれば照会書が届くこともあり、結果として申告漏れや脱税を防ぐ抑止力になっています。
個人事業主と法定調書の関係
個人事業主は、事業において誰かにお金を支払う場合にも、報酬を受け取るフリーランスとしての立場でも、法定調書の対象となります。従業員への給与支払いでは「給与所得の源泉徴収票」、外注先への報酬支払いでは「報酬、料金等の支払調書」を作成・提出する必要があります。これらの調書は支払者(事業者)が税務署に提出するもので、支払先(受け取る側)へ交付が法律で義務付けられているのは「給与所得の源泉徴収票」など一部に限られます。「報酬、料金等の支払調書」には交付義務がないため、法的には問題ないものの、源泉徴収が行われている場合は、自分で把握し確定申告に反映する必要があります。
なお、現在は確定申告書に源泉徴収票や支払調書の添付が不要となったため、受け取っていなくても取引明細や帳簿を基に正確な申告を行うことが求められます。法定調書は見えにくい存在ながら、税務管理の基盤として重要な役割を果たしています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
個人事業主が提出すべき法定調書は?
個人事業主が提出すべき法定調書は、支払う内容や相手の属性によってさまざまです。代表的なものには「給与所得の源泉徴収票」や「報酬・料金等の支払調書」などがあり、それぞれに提出条件が定められています。
【従業員に給与を支払った場合】給与所得の源泉徴収票
個人事業主が従業員やアルバイトに給与を支払った場合には、給与所得の源泉徴収票を作成します。これは年末調整を反映した給与総額や源泉徴収税額を記載するもので、従業員ごとに交付が義務付けられています。加えて、一定額以上の給与を支払った場合には税務署への提出が必要です。年末調整を行った従業員のうち、その年の給与支払額が500万円を超える場合に提出義務があります。なお、提出対象となる源泉徴収票は、毎年1月末までに法定調書合計表とともに税務署へ提出します。
【フリーランスや専門家に報酬を支払った場合】報酬、料金等の支払調書
外注先のフリーランスや士業などに報酬を支払った場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成します。基本的に、同一の個人に対して年間5万円を超える報酬を支払った場合に提出義務が生じます。ただし、外交員や広告賞金など一部の報酬には年間50万円超という基準が適用されることがあります。源泉徴収の有無にかかわらず、税務署への提出が必要なケースもあるため注意が必要です。支払調書は支払先への交付義務はないため、税務署への提出のみで差し支えありません。また、個別の支払調書の提出が不要な少額の支払いであっても、その報酬の年間支払総額は「法定調書合計表」に記載して報告する必要があるため注意が必要です。
【賃料を支払った場合】不動産の使用料等の支払調書
不動産業者である個人事業主が事務所や店舗などの不動産を賃借しており、年間15万円を超える賃料等を支払っている場合は、「不動産の使用料等の支払調書」の提出対象となります。これは主に、貸主が個人の場合に適用されます。貸主が法人の場合は、権利金や更新料など一部の支払いを除き、月々の賃料についての支払調書は提出不要です。不動産業者のうち、仲介のみを事業としている方は提出義務はありません。
その他の支払に関する調書
そのほかにも、不動産の売買に関する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や、仲介手数料にかかる「あっせん手数料の支払調書」などもあります。これらは主に不動産関連の取引で発生する支払いに関するもので、一定額を超えた場合に提出義務が生じます。高額な支払いを伴う場合は、あらかじめ対象調書の要否を確認しておくと安心です。
法定調書の提出先・提出方法と期限は?
法定調書は毎年1月31日が提出期限とされており、提出対象となる支払いが確定した翌年に、所轄の税務署へ提出します。紙による書類提出と電子申告(e-Tax)のいずれかの方法が選べますが、近年は電子化が推進され、一定条件を満たす場合は電子申告が義務化されています。
提出の手順と提出先
法定調書は、納税地(個人事業主であれば主に住所地)を管轄する税務署に提出します。提出書類は「源泉徴収票」や「支払調書」などの個別調書と、それらを集計した「法定調書合計表」です。合計表には、各調書の件数と支払総額を記載し、提出義務の有無にかかわらず全体の支払内容を報告します。
作成した調書一式は、窓口提出または郵送が可能です。ただし1月末は提出が集中しやすく、窓口が混雑する傾向があるため、余裕をもって準備しておくと安心です。
電子申告(e-Tax)義務化の動き
法定調書の提出は、e-Taxを使ってオンラインで行うこともできます。マイナンバーカードなどの電子証明書と、税務署への利用開始届出が必要です。電子申告は手続きの簡素化や受付確認の電子化が可能なため、利用者が増加しています。
従来、同一種類の法定調書を前々年に100枚以上提出している事業者は電子申告が義務付けられていましたが、この基準が引き下げられます。2027年1月1日以降に提出する法定調書(つまり2026年分以降)からは、基準枚数が「30枚以上」となる予定です。たとえば2025年時点で年間30枚以上の調書を提出する個人事業主は、今後の提出でe-Tax対応が必要になります。
会計ソフトや国税庁の無料ソフトを活用すれば、比較的容易に電子化が可能です。枚数が少ない場合でも利便性の面から電子申告を取り入れるのも選択肢のひとつです。
法定調書と確定申告の関係や注意点は?
法定調書は、税務署が確定申告の内容を確認・突合するための資料として活用されています。個人事業主が報酬を受け取る際、支払側が税務署に提出する法定調書と、自身が行う確定申告の申告内容が一致していないと、後に税務署から確認や問い合わせを受ける可能性があります。ここでは、正確な申告と注意点について解説します。
法定調書と申告内容の不一致はトラブルの原因に
法定調書は支払った側の企業や事業者が税務署へ提出するものです。受け取った個人事業主は、その内容と一致するように所得を確定申告する必要があります。
ある事業者がフリーランスに原稿料100万円を支払った場合、その情報は支払調書として税務署に提出されます。このとき、フリーランスが確定申告で100万円を正しく申告していれば問題ありませんが、金額が一致しない場合、税務署はその差異に基づいて「お尋ね」などの照会文書を送付する可能性があります。悪質な過少申告と判断された場合は税務調査の対象にもなり得るため、提出された調書に基づいて正確に申告することが重要です。
源泉徴収された報酬は確定申告で相殺される
個人事業主が受け取る報酬のうち、源泉徴収がされている場合、その税額はあらかじめ納められている前払い分として扱われます。確定申告時には、申告書の「源泉徴収税額」欄に年間の合計金額を記載し、納付すべき税額から差し引いて計算されます。税額が不足していれば追加で納付し、過払いであれば還付を受けられます。
フリーランスへの支払調書は交付義務がないため、実際に受け取っていないこともあります。しかし、支払額や源泉徴収額は自身で帳簿や取引明細から正確に把握し、確定申告書に反映させる必要があります。
なお、現在は源泉徴収票や支払調書の添付は不要となりましたが、記載内容に誤りがないよう注意が必要です。資料が手元にない場合でも、取引先に確認を取り、帳簿と照合して正確な申告を行いましょう。税務署側も調書を通じて情報を把握しているため、内容が一致していればスムーズに処理が進みます。
法定調書の提出後に内容に誤りがあった場合の手続きは?
法定調書を提出したあとに金額や氏名、マイナンバーなどの記載ミスが判明することは珍しくありません。提出後の誤りは、そのまま放置すると税務署からの問い合わせや支払先側の確定申告に支障をきたすおそれがあるため、速やかに手続きを行うことが重要です。
修正の方法には「訂正」と「取消」がある
法定調書に誤りがあると判明した場合、基本的には「訂正」または「無効」のいずれかの形式で再提出します。訂正とは、既に提出した調書の内容を修正するもので、同一の整理番号や支払先情報を用いながら正しい数値・内容に書き換えて提出します。一方で、調書そのものが誤っていた場合(本来提出不要だったなど)は「無効」として処理します。
どちらの場合も、提出済みの調書と同じ調書様式を用い、該当する項目に訂正または無効の内容を記載して再提出します。また法定調書合計表の提出区分を記載する箇所には「訂正」または「無効」と記載します。提出の際は、誤りの内容と訂正理由を明確にしておくと、税務署での処理がスムーズに行われます。
電子申告でも修正は可能
e-Taxを使って法定調書を提出した場合でも、修正手続きは可能です。訂正・無効用のファイルを作成し、再送信するだけで手続きが完了します。多くの会計ソフトでは、提出済みデータをベースに修正用データを作成できる機能が用意されており、手間を最小限に抑えられます。
ただし、訂正のタイミングによっては、支払先側の確定申告書との整合性が取れなくなる場合があるため、早期の対応が推奨されます。また、修正済みの調書を支払先に交付し直す必要がある場合は、その案内も忘れずに行うようにしましょう。
法定調書は個人事業主にとっても重要な税務手続き
法定調書は法人だけでなく、個人事業主にも密接に関係する制度です。報酬や賃料の支払時には該当する調書を作成・提出する義務があり、逆に受け取る立場であっても確定申告の整合性に影響します。期限・提出方法・修正対応まで一連の流れを把握し、適正な申告と納税につなげることが、信頼される事業運営に直結します。制度の概要を理解し、必要な対応を日頃から整えておきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
電気工事士が個人事業主として独立するには?資格・費用・集客について解説
「いつかは自分の力で仕事をしたい」「技術を活かして独立したい」と考えている電気工事士の方は少なくありません。現場での経験を積む中で、自分の裁量で働きたい、収入を増やしたい、仕事の幅…
詳しくみる個人事業主の出張費は経費にできる?食事代や日当は?按分や確定申告のポイントも解説
出張にかかる費用は、事業に関係していれば経費として処理できますが、その範囲や条件を誤ると税務上のトラブルにつながるおそれがあります。 本記事では、交通費・宿泊費・通信費といった代表…
詳しくみる商工会のデメリットとは?個人事業主が知っておくべきメリットや注意点を解説
個人事業主として事業を営む中で、経営や税務、資金繰りなどに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。地域の商工業者を支援する「商工会」は、そうした課題をサポートしてくれる心強い存在…
詳しくみる税務調査が来る時期は?個人事業主が知るべき頻度や備え方を解説
税務調査は、個人事業主にとって日常的な話題ではないものの、いざ通知が届けば大きな不安を感じるものです。「いつ来るのか」「何年分が対象なのか」「自分は調査対象になりやすいのか」といっ…
詳しくみるずっと赤字の個人事業主が見直すべき原因は?赤字の影響や改善策を解説
個人事業主として事業を続けていると、思うように売上が上がらず赤字が続くことがあります。一時的な赤字であれば問題ありませんが、慢性的な赤字の状態が長引くと、税務署からの心証や信用低下…
詳しくみる個人事業主が屋号付き口座を開設するメリットは?手続きの流れや準備について解説
個人事業主が屋号付き口座を作るメリットとして、事業資金と個人資金を明確に分けられることが挙げられるでしょう。取引先や顧客からの信頼性の向上を期待できます。 本記事では、個人事業主が…
詳しくみる