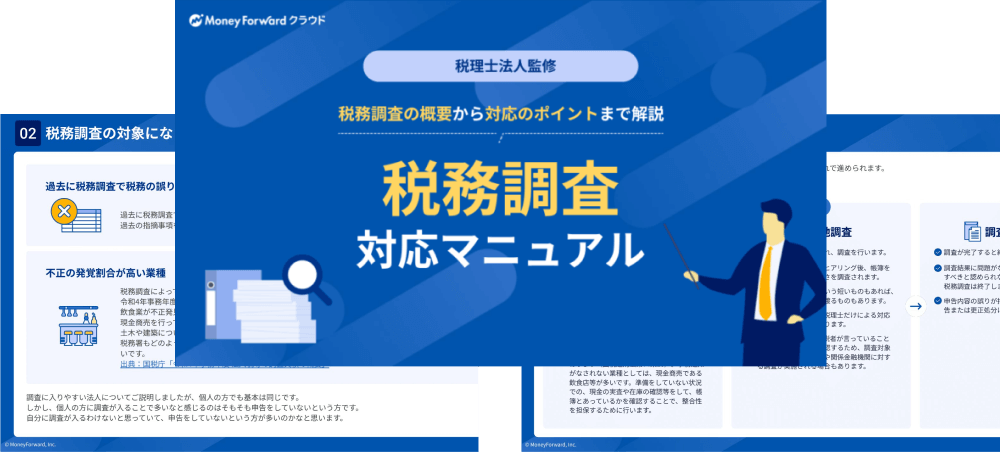- 更新日 : 2025年3月7日
個人事業主が車を売却したら譲渡所得? 仕訳と節税対策を解説
個人事業主が事業で使用している車を売却するケースがあります。税法では、売却により利益が出た場合、税金を納付しなければなりませんが、車の売却にかかる利益はどのような所得区分になるのでしょうか。今回は、個人事業の用に供する車の売却に関する税法の取扱いや仕訳、節税対策などについて解説します。
目次
フォームに順番に入力するだけで、控除や還付金を受け取るための確定申告も簡単に。「マネーフォワード クラウド確定申告」は、医療費控除・社会保険料控除、ふるさと納税・住宅ローン控除…などの各種控除がある方にも、多くご利用いただいています。
スマホのほうが使いやすい方は、アプリからも確定申告が可能です。

個人事業主の車の売却に関わる税金
はじめに、個人事業主の車を売却した場合に課税される税金の種類について解説します。
自動車税
自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村が毎年4月1日時点で車を所有している所有者に対して課税する税金です。自動車税や軽自動車税はその年額を5月31日までに前払いする形になるため、一般的には、車を売却した時点で未経過期間分の税金が還付されます。しかし、売却には納税証明が必要なため、売却時点で税金を滞納している場合には納税が発生します。
所得税
税法のルールとして「もうけが出たら税金を払う」ことになりますが、個人事業主の場合、課税されるのは所得税です。車の売却価額から車の帳簿価額を差引いた残額に対して、所得税が課税されます。
消費税
消費税の課税事業者の場合、本則課税・簡易課税を問わず売却金額の総額は消費税を含んだ金額です。車の売却の場合、適用される消費税率は10%のため「売却金額÷1.1×10%」の消費税が課税されることになります。ただし、本則課税の場合、売却にかかる必要経費に含まれる消費税を「仕入税額控除」として控除することが可能です。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
なお、マネーフォワード クラウド確定申告に無料登録いただくと、「確定申告 お役立ち資料集」から、下記の4つともまとめて閲覧・ダウンロードすることが可能です!
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
個人事業主の車の売却益は所得税の「譲渡所得」扱い
一言で所得税といっても、課税される所得は全部で10種類に区分されています。次に、車の売却に課税される所得税の区分について解説します。
譲渡所得には特別控除がある
譲渡所得は、資産を譲渡する際に生じる所得を指します。したがって、個人事業主が車(動産)を売却する際に発生する利益は、譲渡所得に該当します。譲渡所得の対象となる資産は土地や家屋といった不動産をはじめ、車や機械などの動産も含まれます。
譲渡所得には取引内容に応じて特別控除があり、譲渡により生じた利益からこの特別控除を差し引きした残額に対して所得税が課税されます。
譲渡所得の「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」
譲渡所得は、その資産の所有期間に応じてさらに「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に区分されます。資産の所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得、5年を超えるものは長期譲渡所得となります。両者の大きな違いは適用される税率です。
短期譲渡所得の場合、適用される税率は39%ですが、長期譲渡所得の税率は20%と2倍近い差があります。さらに長期譲渡所得の場合、「収用等のために土地や家屋を譲渡した場合の5,000万円控除」や「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」など、特別控除の種類が多いのも特徴です。
法人の場合、車の売却益には法人税がかかる
同じ車の売却でも、個人事業主と法人では課税される税金の種類が異なります。法人の場合、車の売却で得た利益(売却益)に対して法人税が課税されます。法人の場合、売却資産の所有期間について特に区分はなく、短期長期に関わらず、売却益に対して一定の税率が適用されるのも個人事業主との大きな違いです。
車の購入や売却に関わるリサイクル預託金とは?
車を購入する際、請求書や注文書のなかに「リサイクル預託金」という項目があるのをご存知でしょうか。次に、リサイクル預託金について解説します。
リサイクル預託金とは何か?
2005年に「自動車リサイクル法」が施行され、現在では車の所有者は全員リサイクルに関する費用負担であるリサイクル預託金を支払うことになっています。リサイクル預託金は、最終的に車が廃棄される際に発生する解体費用や破砕費用といった処理費用を車のオーナー自身が預託金として負担する仕組みです。
最終処理にかかる費用は、車を廃棄するときのオーナーが負担することになるため、車を売却する際には、リサイクル預託金もセットで次のオーナーに売却することになります。
リサイクル預託金は資産になる
リサイクル預託金が費用になるのは、車を廃棄する時点です。したがって車を購入した段階では費用にすることはできず、資産計上することになります。具体的には「リサイクル預託金」や「長期前払費用」などの勘定科目を使い、資産として計上するのが正しい会計処理です。車を売却する際には、車両本体のほかにリサイクル預託金という資産も一緒に売却するイメージです。
車の購入時には必ずリサイクル預託金が表記されているため(本体価額に含まれているケースもあります)、忘れずに当該金額を資産計上しましょう。
個人事業主の車の売却益にかかる譲渡所得の計算方法
個人事業主の方が車を売却した際に生じる売却益について、譲渡所得の計算方法を解説します。
車を売却する際の特別控除
先にも解説しましたが、譲渡所得にはその取引内容によって特別控除があります。車を売却する際にも特別控除が設けられており、所有期間による短期譲渡所得・長期譲渡所得に関係なく、一律で50万円の特別控除を適用することができます。
なお、譲渡により生じた利益が50万円に満たない場合、利益の金額が特別控除の上限になるため注意してください。
譲渡所得の計算式
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
上記の算式のうち取得費は、車の取得後に減価償却によって経費化した金額を控除した帳簿価額です。また、売却にかかる経費には代行手数料や名義変更にかかる手数料など、売却するために必要となる経費が該当します。
売却代金と経費の相殺に注意
中古車メーカーに車を売却するケースなどで、売却金額から経費を差し引きした残金だけが支払われることがあります。利益だけをみれば相殺しないケースと同じですが、消費税の簡易課税制度事業者の場合、相殺により入金額が実際の売却金額より少なくなってしまい、消費税の課税標準額が過少に計上されてしまいます。
会計処理をする場合には、必ず相殺前の金額で売却金額を計上するようにしましょう。
個人事業主が車を売却した場合の仕訳方法
次に、個人事業主が車を売却した場合の仕訳処理について、具体例を挙げながら解説します。
例:1,000,000円の車を現金で購入した(リサイクル預託金10,000円)
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 リサイクル預託金 | 1,000,000円 10,000円 | 現金 | 1,010,000円 |
例:車にかかる減価償却費を計上した(償却率0.167 直接法)
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 167,000円 | 車両運搬具 | 167,000円 |
例:上記車両を900,000円で売却した
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 900,000円 | 売却益 車両運搬具 リサイクル預託金 | 57,000円 833,000円 10,000円 |
例:売却にかかる手数料20,000円を支払った
| 借 方 | 貸 方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
支払手数料を払う際、売却益と相殺になっていないか注意し、売却益に関しては特に「総額主義」で処理するようにしましょう。
個人事業主が車を売却する際の節税ポイント
個人事業主が車を売却する際に、注意すべきポイントについて紹介します。
4月までの売却で自動車税がかからない
自動車税(軽自動車税)は、4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、車の売却を3月末までに行えば自動車税は課税されません。
4月2日以降に売却すると、後で未経過期間の自動車税が還付されるにしても、先に一旦全額を納付しなければなりません。売却するタイミングには十分注意しましょう。
事業用の車なら家事按分しなくてもよい
事業とプライベートで共有している車を除き、事業用の車を売却して利益が出たとしても、その利益を事業と家事で按分する必要はありません。取得費や売却にかかる経費などについても同様に、事業にかかる車の経費であれば家事経費と按分計算する必要はありません。
車の売却は下取り、買取りどちらがよい?
車の売却には、車を買い替える際に今乗っている車を下取りに出す場合と、買い替えなしで買い取ってもらう場合の2パターンがあります。いずれのケースでも、税金がかかるのは売却によって生じる利益部分のため、税法上の有利不利はありません。車の販売による利益がある分、下取り価格を高く査定してくれるケースがあるので、下取りと買取りの両方を査定してもらうのも1つの方法です。
個人事業主が車を売却した場合の確定申告方法
ここまでで、車の売却が譲渡所得に該当することは解説しました。では最後に、具体的な確定申告の進め方を見てみましょう。
確定申告書「第二表」の作成
車の売却は総合課税になるため、分離課税と違い「第三表」の作成は必要ありません。まずは確定申告書の「第二表 総合譲渡に関する事項」の欄に、車の売却に関する収入金額と、必要経費、差引金額を記載します。
確定申告書「第一表」の作成
「第二表」に記載した収入金額を「第一表」の譲渡所得の「収入金額」の欄に、差引金額を譲渡所得の「所得金額」の欄にそれぞれ転記します。後は、事業所得やその他の所得を記載し所得税を計算していきます。
なお、車の売却で赤字が出た場合、著しく低額で譲渡するなど特殊なケースを除いてその他の所得の黒字と相殺(損益通算)することができます。
車の売却時には所得区分に注意しましょう
車のような事業用動産の売却をした場合、うっかり事業収入として会計処理してしまうことがあります。同じ事業の取引でも、事業所得に該当するものと譲渡所得に該当するものがあることを正しく理解した上で確定申告をするようにしましょう。
はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法
確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。
個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。
①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。
②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。
③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。
追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える
有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料
マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典


マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
申告納税額とは?納税する方法や申告納税が必要な人を解説
申告納税額という言葉は聞いたことがあっても、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。とくに会社勤めをしていると、税金について触れる機会はそれほど多くないかもしれません。…
詳しくみる贈与税とは?いくらかかる?相続税との違いや暦年課税の仕組みも解説!
個人がお金や住宅などの財産を生前贈与すると、贈与を受けた人は、贈与税を支払わなければいけません。贈与が発生した場合に気になるのが、一体いくらの贈与税がかかるのかということでしょう。…
詳しくみる自由診療の確定申告 – 自費の診療は医療費控除の対象になる?
けがや病気などの診察や治療には、大きく分けて保険診療と自由診療の2つがあります。実は、保険診療と自由診療では費用の負担割合などのほか、医療費控除についても異なる点が多いです。 そこ…
詳しくみる【個人事業主・中小企業経営者向け】小規模企業共済とは?加入するメリットを解説
年金制度の破綻が叫ばれている中、若年層から中高年までの幅広い層において、漠然とした老後の不安を抱えている方も少なくないと思います。 大企業に長年勤めたサラリーマンの大きな味方となる…
詳しくみる課税所得とは?税金に差が出る理由や計算方法、所得控除・税額控除、非課税所得まとめ
所得税の課税所得とは、所得税を計算するために必要な金額です。課税所得の計算を正しく理解することができれば、同じ年収でも税金に差が出る理由が理解できます。 ここでは所得税がどのように…
詳しくみる譲渡損益とは?投資信託・株式の取扱いをわかりやすく解説!
譲渡損益とは資産を売却して生じる損失や利益のことです。例えば、投資信託や株式などを所有している場合であれば、取得したときに支払った金額よりも売却して得られた金額が多ければ譲渡益、反…
詳しくみる