- 更新日 : 2025年10月21日
個人事業主の請求書に押すハンコの位置は?知っておくべきルールを解説
個人事業主として請求書を発行する際、「ハンコは必要なのか」「どこに押すべきか」といった疑問を感じたことはありませんか?ビジネス書類における押印の必要性は、法律・税務・実務慣習によって判断が分かれる場面もあります。さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法など、制度の変化により対応方針も見直しが必要です。
本記事では、請求書におけるハンコの役割や押印する場合の位置などについて解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
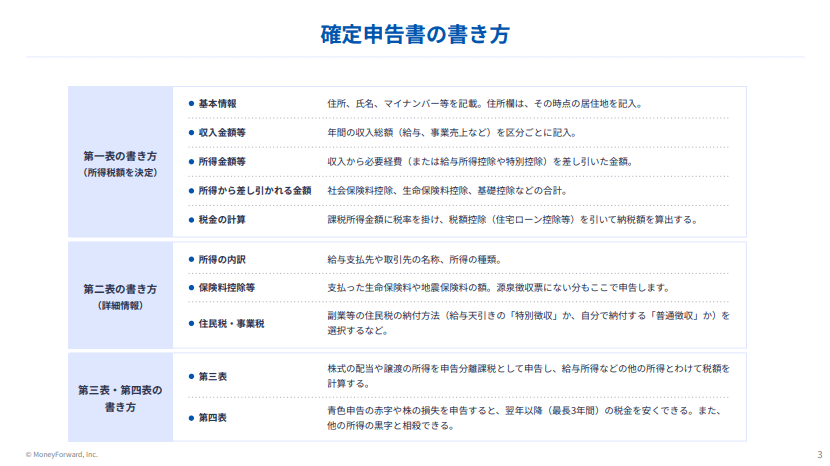
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

請求書にハンコは必要?
請求書を作成する際に、印鑑を押すべきかどうかは、個人事業主にとってしばしば悩ましい問題です。結論から言えば、請求書への押印は法的義務ではなく、ハンコがなくても請求書として有効に扱われます。ただし、取引先との信頼関係や実務上の慣例を考慮する必要があり、現場の運用では押印を求められるケースも少なくありません。以下では、法律と商慣習の双方からこの問題を整理します。
法律上、請求書にハンコは不要
請求書への押印は、法律では義務付けられていません。法的には請求書に押印を必須とする条文は存在しないため、印鑑が押されていないからといって、請求書が無効になることはありません。また、内閣府・法務省・経済産業省は連名で、
「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」
としています。これより、請求書や領収書への押印が法的に義務付けられていないことが明確に示されています。
つまり、請求書はあくまで請求側の「支払いを求める意思表示」であり、その意思が明確に示されていれば、印鑑の有無により法的な効力に影響はありません。
このため、たとえ請求書がデータ形式(PDFなど)で発行され、印影が添付されていない場合でも、記載内容が適切であれば、法的には問題なく請求書として成立します。したがって、税務上においても押印がなくても否認の理由にはなりません。
実務慣行としての押印文化
一方で、実務においては請求書にハンコを押すことが一般的とされています。企業間取引(BtoB)では、請求書に社判(角印など)が押されていることで、慣習により正式な書類と受け止められやすいと考えられています。また、書類の改ざん防止や発行元の明示という意味でも、ハンコは一定の役割を果たしてきました。
こうした背景から、法律上では不要であっても、取引先から「印鑑付きの請求書を出してほしい」と求められることも少なくありません。初回取引時や、大企業とのやりとりでは、押印の有無が相手の安心感に影響する場合があります。
押印廃止の流れと今後の対応
ただし、押印文化は近年大きく見直されています。2021年4月以降、税務関係書類への押印義務は原則廃止され、行政や自治体の手続きでもハンコが不要となるケースが増加しています。リモートワークやペーパーレス化の進展も相まって、紙の請求書にわざわざハンコを押すという作業は、徐々に減少傾向にあります。
個人事業主としては、こうした社会的流れを理解しつつも、取引先ごとのニーズや文化に応じた柔軟な対応が求められます。印鑑のない請求書で問題がないと判断できる相手にはそのまま送付し、逆に押印を求められる場面では、紙面もしくは電子データ上で印影を添付するなど、過不足ない対応を行うことが実務上の最適解といえるでしょう。実務を優先して柔軟な対応を取りつつも、担当者レベルではなく押印が「貴社の規程上必要かどうか」を確認することも視野に入れましょう。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
請求書にハンコを押す場合、位置はどこ?
請求書にハンコを押す場合、どこに押すのが適切か迷うことがあります。取引先にとってわかりやすく、信頼を得やすい請求書を作成するためには、ルールを知っておくことが重要です。
発行者名の右横に押すのが一般的
請求書にハンコを押す場合、最も一般的なのは、発行者名(社名または屋号)の右横に発行者名の末尾1、2文字と重なるように印鑑を配置するスタイルです。この1、2文字分を重ねるのは偽造防止効果が高まるためです。
企業であれば、請求書の右上に自社情報(社名・住所・電話番号など)を記載するのが一般的ですが、その中でも社名や代表者名に近いスペースに社判(角印)を押す形がよく見られます。角印は四角い形状の印鑑で、会社の名称が刻まれたものが多く、対外文書の信用性を高める意味でも使用されます。
個人事業主の場合は、屋号または自身の氏名の右隣に氏名の末尾1、2文字と重なるように押すのが一般的です。住所や連絡先の記載と並べることで、書類全体のバランスも整い、受取側にも「誰がこの請求書を発行したのか」が明確に伝わります。
発行者名に近ければ柔軟な配置で問題ない
請求書に法定の書式はなく、ハンコの押印位置も明確なルールがあるわけではありません。
レイアウトによっては右横に余白がない場合もあり、その場合は社名や氏名の「下」や「左側」など、発行者情報の近くで空いているスペースに押印しても問題ありません。重要なのは、書類を受け取った相手にとって「誰が発行した請求書なのか」が一目でわかることです。
また、押印の際は、インクのかすれが生じやすいシヤチハタ(浸透印)ではなく、鮮明に印影を残せる正式な印鑑(朱肉を使うタイプ)を使用するのがビジネスマナーとして望ましいとされています。印影が薄いと、書類としての信頼性に疑問を持たれる可能性もあるため、見た目にも配慮することが求められます。
電子ファイルの場合も同様の位置に印影画像を配置する
PDFなどの電子請求書を発行する場合でも、ハンコの画像データ(印影)を社名や屋号の近くに配置することで、紙の請求書と同様の見た目を保つことが可能です。
テンプレートやExcelで作成した請求書に画像を挿入する形であれば、相手にも違和感を与えず、信頼感のあるフォーマットに仕上がります。デジタル化が進む中でも、「形式的にハンコがある」ことが安心材料になるケースはまだ多いため、発行者情報の右横、またはその周辺に配置するのが引き続き最適解といえるでしょう。
個人事業主は請求書にどんな印鑑を使うべき?
請求書に押す印鑑は、どの程度正式なものを選ぶべきか、悩む個人事業主も少なくありません。結論から言えば、請求書への押印は認印で十分です。ただし、屋号入り印鑑や角印などを活用することで、相手先への信頼感を高めることも可能です。
認印や実印でも法的に有効
個人事業主が請求書に押す印鑑として、特別な社判や法人印は不要です。法人では代表印や角印が一般的ですが、個人事業主には登記制度がないため、それに相当する印鑑を持っていないことが多いです。苗字入りの認印や、必要に応じて登録した実印など、自分の身元を証明できる印鑑であれば、どれでも問題ありません。
角印は任意、信頼性重視なら活用も可
角印は四角い印鑑で、企業では社外文書に多く使われていますが、個人事業主が必ずしも持つ必要はありません。ただし、信頼性や偽造防止を意識する場合、屋号入りの角印や丁寧に彫られた印鑑を使うと印象がよくなります。すでに所有している場合は積極的に活用するとよいでしょう。
屋号入り印鑑で視認性アップ
ビジネスネーム(屋号)で活動している場合、その名称入りの印鑑を使うと請求書の見た目がわかりやすくなり、取引先にも一目で誰からの書類かが伝わります。形式にこだわる必要はありませんが、発行者が誰かを明確にし、鮮明な印影を残すことが大切です。請求書の効力は印鑑の種類で変わることはないため、「自分が発行したことを示す印影」を意識して選びましょう。
確定申告にハンコは必要?
個人事業主が確定申告を行う際、「ハンコが必要かどうか」は気になるポイントです。先述のとおり、確定申告において押印は必須ではなく、記載内容の正確性こそが重視されます。以下では、税務処理と印鑑の関係を解説します。
税務署への提出書類も押印不要に
2021年以降、税務署に提出する各種書類で押印義務が廃止されました。申告書類や届出書でもハンコなしで受理されるのが原則となり、押印文化そのものが制度上見直されています。この流れは、請求書などの関連書類にも波及していると言えます。
また、申告書等を提出した際に税務署で押印していた「収受日付印」についても2025年1月より廃止となりました。
参考:税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁、令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
請求書と印紙税の違いに注意
混同しがちな点として、「収入印紙と消印」があります。領収書では5万円以上の取引に収入印紙が必要で、その印紙には割印(消印)を押す義務があります。領収書は「金銭または有価証券の受取書」に該当するため、印紙税が課税されるためです。しかし、請求書は「受領証」ではなく「支払請求」の文書であるため、印紙税の対象外です。したがって、収入印紙も消印も不要です。ただし、「請求書兼領収書」のような表現を使うと、領収書と見なされて印紙が必要になる場合があるため注意が必要です。
インボイス制度で請求書のハンコはどうする?
インボイス制度の導入によって、請求書の作成ルールが変わったことから、「ハンコが必要になるのでは?」と不安に思う個人事業主も多いかもしれません。インボイス制度でも請求書への押印は不要です。以下でその理由を整理します。
インボイスの必須項目に押印は含まれない
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、適格請求書に記載しなければならない項目が明確に定められています。たとえば、発行者の氏名または名称、登録番号、取引日付、取引内容、税率ごとの金額と税額、税率ごとの消費税額、取引先の名称などです。しかし、これらの中に印鑑は含まれていません。そのため、請求書にハンコが押されていなくても、法的には有効なインボイスとして扱われます。
これは従来通り、押印の有無だけで取引の成立や税務処理に影響を与えないという原則を踏襲しています。
登録番号と記載内容が最重要
インボイス制度では、請求書に記載する「登録番号」が重要な項目の一つです。この登録番号をもとに、買い手側が仕入税額控除を行えるかどうかが決まります。また、消費税率ごとの区分記載や合計金額、税額の表示なども必要で、内容の正確性と網羅性が求められます。印鑑を押すかどうかは任意であり、記載要件を満たしていれば押印がなくても問題ありません。
デジタル時代の請求書とハンコの扱いはどうなる?
ペーパーレス化が加速する現在、請求書の電子化は個人事業主にとっても避けて通れないテーマです。ここでは、電子帳簿保存法の電子取引との関係や対応について整理します。
電子請求書には押印不要、保存方法が重要に
近年の法改正により、所得税法や法人税法では、電子取引において電子請求書を紙に印刷して保管する従来の方法は認められなくなっています。「電子帳簿保存法」の改正により、メールなど電子データで受け取った請求書をただ印刷するだけでは、正式な保存とは見なされなくなりました。電子データは電子データのまま保存し、タイムスタンプや検索機能の確保といった要件を満たす必要があります。
つまり、電子請求書では「印鑑を押してあるか」よりも、「法令に準拠した方法で保存されているか」が問われる時代になっています。
参考:パンフレット|国税庁、「電子取引データを適切に保存できていますか?」
システム上の電子印鑑が役割を担うことも
クラウド型の請求書発行システムを利用する事業者が増えており、そこでは物理的なハンコは使えません。代わりに、システム内で発行者情報が自動記録されたり、電子印鑑(印影画像や電子署名)が付与されたりと、信頼性を担保する仕組みが整えられています。そもそも、発行から保存までが一連のデータ管理の中で行われるため、改ざんリスクも低く、押印に頼らずとも十分に信頼性を確保できるのが特徴です。
このように、ハンコは慣習的な儀式の一環として残存し、実際の承認は電子署名等の仕組みで行われるように変わりつつあります。
実務では柔軟に対応をしよう
とはいえ、全ての取引先が電子化に慣れているとは限りません。中には「紙の請求書+押印」を今も重視する個人事業主や企業もあります。そのため、デジタル対応が可能な相手には電子請求書を送り、印鑑不要で対応する一方、伝統的な慣習を重視する取引先には紙の請求書+押印を用意するなど、相手に応じた柔軟な運用が求められます。
その上で、印影を省略する際には、「押印を省略しております」といった一言を添えるとよいでしょう。
請求書のハンコ対応は状況に応じて使い分けよう
請求書にハンコを押すかどうかは、法律上の義務ではなく、印鑑なしでも有効です。ただし、商習慣などにより取引先によっては押印を求められることもあり、対応には一定の配慮が必要です。これからの時代は、制度やデジタル化の流れを踏まえながら、相手先の事情やビジネス慣習に合わせて臨機応変に対応する姿勢が大切です。形式よりも実務に即した判断を意識していきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主が建設業許可を取るために必要な書類は?要件や更新手続きも解説
建設業を営む個人事業主にとって、一定規模以上の工事を請け負うためには「建設業許可」の取得が欠かせません。許可を取得すれば受注できる案件の幅が広がり、取引先からの信用向上にもつながり…
詳しくみる個人事業主がメルカリを利用するには?ショップ開設の流れや確定申告について解説
メルカリは個人事業主としても利用は可能です。ただし、本来メルカリは個人間取引の場として設計されているため、個人事業主は「メルカリShops」の利用が推奨されています。 この記事では…
詳しくみる税金貧乏にならない!個人事業主が陥りやすい原因と対策を解説
個人事業主として働く中で、「思った以上に税金を払っていて手元にお金が残らない」と感じたことはありませんか? このような状態は「税金貧乏」となり、所得税・住民税・消費税に加え、社会保…
詳しくみる個人事業主とは?定義やメリット、開業方法・フリーランスとの違いを解説
個人事業主とは、法人ではなく個人で事業を営む自営業者を言います。個人事業主として事業を新たに開始した場合、原則として1ヵ月以内に管轄の税務署へ開業届を提出する必要があります。 この…
詳しくみる個人事業主のエンジニアとして独立するには?手続き・仕事の取り方・税務知識を解説
エンジニアとしての経験を活かし、より自由な働き方や収入アップを目指して個人事業主として独立する人が増えています。しかし、自由と引き換えに必要な準備や知識も多く、開業手続きや税金、案…
詳しくみる個人事業主の商工会費は経費にできる?勘定科目・仕訳・申告方法を解説
個人事業主として商工会や商工会議所に加入する際、会費は経費にできるのか、勘定科目はどうするのか、確定申告ではどこに記載するのかというのは意外と迷いやすいポイントです。 本記事では、…
詳しくみる



