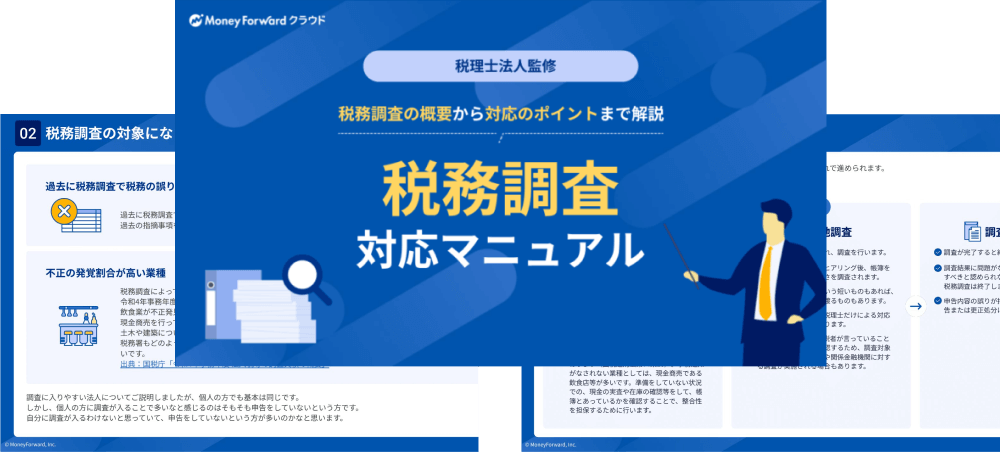- 更新日 : 2025年2月26日
家事消費(自家消費)とは?仕訳と具体例から解説
個人商店や飲食店では、売れ残りの商品がもったいないので家族で消費するといったことが日常的に行われています。これを「家事消費(自家消費)」と呼びます。
しかし、この行為自体を知ってはいても、確定申告できちんと申告していない人が多いようです。家事消費は税務調査の意外な落とし穴になりかねない科目のため、これを機に正しい計上方法を身につけましょう。具体的な金額の算出方法と仕訳例も掲載しているので、ぜひ実務の参考にしてください。
目次
家事消費(自家消費)とは
家事消費(自家消費とも呼ぶ)とは、販売する予定だった商品などの棚卸資産を、自分や家族のために使用することをさします。たとえ小さな金額だったとしても、規定割合の金額を売上として帳簿に記載する義務があります。
家事消費を帳簿に記載しなければならない理由は、商品や材料の仕入れを材料費や仕入原価として計上している以上、自分が消費したものであっても売上として計上しなくてはならないからです。
家事消費は特に個人商店でよく見られる勘定科目だといえます。単純に商品を家族で使用したときだけでなく、誰かに贈与した(あげた)時、定価よりも安く売ったときにも、家事消費として計上する必要があるため注意しましょう。
具体的にどのような場合が家事消費に該当するのか見ていきましょう。
家事消費(自家消費)になるもの
家事消費に該当する具体例には次のようなものがあります。
- パン屋が売れ残りのパンを食べた
- 家電用品店がお店の商品を自宅用にした
食べ物以外の商品も家事消費に該当します。ただし、見本品やサンプルとして使用した商品を自宅用にする場合は、家事消費として計上はしますが、その同額を広告宣伝費などの費用として計上できます。そのため、結果として収支に影響はありません。 - 自転車屋が友人に商品の自転車をプレゼントした
贈与も家事消費の対象です。プレゼントは贈与に該当するため、家事消費として計上します。 - 10万円の商品を友人に定価の40%で販売した
贈与だけでなく、低額譲渡も家事消費の対象です。定価との差額が家事消費に該当します。なお、このパターンはのちほど仕訳例として紹介するので実務の参考にしてください。
パン屋だけでなく、八百屋が売れ残りの野菜を食べる、ケーキ屋が自分のお店のケーキを食べるといったものなどは、すべて家事消費に該当します。また、飲食店で従業員に提供される「まかない」も家事消費であることに注意が必要です。個人商店や小規模店舗ではごく当たり前に見られる光景なだけに、しっかり計上できていないと税務調査で指摘されやすいポイントでもあります。
家事消費(自家消費)にならないもの
家事消費に該当しそうに見えても対象外なものもあります。
- マッサージ師が友人に無料でマッサージをした(役務の提供は対象外)
- 工務店が社長のために家を建てた
設計や大工の工賃など役務の部分は家事消費に該当しませんが、建築資材などの材料費にかかる部分は家事消費として計上する必要があります。 - 事業用の車を友人に安価で譲った(減価償却資産は対象外)
事業用の車は棚卸資産ではないため、家事消費の対象ではありません。車に限らず減価償却資産は家事消費の対象外です。ただし、中古車販売店など、車そのものを販売する業態であれば話が変わってきます。この場合は商品を友人に贈与したことになり、家事消費として計上しなくてはいけません。
家事消費の対象になるのは商品・材料などの棚卸資産です。サービスの提供は対象外となるため、マッサージをいくら無料で提供しても家事消費に計上する必要はありません。その他のサービスについても同様です。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
家事消費(自家消費)の金額はどうやって決める?
家事消費については所得税法に定められており、その金額は原則として定価で計上する必要があります。ただし特例があり、仕入金額または定価の70%のうち、いずれか高いほうの金額で計上することも可能です。
どちらで計上してかまいませんが、一般的には利益の計上額が少なくなるように特例が採用されることが多いようです。仕入単価と販売価格が分かれば、計上価格の計算はそれほど難しくはないため、家事消費した場合は都度記録を残しておくようにしましょう。
家事消費(自家消費)の仕訳例
家事消費は収入科目のひとつで、科目は「家事消費」を使用します。自分宛に商品を販売したと考えれば分かりやすいでしょう。家事消費の計上を怠ると、仕入原価だけが計上されて収入と支出のバランスが崩れてしまいます。そのため、家事消費を適切に計上しなくてはいけません。
それではいくつか具体例を見て見ましょう。
家電用品店がお店の商品を自宅用にした場合
15万円のドラム式洗濯機を自宅用にした場合とします。純粋に商品を自宅用にするシンプルなパターンです。まずは特例を使わず定価で計上してみましょう。
それでは、特例を使ってみるとどうなるでしょう。洗濯機の仕入価格7万5,000円だったとすると、75,000円(仕入価格)<105,000円(定価の70%)。仕入価格と定価の70%、いずれか高いほうを計上することになるため、ここでは10万5,000円が採用されます。
特例を使ったほうが、利益はより圧縮されることが理解できたかと思います。節税対策を重視したい場合には、特例での計上が基本になります。では、もうひとつ事例を見てみましょう。
10万円(仕入価格5万円)の商品を友人に4万円(定価の40%)で販売した
この事例は特例を使って計上してみましょう。まず、家事消費としての計上金額はいくらか考えます。
50,000円(仕入価格)<70,000円(通常販売価格10万円の70%)
上記より、金額の大きい7万円が家事消費に相当する金額です。ただしこの場合は、友人に4万円で販売しているため、この分は通常の売上として計上しましょう。よって、仕訳は次のようになります。
家事消費は税務調査の論点になりやすい
小規模事業者でもサービス業には無縁なことが多いものが家事消費です。ただし、家事消費が発生しやすい業種(特に飲食・小売業)では、1年分積み重ねるとそれなりのウエイトを占める科目でもあります。
家事消費が空欄だったり極端に少なかったりすると、税務調査で指摘されやすいことを覚えておきましょう。
正しく家事消費が計上されていない場合、調査官の裁量で家事消費の金額を認定されることも起こり得ます。ただし、計上金額の根拠を示すことができれば、その限りではありません。こちらが示した根拠を否定するのは調査官にとっても難しいからです。
家事消費は意外にも指摘事項になりがちな科目ですので、適切な計上をこころがけましょう。
確定申告について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
家事消費とは?
家事消費(自家消費ともいう)とは、商品・材料・製品などの棚卸資産を自分や家族のために使用することをさします。詳しくはこちらをご覧ください。
家事消費に該当するケースは?
商品を家庭用に使った、売れ残りを家庭用にした、定価より廉価で販売した、友人にプレゼントしたなどの場合が家事消費に該当します。詳しくはこちらをご覧ください。
家事消費に該当しないケースは?
役務(サービス)の提供や減価償却資産の処分は家事消費に該当しません。例えば、マッサージ店が友人に無料で施術した場合などです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
確定申告 経費の関連記事
新着記事
メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説
メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…
詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説
本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…
詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説
未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…
詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説
米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…
詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説
個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…
詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説
新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…
詳しくみる