- 更新日 : 2025年10月21日
個人事業主はロゴを作成するべき?メリット・作り方・費用処理を解説
ロゴは、個人事業主にとって単なる装飾ではなく、事業の印象や信頼性を左右する大切なビジネス資産です。ブランドを象徴するロゴがあることで、顧客との接点すべてに統一感が生まれ、認知度や信頼性を高められます。
本記事では、ロゴを作成するメリットから業種別の効果、活用シーン、自作・外注の方法、著作権・商標登録の注意点、費用の会計処理などを解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
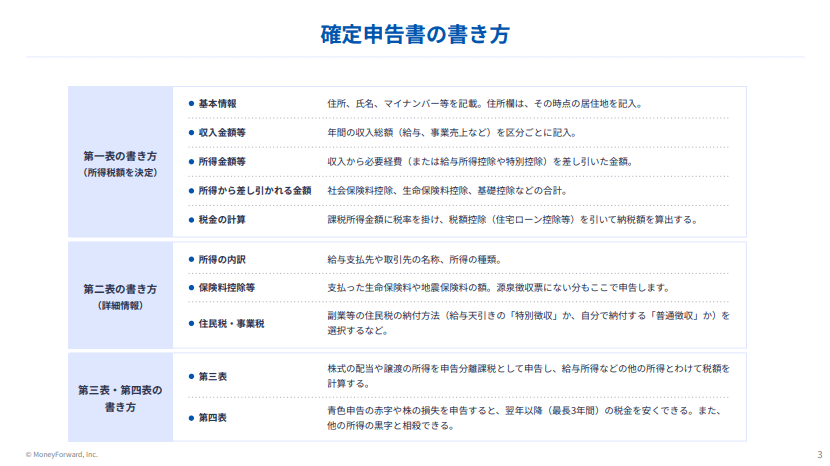
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主がロゴを作成するメリットは?
ロゴは個人事業主にとって、事業の「顔」となります。視覚的な印象が強く残るロゴは、認知度の向上と信頼構築において大きな効果を発揮します。ここでは、ロゴ作成によって得られるメリットを解説します。
ブランド認知が向上する
ロゴは視覚的に記憶されやすく、顧客の印象に残りやすい特徴があります。商品やサービスに満足した顧客は、そのブランド体験をロゴを通じて思い出すことが多く、ロゴを見るたびにその企業やサービスが連想されます。一貫してロゴを使用すれば、Webサイト・SNS・名刺など各種媒体で視覚的な統一感が生まれ、ブランド全体の印象が強化されていきます。
顧客からの信頼につながる
名刺や請求書にロゴがあるだけで、相手に「ちゃんとした事業者である」という印象を与えられます。個人で活動している場合、ロゴがあることでビジネスへの真剣さが伝わり、初対面の相手にも安心感を与えます。サービス業や士業、クリエイティブ系の職種では特に、プロフェッショナルな印象を与える要素としてロゴは有効です。
ブランドの統一感が生まれる
ロゴを名刺・SNS・Webサイトなどで統一して使用することで、顧客にとって分かりやすく、信頼感を生むブランディングが可能になります。媒体ごとに印象がバラバラだと、不安を与える原因にもなりかねませんが、ロゴが一貫して使われていれば、「この人(会社)だ」とすぐに認識されやすくなります。結果として、事業者としての印象が明確に定着します。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
ロゴの効果が大きい業種・場面は?
ロゴの効果は、顧客との接点が多い業種やブランドの印象が重視される場面で大きく発揮されます。店舗経営からオンライン販売、士業、クリエイティブ職に至るまで、ロゴの活用はビジネスの信頼性と認知度の向上につながります。
店舗ビジネスや対面型サービス業
飲食店、美容サロン、小売店などのリアル店舗では、看板やメニューにロゴを使用することで顧客に店舗の印象を強く残せます。外観や内装、ショップカードなどにロゴがあると、初めて訪れる人にも安心感を与えやすくなります。
オンライン販売・個人クリエイター
ネットショップやハンドメイド作家など、オンラインを通じて商品を販売する事業者にとっても、ロゴは重要な記号です。商品ページや梱包資材、SNSアイコンなどにロゴを表示することで、顧客に出品者の存在を印象づけ、リピーターの獲得にもつながります。
士業・コンサル・講師業などの専門職
税理士や行政書士、コンサルタント、講師など、知識や信頼が問われる職種でも、ロゴがプロフェッショナルな印象を与えます。名刺やWebサイトにロゴがあることで、事業への本気度や継続性が相手に伝わりやすくなります。
クリエイティブ職やフリーランス業
デザイナーやフォトグラファー、映像制作者など、自身の作品がブランドとなる職種では、ロゴは自身の個性や世界観を表現する重要なツールです。ロゴを持つことで、自身のブランド価値や差別化を図れます。
下請け・取引先が限定される業種でも効果あり
顧客との接点が少ない業種でも、ロゴを作成することで自分の事業に対する誇りを形にでき、モチベーションの向上にもつながります。外部に向けてだけでなく、内面的なブランディングの要素としてもロゴは活用できます。
ロゴはどんな場面で活用できる?
作成したロゴは、事業のあらゆる接点において活用できます。名刺やWebサイトに限らず、SNS、書類、店舗、商品など多くの場面で一貫してロゴを使うことで、ブランドの認知度や信頼性を効果的に高めることが可能です。ここではロゴの主な活用シーンを見ていきます。
名刺・ホームページ・SNS
ロゴはビジネスの第一印象を左右するため、名刺やWebサイトに掲載するだけでも十分に効果を発揮します。名刺では肩書きとともにロゴを配置することで、より印象に残るツールになります。Webサイトやブログでは、ヘッダーやフッターにロゴを組み込むことで、訪問者が事業主を視覚的に認識しやすくなります。また、SNSのプロフィール画像や投稿にロゴを活用すれば、情報が流れていく中でも発信元の識別が容易となり、視覚的なブランディングが確立されます。複数のメディアで同じロゴを使うことで統一感が生まれ、信頼感のある印象づけが可能になります。
書類・商品・店舗
ロゴは、見積書・請求書・領収書などの帳票類にも活用できます。書類にロゴがあるだけで「ちゃんとした事業体」としての印象を与える効果があります。封筒やレターヘッドにもロゴを入れれば、ビジネスのフォーマルさが伝わります。さらに、商品パッケージやタグ、ショッピングバッグなどにもロゴを印刷することで、顧客が購入後もブランドを記憶しやすくなります。店舗を持つ場合は、店頭看板やスタッフの制服にロゴを用いることで、顧客の目に自然と触れやすくなり、店舗全体のブランドイメージも強化されます。
個人事業主のロゴ作成方法は?
ロゴを作成する方法は大きく分けて「自作」と「外注」の2つです。それぞれの方法の特徴と選び方について解説します。
自分でロゴを作成する
自作はコストを抑えながら自由にデザインできる点が最大の魅力です。 IllustratorやPhotoshopなどのプロ用デザインソフトを使えば、高品質なロゴを一から制作することも可能です。ただし、それなりのデザインスキルと時間が必要となるため、慣れていない人にとってはハードルが高い面もあります。
より手軽な方法としては、Canva(キャンバ)のようなオンラインツールの活用が挙げられます。テンプレートを選んでカスタマイズするだけで、比較的短時間で見栄えの良いロゴが作成できます。また、最近ではMidjourneyやStable Diffusionといった画像生成AIを使い、キーワードからロゴのアイデアを生成する方法も注目されています。
ただし、AI生成画像を商用で使用する際は、著作権や類似デザインの問題に十分注意が必要です。テンプレートや無料素材の使い方によっては他者のロゴと類似しやすくなるため、オリジナリティを出す工夫も欠かせません。
プロのデザイナーに依頼する
外注すれば、完成度の高いロゴを効率良く手に入れられます。 依頼先としては、個人のフリーランスからデザイン事務所、クラウドソーシングサイトなど多様な選択肢があります。ココナラやクラウドワークスでは8,000円前後からロゴ制作を依頼できることもあり、平均は1〜2万円台です。価格が安いほど対応範囲が限られるケースもあるため注意が必要です。
フリーランスデザイナーへの依頼費用は5千円〜数十万円程度と幅広く、実績や提案内容によって大きく変動します。
一方、デザイン会社や制作事務所に依頼する場合、相場は10万〜50万円程度と高額ですが、構成や色彩設計などを含めた総合的な提案が期待できるほか、名刺やホームページとセットでの制作にも対応してもらえることが多く、ビジネス全体のブランディングに効果的です。
ロゴの制作費用は経費にできる?
個人事業主がロゴ作成にかけた費用は、原則として確定申告時に経費として計上できます。ただし、商標登録を行うかどうかによって処理方法が異なるため、正確な理解が必要です。以下では、経費処理できるケースと資産計上が必要なケースについて整理します。
経費処理できるケースと勘定科目
ロゴのデザイン費は通常は役務の対価として「広告宣伝費」や「外注費」として処理され、商標登録を伴わなければ当期の必要経費として計上できます。たとえばデザイナーに15万円を支払った場合、商標登録を行わない限りは全額を当期の広告宣伝費として処理可能です。繰延資産や開発費として計上できるのは法律で定められた限られた費用に限られるため、ロゴ制作費には通常当てはまりません。
一方、ロゴを商標登録して「商標権」として権利化した場合は、無形固定資産に該当します。この場合、取得価額はデザイン費に弁理士報酬などを含めて計上し、原則として10年間の定額法で減価償却します。
このように、商標権として権利化しない限り、ロゴ制作費は多くのケースで当期の費用として処理できます。
資産計上が必要な場合と減価償却
先述のとおり、ロゴ制作費が20万円以上で、商標登録を行う場合には注意が必要です。この場合は「商標権」として無形固定資産に計上し、原則として10年間の定額法で減価償却します。たとえば30万円でロゴを制作し商標登録した場合、毎年3万円ずつ費用計上することになります。なお、20万円未満であれば商標登録しても経費処理または一括償却資産としての処理が認められる場合があります。
また、個人事業主は法人と異なり、登録免許税も含めて資産計上しなければなりません。ロゴと商標登録をセットで考える場合は、これらの費用も含めて資金計画を立てておく必要があります。
経費処理の成否は、「20万円の壁」と「商標登録の有無」が分岐点となります。正確な処理で節税につなげるためにも、会計ソフトや税理士への相談も検討するとよいでしょう。
ロゴの著作権は誰に帰属する?
ロゴを作成した場合、その著作権が誰に帰属するかは、今後の商用利用やトラブル防止において非常に重要なポイントです。外注でロゴを制作する場合、著作権の扱いを契約で明確にしておかないと、思わぬ制限が生じる可能性があります。
自作の場合と外注の場合で著作権の所在が異なる
ロゴの著作権は、原則としてそのデザインを創作した人に自動的に発生します。 つまり、個人事業主が自分で作成した場合は、その事業主自身が著作権者となります。しかし、外部のデザイナーに依頼してロゴを作ってもらった場合は、制作したデザイナー側に著作権が帰属するのが原則です。
このため、納品されたロゴを名刺、Webサイト、パッケージなど多様な形で自由に商用利用したい場合には、契約書で「著作権の譲渡」や「利用許諾の範囲」を明確に取り決めておく必要があります。商標登録を考えている場合には、権利関係があいまいなまま進めるのはリスクとなります。
無料素材やテンプレート利用時も注意が必要
近年では、安価なロゴ作成サービスやテンプレート型のオンラインツールも普及していますが、これらには既存素材やフォントが使われていることも多く、その一部に第三者の著作権が存在する場合があります。
無料素材であっても、著作権が完全に放棄されているケースは稀です。そのため、自作・外注を問わず、使用する素材のライセンスや利用条件を確認し、必要に応じて正規のライセンスを取得することが重要です。ロゴを安全に使用し続けるためにも、著作権の所在と取り扱いについては必ず確認しておきましょう。
ロゴの商標登録はすべき?
ロゴを長く使い続ける予定があるなら、商標登録は強力なリスク回避策になります。特にブランドの独自性を守りたい個人事業主にとって、事業資産としてのロゴを保護することは重要です。ここでは、商標登録によって得られる利益と、実施前に確認すべき点を解説します。
商標登録によってロゴの独占使用が可能になる
商標登録を行うと、ロゴを独占的に使用できる「商標権」が発生します。 この権利を取得することで、他者が同一または類似のロゴを使用することを法的に防止できるため、ブランドの信頼性や競争力を維持するうえで非常に有効です。日本は先願主義のため、先に登録されたロゴが優先され、後から使い始めた側は制限を受けることになります。仮に第三者に商標登録されると、ロゴを使うたびに許可を得たり、場合によっては使用料の支払いが求められたりすることもあります。
ロゴの重要度に応じて登録を検討する
商標登録はすべてのロゴに必要ではなく、用途や将来性に応じて判断すべきです。特定のサービスや商品を象徴するロゴであれば、模倣によるブランド毀損を防ぐ意味でも登録の価値は高いです。一方、短期間のみ使うロゴや、業界内で独自性が低いデザインであれば、費用対効果の観点から登録を見送るという選択もあります。
また、将来的に法人化や全国展開を予定している場合も、早めの登録によって安心してブランド展開ができます。
著作権の整理と素材の利用条件に注意する
商標登録には、登録者がそのロゴを正当に使用できる状態であることが求められます。 自作であれば問題ありませんが、外注で制作したロゴの場合は、著作権が制作者側にあることが多いため、あらかじめ譲渡契約や使用許諾を結んでおく必要があります。また、ロゴに既存フォントやフリー素材を使用している場合、それらが商標利用を許可しているかどうかも事前に確認しておきましょう。フォントの中には、商標登録への利用を禁じているものも存在します。
ロゴは小さな投資で大きな価値を生むビジネス資産
個人事業主にとってロゴは、顧客との信頼関係を築き、ブランドを明確に伝えるための有効なツールです。業種や事業規模を問わず、名刺・SNS・Webサイト・商品パッケージなど幅広い場面で活用することで、認知度や印象が大きく向上します。また、ロゴ制作費は商標登録の有無によって会計処理が変わるため、正しい知識と準備が欠かせません。著作権や商標登録の整理を通じて、安心して長く使えるロゴを持ち、事業の信頼と個性を発信していきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
ヤマトビジネスメンバーズを個人事業主が使うには?メリット・料金・注意点まとめ
ヤマトビジネスメンバーズ(YBM)は、ヤマト運輸が提供する法人・個人事業主向けの発送支援サービスです。個人事業主でも契約が可能で、送り状の発行、集荷依頼、月次請求、Webでの請求書…
詳しくみる【個人事業主向け】出金伝票の書き方とは?勘定科目や注意点、保存について解説
個人事業主は、事業を行ううえで必要な出費があった際に出金伝票を書く場合があります。出金伝票は現金を支出したときに記載する伝票で、勘定科目と支出額を記載することで、事業に必要な支出の…
詳しくみる個人事業主に角印は必要?使用する場面やサイズについて解説
角印は、業務上で使用する四角い形状の認印です。個人事業主にとって角印は法的に必須ではありませんが、取引の信頼性を高め、業務を円滑に進めるために役立つアイテムといえます。 本記事では…
詳しくみるインボイス制度で個人事業主の経費精算方法が変わる?飲食店の注意点も解説
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要です。従来の請求書や領収書では、経費にできません。 本記事では、インボイス制度での仕訳ルールや、仕訳…
詳しくみる個人事業主がお金を残す方法とは?資金繰り・節税・貯蓄のポイントを解説
個人事業主として安定した経営を続けていくためには、「稼ぐ力」だけでなく「お金を残す力」も欠かせません。帳簿上の利益が出ていても手元に現金が残らない背景には、複数の要因があります。 …
詳しくみる個人事業主で手取り月50万円を目指すには?税金・社会保険・節税対策を解説
個人事業主として月収50万円を稼ぐことは、多くの人にとって一つの目標です。しかし「月収50万円」といっても、それが売上なのか、経費を差し引いた事業所得なのか、あるいは税金・保険料を…
詳しくみる



