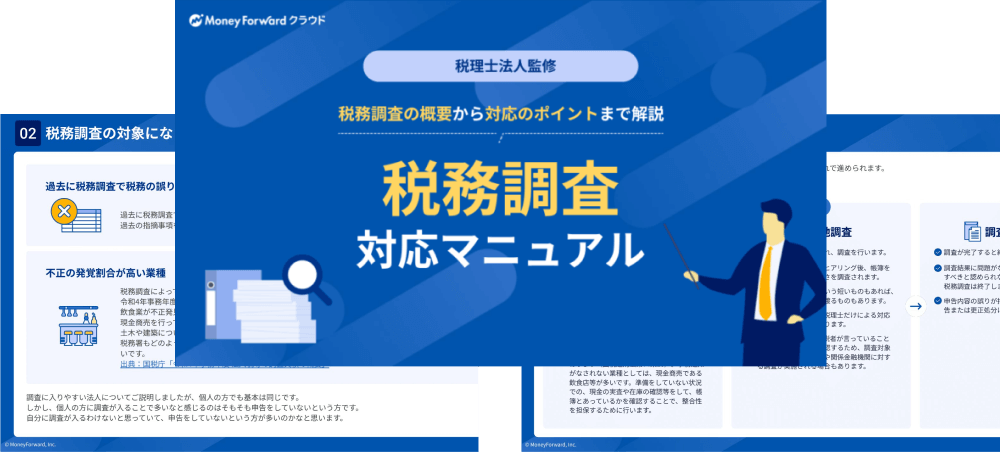- 更新日 : 2025年3月5日
個人事業主の就労証明書の書き方は?フォーマットのダウンロード方法や注意点を解説
保育園の入園審査や住宅ローンの申し込みで使用するため、従業員から就労証明書(雇用証明書)の作成を求められるケースがあります。あまり作成する機会のない書類ですが、今回は個人事業主が従業員を雇用しているケースで就労証明書を作成する方法やフォーマットの入手方法などについて解説します。
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

就労証明書とは
就労証明書とは雇用証明書とも呼ばれ、従業員が現在働いている会社に間違いなく雇用されていることを会社が証明するための書類です。現在雇用されていることの証明だけでなく、雇用されることが決まり、これから就労する予定である場合も、その旨を記載することで就労予定であることを証明できます。
個人事業主が就労証明書を利用する場面
個人事業主が就労証明書を作成する場面として想定されるのは、従業員を雇用していて当該従業員が保育園の入園審査や住宅資金の借り入れをする目的で会社に証明書の発行を求めるケースです。就労証明書の提出が必要な理由は、さまざまな審査における基準の1つとして、従業員が間違いなく雇用されていることを第三者が作成した書類で確認するためです。
就労証明書には法的に定められた様式はなく、任意のフォーマットのなかに雇用形態や入社年月日、勤務時間、勤務日数などの必須項目を記載していれば構いません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
就労証明書のフォーマットのダウンロード方法
就労証明書には、官公庁で定められた法的な様式はなく、任意のフォーマットで作成することになります。就労証明書のフォーマットを入手できるサイトをいくつか紹介します。
こども家庭庁のホームページ
こども家庭庁は内閣府の外局であり、子育て世代の支援や子供の権利保護などを目的に活動する機関です。その一環として、保育園の入園審査や住宅ローンの審査などで必要になる就労証明書のフォーマットをHP上で提供しています。
マイナポータルの就労証明書作成コーナー
マイナポータルは内閣府が運営するポータルサイトの1つであり、申告や申請手続きなどの行政サービスをインターネットを使って効率的に利用できるよう設置されたものです。就労証明書については、HP内のエクセルファイルをダウンロードして作成できます。なお、就労証明書のフォーマットはマイナンバーがなくても利用できます。
各自治体のホームページ
各自治体の多くが、独自の就労証明書のフォーマットを提供しています。お住まいの都道府県や市区町村のHPから、PDF形式やエクセル形式、ワード形式などのフォーマットを入手できます。
参考:就労証明書|江戸川区、「就労証明書」
個人事業主の就労証明書の書き方
次に、就労証明書に記載すべき必須項目を具体的に見ていきましょう。
証明日や代表者名などの右上欄
フォーマットの右上に就業証明書を作成した日付と、作成者である個人事業主の会社名や住所、電話番号、代表者の氏名などを記載します。就業証明書をいつ誰が作成したか分かるようにすることと、内容について照会する際の連絡先が分かるようにしておきます。
業種
従業員が就労している業種について、小売業・製造業・建設業 といった大分類で記載します。「○○の製造販売」「土木工事業」など、具体的な業種を記載しても構いません。
雇用(予定)期間等
従業員をいつからいつまで雇用するのか、その雇用期間を記載します。また、新入社員や中途採用など、これから雇用する予定の従業員について証明書を作成する場合は、雇用予定日を記載します。
本人就労先事業所
従業員が就労する事業所の住所や連絡先を記載します。
雇用形態
正社員・パート・アルバイト・契約社員など、従業員の現在の雇用形態について記載します。これから採用する従業員についても、予定している雇用形態を記載します。
就労時間
従業員の就労時間を「平日」「土曜日」「日曜・祝日」の別に、「午前○○時から午後○○時」といったように記載します。その際、就労時間に含まれる休憩時間を内書きとしてあわせて記載しましょう。
就労実績
当該従業員に過去、どのような就労実績があるかを記載します。例えば、「○○年○○月」に何日就労し何時間働いたか、といった実績データが必要です。証明日直近3ヶ月の実績データを最新のものから順に記載しましょう。
産前・産後休業の取得
就労期間のなかで、当該従業員が取得した産前・産後休業について、その実績データを記載します。また、これから産前・産後休業を取得する予定の場合は、その予定期間を記載します。
育児休業の取得
就労期間のなかで、当該従業員が取得した育児休暇についての実績データを記載します。これから育児休暇を取得する予定の場合は、その取得予定期間を記載します。
産休・育休以外の休業の取得
就労期間のなかで、当該従業員が産前・産後休業や育児休暇以外の休業を取得している場合について実績データを記載します。これから休業を取得する予定の場合も、取得予定期間を記載します。
復職(予定)年月日
産前・産後休業や育児休業、それ以外の休業を取得中の従業員が、復職した年月日を記載します。また、これから復職する予定の場合はその予定日を記載します。
育児のための短時間勤務制度利用有無
育児をしている従業員の希望で短時間勤務を利用できる社内制度がある場合、当該勤務制度利用の有無や、利用している期間、利用期間内の勤務時間などを記載します。
保育士等としての勤務実態の有無
保育士等の資格と就労証明書は直接的な関係はありませんが、保育士等の人手不足であり、子育てをしながら保育士として就労できる人材を採用時に優遇しようという狙いがあるようです。
備考欄
その他、当該従業員について特記すべき事項があれば備考欄に記載します。
個人事業主が就労証明書を書く時のポイント・注意点
次に、就労証明書を作成する際に注意すべき点について解説します。
就労証明書が複数必要になるケースがある
保育園の入園審査の際、複数の子どもを預けるようなケースで人数分の就労証明書の提出を求められることがあります。この場合、同じ内容で複数枚の証明書を作成する必要があるため、手書きよりエクセル形式やワード形式で作成しておくと便利です。ただし、保育園によっては原本のコピーで対応してくれる場合もあるため、提出先に確認してから作成しましょう。
必ずボールペンで記入する
就労証明書は保育園や金融機関などの証明書として利用するため、加除訂正ができないようにする必要があります。鉛筆やシャープペンシルなどでは、文字の訂正が容易にできてしまうため、手書きで就労証明書を作成する際には必ずボールペンを使用しましょう。
提出期限に間に合うように作成する
保育園の入園審査などでは、就労証明書の提出期限が設けられているケースがほとんどです。提出期限内に証明書の提出が間に合わない場合、その年分の入園手続きができなくなる可能性が高くなります。従業員に証明書の提出期限を必ず確認し、間に合うように発行するようにしましょう。
保育園を利用する際に就労証明書とあわせて提出が求められる書類
保育園の入園審査で就労証明書とあわせて提出を求められる書類について、代表的なものを紹介します。
源泉徴収票
従業員が雇用されていることを証明する書類として、源泉徴収票の提出を求められるケースがあります。源泉徴収票は一般的に会社が年末調整を行った後に発行されるため、大切に保管しておきましょう。なお、保育園には毎年直近の源泉徴収票を提出することになります。
確定申告書
個人事業主の場合、就労証明書のかわりに確定申告書の提出を求められるケースがあります。令和7年1月以降、確定申告書の控えに収受印を押印してもらうことはできなくなりましたが、申告書を提出する際には必ず控えを手元に残しておきましょう。
求職受付票
就職活動中に保育園の入園審査を受ける場合には、就職活動中である旨の証明書が必要です。ハローワークを使って就職活動を行っている場合、初回登録時に求職受付票というカードを渡されるため、写しを提出することで間違いなく就職活動を行っていることを証明できます。
就労証明書に記載すべき項目を確認しましょう
就労証明書には、従業員に関するさまざまな情報を記載する必要があります。必須項目に1つでも記載漏れがあると手続きが遅れることがあるため、作成する前にもう一度記載すべき項目について確認してから着手しましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主におすすめの店舗火災保険とは?保険料の相場や比較ポイントなど
店舗を構えて事業をしている個人事業主は、店舗火災保険に加入したほうがよいでしょう。なぜなら万が一、店舗が火災にあっても一定の補償を受けられるからです。 店舗火災保険は、保険会社によ…
詳しくみる個人事業主は傷病手当金を受け取れる?加入しておくべき保険や経費計上について解説
個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がなく、ケガや病気で働けなくなった場合、手当金を受け取ることができません。働けない期間の収入が減少するため、リスクに備える必要が…
詳しくみる小規模企業共済は廃業したらどうなる?個人事業主が知っておきたい手続きや注意点を解説
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業経営者が退職や廃業に備えて積み立てる制度で、老後資金や事業終了時の資金として活用できます。掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果を得なが…
詳しくみる給与計算ソフトは個人事業主に必要?種類・機能・おすすめの選び方を解説
個人事業主として従業員を雇用したり、家族に給与を支払ったりする場面では、給与計算の正確性と効率性が求められます。法令に沿った処理が必要な一方で、税率の変更や年末調整への対応には一定…
詳しくみるダブルワークする個人事業主の社会保険は?勤務先で社会保険に加入する条件や社会保険料を解説
個人事業主がアルバイトやパートなどのダブルワークをする際に、気になるのが社会保険のことです。個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入するのか、アルバイト先の社会保険に加入するの…
詳しくみる仕事中の怪我は国民健康保険で対応できる?個人事業主が知るべき補償や備えを解説
個人事業主は、仕事中の怪我に対する公的な補償が会社員と比べて限定的であることを理解しておく必要があります。会社員であれば労災保険や傷病手当金によって治療費や休業中の収入が保障されま…
詳しくみる