- 更新日 : 2025年7月7日
個人事業主におすすめの就業不能保険は?種類の違いや選び方を解説
個人事業主は、病気やケガで働けなくなった場合に備える「就業不能保険」の活用が重要です。 社会保障制度が会社員ほど手厚くない個人事業主にとって、収入源を失うリスクへの備えは欠かせません。本記事では、個人事業主におすすめの就業不能保険について、主な種類ごとの特徴と違い、選び方のポイントを解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
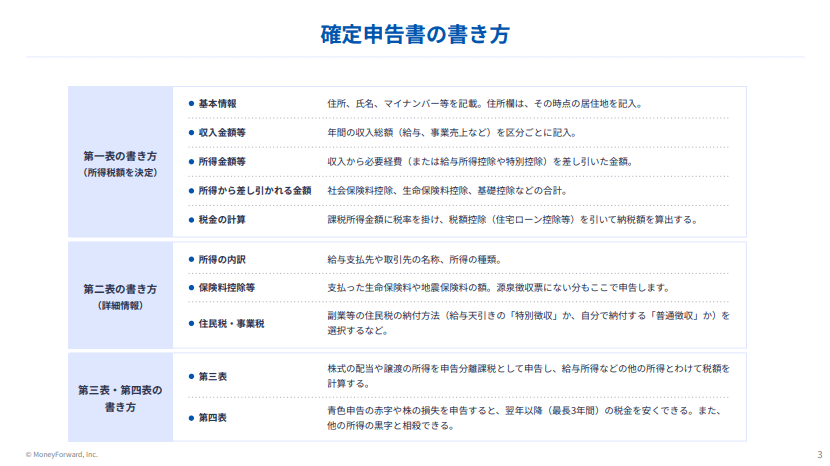
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主に就業不能保険が必要な理由
個人事業主は会社員に比べて公的補償が薄く、病気やケガで働けなくなったときのリスクに直接さらされます。治療費だけでなく、休業中の生活費も自己負担となるため、長期的な所得補償を目的とした保険の重要性が高まります。
ここでは、個人事業主にとって就業不能保険がなぜ必要なのかを解説します。
公的補償制度が限定的である
会社員は健康保険により傷病手当金を受け取ることができますが、個人事業主が加入する国民健康保険にはその制度がありません。結果として、病気やケガで働けない間の収入は完全に途絶える可能性があります。さらに、公的年金制度においても、個人事業主が受け取れる障害基礎年金は、重度の障害に該当する場合に限られ、軽度の就業不能状態では十分な保障が得られません。そのため、民間の就業不能保険を活用して収入減を補う必要性が高まります。
所得減少の直接的な影響に備える
会社員であれば、有給休暇や会社の福利厚生制度を利用して一定期間の所得補償を受けられる場合があります。しかし、個人事業主は休業した瞬間から売上がゼロになるケースも少なくありません。そのため、病気やケガで短期間でも仕事を休まざるを得ない状況が生じた場合、事業と生活に大きな影響を与えかねません。こうしたリスクに備えて、安定した所得補償を提供する就業不能保険の加入が重要になります。
治療費と生活費の両面から家計を守る
病気やケガにより入院や長期療養が必要になった場合、医療費だけでなく、日々の生活費が大きな負担となります。医療保険では通常、入院費用や手術費用など治療面の保障はカバーされますが、生活費の補填までは期待できません。個人事業主にとって、家賃や住宅ローン、食費、光熱費などの固定費は治療中であっても発生し続けるため、就業不能保険で生活費を支える体制を整えておくことで、治療に専念できる環境が生まれます。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
就業不能保険の主なタイプと特徴
就業不能時の収入減少に備える保険には、いくつかの種類があります。ここでは個人事業主に知っておいてほしい主な保障タイプを紹介します。それぞれ保険会社や仕組みが異なり、補償期間や対象となる範囲も違います。自身の業種や働き方に合ったタイプを理解することで、より効果的な備えを選択できるでしょう。
所得補償保険
所得補償保険は損害保険会社が扱う商品で、ケガや病気で一時的に働けなくなった場合の所得減少を補償するタイプです。契約は1年更新型が多く、給付金の支払期間も最長1〜2年程度と短期の補償に特化しています。例えば骨折で数ヶ月間働けないといったケースで、入院中や自宅療養中の収入減をカバーできるのが特徴です。比較的軽度で回復が見込まれる傷病に備えるのに適しており、保険料も長期型に比べると割安になりやすい傾向があります。
適した業種・働き方
肉体労働や建設業などケガのリスクが高い職種の個人事業主に向いています。短期間の入院や療養による売上減少を補いたい場合に有効です。また、開業間もないフリーランスで資金に余裕がない方が手頃な保険料で最低限の保障を確保する際にも検討しやすいでしょう。
就業不能保険
就業不能保険は生命保険会社が提供する商品で、病気やケガで長期間働けなくなった場合の収入途絶に備えるタイプです。保険期間は10年定期や55歳・65歳までなど長期に設定されるのが一般的で、重い病気や障害で何年も就業不能が続くケースまでカバーします。給付金は月々決まった額が年金形式で支払われ、支給期間も保険期間に準じて長期に及びます。例えば脳卒中で長期間寝たきりになった場合や、がんの長期治療で働けない期間などでも、定年相当の年齢まで生活費をサポートできるのが強みです。
適した業種・働き方
家族の生活を支える大黒柱である個人事業主や、住宅ローンなど長期の支出を抱える方に適しています。特に専門職・経営者で自身が働けなくなると事業継続が難しい場合や、慢性疾患による長期療養リスクが心配な方は、この長期保障型で万一に備える意義が大きいでしょう。保険料は短期型より高めですが、その分保障範囲が広く期間も長いため、経済的打撃の大きいリスクに備える安心感があります。
医療保険の就業不能特約(医療+所得保障型)
医療保険の就業不能特約は、民間の医療保険や生命保険に付加できる特約(オプション)として提供される就業不能保障です。
通常の医療保険が入院や手術の費用を保障するのに対し、特約を付けることで働けない間の生活費もサポートできるようになります。たとえば入院や自宅療養が30日以上継続すると所定の就業不能状態と認定され、以後毎月一定額の給付金を受け取れる商品があります。このタイプは入院給付金+就業不能給付金という形でセットになっているため、治療費と生活費の両面を一つの保険で備えたい人に向いています。
適した業種・働き方
既に民間の医療保険に加入している個人事業主や、入院リスクの高い業種の方に適しています。例えば飲食業や運送業で入院を伴う病気に備えて医療保険を検討する際、就業不能特約も付けておけば退院後の自宅療養期間の収入減もカバーできます。ただし、特約型は主契約の医療保険に付随するため、特約だけ単独で加入することはできません。また給付条件や期間が商品ごとに定められている点に留意が必要です(例:就業不能給付金の支払いは最長2年など)。
長期傷病保険(長期療養対応タイプ)
長期傷病保険は、長期にわたる療養や障害状態に備える所得保障保険です。名称は類似しますが、一般的には企業向けの**団体長期障害所得補償保険(GLTD)**などを指すことが多く、社員が長期間就業不能になった場合に定年まで所得を補償する制度を指します。個人事業主の場合、自身のみでこうした団体保険に加入することはできませんが、同様の長期保障を得る手段として前述の就業不能保険(生命保険タイプ)が相当します。要するに、長期傷病に備える保険=長期の就業不能保険と考えてよいでしょう。最近では生命保険各社から、個人で加入できる長期就業不能保障の商品が充実してきており、精神疾患による就業不能までカバーするプランも登場しています。
適した業種・働き方
長期間の収入途絶が致命的となる業種全般に適しています。特に一人会社の経営者や専門職で、代替の働き手がいない場合には長期の所得補償が欠かせません。フリーランスエンジニアやデザイナーで自身が長期離脱するとプロジェクト継続が困難になるケースでは、この種の長期療養対応の保険で事業継続資金を確保できます。またメンタルヘルス面のリスクにも備えたい場合は、全疾病型(精神疾患含む)の就業不能保険を選ぶことで幅広い事由に対応可能です。
個人事業主が就業不能保険を選ぶポイント
自分に合った保険を選ぶためには、いくつかの比較ポイントを押さえることが重要です。以下では、個人事業主が就業不能保険を選ぶ際に重視すべき主な項目を解説します。
保険料(掛け金)を基準にする
毎月支払う保険料は、保障内容と家計負担のバランスを取るうえで大きな判断基準です。所得補償保険のような短期型は保険料が低めで、比較的導入しやすい設計となっています。一方、長期保障型や特約が充実したプランは保険料が高くなりやすいですが、長期間にわたる安心感を得ることができます。また、同じ保障額であっても待機期間を長く設定することで保険料を抑える工夫ができる商品もあります。契約時には現在の収入や貯蓄状況をもとに、無理のない範囲での保険料設定を検討しましょう。
給付金額(保障額)の目安を考える
就業不能状態に陥った際、毎月受け取る給付金額は生活に直結します。生活費、固定費、事業継続費などを総合的に見て、必要最小限の額を設定するのが現実的です。給付金額が高すぎると保険料も上がり、実際の生活ニーズを上回るリスクもあります。保険会社は、加入者の年収や所得に見合った上限を設けており、過剰な保障はできない仕組みです。目安としては、住宅ローン、光熱費、食費など基本的な支出を賄える金額を設定することが有効です。
待機期間(免責期間)の長さとバランスを取る
待機期間とは、就業不能状態が始まってから給付金の支払いが開始されるまでの期間を指します。例えば「60日免責」とは、60日間就業不能であっても給付がなく、61日目から支給されることを意味します。早めに保障が欲しい人には、7日や14日といった短い待機期間が選べる商品もありますが、保険料は上がる傾向にあります。貯蓄などで一定期間を自力で乗り切れる人は、長めの免責期間を選ぶことで保険料を下げる工夫が可能です。生活防衛資金の有無と照らし合わせて選ぶとよいでしょう。
加入条件・引受条件を事前に確認する
就業不能保険には、加入できる年齢範囲や健康状態、職業に応じた引受条件が定められています。契約時の年齢制限や持病の有無、既往歴などによっては加入が制限されたり、特定の病気に対して保障が受けられないケースもあります。また、建設業や配送業など危険度が高い職種の場合、保険料が割増になったり、引受不可となる可能性もあります。個人事業主としての収入証明が求められることもあるため、事前に保険会社の基準をよく確認しておきましょう。
保障対象となる範囲を確認する
給付金の対象となる病気やケガの範囲は保険商品によって異なります。多くの商品では「入院」や「医師の指示による自宅療養」が一定日数以上続くことを要件としていますが、なかには「所定の障害状態」「要介護状態」といった条件が含まれるものもあります。また、精神疾患を給付対象としない保険もあり、うつ病や適応障害などが心配な方は対象範囲をよく確認しておく必要があります。仮に精神疾患がカバーされていても、給付期間に通算制限(たとえば1年まで)が設けられている場合があります。
保険会社の信頼性と対応力をチェックする
就業不能保険は万一の際に頼る保障です。いざという時に確実に給付されるかどうかは、保険会社の財務健全性や顧客対応力にかかっています。支払実績や顧客満足度などの外部評価を確認し、公的なソルベンシー・マージン比率などの財務指標をチェックしておくと安心です。また、保険金請求時のサポート体制や問い合わせ窓口の対応の丁寧さなども比較ポイントになります。長期契約になることが多いため、信頼できる会社との契約が安心につながります。
個人事業主におすすめの就業不能保険
個人事業主に人気の高い就業不能保険を3つご紹介します。
SBI生命「働く人のたより」
SBI生命の「働く人のたより」は、月額保険料が2,415円(40歳男性、月額給付金15万円、65歳満了の場合)と、手頃な保険料で全疾病型の就業不能保障を提供しています。所定の就業不能状態が60日以上継続した場合、保険期間満了まで毎月給付金を受け取ることが可能です。ただし、精神疾患による就業不能の場合、給付は通算18回が限度となります。
ライフネット生命「働く人への保険3」
ライフネット生命の「働く人への保険3」は、月額保険料が3,263円(40歳男性、月額給付金15万円、65歳満了の場合)で、病気やケガによる長期の就業不能に備える保険です。支払対象外期間は60日または180日から選択可能で、14日以上の入院や所定の精神疾患による就業不能状態が継続した場合に一時金が支給される特約もあります。
チューリッヒ生命「くらすプラスZ」
チューリッヒ生命の「くらすプラスZ」は、短期と長期の就業不能状態の両方に備えることができる保険です。月額保険料は4,050円(40歳男性、月額給付金15万円、65歳満了の場合)で、長期収入サポート給付金は保険期間満了まで支給されます。ただし、精神および行動の障害による在宅療養は支払い対象外となる点に注意が必要です。
自分の働き方に合った就業不能保険を選ぼう
個人事業主にとって、就業不能保険は万一の収入減に備える重要なセーフティネットです。短期型・長期型それぞれの特徴を理解し、自身の業種リスクや家族構成にマッチしたプランを選ぶことが肝心となります。保険料や給付条件など比較ポイントをしっかりチェックしながら検討すれば、万が一働けなくなっても生活と事業を支える「頼れる保障」を用意できるでしょう。公的保障が手薄な分、早めの備えで将来の不安に備えておくと安心です。今回解説したポイントを参考に、納得のいく就業不能保険を選んでください。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
個人事業主の出張費は経費にできる?食事代や日当は?按分や確定申告のポイントも解説
出張にかかる費用は、事業に関係していれば経費として処理できますが、その範囲や条件を誤ると税務上のトラブルにつながるおそれがあります。 本記事では、交通費・宿泊費・通信費といった代表…
詳しくみる個人事業主の開業手続きの流れとは?準備から届け出・確定申告までのステップを解説
個人事業主として新たにビジネスを始めたいと考えたとき、まず何から手を付けるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。開業には、事業計画の立案や資金準備だけでなく、税務署への届け出、社…
詳しくみる個人事業主の大型トラック運転手は稼げる?年収相場や経費管理のポイントを解説
大型トラックの運転手として独立し、個人事業主として働くことを検討している方にとって、年収や経費、税金の実態は気になるポイントではないでしょうか。会社員とは違い、自ら仕事を確保しなが…
詳しくみる個人事業主が業務改善助成金を活用するには?要件・助成額・申請の流れを解説
個人事業主にとって、従業員の雇用や設備投資は事業運営の大きな課題です。そんな中、厚生労働省が実施する「業務改善助成金」は、従業員の賃上げと生産性向上を支援する制度として注目されてい…
詳しくみる個人事業主が知っておきたい課税売上高とは?計算方法や1000万を超えた場合の解説
消費税の計算において、「課税売上高」とは事業者の売上高のうち「消費税の課税対象とされる取引の合計額」のことを言います。インボイス制度の導入により、事業者として消費税をより身近に感じ…
詳しくみる個人事業主が雇う従業員の給与の決め方とは?確認項目まとめ
個人事業主が従業員を雇う場合、従業員の給与を決める必要があります。従業員の給与を決める際は、業務範囲や給料の相場などさまざまな点を考慮することが大切です。 本記事では、個人事業主が…
詳しくみる



