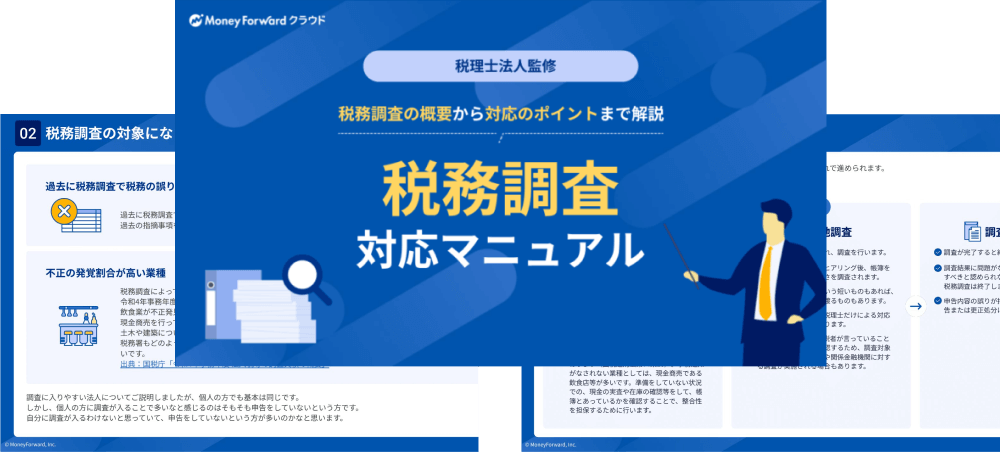- 更新日 : 2023年1月26日
宝くじに当選したら確定申告は必要?
収入額から必要経費を差し引いたものを、「所得額」といいます。所得額をもとにした所得税の計算で、納付すべき所得税がある場合は、所轄の税務署で所得税の確定申告をしなければなりません。
例えば、宝くじを購入して高額当選した場合、購入費を差し引いた当選額が所得になるのではと考える人もいるでしょう。宝くじに当選したら、確定申告は必要なのでしょうか。あるいは、非課税扱いで確定申告は必要ないのでしょうか。
今回は、宝くじの当選金の確定申告は必要かどうか、また注意点について解説していきます。
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

宝くじに高額当選した場合、確定申告は必要?
結論から述べると、宝くじで高額当選しても確定申告は必要ありません。理由は、宝くじによる所得は非課税所得になることと、宝くじ購入の時点ですでに税金を納めているためです。
宝くじの当選金は非課税所得
原則、所得税は納税義務者のすべての所得に課税することと規定されています。しかし、非課税所得に分類されるものは所得税の課税対象から外されます。非課税所得とは、社会政策などの見地から所得税を課さない所得のことです。
宝くじの当選金は、非課税所得になるため、所得税は課税されません。よって、所得税を申告するための確定申告は不要です。
ほかに、地方税である住民税の課税対象からも外れます。対価性がある取引ではないため、消費税も非課税です。つまり、宝くじに当選しても、当選金にかかる税金は発生しないということになります。
宝くじは購入時に税金がとられている
もうひとつ、宝くじに当選しても確定申告が必要ないのは、宝くじを購入した時点で税金を納税したことになるためです。
そもそも宝くじの発売は、一般企業や個人には認められていません。発売元は地方自治体で、発売にかかる事務を銀行などに委託しています。
宝くじの販売による売上高は、当選者への当選金の支払いに充てられるほか、発売のための経費や社会貢献広報費などに充てられます。残りは、収益金として都道府県などに納められ、公共事業に使われます。ちなみに、令和2年度は、36.6%が地方自治体の収益金として納められました。
宝くじの購入費の一部が地方自治体の公共事業に充てられるということは、つまり購入した時点で、実質的に税金を納めていることになるのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
宝くじの当選金の使い道によっては税金が課される
宝くじの当選金は、当選者が自分で使う分には特に問題はありません。しかし、使い道によっては所得税以外の税金が発生することがあります。
当選金を贈与すると贈与税の対象に
宝くじの当選金の一部を家族や友人などにあげることもあるでしょう。当選金を贈与すること自体に問題はありませんが、贈与は贈与税の課税対象になります。贈与税は、贈与をする側(この場合は当選者)が負担するものではありませんが、贈与を受けた人は贈与税を納めなければなりません。
暦年課税の場合は、1月1日から12月31日までの1年間の贈与税の基礎控除額は110万円です。110万円を超える贈与は贈与税が発生しますので、当選金をあげる際は、金額によって贈与税が発生する可能性があることに注意しましょう。
使わずにとっておくと相続税の対象に
高額当選の場合、当選者が当選額にあまり手を付けないまま、または一部を残したまま亡くなってしまうことも考えられます。使わずにとっておいた当選金は、相続時の遺産額に組み込まれます。
亡くなった人が所有していた土地や建物などとは違い、評価の特例などがないため、残った額をそのまま時価で評価しなくてはなりません。
例えば、当選金を銀行に預けたまま、まったく手を付けずに相続が発生した場合は、当選額の入金から相続開始までの間に利息の支払いも行われていることも想定すると、当選額の入金時よりも財産が増えていることになります。
銀行に預けている間に増えた利息も合わせて、当選金は相続税の計算の対象になります。相続額次第では、相続税が発生し、相続した人が相続税を負担しなければなりません。
宝くじ当選後、税務署から税務調査を受ける?
税務調査とは、税務署の職員などが行う手続きで、納税義務者の税額を特定し、必要に応じて処分を行う行為をいいます。基本的には、宝くじに当選したという理由で、税務署から税務調査を受けることはありません。税務調査は、申告の内容が正しいかなどを目的に行われるものであって、宝くじの当選金は非課税であり、所得税の課税対象にはならないためです。
ただし、高額当選すると、税務署に当選金の情報が把握される可能性はあります。当選金を贈与したにもかかわらず贈与税の納税がない場合などは、税務署から指摘を受ける可能性もあるでしょう。
宝くじに当選したら、必ず当選証明書をもらいましょう
宝くじの当選で税務調査を受けることはありませんが、事業を行っている場合など、その事業の申告に関連して税務調査を受けることはあります。
高額当選者は税務署からお金の流れを把握されている可能性がありますが、当選額がそこまで大きくないときは、税務署側が把握していないことも考えられます。事業関連など別の税務調査で、ほかに収入があると疑われないようにするためにも、当選したら当選証明書をもらうようにしましょう。
宝くじに当選しても確定申告は不要!ただし使い道には要注意!
宝くじに当選して高額を手にしても、当選金は非課税所得に該当するため、確定申告は不要です。しかし、当選金の一部を人に渡したり、当選金が残ったまま亡くなったり、その後の当選金の使われ方次第では税金が発生することもあります。使い道には注意しましょう。
はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法
確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。
個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。
①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。
②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。
③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。
追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える
有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料
マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典


マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
宝くじに当選したら確定申告が必要?
宝くじは非課税所得で、購入時に税金を納めていることになるため、高額当選しても確定申告は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
宝くじ当選後の使い道次第で課税される?
宝くじを贈与したときは贈与を受けた人が、当選金の相続があったときは相続を受けた人が、税金を負担しなければならないことがあります。 詳しくはこちらをご覧ください。
宝くじに当選すると税務調査を受ける?
宝くじ当選を理由に税務調査を受けることはないですが、高額当選だと税務署にお金の流れを把握されている可能性がありますし、別の理由で税務調査を受けることはあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
災害による損害が発生した時の確定申告
被災して、住宅や家財の一部またはすべてに損害があると、生活や事業の継続が困難となり、結果として担税力が低下することがあります。そこで設けられているのが、災害による損害を受けた場合に…
詳しくみるアイドルの確定申告のやり方は?芸能事務所の報酬形態や経費による節税対策も
アイドルとして生計を立てている方や、会社員の傍ら副業でアイドルをしている方は働き方や所得によって確定申告が必要になる場合があります。確定申告のやり方は、芸能事務所との契約形態によっ…
詳しくみる配当控除とは?確定申告での配当金の計算方法までわかりやすく解説
配当金があった場合、確定申告にあたって受けることができる所得控除の一つに配当控除があります。この記事では、配当控除の適用方法や計算などについて解説します。 配当控除とは 配当控除と…
詳しくみる非常勤の消防団員は確定申告が必要?
非常勤の消防団員、いわゆる地域の消防団員は、出勤がある場合などに報酬を受け取ります。では、非常勤の消防団員は確定申告が必要なのでしょうか。実は、2022年4月の税制改正で非常勤の消…
詳しくみるタクシー運転手は確定申告が必要?個人タクシーはどこまで経費にできるかも解説
タクシー運転手も、確定申告が必要になる場合があります。この記事では、個人タクシーと法人タクシーの運転手について、確定申告が必要になる場合や確定申告のやり方、個人タクシーの運転手が確…
詳しくみる個人事業主・フリーランスの家賃は確定申告で経費にできる?按分計算の方法も解説!
個人事業主の事業所については、賃貸物件である場合と持ち家である場合とがあります。そのどちらの場合にも、自宅兼事務所となっていることもあります。 例えば家賃については、確定申告で所得…
詳しくみる