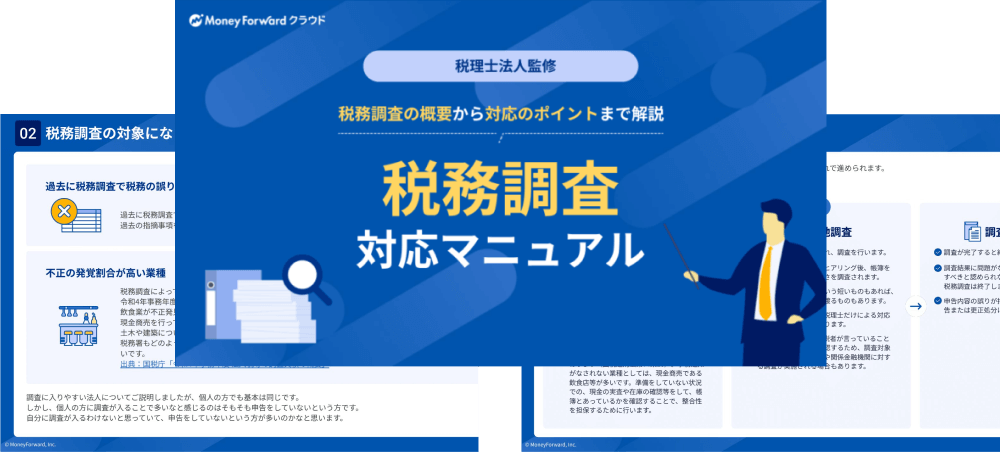- 更新日 : 2023年1月26日
遺族年金とは?受給したら確定申告は必要?
遺族年金は、年金の被保険者が亡くなったときに、配偶者やその子どもに支給される年金です。遺族年金を受給できれば、生活を維持するために必要なお金が得られるため、残された家族にとっても非常に大切な制度といえます。
そこで当記事では、遺族年金とは何かを解説し、受給するための手続きや確定申告が必要かどうかについて紹介します。
目次
フォームに順番に入力するだけで、控除や還付金を受け取るための確定申告も簡単に。「マネーフォワード クラウド確定申告」は、医療費控除・社会保険料控除、ふるさと納税・住宅ローン控除…などの各種控除がある方にも、多くご利用いただいています。
スマホのほうが使いやすい方は、アプリからも確定申告が可能です。

遺族年金とは?
「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金の加入者、もしくは過去加入者だった人が対象の年金です。被保険者が死亡した際に、その人と一緒に生活し、生計を維持されていた配偶者や子どもに対して支払われます。生活の柱がいなくなってしまった際の生活保障が、最大の目的といえるでしょう。
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがおもな制度です。それぞれの違いは「被保険者が国民年金のみの加入だったか」「厚生年金も含めて加入していたか」によります。
条件を満たしていればどちらの年金も受け取れる可能性があるため、加入状況や受給条件を確認しておきましょう。
遺族基礎年金
国民年金に加入者だった被保険者が亡くなったときに受給できるのが、「遺族基礎年金」です。遺族基礎年金の受給者は、先程も紹介したように被保険者の配偶者とその子どもです。
受給の対象となる子どもの年齢は「18歳到達年度の末日までの子」という条件があります。障害を持つ子どもに関しては、障害等級が1級または2級と判定されている20歳までが対象です。
遺族基礎年金は配偶者のみでは受給できず、先程の条件を満たす子どもがいなければいけません。受給を検討する際には、条件を満たしているか確認しましょう。
遺族厚生年金
会社員として企業に雇われて働いている、もしくは公務員は「遺族厚生年金」の対象となります。国民年金を納める個人事業主は、基本的に遺族厚生年金の対象外です。
ただし、過去に厚生年金の加入経歴がある場合は、条件によって受給できる可能性があります。詳しい内容については年金事務所や市区町村の窓口で相談しましょう。
遺族基礎年金との違いとしてもう一つ挙げられるのが、受給できる人の条件です。子どもの年齢条件は遺族基礎年金と同様ですが、特徴として配偶者のみであっても受給が可能となっています。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
遺族年金を請求する場合の手続き
被保険者であるパートナーが亡くなり、遺族年金を受給する際には請求の手続きをしなければなりません。遺族年金を受給するための申し込みには時効があり、受給の権利が発生してから5年経過すると被保険者の支払い分を受けられない場合があるため注意が必要です。
そのため、できる限り早めに手続きを行いましょう。ここからは、遺族年金の手続きする手順について紹介します。
1.年金請求書の記入
遺族年金を受給する際に準備するものが「年金請求書」です。年金請求書は、被保険者と受給者の情報や保険の加入経歴などの情報を記入します。
特に加入状況は詳しい内容の記述が必要になるため、被保険者の年金手帳を手元に準備しておくとよいでしょう。請求書の様式や記入例、注意事項などは日本年金機構のホームページにまとめられています。記入用紙はこちらからダウンロードすると便利です。
2.年金請求書の添付書類を準備
年金請求書が準備できたら、それに添付する書類を準備しましょう。添付書類で必要なものは、以下の通りです。
- 年金手帳
- 戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書など)
- 子の収入が確認できる書類(高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など)
- 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 請求者(遺族)名義の受取先金融機関の通帳など
これら以外にも、年金受給の条件を確認するために必要とされる書類があります。不明点がある場合は、年金事務所や年金相談センターに確認しましょう。
3.年金事務所および年金相談センターに書類を提出
書類が一式揃ったら、近くにある年金事務所か年金相談センターに提出します。窓口での提出と郵送での提出が可能です。
書類の確認には1ヵ月程度を要し、その後年金証書が自宅に届きます。この証書は遺族年金の受給資格をとった証書となります。
指定した口座へ年金が振り込まれるのはその約50日後となるため、書類を提出してから3ヵ月ほど経過してからでなければ受給されません。前述の通り、年金受給の申請には時効となる期間があります。
もし自分では手続きを進めるのが難しい場合は、社会労務士に申請に必要な書類を集める代行をお願いできます。なお、代行を利用する際には委任状が必要です。
遺族年金を受け取ったら確定申告は必要?
遺族年金を受給してお金をもらったとしても、原則確定申告の必要はありません。遺族年金で得たお金は非課税のため、働いて得た収入やほかの年金とは異なり、確定申告の対象からは除外されます。
そのため「遺族年金の受給額によっては課税しなければならないのか」「老齢年金のように申告しなくてよいのか」といった疑問点が挙がるかもしれません。遺族年金は受給金額に応じた課税もありませんし、ほかの年金のような申告は不要です。
ただし、遺族年金を受給していれば確定申告をしなくてよいわけではありません。他の雑所得で課税対象の内容があれば、忘れずに確定申告を行いましょう。
遺族年金の制度を有効活用するべき
遺族年金の制度は、家族の柱となっていた人が亡くなったときの生活保障となります。確定申告の対象からも外れるため、特に子どもがいる家庭にとっては、生活をしていくうえで貴重な収入となるでしょう。
遺族年金を受け取る際には、多くの書類を取り揃える必要があり、自分だけで申請することが難しい場合は、社会労務士に手を借りるのをおすすめします。遺族年金だけでなく、確定申告が必要かどうか判断するためには、どのようなものが申告の対象になるのか理解しておくと役立ちます。
確定申告についてさらに詳しく知りたい人は、以下のページを参考にしてみてください。
はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法
確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。
個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。
①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。
②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。
③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。
追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える
有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料
マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典


マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
遺族年金とは?
遺族年金とは、「国民年金」または「厚生年金」の被保険者の方、もしくは被保険者であった方が亡くなったときに、遺族が受けられる年金です。 詳しくはこちらをご覧ください。
遺族年金に確定申告は必要?
遺族年金は非課税のため、遺族年金だけで他の所得がなければ確定申告は必要ありません。 詳しくはこちらをご覧ください。
遺族年金を受け取るには?
国民年金および厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取れます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
消費税の割戻し計算とは?積み上げ計算との違いも解説
インボイス制度の導入により、消費税の制度が大きく変わりました。代表的な変更点は、仕入税額控除を受けるためには取引先からの適格請求書等(インボイス)が必要になることです。また、消費税…
詳しくみる申告納税額とは?納税する方法や申告納税が必要な人を解説
申告納税額という言葉は聞いたことがあっても、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。とくに会社勤めをしていると、税金について触れる機会はそれほど多くないかもしれません。…
詳しくみる障害者控除とは?障害年金を受給したら確定申告は必要?
障がいがある人、もしくは親族に障がいがある人がいると、気になるのが確定申告のことです。何か控除を受けられるのか、障害年金をもらっているが確定申告をどうしたらよいのかなど、気になる人…
詳しくみる扶養控除とは?配偶者控除との違い、年収の壁、控除金額などをわかりやすく解説
扶養控除とは、所得税法上の扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度のことです。 税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族となる点がポイントで、配偶者の場合は扶…
詳しくみる確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を申請する方法は?青色申告の場合も解説!
所得税の計算では、公正に所得税を課すために、各納税者の事情を加味する所得控除が認められています。所得控除は、全部で16個の項目があり、確定申告時には、青色申告、白色申告を問わず合計…
詳しくみる確定申告でインプラントの医療費控除を申請する方法を解説!
インプラントの治療費用は見た目の改善が目的の美容手術や矯正とは異なるため、医療費控除の対象です。医療費控除は年末調整で対応してもらえないので、控除を受けるには確定申告の手続きが必要…
詳しくみる