- 更新日 : 2025年7月7日
個人事業主が交通事故にあったら休業補償はどうなる?手続きや税務のポイントを解説
交通事故で負傷し、仕事を休まざるを得なくなった個人事業主の方は、売上が途絶える不安を抱えることでしょう。そのような場合に助けとなるのが「休業補償」です。本記事では、個人事業主のための交通事故休業補償について、制度の概要から請求手続き、税金や証明書類のポイントまで解説します。
おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?
「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。
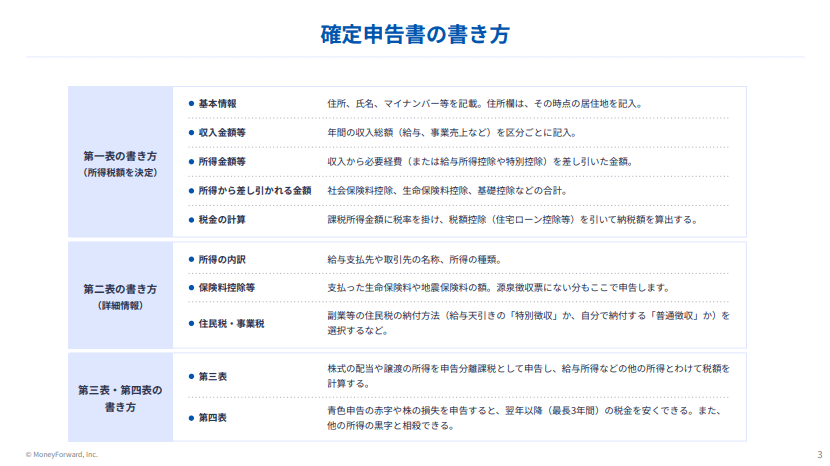
目次
「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。
取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。
PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

交通事故による休業補償とは
交通事故で仕事を休んだ際の休業補償には、複数の保険制度が関係します。主なものに自賠責保険、任意保険、労災保険、そして民間の保険があります。それぞれ加入状況や補償内容が異なるため、まずは各制度の概要と違いを押さえておきましょう。
自賠責保険による休業補償
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)はすべての車に加入が義務づけられている強制保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を行うものです。対人事故のみが対象で、人身傷害に関する損害(治療費や慰謝料、休業による損害など)を上限額の範囲内で補償します。自賠責保険で支払われる休業補償(休業損害)は、原則として1日あたり6100円が基準となっています。10日間仕事を休んだ場合は最大で約6万1千円が補償される計算です。ただし、自賠責保険全体で傷害部分の補償上限は120万円までと定められており、治療費やその他の損害と合算して120万円を超える場合は、自賠責だけでは賄いきれない分を後述の任意保険で補うことになります。
任意保険による休業補償
任意保険は加入が任意の自動車保険で、対人・対物を含め自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する役割があります。加害者が任意保険に加入していれば、自賠責の上限を超える損害についても、その任意保険から休業による損害の補償を受けることができます。被害者の実際の収入減に基づいて算出された休業損害額は、自賠責の6100円/日という基準や120万円の枠を超える部分も任意保険でカバーされます。また、自動車保険に「人身傷害補償保険」の特約を付けていれば、自分自身が被害者となった事故で、自分の保険会社から休業損害の補償金を直接受け取ることも可能です。
労災保険による休業補償
業務中や通勤中の交通事故であれば、労災保険(労働者災害補償保険)から休業補償を受けられる場合があります。労災保険は本来、会社員など労働者向けの公的保険ですが、個人事業主でも一定の要件を満たせば「特別加入」によって加入でき、業務災害に対する補償を受けることが可能です。労災保険の休業補償給付は、ケガで仕事を休み始めた4日目以降について1日あたり基礎日額の60%が支給され、さらに休業特別支給金として20%が上乗せされます。つまり休業1日につき基礎日額の合計80%が補償される仕組みです。例えば基礎日額が1万円と認定された場合、1日休業ごとに労災から8000円が支払われます。ただし、労災保険からの給付は業務上または通勤中の災害に限定され、対象とならない私的な状況での交通事故には適用されません。また、個人事業主が労災に特別加入していない場合はこの補償を受けられない点に注意が必要です。
民間保険(所得補償保険等)による休業補償
個人事業主自身が任意で加入している民間の保険から休業補償を受けられる場合もあります。代表的なものに所得補償保険や傷害保険があります。これらは病気やケガで働けなくなった場合に一定期間の所得を補償する保険で、交通事故によるケガで就業不能になった場合も給付金を受け取れる可能性があります。民間保険からの給付は契約内容によりますが、上記の自賠責・任意保険や労災保険とは別に、自身で備えていた保障を受け取れる点で心強い制度と言えるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
青色申告1から簡単ガイド
40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
白色申告1から簡単ガイド
これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!
「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!
1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。
確定申告控除ハンドブック
確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?
「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています
個人事業主が受けられる休業補償の種類と給付対象
個人事業主であっても、交通事故の被害者になれば適切な手続きを取ることで休業による損失の補償を受けられます。基本的には加害者側の自賠責保険・任意保険から休業損害(減収分)の賠償金を受け取ることができ、仕事中・通勤中の事故で労災保険に加入していれば労災から休業補償給付を受けることも可能です。さらに、自身で加入している所得補償保険や人身傷害補償保険があれば、その保険から休業補償の給付金を受け取ることもできます。給付の対象となるのは、事故によって業務に支障をきたし、実際に収入の減少が発生したと認められる場合です。収入の証明には、確定申告書や帳簿、医師の診断書などが必要となります。自営業者は会社員とは収入形態が異なりますが、状況に応じて利用できる制度があります。
休業補償の請求に必要な書類と手続きの流れ
休業補償を受け取るには、請求先に応じた手続きを踏み、必要書類を整えて提出する必要があります。加害者側の保険会社に請求する場合と、労災保険に請求する場合、自身の保険に請求する場合とで書類や流れが異なりますが、代表的なポイントを説明します。
加害者側の保険会社へ請求する場合
まず相手方の自賠責保険または任意保険の担当者に連絡し、休業損害を請求したい旨を伝えます。保険会社から案内される必要書類を揃えて提出しましょう。個人事業主の場合、勤務先が発行する「休業損害証明書」の提出は不要で、その代わりに前年分の確定申告書の控えを提出して収入を証明します。確定申告書に記載された事故前年の所得額を基に1日あたりの収入額が算定され、休業損害額が計算されます。このほか、医師の診断書も提出が必要です。診断書には負傷の内容や治療期間、労務不能期間などが記載され、事故によるケガで仕事ができなかったことを証明します。必要書類を提出すると保険会社で審査が行われ、認められた休業損害額が支払われます。
労災保険に請求する場合
労災保険から休業補償給付を受けるには、所轄の労働基準監督署で所定の請求書に必要事項を記入し、医師の診断書(労災用)を添付して提出します。交通事故(第三者行為)によるケガの場合は、加害者からの賠償との調整のため「第三者行為災害届」の提出も必要です。申請が認められると、休業4日目以降について休業補償給付と休業特別支給金が支給されます(通常1ヶ月ごとに指定口座へ振り込まれます)。なお、労災と加害者側保険の両方に請求する場合は、後述するように二重に受け取れない部分の調整が行われます。
自身の保険会社に請求する場合
個人事業主自身が加入している民間保険に休業補償を請求する際も、基本的な流れは同様です。契約先の保険会社に連絡し、事故の発生とケガによる就業不能を伝えて、所定の請求手続きを行います。必要書類は保険の種類によって異なりますが、事故状況を証明する書類(交通事故証明書など)、ケガの程度や治療期間を証明する書類(診断書など)、収入減を証明する書類(確定申告書控えや帳簿の写しなど)が求められる点は共通です。人身傷害補償保険であれば所定の請求書と診断書等を提出し、契約に応じた保険金が支払われます。所得補償保険の場合も、医師の就業不能証明書や所得証明資料を提出して給付金を受け取る流れです。
確定申告による収入証明・申告額と実収入のギャップへの対応策
個人事業主が休業補償を請求する際、収入の証明として提出を求められるのが「確定申告書」の控えです。確定申告書は前年の所得を公式に証明する書類であり、保険会社もこれを基準に休業による減収額を算定します。自営業者の場合、毎月の収入が一定ではないため、事故前の年間所得(申告所得額)をもとに1日あたりの収入を割り出す方法が取られるのです。したがって、申告所得が高ければ補償額も大きくなり、低ければその範囲内での補償となります。
では、申告所得額と実際の収入に差がある場合はどうなるでしょうか。結論から言えば、申告上の所得が低いと補償額も低く算定され、大きな補償は期待できません。事故後になって「本当はもっと収入があった」と主張しても、公式記録である確定申告書の金額以上を認めてもらうのは困難です。特別な事情がある場合に帳簿や契約書類で増収傾向を示し交渉に加味してもらう余地はありますが、基本的には平時から正しく所得を申告しておくことが肝心と言えます。万一に備えて、日頃から適切に申告・納税し、必要に応じて税理士に相談するなどしておきましょう。
保険金・補償金の税務上の取り扱い
休業補償として受け取る損害賠償金や保険金が税金面でどう扱われるかも気になるところです。基本的には、交通事故による損害に対する賠償金や慰謝料、休業損害などの受取金は非課税所得として扱われ、所得税は課されません。事故で被った損失の補填であり、利益ではないという考えによるものです。したがって、加害者側の保険会社から支払われる休業損害や慰謝料、労災保険からの休業補償給付、自身の人身傷害保険や所得補償保険から受け取る給付金などは、いずれも所得税の課税対象にはなりません。
ただし、例外的に課税されるケースもあります。それは、事業の必要経費や資産損害の補填として受け取った金銭です。例えば、事故で事業用設備が壊れ、その修理費用を加害者から賠償してもらった場合や、店舗休業中の家賃補填を受けたような場合、その部分の金銭は事業所得として計上する必要があります。また、事故で売り物の商品が損壊し、その代金を補填してもらった場合も、売上の補填とみなされ課税対象となります。このように、休業による収入減や精神的苦痛に対する補償は非課税ですが、経費や資産の損失補填に相当する部分は課税対象となる点に注意しましょう。
売上変動の証明に使える書類例や帳簿管理のポイント
交通事故前後でどれだけ売上が減少したかを示すことは、個人事業主が休業損害を請求する上で重要です。その証明に役立つ書類としては、事故前後の月次売上帳簿や損益計算書、受注のキャンセルを示す契約書や発注書、キャンセル連絡のメール、さらには銀行口座の入出金明細などが挙げられます。事故前の同じ時期と比べて売上がどれほど減ったかを数字で示すことで、減収が交通事故によるものであることを裏付けられるでしょう。
また、平時からの帳簿管理も欠かせません。日々の売上や経費をきちんと記帳し、月ごとの損益を把握しておけば、事故前後の比較資料を容易に作成できます。会計ソフトを活用すれば前年同月比のレポートなどもすぐに出力できて便利です。重要な取引や契約は書面やメールで形に残し、キャンセル時にも証拠を提示できるようにしておきましょう。さらに、確定申告書の控えや納税証明書、決算書といった公的な書類も整理保管しておきます。そうした書類は、事故後に保険会社へ収入証明を提出する際にも有用です。日頃から記録を整備し書類を保管しておくことで、いざというとき速やかに対応でき、自身の権利を確実に主張できるでしょう。
仮渡金制度と複数制度を併用する時の注意点
最後に、休業補償に関連する制度として「仮渡金制度」と、複数の補償制度を併用する場合の注意点について触れておきます。
仮渡金制度とは
仮渡金制度とは、被害者が早急に資金を必要とする場合に、示談前でも自賠責保険から定められた額の前払い金(仮渡金)を受け取れる制度です。後の本支払い時に前払い分は差し引かれて精算されます。収入が止まってしまった個人事業主にとって、治療中でも早めに現金を得られる有用な制度と言えます。
労災保険と自賠責保険を併用する際の注意
業務中の交通事故で労災保険と加害者側の自動車保険(自賠責・任意)を併用できるケースでは、同じ休業補償について二重に受け取ることはできないため調整が行われます。通常は自賠責保険(および任意保険)が優先適用され、上限を超える部分について労災保険から給付が行われます。もし労災を先行利用した場合、後から自賠責保険に休業損害を請求しても支払われないか、労災側が自賠責に求償する形で清算されます。急ぎで資金が必要な場合は仮渡金の利用も検討できますが、その後の労災給付に影響する可能性がある点に注意しましょう。いずれの場合も、各保険の担当者に他方の利用状況を伝え、適切に調整してもらうことが大切です。
交通事故で収入が止まる前に、休業補償の仕組みを知り備えよう
交通事故によって個人事業主が受けられる休業補償について、制度概要から手続き、注意点まで解説しました。事故で仕事を休むことは大きな痛手ですが、適切な制度を活用し必要な補償を受け取ることで、経済的ダメージを軽減できます。平時から備えを万全にし、万一の際には本記事を参考にスムーズに対応してください。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
確定申告の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【個人事業主向け】簿記の活用法とは?青色申告や確定申告のポイントを解説
個人事業主にとって、簿記は避けて通れない重要なスキルです。日々の売上や経費を正確に記録することで、事業の収支を可視化でき、経営判断や確定申告にも役立ちます。さらに、青色申告での特別…
詳しくみる【個人事業主向け】インボイス制度の消費税計算方法は?注意点や特例制度も解説
インボイス制度は、個人事業主の消費税計算や申告方法に大きな影響を与える制度です。免税事業者と課税事業者の区分や、仕入税額控除のための適格請求書保存義務、売上・仕入の計算方法、端数処…
詳しくみる薬代は経費になる?個人事業主が知っておくべき申告のルールや控除を解説
個人事業主が薬局で購入した薬代や衛生用品の費用を経費にできるのかは、多くの人が疑問に感じるポイントです。その答えは「場合による」であり、支出の内容や目的によって取り扱いが異なります…
詳しくみる個人事業主が従業員を1人でも雇用したら社会保険に加入が必要?加入条件や手続き方法を解説
個人事業主が従業員を雇い入れた場合、1人であっても社会保険のうち労働保険に入らなければなりません。労災保険と雇用保険は計算方法や手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。 本…
詳しくみるアルバイトの源泉徴収なしでも個人事業主は確定申告が必要?書き方も解説
個人事業主が事業活動とは別に、アルバイトでも給与収入を得ているケースにおいて、源泉徴収票が手元にない場合について考えます。 確定申告時は、1年間の事業所得と給与所得を申告しなければ…
詳しくみる保険外交員はなぜ個人事業主?メリットや確定申告・経費についても解説
保険外交員とは、保険契約の勧誘や代理、契約後のサポートなどを行う職種です。本記事では、保険外交員の雇用形態をはじめ、個人事業主として働くメリットやデメリットについて解説します。 保…
詳しくみる



