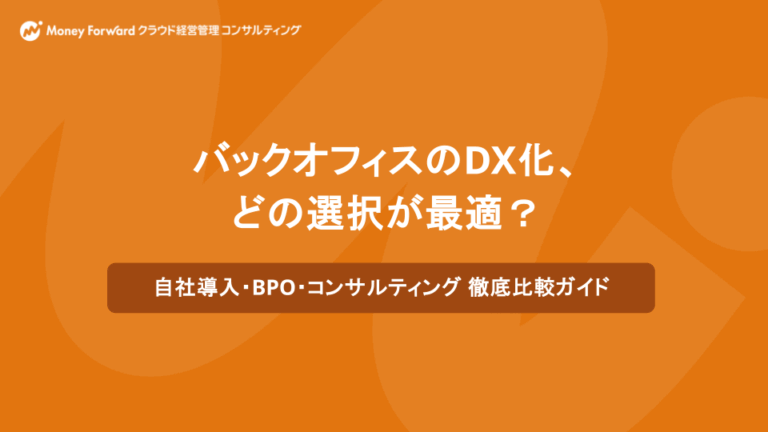- 更新日 : 2025年10月1日
コンサルティング支援とは?経営課題を解決する種類、内容、費用から成功の秘訣まで徹底解説
この記事では、企業の成長や変革に不可欠なコンサルティング支援について、その概要や具体的なサービス内容、費用体系、そして失敗しない会社の選び方や成功の秘訣までを解説します。
専門家による経営コンサルティングは、客観的な視点から現状を分析し、持続的な成長を実現するための羅針盤となり得る存在です。全社的な経営課題に直面している経営層の方から、特定部門の業績改善や日々の業務効率化に取り組む責任者・担当者の方まで、企業の成長を目指す多くの方にとって、課題解決のヒントとなる内容です。
目次
コンサルティング支援とは何か?
コンサルティング支援とは、企業が抱える経営上の課題に対し、専門的な知識と経験を持つコンサルタントが客観的な立場から分析・助言を行い、解決へと導くサービスです。
契約内容に応じて、単なるアドバイスに留まらず、クライアント企業と伴走しながら具体的な実行計画の策定やその実行をサポートする場合もあります。これにより、課題の根本的な解決と企業の成長を目指します。
専門知識で課題解決を包括的にサポート
コンサルタントは、特定の業界や業務領域に関する深い知見、問題解決のための論理的思考力、そして多岐にわたるプロジェクトで培った経験を持っています。これらの専門性を活用し、企業内部だけでは見つけにくい問題点や、解決が困難な複雑な課題に対して、効果的な解決策を提示します。
例えば、新規事業の立ち上げ、業務プロセスの効率化、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、企業のさまざまな局面でその価値を発揮する可能性があります。
経営におけるコンサルティングの重要性
変化の激しい現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには、常に経営判断を最適化し、外部環境の変化に迅速に対応する必要があります。
しかし、社内のリソースやノウハウだけでは限界があるのも事実です。 コンサルティング支援を活用することで、以下のようなメリットが期待できるため、有効な選択肢の一つとして考えられています。
- 客観的な視点の獲得:第三者の視点から自社の強み・弱みを冷静に分析できる。
- 専門知識の活用:自社にない専門的な知見や最新のノウハウを取り入れられる。
- 迅速な意思決定:的確な情報収集と分析に基づき、経営判断のスピードと質の向上を後押しする。
- 実行力の強化:計画倒れを防ぎ、変革プロジェクトの推進をサポートする。
コンサルティング支援の対象は誰か?
コンサルティング支援の対象は、スタートアップから大企業まで、多様な企業です。経営課題は企業の成長ステージや事業内容によって様々であり、それぞれの課題に応じたコンサルティングサービスが存在します。
事業規模や成長ステージ別の対象課題
企業の規模や発展段階によって抱える経営課題は大きく異なり、コンサルティング支援で扱うテーマも変化します。ここでは主な事業規模別に、対象となる課題例を見ていきましょう。
対象となる主な部門
コンサルティング支援は、特定の部門だけでなく、企業の様々な部門を対象とします。
| 対象部門 | 主な課題例 |
|---|---|
| 経営層 | 全社戦略の策定、M&A戦略、新規事業開発、コーポレートガバナンス強化(※) |
| 事業部門 | マーケティング戦略、営業力強化、製品開発プロセスの改善 |
| 管理部門(バックオフィス) | 経理・財務プロセスの効率化、人事制度改革、ITシステム導入・刷新 |
| 製造・開発部門 | サプライチェーン・マネジメント(SCM)の最適化、品質管理体制の構築、R&D戦略 |
(※)ガバナンス体制の設計や運用支援が中心です。法務・税務などの専門的な判断が必要な業務は、弁護士や税理士といった有資格者と連携して対応します。
コンサルティング支援の主な内容は?
コンサルティング支援の主な内容は、経営戦略の策定から業務プロセスの改善、IT戦略、人事・組織開発まで多岐にわたります。
クライアントが抱える課題に応じて、最適な支援内容がカスタマイズされます。ここでは、代表的な支援内容を5つ紹介します。
経営戦略の策定・実行支援
企業の将来像(ビジョン)を描き、それを実現するための具体的な道筋(戦略)を策定します。市場分析、競合分析、自社の強み・弱みの分析(SWOT分析など)を通じて、中期経営計画の策定や新規事業戦略の立案などを支援します。策定した戦略が絵に描いた餅で終わらないよう、KPI設定や実行体制の構築までサポートすることも少なくありません。
業務プロセスの改善(BPR)
既存の業務プロセスを根本的に見直し、非効率な作業や無駄を排除して、生産性を最大化するための支援です。BPR(Business Process Re-engineering)とも呼ばれます。業務フローの可視化、ボトルネックの特定、ITツールを活用した自動化などを通じて、コスト削減やサービス品質の向上を支援します。
IT戦略・DX推進支援
経営戦略と連動したIT戦略の策定や、DXの推進を支援します。最新のデジタル技術(AI、IoT、クラウドなど)を活用して、新たなビジネスモデルの創出や、既存業務の抜本的な変革を支援します。基幹システム(ERP)の導入支援や、データ活用基盤の構築なども含まれます。
人事・組織開発支援
「ヒト」に関する課題を解決し、企業の持続的な成長を支える組織作りを支援します。具体的には、人事評価制度の再構築、人材育成体系の設計、従業員エンゲージメントの向上施策、組織風土の改革などが挙げられます。優秀な人材の採用・定着を促し、従業員一人ひとりのパフォーマンスを最大化することを目指します。
M&A・事業再生支援
M&A(企業の合併・買収)における戦略立案からPMI(M&A後の統合プロセス)までを支援します。その過程で行われるデューデリジェンス(対象企業の調査)については、当社の専門である事業やIT面に加え、必要に応じて弁護士(法務)や税理士(税務)といった外部の専門家と連携して対応します。
また、経営不振に陥った企業の再生計画を策定し、財務改善や事業のリストラクチャリングなどを通じて、企業の再建をサポートします。
コンサルティング支援にはどのような種類があるか?
コンサルティング支援は、その専門領域によって一般的に「戦略系」「総合系」「IT系」「人事系」「専門分野特化型」などに分類されることがあります。
自社の課題がどの領域に属するのかを明確にすることで、最適なコンサルティングファームを選ぶことができます。
| 種類(※) | 主な特徴と支援領域 |
|---|---|
| 戦略系コンサルティング | 企業のトップマネジメントが抱える経営戦略上の重要課題(全社戦略、M&Aなど)に特化。少数精鋭で高レベルな分析力・提言力が求められる。 |
| 総合系コンサルティング | 戦略立案から業務改善、システム導入、実行支援まで、企業の幅広い経営課題をワンストップで支援。幅広い業界・業種に対応できる組織力を持つ。 |
| IT系コンサルティング | IT戦略の立案、システム導入、DX推進など、IT・デジタル領域に特化した支援を提供。技術的な知見とビジネス理解の両方が求められる。 |
| 人事系コンサルティング | 人事制度設計、組織開発、人材育成、チェンジマネジメントなど、「人・組織」に関する課題解決を専門とする。 |
| 専門分野特化型コンサルティング | 財務(FAS)、マーケティング、サプライチェーン、事業再生など、特定の機能や領域に特化した高い専門性を持つ。 |
| 中小企業向けコンサルティング | 中小企業の特有の課題(事業承継、資金繰り、生産性向上など)に精通し、地域に密着したきめ細やかな支援を提供する。 |
(※)種類の分類はあくまで一例です。
コンサルティング支援の費用や料金体系はどうなっているか?
コンサルティング支援の費用は、プロジェクトの難易度や期間、コンサルタントの役職などによって大きく変動します。料金体系は主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つです。
費用対効果を最大化するためには、自社の課題や予算に合った料金体系を選ぶことが重要です。
料金体系の種類
費用は契約形態、コンサルタントの役職・人数・稼働率、プロジェクト期間、実費(交通費等)で大きく変動します。例えば人月単価も数十万円~200万円超と幅があり、以下はあくまで大まかな参考例です。
- 顧問契約型
- 概要: 毎月定額の料金を支払い、継続的にアドバイスや支援を受ける契約形態。
- メリット:経営に関する相談役として、いつでも気軽に相談できる。長期的な視点で伴走してもらえる。
- 料金の目安(一例):月額20万円~50万円程度
- プロジェクト型
- 概要:特定の課題解決(例:新規事業立案、システム導入)のために、期間とゴールを定めて契約する形態。
- メリット:成果物が明確で、予算の見通しが立てやすい。
- 料金の目安(一例):数百万円~数千万円以上(個別見積もり)
- 計算方法:「(人月単価 × 人数 × 期間)+ 実費経費」で算出されることが多い。
- 成果報酬型
- 概要:プロジェクトによって得られた成果(例:コスト削減額、売上増加額)の一部を報酬として支払う契約形態。
- メリット:初期費用を抑えられる。コンサルタントと成果目標を共有できるため、高いコミットメントが期待できる。
- デメリット:成果の定義や測定方法を事前に明確にする必要がある。成果が大きい場合、総支払額が高額になる可能性がある。
- 料金の目安(一例):契約時に定めた成果(例:削減コスト)の10%~30%程度
費用を抑えるポイント
- 課題を明確にする:相談内容を具体的に整理し、論点を絞ることで、不要な作業を減らし、期間の短縮や費用の抑制につながります。
- 複数のファームから見積もりを取る:複数のコンサルティングファームに相談し、提案内容と見積もりを比較検討(相見積もり)することが重要です。
- 自社でできることを切り分ける:データ収集や資料作成など、自社で対応可能な作業を事前に切り分けておくことで、コンサルタントの稼働を減らし、費用を抑えることができます。
コンサルティング支援で活用できる補助金は?
コンサルティング支援の費用負担を軽減するために活用できる国や地方自治体の補助金・助成金があります。
特に中小企業を対象とした制度が充実しており、専門家への依頼費用(コンサルティング費用)が補助対象経費に含まれる制度もあります。
代表的な補助金制度
以下は、コンサルティング支援に活用できる可能性のある代表的な補助金です。これらの補助金を活用することで、費用面のハードルを下げ、質の高いコンサルティング支援を受けることが可能になります。
- 事業再構築補助金:新市場進出、事業・業種転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業を支援する補助金。コンサルタントへの依頼費用も対象経費に含まれる場合がありますが、制度や公募回によって対象可否、上限額、専門家の要件は大きく異なります。
- IT導入補助金:中小企業が生産性向上に役立つITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際の経費の一部を補助します。IT導入支援事業者として登録されたベンダーが提供する、認定ITツールの導入に関する専門家への費用が対象となることがあります。
- ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金):革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。専門家経費としてコンサルティング費用が認められる場合があります。
- 小規模事業者持続化補助金:小規模事業者が販路開拓や生産性向上のために取り組む経費の一部を補助します。専門家からの助言・指導にかかる費用も対象となる場合があります(ただし、申請代行や一部ウェブ関連のコンサルティング費用は対象外となるケースが多いため、公募要領の確認が必須です)。
補助金の利用を検討する際は、必ず管轄省庁や事務局が公開する最新の公募要領を確認し、「専門家経費」の対象範囲や上限、除外項目(申請代行費など)を精査してください。
失敗しないコンサルティング支援会社の選び方
コンサルティング支援会社選びで失敗しないためには、「課題の明確化」「実績・専門性の確認」「担当者との相性」「複数社の比較検討」という4つのステップを踏むことが重要です。
高額な費用をかけても期待した成果が得られない、といった事態を避けるために、慎重に自社に合ったパートナーを選びましょう。
ステップ1. 相談したい課題と目的を明確にする
最初に、自社が何を課題と感じており、コンサルティングによってどのような状態(目的)を達成したいのかを具体的に言語化します。ここが曖昧なままだと、コンサルティング会社も的確な提案ができず、プロジェクトの方向性が定まりません。
「売上を上げたい」といった漠然としたものではなく、「若年層向けの新規顧客を半年で20%増やしたい」「3ヶ月以内に経理部門の月次決算業務を5営業日短縮したい」のように、できるだけ具体的に整理することが成功の第一歩です。
ステップ2. 会社の得意分野や実績を確認する
次に、明確にした課題を解決できる専門性や、類似業界・類似課題での支援実績があるかを確認します。
コンサルティング会社には、それぞれ得意な領域(戦略、IT、人事など)や業界があります。会社の公式サイトで公開されている導入事例やクライアントの声を確認し、自社の状況と近いケースで成果を出しているかをチェックしましょう。実績の豊富さは、信頼性を判断する上での重要な指標となります。
ステップ3. 担当コンサルタントとの相性を見極める
プロジェクトの成否は、担当コンサルタントのスキルや人柄、そして自社担当者との相性に大きく左右されます。
契約前の面談や提案の場で、以下の点を確認しましょう。
- コミュニケーションは円滑か:専門用語ばかりでなく、分かりやすい言葉で説明してくれるか。こちらの話を真摯に聞いてくれるか。
- 業界への理解度:自社のビジネスや業界特有の事情について、どれだけ理解しようと努めてくれるか。
- 信頼感・熱意:プロジェクトを「自分ごと」として捉え、熱意をもって取り組んでくれそうか。
長く付き合うパートナーとして信頼できる人物かを見極めることが非常に重要です。
ステップ4. 複数の会社から提案と見積もりを取得し比較検討する
可能であれば2〜3社以上のコンサルティング会社に声をかけ、提案内容と見積もりを比較検討(相見積もり)しましょう。
比較する際は、費用の安さだけで選ぶのは危険です。以下の観点から総合的に評価し、最も自社に適した会社を選びます。
| 比較する観点 | チェックポイント |
|---|---|
| 提案内容 | 課題認識が的確か。解決策は具体的で、実現可能性があるか。 |
| 支援体制 | どのようなメンバーが、どれくらいの頻度で関与してくれるのか。 |
| 費用 | 料金体系は明確か。支援内容に見合った妥当な金額か。 |
| 成果の定義 | 何をもってプロジェクトの成功とするかが明確に定義されているか。 |
これらのステップを踏むことで、自社の課題解決に真に貢献してくれる、最適なコンサルティング支援会社を見つけられる可能性が格段に高まります。
コンサルティング支援を成功に導く3つのポイント
良いコンサルティング会社を選ぶだけでは不十分で、支援の効果を最大化するためには、依頼する企業側の「受け入れ方」も同様に重要になります。
コンサルタントを最大限に活用し、プロジェクトを成功に導くために、以下の3つのポイントを意識してください。
ポイント1. 目的を共有し、丸投げにしない
プロジェクトの主体はクライアント企業自身であるという意識を持つことが最も重要です。
コンサルタントは魔法使いではなく、あくまで実行を支援するパートナーです。「専門家にお金を払うのだから、あとは全部お任せ」という受け身の姿勢では、プロジェクトの成功は難しくなります。自社の課題や目指すべきゴールを自分たちの言葉で語り、コンサルタントと密に議論を交わしながら、共に考え、行動する姿勢が成果を最大化させます。
ポイント2. 経営トップが積極的に関与する
特に業務改革や組織変革など、全社にまたがるプロジェクトでは、経営トップの明確なコミットメントが成功の鍵を握ります。
担当部署や担当者に任せきりにすると、部門間の利害対立や変革への抵抗によって、プロジェクトが停滞するリスクが高まります。経営トップが「なぜこの変革が必要なのか」というメッセージを社内に繰り返し発信し、改革を推進する強いリーダーシップを示すことで、初めて組織全体が同じ方向を向いて動き出します。
ポイント3. 社内に専任の担当者やチームを置く
コンサルタントと自社をつなぐ、コミュニケーションのための専門窓口を設置することが、プロジェクトを円滑に進めるための鍵となります。
専任の担当者がいないと、情報伝達の遅延や認識の齟齬が生まれ、プロジェクトの進行を妨げる原因となります。担当者は、定例会の設定、コンサルタントが必要とする社内情報の収集、コンサルタントからの提言を現場に展開する役割などを担います。この「ハブ」となる存在がいることで、プロジェクトが円滑に進みやすくなります。
自社導入・BPO・コンサルティング 徹底比較ガイド
マネーフォワード クラウドでは「自社導入・BPO・コンサルティング 徹底比較ガイド」をご用意しております。
「自社導入」「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)」「コンサルティング支援」という複数のアプローチを比較し、貴社のDX化を成功に導くための最適な進め方を考える際のヒントをご提供していますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご覧ください。
>自社導入・BPO・コンサルティング 徹底比較ガイドをダウンロードする
コンサルティング支援の活用で、課題解決を目指す
本記事では、コンサルティング支援の基本的な内容から対象、種類、費用、そして失敗しない会社の選び方や成功させるためのポイント、活用できる補助金制度まで、幅広く解説しました。
コンサルティング支援は、自社だけでは解決が難しい経営課題を乗り越え、持続的な成長を実現するための強力なパートナーとなり得ます。まずは自社の課題を明確にし、本記事を参考に最適なパートナー選びと受け入れ態勢の準備を進めてみてはいかがでしょうか。それが、未来の飛躍に向けた重要な一歩となり得るでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選【部署別紹介】
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
経理担当者向け
①Excel関数集 32選まとめブック
経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。
②勘定科目・仕訳辞典(税理士監修)
勘定科目・仕訳に関する基本知識、および各勘定科目の仕訳例を具体的かつ網羅的にまとめた、50ページを超えるガイドを無料で提供しております。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。
人事労務担当者向け
①入社・退職・異動の手続きガイドブック
書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。
最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。
②社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
総務・法務担当者向け
契約書ひな形まとめ30選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い30個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
営業の自動化はどこから始めるべき?具体的なステップや導入メリットを紹介
企業の成長に不可欠な営業活動ですが、「本来注力すべき業務に時間を使えない」といった課題を抱えていませんか。その解決策となるのが「営業自動化」です。営業自動化は、これまで手作業で行っ…
詳しくみるフォーメーションの意味とは?使い方や英語表現、言い換えを解説
フォーメーションとは、サッカーやスパイ映画などで耳にすることがありますが、特定の配置や形状を意味する言葉です。「フォーメーションを組む」という使い方をし、主にチームの戦術や計画を実…
詳しくみる営業効率化の成功事例10選 中小企業が明日から使える方法を解説
営業活動における人手不足や働き方改革への対応が急務となる中、「営業効率化」は多くの企業にとって重要な経営課題です。この記事では、中小企業が明日からでも取り組める営業効率化の成功事例…
詳しくみるヒヤリハット報告書とは?書き方や例文、テンプレート紹介
ヒヤリハット報告書は、重大な事故やトラブルにはならなかったものの、危険が潜んでいた瞬間を記録するものです。現場での「ヒヤリ」とした気づきを放置せずに共有することで、再発防止や安全教…
詳しくみる電子承認ワークフローとは?導入メリットからシステムの選び方まで
企業の申請・承認業務は日常的に発生するため、処理スピードや正確性が組織全体の生産性に直結します。電子承認を効率化する仕組みとして注目されているのが、電子承認ワークフローです。電子化…
詳しくみる製造業の営業DXとは?課題解決と売上向上を実現する具体的な進め方を解説
人手不足やグローバルな競争激化など、多くの課題に直面する日本の製造業にとって、「営業DX」は事業成長の鍵です。営業DXは単なるツール導入による業務効率化ではなく、データに基づいた科…
詳しくみる