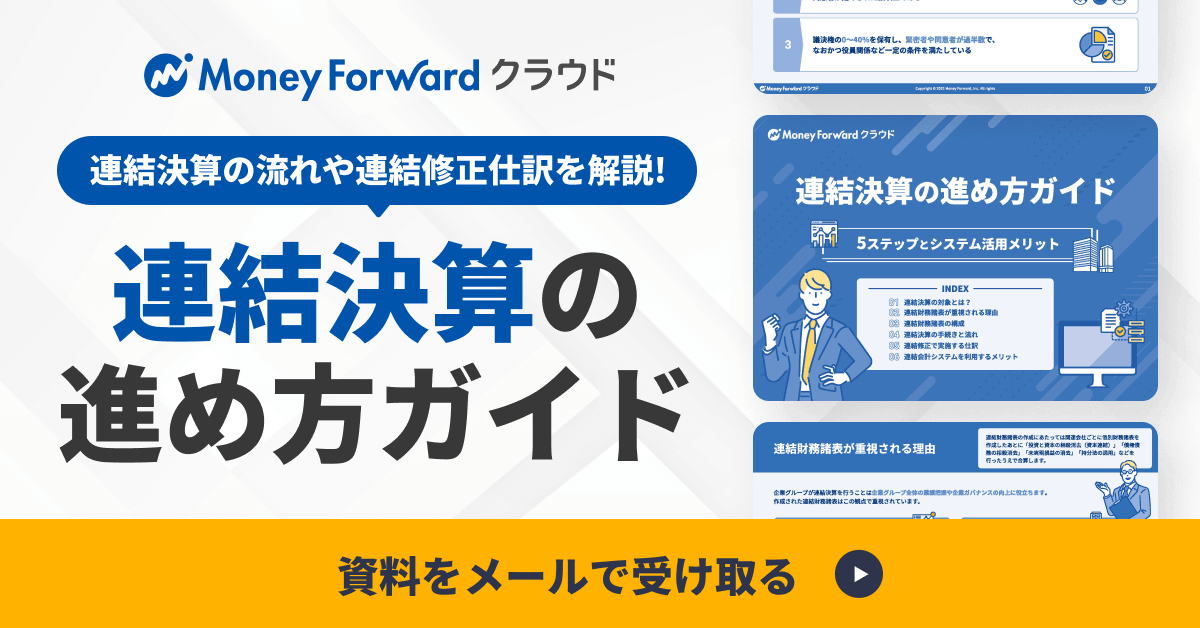- 更新日 : 2025年6月30日
データマートの意味とは?メリットや作り方、活用法をわかりやすく解説
データ分析を効率的に行うには、必要な情報だけを取り出して使える仕組みが欠かせません。データマートは、目的別に絞り込まれたデータの集まりで、部門ごとや分析目的に合わせて柔軟に活用できます。この記事では、データマートの意味や構築方法から、他システムとの違い、活用例まで詳しく解説します。
目次
データマートとは?
データマートは、データウェアハウスから特定の目的や部門に必要なデータを抽出・加工し、利用しやすくカスタマイズしたデータベースです。
たとえば、スーパーマーケットのPOSデータ全体をまとめたものがデータウェアハウスだとすると、特定店舗の売上データや特定商品の販売データだけを抜き出して分析できるようにしたものがデータマートにあたります。これにより、部門担当者は必要な情報に素早くアクセスし、より深い分析や意思決定を行うことが可能になります。
データマートとデータウェアハウス・データレイクとの違い
データマートは、データウェアハウスやデータレイクと似ていますが、異なる意味を持つため、まずは用語の理解を深めましょう。それぞれ構築する目的や用途に違いがあります。
データウェアハウスは、全社的なデータを統合し、幅広い視点での分析に使われる事実の情報源となるデータベースです。
データマートは特定の業務や部門に最適化されたデータを格納し、より迅速な意思決定を支援します。
データレイクは、生データも含めて、あらゆるデータをそのまま蓄積するデータベースです。長期的なデータ保全を重視しているために、データマートのように特定の分析目的に合わせてデータを整理・加工する用途は想定されていません。
データマート:部門ごとの迅速な分析
データマートは、特定部門の目的や要件に応じて抽出・加工された構造化データを保全する小規模なデータベースです。目的別のデータベースであり、構築が早く、実務に直結する分析を行う際に使用されます。
開発や分析スキルを持たない、業務ユーザーでも扱いやすい点が特徴です。
【主なユースケース】
- 営業部門が顧客データを分析し、キャンペーンの反応を把握したい
- 経理部門が月次の収支をスピーディに集計したい
- 全社DWHの負荷を避け、軽量な分析基盤を導入したい
データウェアハウス:全社的なデータの一元分析
データウェアハウスは、多数のソースから企業全体のデータを集約したデータベースです。ETL処理(データクレンジング処理)された、完全かつ詳細な構造化データを保全し、長期的な分析及び経営判断に使われます。
データの品質と統一性が高く、複数部門を横断した分析にも適しています。
【主なユースケース】
- 全社のデータを統合し、長期的な傾向を分析したい
- 経営層が戦略判断のために信頼性の高いデータを使いたい
- 複数の部門をまたぐ横断的な分析が必要
データレイク:自由度の高いデータ蓄積
データレイクは、フォーマットを問わず、未加工の生データを含むさまざまなデータをそのまま保存するデータベースです。事前のデータ整形や変換が不要で、探索的な分析やAI開発に使用されます。
【主なユースケース】
- 画像やテキスト、ログなどの非構造化データも扱いたい
- 将来的な分析のために、あらゆるデータを集めておきたい
- 機械学習用のトレーニングデータとして多様な形式を扱いたい
データマートの種類
データマートには、主に「従属型」「独立型」「ハイブリッド型」の3つの種類があります。
従属型データマート
従属型データマートは、既存のデータウェアハウスからデータを抽出し、特定の部門や業務の利用ニーズに応じて整理・加工した上で構築されます。データウェアハウスに一元化された信頼性の高いデータを活用できるため、データの整合性が保たれやすく、データガバナンスも比較的容易です。ただし、データウェアハウスの構造に依存するため、柔軟性に欠ける場合があります。
独立型データマート
独立型データマートは、特定の部門やプロジェクトのニーズに合わせて、既存のデータウェアハウスとは独立して構築されます。自由に設計でき、外部データソースや部門独自のシステムからデータを統合するために柔軟性が高く、従属型より安価に構築できる点が特徴です。しかし、データの整合性や一貫性には注意が必要な点を押さえておきましょう。
ハイブリッド型データマート
ハイブリッド型データマートは、名前の通り、従属型と独立型の両方の特徴を持つデータベースです。データウェアハウスからのデータと、部門独自のデータソースからのデータを組み合わせて構築することで、柔軟性とデータ整合性のバランスを取ることができます。ただし管理が複雑になりがちであることから、構築時にデータ統合の戦略を明確にした上で設計する必要があります。
データマートを導入するメリット
データマートを導入することで、データ分析の効率化や迅速な意思決定の実現など、多くのメリットが得られます。
必要なデータにすぐアクセスできる
データマートは、特定の目的や部門が分析に必要とするデータだけを集約しています。広範囲なデータの中から必要な情報を見つけ出す手間が省け、データ探索にかかる時間を大幅に短縮できる点がメリットです。
たとえば、営業担当者が特定製品の売れ筋顧客を分析したい場合、関連するデータがデータマートに集約されているため、すぐに分析に取りかかることができます。
分析の質が向上する
データマートは、特定の分析テーマに合わせて最適化されたデータ構造を持っています。そのため、より詳細なデータの関連性や傾向を把握することができ、多角的な分析が可能になる点がメリットです。
たとえば、マーケティング担当者がキャンペーンの効果を最大化したい場合、顧客の属性データや購買データ、Webアクセスログなどを統合したデータマートを用いることで、効果的なターゲット層を特定し、より精度の高いマーケティング戦略を立てられます。
各部門が柔軟に使える
データマートは、各部門の独自のニーズに合わせて自由に構築できるため、全社共通のデータ基盤に依存することなく、柔軟にデータを活用できる点がメリットです。
たとえば、人事部門が従業員の離職要因を分析したい場合、人事システムやアンケート結果などのデータを統合したデータマートを独自に構築することで、部門内で必要な分析を自由に行えます。データ分析の結果をもとに、各部門がそれぞれの課題解決に向けて、主体的に意思決定を行えます。
コストを抑えた導入と運用ができる
データマートは、既にデータウェアハウスを運用していれば、必要最小限のスコープで構築できるため、導入時のコストが抑えられます。処理対象のデータ量も限定的であるため、運用や保守も比較的容易です。
データマート導入前に考慮すべき注意点
データマートの導入には多くの利点がありますが、運用を安定させるためには事前の検討が欠かせません。以下の点を見落とすと、かえって業務の混乱を招くことがあります。
複数のデータマートが乱立する可能性
部門ごとにデータマートを構築すると、同じようなデータマートが複数存在し、更新タイミングや定義に差が生まれます。たとえば、売上データの定義が部門で異なると、集計結果が一致せず意思決定に支障をきたします。データ重複と不整合などの問題を回避するためにも、全体統一の定義書と管理ルールを設けることが必要です。
専門人材が不足しやすい
データマートの設計・構築には、ETL処理やデータベースの知識が必要です。スキルを持った人材が社内にいない場合は、外部パートナーへの依頼や、担当者の育成を検討する必要があります。中途半端な体制で進めると、導入後の保守が困難になります。
セキュリティとアクセス権限を設定する
データマートには顧客情報や人事情報など、センシティブな内容が含まれることがあります。アクセス権限を明確に設定し、誰がどの情報を閲覧できるかを厳密に管理しなければなりません。閲覧ログの記録も忘れずに設計に組み込みましょう。
運用と保守作業に備える
構築した後も、データ構成の変更や新項目の追加など、保守作業は継続的に発生します。更新が属人化すると、トラブル時の対応が遅れるために注意が必要です。マニュアル整備、定期点検、担当分担など、継続運用を見越した仕組みを準備しておくことが必要です。
データマートの効率的な構築・作り方
データマートを効果的に構築するためには、以下のステップで進めることが重要です。
1. 利用目的と範囲を明確にする
まず、データマートの利用目的と範囲を明確に定義します。どの部門の、どのような業務で、どのような分析を行いたいのかというビジネス要件を具体的に洗い出します。
たとえば、「営業部門が、過去1年間の顧客の購買履歴を分析し、優良顧客を特定するためのデータマート」といったように、目的、利用者、分析対象、期間などを明確にします。
この初期段階で関係者間で認識を共有することが、その後の工程をスムーズに進める上で不可欠です。
2. データソースを特定する
次に、技術要件も定義しましょう。「業務プロセスにおいてどのようなデータが収集されているか」も洗い出してください。効率的かつ安定的にデータを入手できるデータソースを特定しましょう。
基幹システム、顧客管理システム、Webアクセスログ、外部のマーケティングデータなど、複数のデータソースが考えられます。それぞれのデータの形式(データベースの種類、ファイル形式など)やデータ量、更新頻度、そしてデータの品質(欠損値、誤りなどがないか)を確認することも重要です。
この確認作業を怠ると、後のデータ統合や分析に支障をきたす可能性があります。
データマートで利用したい機能を踏まえて、サブセットも要件に合わせて選択してください。
3. データの設計と加工方法を決める
定義した全体設計に合わせて、データの抽出、加工、統合を行うためのデータ定義を行います。
どのようなテーブル構成にするか、各テーブルにどのような項目(カラム)を持たせるか、データの粒度(どの程度の細かさでデータを保持するか)などを決定します。
また、データソースからデータを抽出・加工し、データマートに格納するまでの一連の処理(ETL/ELTプロセス)をどのように行うかを設計します。たとえば、「顧客IDで各データを紐づける」「過去の購入金額に基づいて顧客をランク分けする」といった具体的な加工ルールを定義します。
4. 設計に基づきデータベースを構築する
設計に基づき、実際にデータベースを構築します。既存のデータベース管理システム(DBMS)を利用するのか、クラウドベースのデータウェアハウスサービスを利用するのかなど、環境を準備します。
次に、設計したETL/ELTプロセスに従って、データソースからデータを抽出し、設計通りに加工・統合し、データマートに投入します。
この際、自動化ツールを活用することで、効率的かつ安定的なデータ投入が可能になります。データの論理構造(スキーマ・オブジェクト)も、物理環境とともに作成しましょう。
5. ユーザーによるテストを行う
データマートが完成したら、実際に利用するユーザーによるテストを行います。意図したデータが格納されているか、分析に必要な情報が過不足なく含まれているかなどを確認してもらいます。
テストの結果に基づいて修正を行い、品質を高めます。その後、データマートの継続的な運用体制を構築します。データの更新頻度、メンテナンス方法、セキュリティ対策、利用者のサポート体制などを整備することで、データマートを長く活用できる環境を整えます。
データマートを活用した具体例
データマートは、さまざまなビジネスシーンでデータ活用を促進し、成果を上げています。
小売業:顧客ニーズに応じた販促
あるアパレルショップでは、顧客の購買履歴やWebサイトの閲覧履歴を統合したデータマートを構築しました。そのデータから、「このブランドのワンピースを購入した人は、新作のブラウスにも関心を持つ」というパターンを特定しました。
この分析結果をもとに、該当する顧客に対して関連商品の案内メールを配信したところ、通常のメルマガよりもクリック率・購入率ともに高くなりました。顧客一人ひとりの関心に合わせた情報提供が可能になったことで、販促の精度が高まり、売上アップにも直結しました。
製造業:設備の異常を事前に察知
製造工場では、温度センサーや稼働時間などの設備情報を集約したデータマートを導入しました。過去のトラブルデータと比較することで、「温度の微細な上昇が数日後の故障につながる」といった傾向が明らかになりました。
そこで、異常値を検知した段階で自動的にメンテナンス担当者に通知が送られる仕組みを構築し、部品の早期交換によって、大きな故障を防止しています。結果としてダウンタイムを削減し、全体の生産性向上につながりました。
金融業:不審な取引を自動で検出
クレジットカード会社では、顧客の過去の取引データや利用パターンなどをまとめたデータマートを活用しています。「普段は日中に少額の買い物が多い顧客が、深夜に高額なオンライン取引を行っている」といった通常とは異なる動きをデータマートから検知する仕組みを構築しました。
このような異常な取引が検知された場合、顧客に確認の連絡を入れるなどの対応を行うことで、不正利用を未然に防ぐことに成功しています。データマートを用いることで、大量の取引データの中から不審な動きを早期に発見し、顧客の資産を守ることにつながりました。
データ活用を加速するデータマート
データマートは、特定の目的や部門に特化することで、データ分析のスピードを上げ、より深い洞察を得るための強力なツールとなります。導入の際には、目的の明確化、適切な種類の選択、そして長期的な視点での運用計画が不可欠です。データマートを効果的に活用することで、ビジネスの成長を力強く後押しできるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
HubSpotのワークフロー機能とは?作成方法や活用例・注意点を解説
HubSpotのワークフロー機能は、条件にもとづいてメール送信やステータス更新などの業務を自動化できる機能です。メール配信やステータス更新、タスク作成、社内通知などを条件に応じて自…
詳しくみるシステム化とは?メリット・デメリットや手順を解説
システム化とは、企業の業務プロセスをデジタル技術や仕組みによって自動化・効率化することで、人的リソースの最適配置と生産性向上を実現する取り組みです。 この記事では、システム化の基本…
詳しくみる課題解決能力とは?問題解決力との違いや高める方法を解説
ビジネスシーンでは、業務を進める中で発生した課題に適切に対処する「課題解決能力(課題解決力)が求められます。課題解決力が高い人は、仕事で現れた課題をより素早く、適切な形で解決できる…
詳しくみる広報スケジュール(年間広報計画)の立て方とポイント|テンプレも紹介
広報活動はその時考えたことをやみくもに実施していくのではなく、事前に戦略を立てて計画的に顧客に商品やサービスをアピールしていくことが大切です。近年ではインターネットの普及、またSN…
詳しくみる【始末書テンプレ付き】ヒューマンエラー対策の具体例10選!ミスの原因と実践方法を解説
ヒューマンエラーとは、人間が原因となって発生するミスや事故のことです。ヒューマンエラー対策には、「業務フロー・マニュアルの見直し」「ヒヤリハットの共有」「システム・ツールの活用」「…
詳しくみる回覧板の電子化はどう始める?メリット・デメリット、アプリの紹介
回覧板の電子化は、情報の伝達をより早く、効率的に行う手段として注目されています。紙を使った回覧板は時間や手間がかかり、特に急ぎの連絡には不向きです。近年では、社内や町内会を問わず、…
詳しくみる