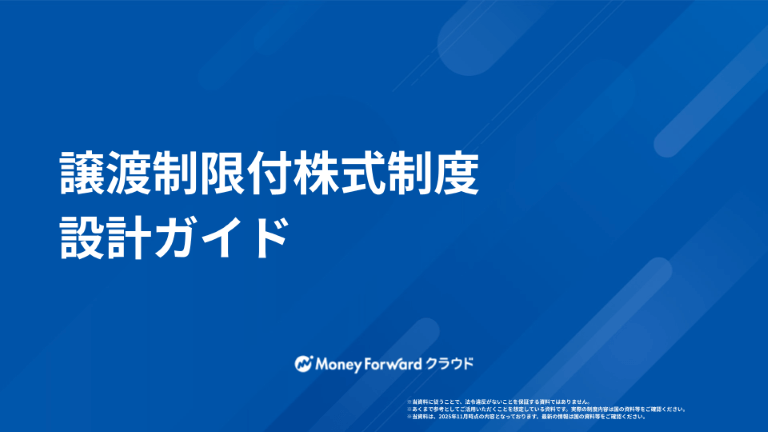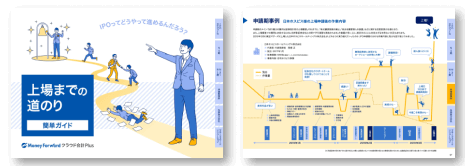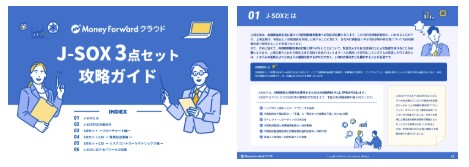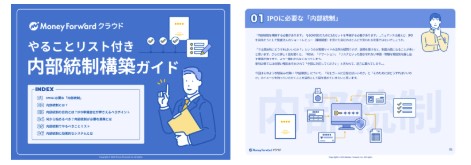- 更新日 : 2025年12月2日
譲渡制限付株式報酬(RS)のメリットやデメリット、導入プロセスを解説
譲渡制限付株式報酬(読み:じょうとせいげんつきかぶしき)とは、役員や従業員に対し、一定期間の譲渡(売却など)ができない制限が付いた株式を交付する制度です。主に、インセンティブの付与によって従業員や役員の意欲を高める目的で活用されます。
本記事では、IPO準備企業を対象に、譲渡制限付株式報酬制度のメリットやデメリット、会計・税務処理を解説します。
目次
譲渡制限付株式報酬(RS)とは
譲渡制限付株式報酬とは、一定期間の譲渡制限が付された自社の株式を役員や従業員に交付する報酬制度です。
リストリクテッド・ストック(RS)とも呼ばれる本制度は、役員や従業員にインセンティブを与えることで、中長期的に経営や企業価値の向上に貢献してもらう目的で活用されます。
株式が交付される役員などは、条件(主に一定期間以上の勤務)を達成するまで、自由に株式を譲渡(売却)できません。条件を達成した場合には、株式の売却して現金化できるようになります。
もし条件を達成できなかった場合(例:制限解除前に退職)、会社側に株式が没収されるため、利益は得られなくなります。
ストックオプション(SO)との違いは?
株式を使った報酬制度には、ストックオプション(SO)もあります。譲渡制限付株式報酬(RS)との主な違いは以下の点です。
| 項目 | 譲渡制限付株式報酬(RS) | ストックオプション(SO) |
|---|---|---|
| 内容 | 株式そのものを交付(譲渡制限付) | 将来、一定価格で株式を購入できる権利を付与 |
| 権利行使価格 | なし(株式を直接交付) | あり(あらかじめ決められた価格) |
| 付与時の費用 | 実質的な費用負担なし(※1) | なし(権利付与時) |
| 権利行使時 | 制限解除時に株式を取得 | 権利を行使して株式を購入(払込が必要) |
| 株価下落時 | 株価が下がっても価値は残る(ゼロにはなりにくい) | 株価が行使価格を下回ると、権利行使の価値がなくなる |
※1:多くの場合、金銭報酬債権を会社に支給し、役員・従業員がそれを現物出資する形で株式の交付を受けるため、現金の支出は発生しません。
譲渡制限付株式報酬における4つのメリット
譲渡制限付株式報酬制度の導入には、以下4つのメリットがあります。
- 中長期のモチベーションアップ
- 人材流出の防止(リテンション効果)
- コーポレートガバナンスの向上
- 現金不要
以下では、それぞれのメリットを詳しく解説します。
メリット1:モチベーションアップ
業績アップなどによって受け取った株式の価格が上がるほど、将来的に得られる報酬の金額も増えます。業績向上に貢献するインセンティブがあるため、株式を付与された役員や従業員のモチベーション向上が期待できます。
役員や優秀な従業員がより一層主体的に働くことで、会社の成長が加速しやすくなります。
また、ストックオプションとは異なり、株式そのものが付与されるため、株価が付与時より下落したとしても、価値がゼロになりにくい(※)という側面もあります。
※ストックオプションは、あらかじめ決められた価格(行使価額)で株式を購入する権利のため、株価が行使価額を下回ると権利行使の価値がなくなります。
以下の記事では従業員のモチベーションを高めるための仕組みについて解説していますので、ぜひご参照ください。
メリット2:人材流出の防止(リテンション効果)
譲渡制限付株式報酬は、一定期間以上働かないと、譲渡制限付株式の売却によって利益を得ることはできません。付与された役員や従業員は、その期間が経過する前に退職すると、株式を受け取る権利(あるいは売却する権利)を失うことになります。
そのため、キーパーソンとなる役員や優秀な従業員が離職する事態を防ぎ、人材を引き留める効果(リテンション効果)が期待できます。
メリット3:コーポレートガバナンスの向上
株式を付与された役員・従業員は、株主としての側面も持つことになります(議決権や配当権が付与される場合)。これにより、自身の報酬が株価と連動するため、「どうすれば株価が上がるか」という株主と同じ視点を持つようになります。
短期的な利益追求ではなく、中長期的な企業価値の向上を目指す意識が働きやすくなり、結果としてコーポレートガバナンスの向上にもつながります。
こうした理由により、役員・従業員が株主の意向に反する意思決定や行動を行うリスクを軽減できます。
以下の記事ではコーポレートガバナンスの基礎や実践的な取り組みについて詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。
メリット4:現金が不要
譲渡制限付株式報酬は、株式を付与する制度であるため、現金(キャッシュ)を支出せずに報酬を用意できます。そのため、会社のキャッシュ・フローを圧迫せず、手元の現金を事業投資や研究開発、採用活動などに充当できます。特に、手元に十分なキャッシュがない傾向のあるIPO準備中の企業にとっては大きなメリットだといえます。
譲渡制限付株式報酬制度のデメリット
メリットが多い譲渡制限付株式報酬制度ですが、導入に際してはデメリットも考慮する必要があります。
譲渡制限付株式報酬制度の導入には、以下のデメリットがあります。
- 従業員側の課税タイミング
- 株価下落時のインセンティブ低下リスク
- 株式の希薄化のおそれ
- 導入・運用手続きの負担
こちらのデメリットも詳しく見ていきましょう。
デメリット1:従業員側の課税タイミング
株式の付与を受ける従業員側にも注意が必要です。譲渡制限付株式は、譲渡制限が解除された時点で「給与所得」または「退職所得」として課税対象となります。売却して現金化していなくても、その時点の株価を基準に所得税と住民税が計算されるため、一時的に税負担が生じる可能性があります。
そのため、制限解除時には納税資金を確保しておくなど、現金の準備を事前に検討しておくことが重要です。
デメリット2:株価下落時のインセンティブ低下リスク
メリットの裏返しとして、会社の業績低迷などにより株価が下落し続けた場合、報酬としての魅力が薄れてしまいます。 株価が低迷すると、期待していた報酬額が得られないため、従業員のモチベーション維持やリテンション効果が弱まる可能性があります。
デメリット3:導入・運用手続きの負担
譲渡制限付株式報酬制度を導入するには、報酬として付与する株式数の上限や条件などを定め、株主総会での決議(※)を経る必要があります。 また、対象者との間で「譲渡制限付株式割当契約」を締結したり、その後の株式管理や制限解除の手続きなど、法務・労務・経理面での事務的な負担が発生します。
会社設立後からの導入は手続きが伴います。会社設立後に譲渡制限付株式報酬の制度を導入するためには、株主総会による特別決議をはじめとした手続きが必要となります。
実行までに手間がかかる上に成立しない可能性もあるため、会社設立(定款作成)の際に導入することが理想的です。
※報酬枠の設定自体は普通決議ですが、発行方法(特に有利発行)や定款変更が関わる場合は特別決議が必要となるケースもあります。
デメリット4:株式の希薄化
報酬として新たに株式を発行(新株発行)する場合、発行済株式の総数が増えるため、1株あたりの価値や株主の議決権の割合が相対的に低下する「株式の希薄化(ダイリューション)」が発生します。
株式が希薄化すると、企業の利益を発行済株式数で割って算出する「1株あたりの利益(EPS)」が減少し、将来的に配当額が減ったり株価が下落したりする可能性があります。また、議決権の割合が下がることで、株主総会における経営への影響力(権利面)が弱まるおそれもあります。
なお、会社が保有する自己株式を報酬として交付する場合は、新たな株式を発行しないため、発行済株式総数は増えず、直接的な希薄化は生じません。
譲渡制限付株式報酬を導入する流れ
譲渡制限付株式報酬は、会社の決議から始まり、従業員との契約、株式の交付、そして条件達成後の制限解除という流れで進みます。
- 株主総会での決議
- 割当契約の締結
- 金銭報酬債権の付与と現物出資
- 株式の交付(新株発行と自己株式処分の違い)
- 譲渡制限期間の経過
- 譲渡制限の解除(または無償取得)
以下では、それぞれの手続きを詳しく解説します。
手順1:株主総会での決議
まず、会社は株主総会を開き、この制度の導入を決定します。ここでは、報酬として付与する株式数の上限、対象者(役員や従業員の範囲)、譲渡制限の期間、制限解除の条件(例:3年間の継続勤務など)といった、制度の基本的な枠組みを決議します。
手順2:割当契約の締結
株主総会での決議に基づき、会社は対象となる役員や従業員と個別に契約を結びます。この際、「譲渡制限付株式割当契約」と呼ばれる契約書を締結するのが一般的です。
この契約には、具体的な株式数、正確な譲渡制限期間、退職時などの条件未達の場合に会社が株式を無償で取得(没収)する旨など、詳細な条件が定められます。
手順3:金銭報酬債権の付与と現物出資
株式を交付するため、会社はまず対象者に金銭(例:1株1,000円で100株なら10万円)を報酬として支払う権利(金銭報酬債権)を付与します。すぐには現金は渡しません。
次に対象者は、その「10万円を受け取る権利(金銭報酬債権)」を会社に差し出し(これを現物出資と呼びます)、その見返りとして株式を受け取ります。この方法により、対象者は現金を準備することなく株式を取得できます。
手順4:株式の交付(新株発行と自己株式処分の違い)
現物出資を受け、会社は対象者に譲渡制限が付いた株式を交付します。この時、会社が株式を準備する方法が2つあります。
- 新株発行:会社が新たに株式を発行して(刷って)交付する方法です。これにより、発行済株式総数が増加します。
- 自己株式の処分:会社が既に保有している自社の株式(金庫株)を交付する方法です。この場合、発行済株式総数は変わりません。
いずれの方法でも、この時点で対象者は株主となりますが、まだ売却はできません。
手順5:譲渡制限期間の経過
対象者は、「譲渡制限付株式割当契約」で定められた条件(例:継続勤務)が満了するまでの期間、勤務を継続します。この期間中は、株価が変動しても株式を売却することはできません。
手順6:譲渡制限の解除(または無償取得)
契約で定められた条件(例:3年間の勤務)を達成すると、株式にかかっていた譲渡制限が解除されます。この時点で、対象者は初めて株式を自由に売却して現金化できるようになります。これが実質的な報酬の受け取りとなります。 もし、制限期間中に退職するなど条件を満たせなかった場合は、契約に基づき、会社がその株式を無償で取得(没収)します。
参照:『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました|経済産業省
譲渡制限付株式報酬の会計や税務処理
譲渡制限付株式を受け取った役員や従業員には、さまざまなタイミングで税金が課税されます。また、株式を付与する法人側では会計処理が発生します。
譲渡制限付株式報酬の 処理が発生する主なタイミングは、付与時、譲渡制限期間中、譲渡制限の解除時、株式売却時 です。
譲渡制限付株式報酬制度の会計・税務処理を解説します。
付与時
株式を交付した時点に、法人側で会計処理が生じます。この時点では、役員や従業員からの労働(譲渡制限期間中の勤務)はまだ提供されていないため、交付した株式の価値(発行価格や時価)を、将来の費用に対する前払いとして「前払費用」といった資産の勘定科目で(借方)に計上します。相手勘定(貸方)は、株式の準備方法によって異なります。
受け取る従業員側は、譲渡制限があり自由に売却できないため、この時点では所得として認識されず、課税されません。
譲渡制限期間中
法人側は、付与時に資産計上した「前払費用」を、譲渡制限期間(=従業員が勤務を提供する期間)にわたって按分し、「株式報酬費用」として会計上、費用計上していきます。例えば、制限期間が3年であれば、3年間に分けて費用として認識します。
譲渡制限の解除時
法人側では、譲渡制限期間が満了し、従業員が勤務条件などを達成した時点で、「前払費用」の費用計上が完了します。税務上は、この制限解除のタイミングで、それまで会計上で費用計上してきた累計額が、役員・従業員への給与(報酬)として「損金」に算入できます。
一方で、株式を保有する役員・従業員側は、この制限解除の時点で初めて株式が自由に売却できる(価値が確定する)ため、所得税・住民税が課税されます(1回目の課税)。
- 課税対象額:譲渡制限解除時の株価 × 株式数
- 所得区分:原則として「給与所得」。
給与所得は他の給与や賞与と合算され、累進課税が適用される「総合課税」の対象。売却して現金化する前に課税されるため、納税資金の準備が必要になる場合がある。
ただし、役員の退職に伴って譲渡制限が解除されるケースなどでは、税制上優遇される「退職所得」に該当することもあります。
株式売却時
制限解除後、従業員がその株式を売却して利益(売却益)が出た場合、その利益に対して再度、所得税・住民税が課税されます(2回目の課税)。 この所得は「譲渡所得」という区分になります。これは給与所得とは分離して税額を計算する「申告分離課税」が適用されます。売却益は以下のように計算されます。
- 売却益:(売却時の株価 - 取得価額) × 売却株式数
この計算式における「取得価額」とは、制限解除時に給与所得として課税された時の株価を指します。既に給与所得として課税された部分(価値)を取得価額とみなすことで、二重に課税されない仕組みになっています。
以上が基本的な流れですが、会計基準(「株式報酬に関する会計基準」など)や税制は変更される可能性があり、個別の契約内容によって取り扱いは異なります。実務を行う際は、税理士や公認会計士などの専門家に相談してください。
譲渡制限付株式報酬制度は、企業と従業員の利害を一致させる仕組み
譲渡制限付株式報酬(RS)は、役員や従業員に自社株を持ってもらうことで、中長期的な企業価値の向上を目指すインセンティブ制度です。人材の確保・定着や、現金支出を抑えたい企業にとって選択肢の一つとなります。 一方で、導入には株主総会決議などの手続きが必要であり、会計処理や税務処理も伴います。
導入を検討する際は、制度の目的を明確にし、弁護士や税理士、公認会計士などの専門家の助言も得ながら進めるとよいでしょう。
IPOコンサルタントを依頼すると内部管理体制の構築や書類作成などのサポートを得ることができます。より詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリットを解説
Pointジョブ型雇用とは? ジョブ型雇用は、職務内容と責任範囲を明確に定めた上で人材を配置・評価する雇用形態です。 職務記述書で業務を明確化 専門性・成果で評価される メンバーシ…
詳しくみる退職後のストック・オプション行使は難しい?理由や裁判例を紹介
一部の例外を除いて、ストック・オプションを行使するためには在職を行使条件としている会社が多く、退職するとストック・オプションが行使できなくなります。しかし一部の例外も存在しており、…
詳しくみるストックオプションに関連する法律は?種類・要件・注意点も解説
ストックオプションは企業の成長を支える戦略的な報酬制度です。とくにスタートアップやベンチャー企業にとっては、現金報酬に代わる強力なインセンティブ手段として注目されています。しかし、…
詳しくみる株主総会とは?決議事項や開催時期・成立要件・運営方法をわかりやすく解説
株主総会とは、株式会社の株主が集まり、会社の重要な事項を決定する会議です。 会社の運営や方向性に関する重要な意思決定の場であり、株主が会社経営に直接参加できる唯一の機会でもあります…
詳しくみるIPO直前期の離職率は上場審査に影響する?目安や審査基準を解説
IPOを目指す企業において、離職率が高いとマイナスなイメージになります。 離職率が高いと上場審査に悪影響を及ぼすとも言われており、IPOを目指すのであれば、離職率を引き下げたいとこ…
詳しくみるIPOにおける労務DD(デューデリジェンス)とは?重要性、調査項目、プロセスを解説
労務DD(デューデリジェンス)とは、IPOを目指す企業が自社の人事・労務に関する状況を詳細に調査する業務です。IPOにおいては、主に上場審査をクリアする可能性を高めたり、労務面での…
詳しくみる