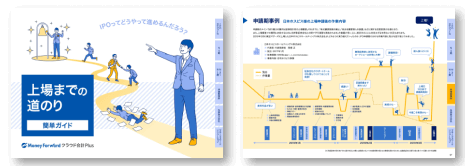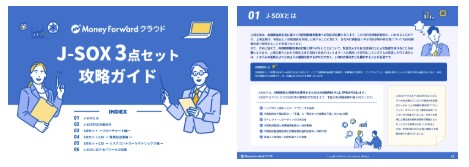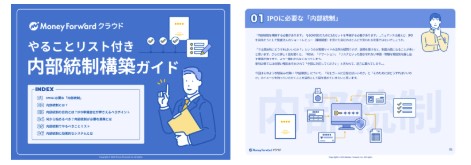- 作成日 : 2025年4月23日
税制非適格ストックオプションとは?税金・会計処理・確定申告まで詳しく解説
ストックオプションは、スタートアップや上場企業を中心に導入が進んでいる報酬制度です。
なかでも税制非適格ストックオプションは設計の自由度が高く柔軟に活用できる反面、税制優遇がなく税負担や会計処理が複雑になる点に注意が必要です。
本記事では仕組みや他制度との違い、課税タイミング、申告の要否をわかりやすく解説します。
目次
税制非適格ストックオプションとは
税制非適格ストックオプションとは、企業が役員や従業員に対して付与するストックオプションのうち、一定の税制要件を満たしていないものを指します。
税制適格ストックオプションと異なり、付与対象者に制限がないため、大株主や社外取締役、法人や監査役などにも柔軟に設計・付与が可能です。
さらに税制非適格ストックオプションは、権利行使価額を株式の時価より低く設定できます。
行使期間についても、税制適格では原則として付与から2年以上が必要ですが、非適格ではそのような制限はありません。
さらに有償ストックオプションとして、取得時に一定の金額を支払わせる形にすることも可能です。
ただし上記のような設計の自由さがある一方で、税制面での優遇がないため、一般的には税負担が大きくなる傾向にあります。
なお以下の記事では、基本概要や税制適格ストックオプションについてより詳しく解説していますので、導入を検討している方は、あわせて参考にしてみてください。
税制適格ストックオプションとの違い
税制適格ストックオプションは、所定の要件を満たすことで税制上の優遇措置が受けられる制度であり、無償税制適格ストックオプションとも呼ばれています。
権利を行使して株式を取得した際には課税されず、株式を売却した時点ではじめて譲渡所得として課税されます。その際の税率は、他の所得に比べて比較的低めに抑えられているのも特徴といえるでしょう。
また対象となるのは原則として会社の役員や従業員に限られ、行使期間も契約締結から2年以上10年以内と定められています。
上記のように、税制適格ストックオプションは一定の制限がある代わりに、税負担を抑えられるのがメリットです。
| 項目 | 税制適格ストックオプション | 税制非適格 ストックオプション |
|---|---|---|
| 権利対象者 | 会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人であること | 付与制限なし |
| 課税のタイミング | 売却時に譲渡所得が課税 | 権利行使時に給与所得が課税 売却時に譲渡所得が課税 |
| 権利行使期間 | 2年~10年以内に権利行使が必要 | 自由に設定が可能 |
| 権利行使価額 | 時価以上の価格設定が必要 | 自由に設定が可能 |
| 権利付与時の対価支払い | 権利付与は無償 | 無償もしくは有償どちらでも可能 |
有償ストックオプションとの違い
有償ストックオプションは、取得時に対価を支払って権利を得るストックオプションです。
金融商品とみなされるため、権利を行使する段階では課税されず、株式を売却して利益を得た時にのみ譲渡所得として課税されます。
取得時に費用はかかるものの、発行価額が市場価格より低く設定されることもあり、将来的な値上がりによって利益を得やすい仕組みです。
税制非適格ストックオプションとは異なり、課税のタイミングが異なる点に注意が必要です。
| 項目 | 無償税制適格 ストックオプション | 有償 ストックオプション |
|---|---|---|
| 課税のタイミング | 売却時に譲渡所得が課税 | 売却時に譲渡所得が課税 |
| 権利付与時の対価支払い | 権利付与は無償 | 権利付与は有償 |
有償ストックオプションのメリットや多くの企業が導入する理由について、以下で詳しく解説しています。
税制非適格ストックオプションの課税されるタイミング
税制非適格ストックオプションでは、「権利を行使する時」と「株式を売却する時」の2段階で課税が発生します。それぞれ異なる種類の所得とされるため、税率や処理方法にも注意して処理しましょう。
権利行使時:住民税と所得税が課税
ストックオプションを行使して株式を取得した時点で、株式の時価と権利行使価額との差額が利益とみなされ、給与所得として課税対象になります。
課税対象の利益は以下の式で算出されます。
課税されるのは所得税と住民税、復興特別所得税の3つで、所得税は5%から最大45%までの累進課税、住民税は一律10%であり、復興特別所得税は、基準所得税額×2.1%となります。
したがって合計税率は最低15.105%〜最高で55.945%になります。給与所得として課税された場合、企業は源泉徴収を行う義務がある点を覚えておきましょう。
なお以下の記事では、ストックオプションの行使方法について、解説しています。企業は権利を付与した相手に解説できるよう、知識を深めておくことが大切です。
売却時:譲渡所得として課税
株式を実際に売却した際には、譲渡所得として課税され、利益は以下のように計算されます。
ここで適用されるのは所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%の合計20.315%が課税される税率です。
税制非適格ストックオプションの会計処理
税制非適格ストックオプションの導入を検討しているけど、会計処理が不安、と感じる方もいるでしょう。
本項では、権利付与時から株式売却までの会計処理について、解説します。
下記の記事ではストックオプション全般の会計処理について解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
権利付与時の会計処理
ストックオプションは、企業が従業員や役員に対して将来的な報酬として付与するものです。
多くの企業では「一定期間の勤務継続」や「業績目標の達成」といった条件を満たすとはじめて、ストックオプションの権利が確定します。
したがって、付与時点はあくまで約束に過ぎず、会計上の処理は行われません。
権利確定までの会計処理
ストックオプションの権利が確定するまでの間、企業は段階的に費用を計上する必要があります。
上場企業や上場を目指す企業の場合には「公正な評価額」をもとに、未上場企業では株価と行使価額の差、いわゆる「本源的価値」を基準に算定されるのが一般的です。
なお、非上場企業では市場価格が存在しないため、株価評価には注意が必要となります。
とくにセーフハーバールールの導入により、過去には行使価額が高く設定されていた結果、費用がゼロで済んでいた状況から、現在では費用認識が生じるケースも増加しています。
また税制非適格ストックオプションは、権利確定までの期間設定に制限がないため、権利を即時に確定する設計も可能です。
付与から行使まで即時に確定した場合は、付与した期に一括で費用計上を行います。費用は「株式報酬費用」として、対応する資本項目として「新株予約権」を計上しましょう。
新株予約権について知識を深めたい方は、以下の記事もご覧ください。
権利行使時の会計処理
従業員が実際にストックオプションを行使して株式を取得する段階では、企業側では費用の計上は行われません。
なぜなら権利行使時は従業員が株式購入により資金を支払い、それが企業の資本に組み込まれるためだからです。
具体的な処理としては、これまで会計上で資本として計上していた「新株予約権」の残高を取り崩し、受け取った資金を「資本金」や「資本剰余金」として計上します。
したがって税制非適格ストックオプションにおける会計処理は、権利確定期間までの間は費用を計上、権利行使時には、資本として計上する処理が必要となるわけです。
ストックオプションの中でも、税制非適格ストックオプションは、設計の自由度が高い制度であるため、各企業の運用実態に応じた正確な会計処理が重要となります。
税制非適格ストックオプションの確定申告は必要か?
税制非適格ストックオプションに関連して課税が発生するタイミングは主に2回あります。
ひとつは権利を行使して株式を取得した時、もうひとつはその株式を売却した時です。いずれも、場合によっては確定申告が必要になることがあります。
次項で詳しく解説しますので、順に見ていきましょう。
なお以下の記事では、税金額や課税時期について、詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
源泉徴収ありの特定口座なら確定申告は不要
オプションの権利行使によって発生する利益は、税務上「給与所得」として扱われ、企業が源泉徴収を行うのが一般的です。たとえば在職中にオプションを行使した場合、その利益にかかる所得税はすでに給与と一緒に徴収されているため、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、退職後にオプションを行使したケースや、医療費控除や寄附金控除などを受ける目的で確定申告を行う場合は、あわせてオプション行使分も申告が必要になる可能性があります。
源泉徴収なしの一般口座なら確定申告が必要
ストックオプションで取得した株式を売却した際に得られる利益は「譲渡所得」として扱われますが、確定申告の要否は証券会社の口座の種類によって異なります。
源泉徴収ありの特定口座の場合、売却益に対する税金は証券会社が自動で計算し、あわせて源泉徴収も行われるため、基本的には確定申告は不要です。
ただし源泉徴収なしの特定口座または一般口座の場合は、自身で譲渡所得を計算し、確定申告で申告と納税を行う必要があります。
税制非適格ストックオプションのメリットとデメリット
税制非適格ストックオプションは、税制適格ストックオプションと比べて制度設計の自由度が高いという特徴があります。
一方で税務面や会計処理における注意点も多く、制度を導入・運用するうえでは慎重な検討が必要です。
次項では、非適格ストックオプションの主なメリットとデメリットについて解説します。
メリット
税制非適格ストックオプションを導入する、主なメリットは以下の3つが挙げられます。
- 付与条件を自由に設定できる
- スタートアップや成長企業に向いている
- 多様な活用が可能である
税制非適格ストックオプションは、法律上の要件が課されていないため、企業が自社の状況や戦略にあわせて柔軟に条件を決めることが可能です。
たとえば社外取締役や外国人従業員、大株主といった、税制適格では対象外となる人にも付与できます。
また手元の資金が限られているスタートアップ企業にとって、非適格ストックオプションは現金を使わずに優秀な人材への報酬を設計できる手段にもなり得ます。
将来的な企業価値の上昇を見越して、権利行使時や株式売却時に報酬を得られる仕組みは、成長志向が高い企業との相性がよいといえるでしょう。
そして税制適格ストックオプションのように「無償でなければならない」「行使期間は2年以上10年以内」といった制限がありません。ゆえに企業の方針に応じた多様な活用方法が検討できます。
デメリット
多数のメリットがある一方で、以下のような留意点もあります。
- 税負担が大きくなりやすい
- 株式を売却した時にも課税される
- 会計処理や税務申告が複雑になる
非適格ストックオプションでは、権利を行使した時点で給与所得として課税されます。給与所得は累進課税の対象となるため、高所得者の場合は最大55%もの税率が適用されることもあります。売却時のみ課税される税制適格と比べて、明確なデメリットといえるでしょう。
また権利行使時に課税された後、株式を売却した時にも譲渡所得として再度課税されるため、2段階で税金がかかります。ゆえに税制面での優遇がない分、実質的な税負担が大きくなる傾向にあります。
そして非適格ストックオプションは、自由度が高い反面、企業側の会計処理や税務対応が煩雑になりやすい点は課題といえるでしょう。
とくに未上場企業では、株価評価や本源的価値の計算、費用の按分処理など専門的な対応が必要になるケースが多く、税理士や公認会計士との連携が欠かせません。
税制非適格ストックオプションに関するよくある質問
税制非適格ストックオプションを活用する際には、税務上や手続き面での疑問が生じることがあります。
本項では、とくに多い2つの質問について、ポイントをわかりやすく解説します。
法定調書や支払調書の提出は必要か?
法定調書は、権利を付与した段階では提出不要ですが、行使された場合は提出が必要です。
税制非適格ストックオプションを付与するだけでは、権利を与えただけのため、提出は必要ありません。しかし従業員などがオプションを行使し利益が確定した場合には、「新株予約権の行使に関する調書」として税務署に報告する必要があります。
企業は個別の支払調書および合計表を作成し、期限内に提出しましょう。
退職後の権利行使は確定申告が必要か?
退職後に権利を行使して利益を得た場合は、確定申告が必要になります。
在職中に行使した場合は企業が源泉徴収を行いますが、退職後にオプションを行使して利益を得た場合は、源泉徴収がされないため、個人での申告が求められます。
この際の所得区分は「給与所得」ではなく、「雑所得」として扱われるケースが一般的です。
退職後の収入については、税務署への申告・納税は自己責任での対応となるため、年度末までに必要書類を揃え正確に申告を行うように、企業は退職者に伝えましょう。
なお、退職希望者の中に、退職後に権利行使を行う従業員がいる場合に備えて、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
税制非適格ストックオプションは会計処理に注意が必要
税制非適格ストックオプションは、制度設計の自由さが魅力ですが、税務や会計における対応は慎重さが求められます。
行使時と売却時の二重課税や口座の種類による申告要否、退職後の対応、調書の提出義務なども理解が不可欠です。
活用にあたっては、専門家に相談しながら、自社にとって最適な制度設計を行うのが大切といえるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
株式交付信託とは?導入の流れ、メリット・デメリット、会計・税務処理、事例を解説
株式交付信託は、インセンティブ報酬の一つです。 株式の形で報酬が提供される仕組みにはさまざまな形式があります。 そこで本記事では、株式交付信託に初めて興味を持つ方でも理解しやすく、…
詳しくみるストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説
上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリッ…
詳しくみるストックオプションの行使価格の決め方は?計算方法や注意事項を解説
ストックオプションの行使価格の決め方は、ストックオプションが税制適格か非適格か、上場企業か非上場企業かなど、さまざまな条件により異なります。 この記事ではストックオプションの行使価…
詳しくみるチームビルディングとは?意味や目的、具体例を紹介!
現代のように競争が激しいビジネス環境では、優れた個人の力だけで成功することは難しいでしょう。多くの企業はチームビルディングの重要性に気付き、組織内の人材が円滑に協力し合えるようなチ…
詳しくみる成果主義とは?意味や能力主義との違い、向いている人、企業の導入方法
成果主義とは、仕事の成果に基づき評価を行う制度のことです。バブル崩壊後の業績悪化に伴い人件費負担を減らしたい企業のニーズから導入が広がりました。また、昨今の働き方改革の中でも再び注…
詳しくみる労働生産性とは?定義や上げるメリット解説!
労働生産性とは、従業員1人当たり、または労働時間1時間当たりどのくらいの生産性を生み出したかを数値化した指標のことです。 労働生産性には、物理的な量を表す物的労働生産性と、付加価値…
詳しくみる