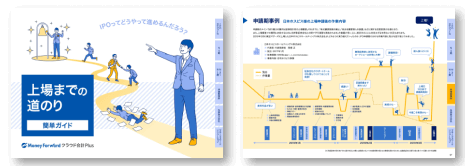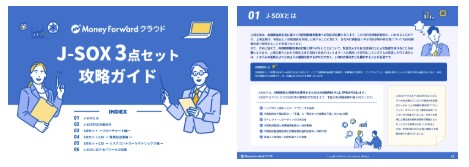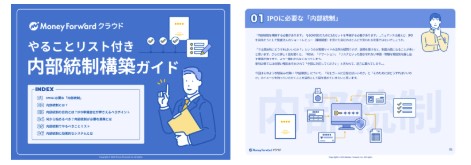- 作成日 : 2025年4月23日
無償ストックオプションとは?メリット・デメリットや注意点を徹底解説
無償ストックオプションは、従業員や役員に対して無償で自社株購入権を付与する制度で、資金負担なくインセンティブを与えられるのが大きな魅力です。一方で、税務や会計処理が複雑であり、制度設計には注意が必要です。
本記事では、無償ストックオプションと有償ストックオプションの違いやメリット・デメリットなどを解説します。
目次
無償ストックオプションとは|金銭の払込なしで付与されるストックオプション
無償ストックオプションは、従業員や役員が金銭の負担なく、あらかじめ定められた価格で自社株を購入できる権利を受け取れる制度です。
とくにスタートアップ企業においては、十分な資金を持たない従業員に対して金銭的な負担をかけず、将来的な利益の機会を提供できる点が特徴です。
企業の成長により株価が上昇すれば、権利行使価格よりも市場価格が高くなることで、従業員は株式売却時に利益を得られます。
無償で付与できるため、資金面で制約のあるスタートアップ企業でも導入しやすく、初期メンバーへの重要な報酬インセンティブとして活用されています。
ストックオプションの基本情報については、下記の記事で具体的に説明しているため、ぜひ参考にしてみてください。
税制適格と税制非適格
ストックオプションには「税制適格」と「税制非適格」の2種類があります。
税制適格ストックオプションは、権利行使時の課税がなく、株式売却時に1回だけ課税される仕組みです。一定の条件を満たすことで、税負担を抑えながらインセンティブを受け取れます。付与対象は原則として役員や従業員に限られるため、注意が必要です。
また、税制適格ストックオプションとして認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 権利行使価額が付与時の時価以上であること
- 行使期間が2年以上10年以内であること
- 年間の権利行使価額が1,200万円以下であること など
一方、税制非適格ストックオプションは上記の要件を満たさないため、税制上の優遇を受けられません。権利行使時に給与所得として課税され、所得税と住民税を合わせて最大約55%の税率が適用されます。
税制適格か非適格かによって、課税タイミングや税負担に大きな差が生じます。ストックオプションを活用する際は、それぞれの制度の違いを理解したうえで、適切に判断することが重要です。
無償ストックオプションと有償ストックオプションの違い
無償ストックオプションと有償ストックオプションの違いは、発行時に付与対象者がオプションの対価として金銭を支払うかどうかです。
有償ストックオプションでは、対象者が事前に定められた金額を負担して取得する必要があります。発行価額は、ストックオプションに見合った業績や株価などに基づいて算出されます。
報酬ではなく時価で購入した有価証券とみなされるため、権利行使時には課税されません。
一方、無償ストックオプションは、企業が金銭の支払いを受けずに付与するインセンティブです。通常は職務執行の対価として付与されるため、給与として課税されることがあります。
課税を回避するには、税制適格ストックオプションとしての条件を満たす必要があります。
有償ストックオプションについては、下記の記事で詳しく説明しているため、あわせてご覧ください。
無償ストックオプションの会計処理
無償ストックオプションでは、付与・行使・失効のタイミングで会計処理が必要です。ストックオプションの評価額は、企業の上場・未上場の別によって扱いが異なるため、事前に確認しておく必要があります。
以下では、上場企業の場合と未上場企業の場合に分けて会計処理方法を紹介します。
上場企業の場合
上場企業が無償ストックオプションを付与する場合、まず、ブラック=ショールズ・モデル等のオプション評価モデルを用いて公正価値(評価単価)を算出し、評価単価に個数をかけて付与総額を算出しましょう。
公正価値とは、ストックオプションの本源的価値(算定時においてストックオプションが行使されると仮定した場合の価値)に、時間的価値(権利行使期間期限までの株価の変動による価値)を加味して求められる価値です。
株価の変動性が大きい場合には、将来株価が大きく上昇する可能性があるため、ストックオプションの評価単価も大きくなります。
評価単価に株数をかけて算出したストックオプションの総額を、対象者の権利確定期間に応じて按分し、各期末に以下の仕訳を行います。
- 借方:株式報酬費用 ◯◯円
- 貸方:新株予約権 ◯◯円
なお、無償ストックオプションは、職務執行の対価として付与される報酬であるため、会計上は「人件費」として扱われる場合があります。
未上場企業の場合
未上場企業では、上場企業と異なり、公正価値の算定が困難な場合が多く、「本源的価値(インストリンシック・バリュー)」のみを用いた会計処理が特例として認められています。
会計処理上は、株式報酬費用として費用計上し、新株予約権として純資産に計上する点は、上場企業と共通です。
本源的価値とは、権利を行使したと仮定した場合のストックオプションの金銭的価値を指し、「自社株式の評価額 - 権利行使価額」で算出します。
たとえば、株式評価額が1,200円、権利行使価額が1,000円であれば、本源的価値は200円です。そのため権利行使価額が株式評価額以上の場合、上場企業の場合と異なり、会計処理は発生しません。
付与時および期間中の仕訳は以下のとおりです。
- 借方:株式報酬費用 〇〇円
- 貸方:新株予約権 〇〇円
権利が失効した場合は、 以下のようになります。
- 借方:新株予約権 〇〇円
- 貸方:新株予約権戻入益 〇〇円
また、行使された場合は、
- 借方:新株予約権 〇〇円、現預金 〇〇円
- 貸方:資本金等 〇〇円
となります。
無償ストックオプションの仕訳タイミング
無償ストックオプションの会計処理は、主に3つのタイミングで仕訳が必要です。まずは前提となる条件を紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行総数 | 100個 |
| 評価単価 | 1,000円 / 個 |
| 権利行使価額 | 1,000円 / 個 |
| 対象者数 | 10名 |
| 1人あたりの付与数 | 10個 |
上記の前提をもとに、以下では各タイミングにおける仕訳方法を解説します。
ストックオプションを付与するとき
企業が無償ストックオプションを役員や従業員に付与した場合は、会計上、対応する費用を仕訳として計上する必要があります。
具体的には、評価単価1,000円のストックオプションを100個発行したため、「1,000円 × 100個 = 100,000円」となり、計算をもとに仕訳を行うと以下のようになります。
- 借方:株式報酬費用 100,000円
- 貸方:新株予約権 100,000円
株式報酬費用とは、ストックオプションなどの株式を報酬として付与することで発生する会計上の費用です。一方、新株予約権は、将来的に株式が発行されることを見越して、純資産の部に計上される項目です。
無償であってもストックオプションには経済的価値があるため、評価単価に基づいて処理されます。
今回のケースでは、評価単価1,000円のストックオプション100個を、ひとつの会計期間にまとめて費用として計上しています。ただし、実務では、3年などの権利行使期間に合わせて、費用を分割して計上することが一般的です。
ストックオプションの権利が行使されたとき
対象者がストックオプションを行使した場合、企業は取引に応じた仕訳を計上する必要があります。権利行使とは、対象者があらかじめ定められた価格で自社株を取得することをいいます。
対象者6名がそれぞれ10個ずつの計60個のストックオプションを行使した場合の仕訳は、以下のとおりです。
- 借方:当座預金 60,000円
- 借方:新株予約権 60,000円
- 貸方:資本金 120,000円
企業は、対象者からの株式購入代金の受け取りにより当座預金が増加します。同時に、以前に計上していた新株予約権を取り崩して、資本金に振り替えます。
今回のケースでは、6名が10個ずつ権利を行使したため、当座預金は「6名 × 10個 × 1,000円 = 60,000円」です。新株予約権については、発行総数100個・評価額100,000円のうち、行使された60個分にあたる60,000円(= 100,000円 × 60個 / 100個)を取り崩します。
当座預金と新株予約権を合算し、資本金には合計で120,000円を計上します。
ストックオプションの権利が失効したとき
ストックオプションにはあらかじめ定められた行使期間があり、期間満了後は権利が失効します。権利が失効すると、会計上は仕訳処理が必要です。
失効とは、対象者が期限内にストックオプションを行使せず、株式を取得する権利を失った状態を指します。
たとえば、10名に10個ずつストックオプションを付与したうち、4名が期限内に行使せずに失効した場合(失効数40個)の仕訳は、以下のとおりです。
- 借方:新株予約権 40,000円
- 貸方:新株予約権戻入益 40,000円
評価単価が1,000円の場合、失効した40個分の新株予約権は40,000円になり、あらかじめ計上していた金額を取り崩す必要があります。新株予約権戻入益とは、使われなかった株式報酬費用が収益として戻ることを意味します。
上記のように、ストックオプションの失効時にも適切な会計処理が必要です。
無償ストックオプションのメリット
無償ストックオプションは、企業が金銭負担なく優秀な人材を引き留めたり、モチベーションを高めたりする手段として活用されています。制度の仕組みだけでなく、導入によって得られる効果を正しく理解することが重要です。
以下では、無償ストックオプションのメリットについて紹介します。
初期の資金負担なしで優秀な人材を確保できる
無償ストックオプションは、企業が従業員や役員に対して金銭的な負担をかけずに付与できる制度です。そのため、資金に余裕のないスタートアップ企業でも導入しやすく、優秀な人材を確保する手段として活用されています。
従業員は、無償ストックオプションにより、企業の成長に応じた利益を得る機会を持てます。たとえば、企業の成長によって株価が上昇した場合、権利行使時の価格より高い市場価格で株式を売却することで、利益を得ることが可能です。
上記のように、無償ストックオプションは人材にとって将来の利益が見込める魅力的な制度であり、企業にとっては初期の資金負担なしに優秀な人材の獲得と定着を図れるメリットがあります。
退職防止・中長期的なインセンティブになる
無償ストックオプションは、退職防止や中長期的なインセンティブとして有効です。多くの場合、ストックオプションの権利行使には在籍期間などの条件が設定されており、従業員の長期的な定着を促す効果が期待できます。
また、企業の成長に伴い株価が上昇すれば、従業員は利益を得られるため、日々の業務に対する意欲も高まります。
企業と従業員の利益が一致すれば、双方にとってメリットのある関係の構築が可能です。無償であっても、将来的な利益を見込めるため、中長期的なモチベーションにつながるでしょう。
無償ストックオプションのデメリットと注意点
無償ストックオプションは魅力的な制度ですが、会計や税務、従業員とのトラブルリスクなど、導入にあたって注意すべき点も存在します。
制度を正しく理解せずに導入すると、予期せぬコストや混乱を招く可能性があるため注意が必要です。以下では、無償ストックオプションのデメリットと注意点を紹介します。
税制適格でない場合は累進課税が課される
無償ストックオプションでも、税制適格要件を満たさない場合は税制非適格とされ、給与課税の対象です。課税は累進課税で行われ、所得税と住民税を合わせて最大約55%が課される可能性があります。
ストックオプションの課税の流れは、権利行使時と株式売却時の2段階に分けられます。税制非適格の場合は、権利行使時に給与所得として、売却時に譲渡所得として、それぞれ別の所得区分で課税される点が特徴です。
とくに、売却前の行使時点で先に課税される点は注意が必要です。納税資金を事前に自己負担で準備する必要があるケースもあります。
無償のため従業員への効果が薄い
無償ストックオプションは金銭の負担なく付与されますが、従業員の報酬としての実感が湧きにくいというデメリットがあります。
とくに株式投資に関心がない従業員やリスクを避けたいと考える人にとっては、ストックオプションの価値が伝わりにくく、モチベーション向上に結びつかない場合があります。
そのため、制度を導入する際は、無償であっても従業員が意義を理解できるように、メリットや将来的な利益の仕組みを丁寧に説明することが重要です。
株主総会での決議が必要である
無償ストックオプションを発行する場合は、会社法第238条に基づき、原則として株主総会での決議が必要です。
上記は役員に限らず、広く新株予約権を発行する場合に適用されます。ただし、定款に報酬としての付与上限が定められている場合は、会社法第361条により株主総会の決議を省略できることもあります。
株主総会の招集や決議には一定の手続きと時間がかかるため、導入や変更を迅速に進めるのが難しくなることもあるでしょう。
また、株主の賛同が不可欠であり、無償ストックオプションが株主利益にどう影響するかを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。
参考:会社法(平成十七年法律第八十六号) 第238条|e-Gov 法令検索
参考:会社法(平成十七年法律第八十六号) 第361条|e-Gov 法令検索
リスクを踏まえて無償ストックオプションをうまく活用しよう
無償ストックオプションは、初期コストを抑えつつ優秀な人材に報いる手段として有効ですが、税務や会計処理の複雑さ、制度設計上のリスクも伴います。
制度の特徴と注意点を正しく理解し、自社の状況に合った形でうまく活用していきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
人的資本可視化指針とは?可視化のメリットや具体的な方法を解説
人的資本可視化指針とは、人的資本の開示に関する方向性などが定められた指針です。 これを導入することにより、投資家からの評価向上や従業員の満足度向上といったメリットが見込めます。ただ…
詳しくみるチームビルディングとは?意味や目的、具体例を紹介!
現代のように競争が激しいビジネス環境では、優れた個人の力だけで成功することは難しいでしょう。多くの企業はチームビルディングの重要性に気付き、組織内の人材が円滑に協力し合えるようなチ…
詳しくみるベースアップとは?昇給との違いや計算方法を解説!
ベースアップとは、会社の労働者全員を対象として賃金水準の底上げを図ることです。ベースアップには一律に賃金額を上乗せする方法と、基本給に対して一律の率を掛けた分だけ昇給させる方法があ…
詳しくみるナレッジマネジメントとは?SECIモデルや導入方法についても解説!
ナレッジマネジメントとは、従業員が保有する知識や経験などを企業内で共有して活用する経営手法のことです。ナレッジマネジメントを有効活用することで、企業の競争力や企業価値を向上させるこ…
詳しくみるファントムストックとは?仕組みやメリット・デメリット、注意点などを解説
ファントムストックは、企業が役員や従業員に対して提供する金銭報酬の一種です。企業の成長に貢献した役員や従業員を評価し、モチベーションを高めるための仕組みです。この制度では、対象者に…
詳しくみるストック・オプションとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
「ストック・オプション」という言葉は耳にしたことがあるものの、概要や制度の仕組みなど詳しく知らない方は多いでしょう。ストック・オプションとは、自社の株を購入できる権利のことです。購…
詳しくみる