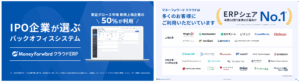- 更新日 : 2025年12月2日
IPO(新規上場)における売上高の目安は?上場審査のポイントも解説
IPO(Initial Public Offering)を目指す企業にとって、「どの程度の売上高があれば上場できるのか?」という問題は重要なテーマです。上場する市場区分(東証グロース、スタンダード、プライムなど)によってIPO時の売上高の目安は異なり、上場審査では売上以外の指標も重視されます。
本記事では、IPOの売上高目安を市場別に解説し、あわせて売上高以外に重要視される審査ポイントについて説明します。
目次
東証グロース市場におけるIPO売上高の目安
東証グロース市場は、革新的なビジネスモデルや成長性を武器にする企業にとって、最も親和性の高い市場です。この市場では売上高に関する厳格な数値基準がなく、赤字の企業でも上場が可能となる柔軟な特徴があります。ここでは、東証グロース市場におけるIPO売上高の実情や傾向、さらには実際の上場事例から見える特徴を解説していきます。
グロース市場では売上高に明確な基準がない
東証グロース市場(旧マザーズ市場)では、上場基準に売上高に関する明確な条件が設けられていません。そのため、上場する企業の売上規模には大きな幅があり、小規模なスタートアップから中堅企業までが対象となります。
実際、グロース市場では時価総額60億円未満の企業が上場企業の過半数を占めています。さらに営業利益についても、2億円未満または赤字で上場した企業が全体の約6割にのぼります。たとえば、フリマアプリで知られるメルカリも、上場直前期には赤字を計上していましたが、事業の成長性が高く評価され、上場に至りました。
このように、現時点での業績よりも、将来的な企業の成長性を重視する傾向がグロース市場の特徴となっています。
審査方針は成長性重視
グロース市場では、上場時点における売上高や利益水準よりも、将来の成長可能性が強く評価されます。上場のために黒字化を急ぐ必要はなく、むしろ事業拡大を見据えて先行投資を行い、一時的に赤字であることは必ずしもネガティブに受け止められません。
この市場では、売上高が数億円程度でも上場が可能です。2022年4月以降にグロース市場へ上場した企業の内訳を見ると、売上高が10億円未満の企業が4社、10億〜100億円の企業が8社、100億円以上の企業が4社という分布でした。これにより、グロース市場が比較的小規模な企業の受け皿として機能していることが分かります。
また、すでに数百億円規模の売上高を持っていたとしても、利益面でスタンダード市場の基準を満たさない場合、グロース市場での上場を選択する企業も見受けられます。
東証スタンダード市場におけるIPO売上高の目安
東証スタンダード市場は、比較的規模の整った中堅企業が多く上場を果たしている市場です。グロース市場よりも収益の安定性が重視され、明確な利益水準の基準も設けられています。ここでは、スタンダード市場における売上高の目安や上場審査の観点、実際の上場企業の傾向について詳しく見ていきます。
スタンダード市場では黒字経営が前提となる
東証スタンダード市場では、グロース市場と異なり、上場時の業績に一定の水準が求められます。形式要件の一つとして、直近年度における税引前利益または当期純利益の合計が1億円以上である必要があります。
このため、赤字での上場は事実上不可能であり、黒字経営が基本的な前提となります。安定的な利益を確保していることが、市場や投資家からの信頼を得るうえで不可欠です。
売上高30億円前後が目安
スタンダード市場におけるIPO企業の売上高には、一定の下限ラインが見られます。2022年4月から12月の期間に新規上場した10社のデータでは、最も売上の少ない企業でも約30億円の売上高を記録していました。
このことから、スタンダード市場では、売上高30億円前後が一つの目安と捉えることができます。もちろん業種によって収益構造や利益率は異なりますが、一定の売上ボリュームとあわせて、継続的に黒字を計上できる体制が求められています。
また、多くのスタンダード上場企業では、売上高が数十億円以上に達しており、グロース市場に比べるとやや大きな企業規模が一般的です。これは、収益安定性を重視するスタンダード市場の性格を反映しているといえるでしょう。
着実な成長と株主還元が評価される市場特性
スタンダード市場では、上場後の企業に対しても、着実な業績成長と安定した株主への還元姿勢が期待されます。そのため、IPO時の審査でも、一時的に黒字であるかどうかよりも、継続的な収益力を持つビジネスモデルかどうかが重要視されます。
また、単に成長することだけでなく、収益のブレが少ない、事業のリスクが低いといった点も審査対象になります。これは、長期的な視点での投資先としての信頼性を確保するために重要なポイントです。
そのため、上場準備を行う際には、単年度の損益計画に加えて、複数年にわたる中期的な経営戦略や安定的な収益見通しの提示が求められる傾向にあります。
東証プライム市場におけるIPO売上高の目安
東証プライム市場は、東京証券取引所の中で最も厳格な上場基準が設けられており、持続可能な成長と高度なガバナンス体制を備えた大企業が主な対象となります。この市場でのIPOを目指す場合には、売上高・利益ともに高い水準が求められるため、他の市場とは一線を画しています。ここでは、プライム市場における売上目安や審査基準、実際の事例から見る傾向について詳しく解説します。
プライム市場では高水準の利益・売上要件が設けられている
東証プライム市場における上場基準は、他の市場に比べて格段に高いハードルが設定されています。具体的には、直近2年間の累計利益が25億円以上、または直近年度の売上高が100億円以上かつ上場時予想時価総額が1,000億円以上であることが求められます。
このような基準からも分かるとおり、プライム市場では黒字経営にとどまらず、相当な利益規模と財務体質の強さが必要とされます。単なる収益性だけでなく、企業としての安定性や上場後の透明性、持続的な成長力が広く審査対象となります。
そのため、創業からの歴史が浅いスタートアップ企業が、いきなりプライム市場でのIPOを実現するのは非常に難しく、段階的な市場ステップアップが現実的な戦略となる傾向があります。
プライム市場に上場した企業の売上規模と特徴
2022年4月から12月にかけてプライム市場に新規上場した企業はわずか2社でした。その売上高を見ると、いずれも600億円を超えており、一方は1,000億円を超える大企業です。このような実例からも、プライム市場におけるIPOでは、売上高が最低でも500億円以上、可能であれば1,000億円規模であることが一般的な目安となります。
また、売上だけでなく、営業利益・純利益においても高水準を維持していることが共通しており、財務の健全性に加え、事業ポートフォリオの多様性や国内外での事業展開なども評価される傾向があります。
加えて、これらの企業はすでに上場前から社会的な認知度が高く、幅広いステークホルダーと関係を構築してきた実績を有しています。上場によってさらなる企業価値向上や国際競争力の強化を目指す段階にある企業が中心です。
市場選択と戦略的ステップアップの重要性
プライム市場に直接IPOを果たす企業は非常に限られており、多くの企業はまずグロース市場やスタンダード市場で上場した後、実績を積んでから市場変更という形でプライムを目指すケースがほとんどです。
これは、プライム市場での上場に必要な要件が厳格であることに加え、上場後も高度な情報開示体制やガバナンス体制を維持し続ける義務があるためです。上場企業には持続可能性、環境・社会・ガバナンス(ESG)対応、機関投資家との対話(エンゲージメント)といった高度な企業統治が期待されます。
そのため、企業にとっては上場市場を慎重に選び、段階的に成長しながらステップアップしていく戦略が求められます。スタンダード市場で安定した成長を続けた後、プライム市場への市場変更を検討する企業も増えています。
売上高以外で重視されるIPO審査指標
IPO審査では売上高も重要ですが、それだけで可否は決まりません。企業の信頼性や成長性を総合的に評価するため、収益性やガバナンスなど多角的な視点が求められます。以下に、売上以外で重視される指標を紹介します。
営業利益・純利益などの収益性
収益力は重要な判断基準です。スタンダード市場では直近の税引前利益か純利益が合計1億円以上、プライム市場では2年間で累積25億円以上の利益、または売上100億円超かつ時価総額1,000億円以上が求められます。グロース市場では赤字でも将来的な収益化が見込まれるビジネスモデルであれば、上場は可能です。
成長性と事業の継続性
特にグロース市場では成長余地が重視されます。中期経営計画や競争優位性のあるビジネスモデル、具体的なKPIやマーケットサイズなどで、成長ストーリーを明確に示す必要があります。また、資金繰りの見通しや依存度の高い取引先リスクも審査され、「継続企業の前提」に関する注記があると上場は困難です。
ガバナンス体制と内部管理
上場企業には、経営の透明性と内部統制が求められます。社外取締役や監査役会、コンプライアンス委員会などの設置がチェックされ、経理・財務の内部統制、リスク管理、反社会的勢力排除の体制も審査されます。内部監査の実施や社内規程の整備など、違反の予防体制も重要です。
株主構成と流通株比率
スタンダード市場では株主数400名以上、流通株比率25%以上が必要です。審査では、特定株主の支配や株式の分散状況、ロックアップの有無も確認されます。ベンチャーキャピタルや創業者の高持株比率は、株価安定や流動性の懸念から注意が必要で、ストックオプション発行も含めて資本政策の妥当性が評価されます。
監査意見とコンプライアンスの遵守
直前期を含む数年間の財務諸表で「無限定適正意見」を受けていることが必須です。限定付き意見がある場合、上場は原則不可となります。法令違反や不祥事の有無、税務・労務・環境規制の順守状況も確認され、近年ではESGへの取り組みも注目されています。上場準備では社内監査の実施や外部専門家の助言体制も評価され、日常的なコンプライアンスの実践が問われます。
IPO事例にみる売上・利益水準の傾向
近年のIPO市場では、売上や利益水準に幅広い傾向が見られます。特に2023〜2024年は、小規模企業の上場が目立つ一方、大型IPOも実施され、多様な動きが確認されています。以下、最新データをもとに傾向を解説します。
売上高50億円未満の企業が多数
2023年のIPO企業では、売上高10億円未満が28社(21.9%)、10億〜50億円未満が54社(42.2%)で、全体の約3分の2が売上50億円未満でした。2024年上半期も同様で、10億円未満が15社(24.6%)、10億〜50億円未満が32社(52.5%)と、約4分の3を占め、小規模企業の上場が続いています。
大型IPOの実施
一方で、2024年には東京メトロが約9,500億円の初値時価総額で上場し、2018年のソフトバンク以来の大型IPOとなりました。
さらに、トライアルホールディングスは売上高6,531億円、経常利益1,435億円で上場し、時価総額は2,021億円に達し、市場の活性化に寄与しています。
赤字上場企業の増加
赤字企業の上場も増えており、2024年は全体の24.4%(21社)と前年(21.9%)より増加。東証グロース市場では将来性が重視され、アストロスケールホールディングスのように赤字(経常損失93億円)でも、時価総額960億円で上場を果たす例が見られます。
市場別の傾向と特徴
東証グロース市場への上場は74.4%と前年より増加。スタンダード市場は15.1%に減少しました。売上200億円超の企業は、東証プライム2社、スタンダード5社、グロース4社、PRO Market2社の計13社で、市場ごとに規模や特徴の違いが見られます。
IPOを目指すなら、売上目安と審査基準を正しく理解しよう
IPOでは収益性、成長性、ガバナンス体制など総合的な評価が行われるため、単なる売上高だけでなく企業としての信頼性や将来性を示す準備が欠かせません。
これからIPOを目指す企業は、自社の現状の業績がどの市場区分の目安に合致するかを見極めるとともに、上場に耐えうる経営基盤(ガバナンスや内部管理)を整備し、将来展望を示せるよう準備を進める必要があります。上場準備には通常3~5年の期間が必要と言われますが、計画的に業績拡大と体制整備を行えば、たとえ現時点で売上規模が小さくても適切な市場を選択することでIPOの道は開けるでしょう。上場基準や最近のIPO事例を参考に、自社に合った戦略で着実にIPO準備を進めてください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
マネーフォワード クラウドERP サービス資料
マネーフォワード クラウドERPは、東証グロース市場に新規上場する企業の半数※1 が導入しているクラウド型バックオフィスシステムです。
取引データの自動取得からAIによる自動仕訳まで、会計業務を効率化。人事労務や請求書発行といった周辺システムとも柔軟に連携し、バックオフィス業務全体を最適化します。また、法改正に自動で対応し、内部統制機能も充実しているため、安心してご利用いただけます。
※1 日本取引所グループの公表情報に基づき、2025年1月〜6月にグロース市場への上場が承認された企業のうち、上場時にマネーフォワード クラウドを有料で使用していたユーザーの割合(20社中10社)
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
VRIO分析とは?やり方や注意点・具体的な企業事例をわかりやすく解説
VRIO分析は企業戦略の核心をなす手法です。この分析を駆使し、独自の価値を持ち、希少性のあるリソースを識別、保護し、最大限に活用する方法を探ります。 本記事では、VRIO分析の概要…
詳しくみる財務デューデリジェンス(財務DD)の目的や進め方は?その全体像を解説
上場企業の時価総額のように、株式会社として資本市場でビジネスを行う上で自社の企業価値は多くのステークホルダーから重要視されます。M&Aにおける企業買収はその最たる例ですが、…
詳しくみるCSR調達とは?概要や実現に向けたポイントを解説
CSR調達とは、CSRの視点を持って行う調達活動です。CSR調達の取り組みでは、対外的なイメージ低下リスクを回避できたり、競合との差別化による事業の成長につながったりするメリットが…
詳しくみるIPOにおける目論見書とは?交付義務や種類、記載内容を解説
目論見書とは、投資家に対して発行されるもので、投資判断に用いる重要情報が記載された資料です。金融商品取引法に基づき、IPOや増資などの際には目論見書の交付が原則として義務づけられて…
詳しくみる決算説明会とは?株主総会との違いや開催時期・スケジュールを解説
決算説明会とは、企業が投資家やアナリストに対して財務状況や業績を報告し、経営戦略や今後の見通しを共有する重要な会議です。 四半期ごと、半期ごと、または年度ごとに開催され、企業の透明…
詳しくみる福岡証券取引所で上場するメリット4選!基本情報から取り組みまで解説
上場を目指す企業や経営者の中には、上場するのに東京証券取引所と地方証券取引所でするのとのちがいに迷う人も多いのではないでしょうか。その中でも福岡証券取引所は、九州に本社を置く企業や…
詳しくみる