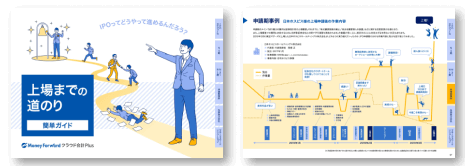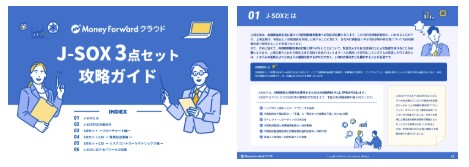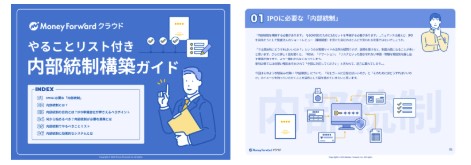- 作成日 : 2025年4月23日
税制適格ストックオプションとセーフハーバールール|適用条件と会計処理の注意点
スタートアップ企業を中心に活用が進む「税制適格ストックオプション」の適正な運用には、セーフハーバールールの理解が不可欠です。
本記事ではストックオプションの基本を説明した上で、税務や会計処理、最新ルールであるセーフハーバールールの適用条件、注意点をわかりやすく解説します。
目次
セーフハーバールールとは?
セーフハーバールールとは、特定の条件や基準を満たした場合に、法律違反や罰則の適用を免れる仕組みです。
法律や規制は、企業活動を公正かつ適切に保つために必要ですが、基準があいまいだと、以下のような問題のリスクが考えられるでしょう。
- 法律を厳格に適用すると、必要以上に活動が制限される可能性がある
- 企業がリスクを恐れて本来問題のない行動でも控えてしまう
- 不確実性が増し、不要な法的トラブルが発生する
たとえばセーフハーバールールは「独占禁止法」にも活用されています。企業同士の取引や合併が「市場の競争を制限する」とみなされると、独占禁止法に違反するリスクがあります。
しかし競争を実質的に制限しない水準を「セーフハーバールール」として設定することで、企業は違反の不安を感じることなく取引が可能になるでしょう。
セーフハーバールールは、「安全な港に停泊している船は海難事故を避けられる」という概念に由来しています。つまりルールがあいまいで適用基準がはっきりしない場合でも、事前に明確な基準を設けることで、企業が不安なく行動できる環境を整えるのが目的の制度ということです。
セーフハーバールールのメリット
セーフハーバールールには、企業にとってさまざまなメリットがある一方で、注意すべき点もあります。本項では、それぞれをわかりやすく解説します。
セーフハーバールールを導入する主なメリットは、以下のとおりです。
- 法的リスクを軽減できる
- 企業の信頼性や透明性が向上する
- リスク対策を事前に講じるため、経営の安定化につながる
あらかじめ明確な基準が定められているため、訴訟リスクや罰則を回避できるようになり、安心して事業を展開できます。そしてルールに従って適切に経営を行うことで、投資家や顧客からの信頼を得やすくなるでしょう。
セーフハーバールールの留意点
セーフハーバールールを導入した際の留意点は、以下のとおりです。
- 自社の業務や業界に適した基準を理解する
- 最新の法令や規制を常にチェックする
- セーフハーバールールに依存しすぎない
セーフハーバールールは業界ごとに異なるため、自社に合ったルールを把握し、適切な手続きが求められます。また法律や規制は変更されることがあるため、情報を定期的にアップデートし、適用される基準が変わっていないか確認することが重要です。
さらにルールがあるからといって、それだけに頼るのは危険です。企業としての倫理や社会的責任を考えながら、適切な判断が必要となります。
ストックオプションとは?
ストックオプションとは、企業が役員や従業員などに対して、自社の株式を「事前に定められた価格」で購入できる権利を与える制度です。
たとえば「今は1株あたり500円で買える権利」が与えられたとします。将来的に株価が1,500円まで上がれば、500円で買った株を売ると1,000円の差額が利益となります。この差額が、いわば報酬として手に入るという仕組みです。
ストックオプションの制度は、会社の成長が従業員の利益にも直結するため、従業員のモチベーションを高める効果が期待できるでしょう。
また手元資金が限られているスタートアップ企業でも、将来のリターンを提示することで優秀な人材を確保しやすくなるというメリットもあります。
制度の中では、あらかじめ決められた購入価格を「権利行使価額」、株式を買う権利そのものを「新株予約権」と呼びます。
なお、株価が期待通りに上がらず、当初の購入価格より下がってしまった場合は、利益を得られません。しかし権利は「使わない」選択も可能なため、実際に株を買わなければ損失もないということです。
以下の記事では、ストックオプション活用によるメリットや行使のタイミングについて、解説しています。ストックオプションに興味関心がある方は、ご覧ください。
ストックオプションの税務上の取り扱い
ストックオプションは、種類や条件によって課税のタイミングや税務上の取り扱いが異なります。
ストックオプションは、大きく分けて以下の3つです。
- 有償ストックオプション
- 無償税制適格ストックオプション
- 無償税制非適格ストックオプション
それぞれに特徴や税務上の扱いがあるため、順に見ていきましょう。
有償ストックオプション
有償ストックオプションとは、権利を取得するためにあらかじめ定められている発行価額を、対価として支払うタイプのストックオプションです。
このタイプは金融商品として扱われるため、権利を行使して株式を取得する時点では課税されません。その後に取得した株式を売却したときに初めて課税され、譲渡所得に該当します。
権利取得時に費用が発生しますが、多くの場合、発行価額は市場価額よりも低く設定されるため、将来的に株価が上昇すれば利益を得やすいというメリットがあります。
無償税制適格ストックオプション
無償で付与され、かつ一定の要件を満たすことで税制上の優遇が受けられるのが、無償税制適格ストックオプションです。
税制適格ストックオプションは、権利行使時には課税されず株式売却時に初めて課税されます。課税対象は譲渡所得となり、先述の有償ストックオプションと同様に20.315%の税率が適用されます。
税制適格と認められるためには、以下のような条件をすべて満たす必要があるため、自社が要件を満たしているか確認しておきましょう。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 発行価額 | 発行価額が無償であること |
| 付与対象者 | 会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人であること |
| 権利行使期間 | 新株予約権の付与決議後から2年経過したのち、当該権利が付与された日から10年経過する日までと定められていること |
| 権利行使価額 | 権利行使価額が発行時の株価以上であること |
| 譲渡禁止規定 | 譲渡が禁止されていること |
| 権利行使限度額 | 権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えない ※令和6年度改正により、権利行使価額については以下が適用される 設立から5年未満の会社は年間の上限が2,400万円であること 設立から5年以上20年未満かつ、非上場会社または上場から5年未満の上場会社は年間の上限が3,600万円であること |
| 保管委託 | 金融商品取引業者に保管委託・信託することまたは、自社内で株式の保管管理が可能であること |
上記の項目をすべて満たすことで、権利行使時の課税を避けられ、大きな節税効果が期待できます。
無償税制適格ストックオプションについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
無償税制非適格ストックオプション
税制適格の条件を満たさないストックオプションが「税制非適格ストックオプション」です。こちらも無償で付与されますが、税務上の負担が比較的重いという特徴があります。
無償税制非適格ストックオプションは、権利を行使した時点で課税対象となり、行使価額と時価の差額が「給与所得」として課税されます。
給与所得は累進課税の対象となるため、所得が高い場合には税率が大きくなる点に注意が必要です。さらに株式を売却した際も、ほかのストックオプション同様に譲渡所得として課税されます
そのため税制非適格ストックオプションを活用する場合は、権利行使のタイミングや株価の推移を慎重に見極めることが重要です。
税制適格ストックオプションにおけるセーフハーバールール
税制適格ストックオプションには、税務上の優遇を受けるために満たさなければならない要件がいくつかあります。中でも重要な要件のひとつが、「1株あたりの権利行使価額が、付与契約締結時の時価以上であること」です。
この「時価」は、一般的に所得税基本通達を用いた「原則方式」によって定められます。非上場企業の場合、具体的には以下のような方法で評価されます。
- 最近の売買実績に基づき、適正と認められる価額
- 公募価格など、市場で通常取引されるとみなされる価額
- 「事業の種類・規模・収益の状況等」が類似するほか企業の株価を参考にした価額
- 上記以外で1株または1口あたりの純資産価額をもとに算定された価額
ただし上記の方法では判断に幅があり、「どの価額が正しいのか」が明確ではありません。そのため過去には、企業側が税務署からの指摘を避ける目的で、意図的に高めの行使価額を設定するケースが多く見られました。
そこで導入されたのが、セーフハーバールールです。ルール導入により、所得税基本通達ではなく、財産評価基本通達にもとづく評価方式を用いることが認められるようになっています。
財産評価基本通達には、「原則的評価方式」と「特例的評価方式」があり、取引相場のない株式の評価価格を客観的かつ明確な方法で株価を算出できるようになりました。
ただし財産評価基本通達で価額を決められるのは、非上場企業のみが認められているルールとなっています。
財産評価基本通達(特例方式)で算定する場合
セーフハーバールールを用いる際、株価の評価方法として「財産評価基本通達」が適用されます。「特例方式」による評価では、ストックオプションの付与契約時点の資産と負債にもとづいて価額を算定するのが原則です。
なお、直前期末の決算データをもとに算出しても問題ありません。しかし以下の条件に該当する場合は、より正確な価額を反映するために「仮決算」を行う必要があります。
- ストックオプションの付与契約日が直前期末から6ヶ月以上経過しており、かつ、その日の純資産価額が2倍以上に増加している場合
- 上記には該当しないが、直前期末以降からストックオプションの付与契約日までの間に株式発行を行っている場合
このように、企業の状況によって価額を算出するためのデータを柔軟に変更することで、より公平かつ実態に即した株価の算定が可能となります。
行使価額引き下げに伴う契約変更の場合
税制適格ストックオプションでは、付与されたストックオプションを契約にもとづいて行使するのが前提です。そのため原則として、契約内容を途中で変更すると税制非適格扱いとなり、税制優遇が受けられなくなります。
ただしセーフハーバールールが公表される前、税務リスクを避けるために高めの行使価額を設定していた場合は、例外とされるケースがあります。
たとえばセーフハーバールールの導入後に「本来はルールに従って適正な価額に設定したかった」として、行使価額の引き下げを行う企業もあるでしょう。その場合、税制適格要件を満たしていれば、例外的に「契約変更あり」としても適格ストックオプションと認められるのです。
税制適格ストックオプションにおける会計上のルール
税制適格ストックオプションは、企業が従業員や役員に対して報酬の一環として付与する制度です。
ストックオプションの権利行使価額が発行時点の株価を下回る場合、企業は差額分を会計上の「費用」として計上する必要があります。
そのため企業は、ストックオプションの権利が確定するまでの期間と、実際に権利が行使された時点でそれぞれ異なる対応が求められます。
以下に、その流れを見ていきましょう。
権利付与時の会計処理
ストックオプションが付与された段階では、会計上の処理は不要です。
この段階ではまだ従業員が権利を行使できる状態にないため、正式な「報酬」としては確定していないためです。
多くの場合、ストックオプションには「一定の期間、継続して勤務する」など、権利が確定するための条件が定められています。そのため実際の会計処理は、権利確定したのちに必要になる処理となります。
権利確定までの会計処理
権利確定に至るまでの期間においては、企業は段階的に費用を計上する必要があり、上場企業と非上場企業で処理は異なります。
上場企業の場合は、ストックオプションの「公正な評価額」をもとに、各会計期間に応じて費用を計上しましょう。
一方で非上場企業は市場価格が存在しないため、代わりに本源的価値である「発行時の株価 - 権利行使価額」を基準に計上します。
セーフハーバールール導入前は税務上の安全を優先し、権利行使価額を高めに設定していた企業が多かったため、「本源的価値」はゼロとなり、費用計上も不要でした。
しかしセーフハーバールールの導入により、適正な行使価額の設定が可能になった結果、本源的価値が生じ、費用として会計処理を行う必要があるケースが増えています。
仕訳としては、費用を「株式報酬費用」という勘定科目で処理し、相手科目は「新株予約権」です。期間按分により、権利確定までの各会計期に分割して費用化していくのが基本的な流れです。
権利行使時の会計処理
従業員がストックオプションを行使し、実際に株式を取得した時点では、企業の資本が増えることになります。このため、費用としての処理ではなく、株式の発行として会計処理が必要です。
具体的には、これまで計上していた「新株予約権」を振り替え、その金額を「資本金」や「資本剰余金」として処理します。
ストックオプションはセーフハーバールールを適切に活用しよう
税制適格ストックオプションを正しく運用するためには、制度の仕組みや会計・税務の取り扱いに加え、セーフハーバールールの適用条件を把握することが重要です。
とくに非上場企業では適正な株価評価が求められるため、実務上の判断には慎重さが求められます。しかし継続的な制度理解と対応が、企業の信頼性向上につながるため適切に活用しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
Web面接(オンライン面接)とは?当日の流れや事前準備、マナーなどを解説!
Web面接(オンライン面接)とは、インターネット上で行う面接を言います。離れた場所で面接でき、移動や会場準備が不用になります。ただし回線の接続状況により通信が途切れたり、画像に乱れ…
詳しくみるサテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説
Pointサテライトオフィスとは? サテライトオフィスは、本社外に設置された小規模拠点で、通勤負担の軽減やBCP対策、人材確保に有効です。 通勤時間短縮により働き方改革を促進 BC…
詳しくみるタレントマネジメントとは?導入のメリットや方法、システム利用について解説!
この記事では、タレントマネジメントの基本的な定義から、導入を成功に導くための具体的なステップ、よくある失敗例とその回避策、そして自社に合ったシステムの選び方まで、実務担当者が知りた…
詳しくみるCOO(最高執行責任者)とは?意味や役割・CEOとの違いを解説
COOとは、企業における最高執行責任者のことです。COOは、CEOが決定した経営方針に則って業務を執行し、CEOのサポートを行います。この記事では、COOの意味やCEOとの違い、仕…
詳しくみる人材アセスメントとは?企業の導入メリットや手順・活用のポイント
人材アセスメントは、人材のスキルや適性、能力などを打算社が客観的な目線で分析し、組織の成功の鍵を握る重要なプロセスです。 適切な人材アセスメントを行うことで、従業員の能力と潜在力を…
詳しくみる相談役とは?設置した方が良い?役割や顧問との違い、報酬の相場を解説
相談役は、会社で生じるさまざまな経営上の問題を解決するために助言を行う役職です。豊富な経験や知見を活かして企業に貢献しますが、不透明な影響力であるとの批判があり日本の国際競争力を弱…
詳しくみる