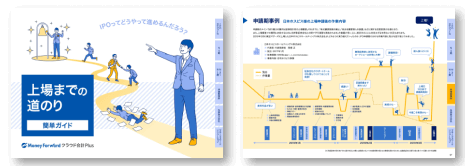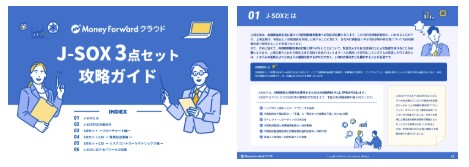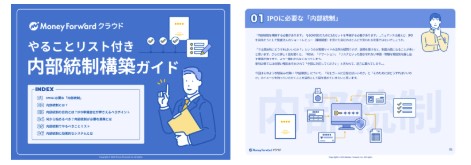- 更新日 : 2025年4月23日
ストックオプションの行使価格の決め方は?計算方法や注意事項を解説
ストックオプションの行使価格の決め方は、ストックオプションが税制適格か非適格か、上場企業か非上場企業かなど、さまざまな条件により異なります。
この記事ではストックオプションの行使価格の決め方や注意事項、行使のタイミングについて詳しく解説していきます。
目次
ストックオプションの行使価格を決定する流れ
まずはストックオプションの行使価格を決めていく流れを解説します。
行使価格とは、ストックオプションの権利者がその権利を行使して自社株を購入する際に支払う金額のことです。
行使価格は税制適格ストックオプションか、税制非適格ストックオプションかで異なります。
税制適格ストックオプションの場合、権利行使価額はストックオプション契約締結時の会社の株式時価以上でなければなりません。
一方で、税制非適格ストックオプションの場合は、たとえば1株あたりの市場価格が1,000円であっても、行使価格は100円や500円など自由に設定できます。
上記の点を踏まえて、上場企業の場合と非上場企業の場合の2パターンに分けて、行使価格の決め方を解説していきます。
ストックオプションの行使価格の決め方【上場企業の場合】
上場企業は、東京証券取引所や名古屋証券取引所といった株式市場へ上場しています。
そのため、税制適格ストックオプションの行使価格を決定する際は市場価格を基準にするとよいでしょう。
たとえば下記の2社は、新株予約権(ストックオプション)の付与日の東京証券取引所における株価の終値を基準に、行使価格を決定しています。
- 株式会社リクルートホールディングス
- Sansan株式会社
参考:ストックオプション(新株予約権)の発行について | ニュース|リクルートホールディングス
参考:当社従業員に対する株価条件付税制適格ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | Sansan株式会社
例外として、株式分割や「時価を下回る価額での新株発行」を行う場合は行使価格を調整します。
ストックオプションの行使価格の決め方【非上場企業の場合】
非上場企業の場合は自社の置かれた状況により、原則方式か特例方式を選択して行使価格を決定します。
原則方式
原則方式を選択した場合、「売買実例のある株式」の場合は売買実例価額を基に行使価格を決めます。
売買実例のある株式とは、おおむね6ヶ月以内に売買の行われた株式のことで、1件でも事例があれば売買実例として扱われます。
また、株式の売買実例がない場合は類似会社の株式の価額に比準して推定したり、純資産価額等を参考にしたりして算定するようにしましょう。
特例方式
特例方式の分類のなかには、さらに原則的評価方式と特例的評価方式の2つがあります。
原則的評価方式
同族株主などが株式を取得している場合は、原則的評価方式を用います。
同族株主とは、会社の株主1人とその同族関係者の持つ議決権の合計数が、その会社全体の議決権総数の30%以上である場合の株主や同族関係者を指します。
また、議決権の割合が50%を超えるグループがある場合はそのグループが同族株主となり、他の30%以上の議決権を占めるグループは同族株主に該当しません。
原則的評価方式では、会社の規模によって評価の方法が異なります。
| 企業規模 | 算定方法 |
|---|---|
| 上場会社に匹敵するような大会社 | 類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可) |
| 大会社と小会社の中間の中会社 | 類似業種比準価額と純資産価額を一定の割合で掛け合わせた併用方式(純資産価額方式も選択可) |
| 個人企業とそれほど変わらない小会社 | 純資産価額方式(類似業種比準方式との併用方式も選択可) |
また、算定方式については下記のように行います。
| 算定方式 | 概要 |
|---|---|
| 類似業種比準方式 | 事業内容が類似する上場企業の株価を参考に、会社の規模や収益性などを比較して株価を算定 |
| 純資産価額方式 | 会社の時価評価の総資産から負債を差し引き発行済株式数で割って株価を算定 |
企業規模に応じ、適切な算定方法を選びましょう。
特例的評価方式
同族株主以外が株式を取得している場合は、特例的評価方式を用います。
この場合は配当還元方式を使い、株価の算定を行います。
▼計算例
※1株当たりの資本金等の額を50円として計算
無配であったり、配当金額が2.5円未満であったりする場合は、配当金額を2.5円として計算します。
特例方式で行使価格を算定!ケース別に注意事項を解説
特例方式で行使価格を算定する際の注意事項を、ケース別に解説していきます。
中心的な同族株主がいる場合
新株予約権を与えられた人が発行会社にとって「中心的な同族株主」である場合、その会社は小会社として扱われる点に注意しましょう。
中心的な同族株主とは、ある同族株主とその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族が会社の議決権を合計25%以上保有している場合の、その株主を指します。
この場合は、純資産価額方式(もしくは類似業種比準方式との併用)で株価を算定します。
土地や上場有価証券を保有している場合
発行会社が土地や「土地の上に在する権利」、上場している株式などの有価証券を持っている場合、それらの資産の評価額は新株予約権の付与契約を結んだ時点の価格で計算されます。
土地の上に存する権利とは、土地の所有者以外の者がその土地を利用したり、収益を得たりするために認められる権利のことです。
- 地上権:他人の土地に建物などを所有しており、その土地を使用する権利
- 耕作権:農地の所有者から土地を借りて、その農地を耕作・牧畜する権利
- 温泉権:土地から湧出した温泉や汲み上げた温泉を利用する権利、または引湯を受ける権利
計算時は保有する資産の抜け漏れがないよう気を付けましょう。
純資産価額で評価する場合
会社の純資産額にもとづいて株価を計算する際、含み益(評価差額)に対する法人税額等の相当額は差し引かれません。
正味の財産価値をそのまま反映するようにしましょう。
ストックオプションの行使と売却は同時にできる?
基本的にストックオプションの行使と売却を同時に行うことはできません。
ストックオプションを売却するためには、まず権利を行使して自社株を取得し、その後に市場で売却するという手順を踏みます。
しかし、権利を行使するためには、自社内や証券会社で権利行使のための手続きを行う必要があります。
権利を行使してもすぐに株式を購入できるわけではないので、行使と売却のタイミングにはズレが発生し、これらを同時には行えません。
ストックオプションを行使するおすすめのタイミング
ストックオプションを行使するおすすめのタイミングを従業員に質問されたら、「株価が行使価格を上回ったとき」と答えるとよいでしょう。
このタイミングで権利を行使し、株式を売却すれば利益を得られます。
ただし、税制適格ストックオプションの場合は権利行使期間が定められています。
租税特別措置法により、権利をもらった日(付与決議の日)から2年後~10年後の期間内でしか行使ができないため、注意しましょう。
例外として、設立5年未満の非上場企業であれば、付与決議日から2年を経過した日から15年を経過する日までに行使すればよいことになっています。
ストックオプションの行使は義務ではないため、行使価格が自社の株価を下回っている場合は、権利を行使しなくてもよいと従業員へ伝えておきましょう。
なお、特別な取り決めがない限り売却のタイミングは自由となっています。
行使のタイミングについて、より詳しくは下記の記事をご参照ください。
ストックオプションは種類によって税金がかかる
ストックオプションは種類によって、下記のように税金がかかります。
| 権利行使時 | 株式の売却時 | |
|---|---|---|
| 税制適格ストックオプション | なし | 譲渡所得として課税(20.315%) (所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%) |
| 税制非適格ストックオプション | 給与所得として課税 (所得税5~45%+復興特別所得税として所得税の2.1%+住民税10%) | |
| 有償ストックオプション | なし | |
| 信託型ストックオプション(税制適格) | なし | |
| 信託型ストックオプション(税制非適格) | 給与所得として課税 (所得税5~45%+復興特別所得税として所得税の2.1%+住民税10%) |
一部のストックオプションは権利行使時に課税されますが、権利付与時は一律で税金はかかりません。
上場できなかったらストックオプションはどうなる?
会社が上場できなかった(しなかった)場合、下記の2パターンで従業員のストックオプションの扱いが異なります。
権利行使の条件が上場であった場合(株を持っていない)
IPO(上場)を見据えている会社がストックオプションを発行する場合、多くの場合IPOを権利行使の条件として設定しています。
この場合、上場できなければ従業員は権利の行使ができないため、権利行使期間を過ぎればストックオプションは消滅します。
権利行使の条件が上場でない場合
上場が権利行使の条件に含まれていなければ、従業員はストックオプションを行使して株式を購入できます。
また、従業員がストックオプションを行使して株式を持っているにも関わらず会社が上場できなかった場合、契約内容次第で会社は株式を買い取ることになります。
ストックオプションの行使価格は慎重に定めよう
ストックオプションの行使価格は、上場企業では株価を基準とすることが一般的です。
一方で非上場企業の場合は、自社の状況により、原則方式か特例方式で行使価格を定めます。
ストックオプションは丁寧に制度設計を行えば、従業員のモチベーション向上や採用強化に力を発揮する制度です。
行使価格の計算方式を理解し、適切な行使価格を設定しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
常勤監査役とは?IPO準備における役割・設置要件・報酬を解説
企業がIPO(新規株式公開)を目指す際、体制整備の一環として避けて通れないのが「常勤監査役」の選任とその機能強化です。常勤監査役は、会社の業務や財務の状況を日常的に監査し、経営の健…
詳しくみるCFOの年収相場はいくら?企業規模やフェーズごとに解説
企業の財務戦略を支えるCFO(最高財務責任者)は、近年その役割の重要性が一層高まっています。それに伴い、CFOの年収相場も企業の規模や成長フェーズ、求められる専門性によって大きく異…
詳しくみるナレッジマネジメントとは?SECIモデルや導入方法についても解説!
ナレッジマネジメントとは、従業員が保有する知識や経験などを企業内で共有して活用する経営手法のことです。ナレッジマネジメントを有効活用することで、企業の競争力や企業価値を向上させるこ…
詳しくみるABWとは?新しい働き方に合わせたオフィス – メリット・デメリットを紹介
ABWとは、業務内容や気分によって働く場所や時間を決める働き方です。フリーアドレスはオフィス内の自由な席で働くワークスタイルを指すのに対し、ABWはカフェや自宅など自由なスペースで…
詳しくみるジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリットを解説
Pointジョブ型雇用とは? ジョブ型雇用は、職務内容と責任範囲を明確に定めた上で人材を配置・評価する雇用形態です。 職務記述書で業務を明確化 専門性・成果で評価される メンバーシ…
詳しくみるストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説
上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリッ…
詳しくみる