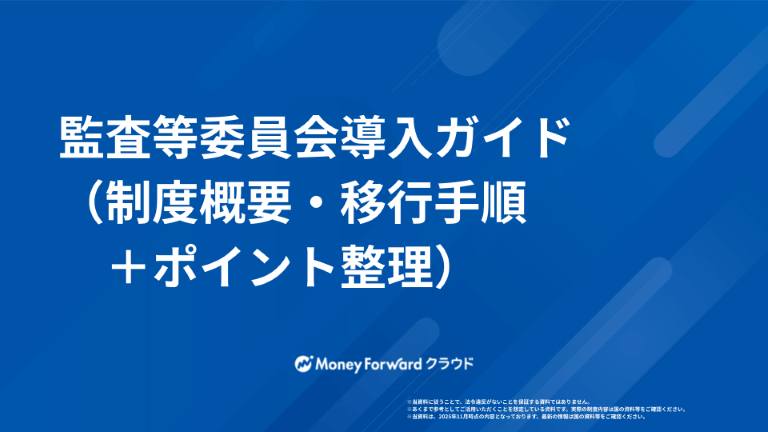- 更新日 : 2025年12月2日
監査等委員会設置会社とは?制度概要とメリット・デメリット
監査等委員会設置会社は、2015年の会社法改正で新たに導入された株式会社の形態です。取締役会の中に監査等委員会を設置し、従来の監査役会に代わって取締役(3名以上、過半数は社外取締役)の監査等委員会が取締役の職務執行を組織的に監査します。監査役会設置会社(従来型)と指名委員会等設置会社(いわゆる三委員会設置会社)の中間的な性格を持ち、上場企業を中心に急速に普及が進んでいます。
この記事では、監査等委員会設置会社の基本制度や他の機関設計との違いやメリット・デメリット、移行のプロセスについて解説します。
目次
監査等委員会設置会社の制度概要と導入の背景
監査等委員会設置会社は、社外取締役を活用した新しい監査体制として2015年に創設されました。従来の監査役会に代わる形で取締役会内に監査等委員会を置き、機関設計の選択肢を増やした制度です。その背景には、日本のコーポレートガバナンス強化の流れがあります。
新制度導入の背景と目的
監査等委員会設置会社制度は、平成26年会社法改正(2015年施行)によって新設されたものです。背景には、日本企業のガバナンス改革の要請がありました。2003年に導入された指名委員会等設置会社(旧称:委員会設置会社)は、指名・報酬・監査の三委員会それぞれで過半数が社外取締役とされるため社外役員を多数確保する必要があり、導入企業は2021年時点でも85社となっています。また、従来の監査役会設置会社では社外監査役に加え社外取締役も選任する重複負担が指摘されており、より柔軟な機関設計へのニーズが高まっていたのです。
このような状況を受けて、「監査役会型」と「三委員会型」の中間的な選択肢として導入されたのが監査等委員会設置会社です。取締役会による監督機能の強化と社外取締役の一層の活用を目的に、新たなガバナンス体制の選択肢が企業に提供されることになりました。
監査等委員会設置会社の基本的な仕組み
監査等委員会設置会社では、取締役会の中に監査等委員会を置き、従来の監査役(監査役会)を設置しません(会社法327条4項)。監査等委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数が社外取締役でなければなりません(会社法331条6項)。取締役の中から監査等委員となる者を株主総会で別枠に選任し(会社法329条)、これらの監査等委員が取締役会とは別に監査等委員会を構成します。
監査等委員会の主な職務権限は、取締役の職務執行の監査と監査報告の作成、および取締役の選解任や報酬に関する株主総会での意見陳述等です(会社法399条の2)。監査等委員である取締役の任期は2年(短縮不可)と定められており、一般の取締役(監査等委員でない取締役)は従来どおり最大2年ですが、公開会社では定款で1年に短縮することが多く、監査等委員会設置会社では1年任期とするケースが一般的です。また、監査等委員の解任には株主総会の特別決議が必要となるなど、職務の独立性が一定程度確保されています。
監査等委員である取締役は、他の取締役とは別に株主総会決議で選任されます。また、監査等委員の報酬も他の取締役と区別して定め、各監査等委員の具体的な報酬額は監査等委員間の協議で決定する仕組みとなっています(会社法361条)。これは経営陣から独立した監査機能を担保するための制度設計です。
監査役会設置会社・指名委員会等設置会社との違い
監査等委員会設置会社は、従来の監査役会設置会社(いわゆる監査役制度)や、指名委員会等設置会社(三委員会設置会社)とどのように異なるのでしょうか。それぞれの機関構成や権限の違いを押さえることが、制度の理解に役立ちます。
監査役会設置会社との違い
監査役会設置会社では、取締役会の下に監査役会を設置し、3名以上の監査役(過半数は社外)が監査を担当します。監査役は取締役会で議決権を持たず、独立して監査権限を行使するのが特徴です。一方、監査等委員会設置会社では監査役を置かず、取締役会内に3名以上(過半数は社外取締役)の監査等委員会を設け、委員は取締役として議決権を持ちます。これにより、社外取締役が経営判断に直接関与でき、監督機能が強化されます。また、社外役員の重複がなくなり負担軽減にもつながります。ただし、監査等委員会は合議体であり、個々の委員が単独で権限を行使することはできません。常勤委員の設置義務もないため、企業によっては事務局などの補助体制を設けて監査機能の実効性を補完しています。
指名委員会等設置会社との違い
指名委員会等設置会社は、取締役会の下に指名・報酬・監査の3委員会を設置し、各委員会および取締役会の過半数を社外取締役が占めます。業務執行は執行役に委任され、取締役会は監督に専念するアメリカ型のガバナンスモデルです。これに対し監査等委員会設置会社は、監査等委員会のみを設置すればよく、指名・報酬委員会の設置は不要なため社外取締役も少人数で済みます。また執行役は置かず、取締役が自ら業務執行を担います。三委員会型に比べ導入しやすく、迅速な意思決定が可能です。ただし、経営陣の人事・報酬に対する独立した監督機能は限定的であり、ガバナンスとして不十分との指摘も一部ありますが、海外投資家からは現実的な強化策として評価されるケースも増えています。
監査等委員会設置会社のメリット
監査等委員会設置会社へ移行することで、企業のガバナンス体制や経営効率においてさまざまな利点があります。ここでは、企業にとって実際に得られる主なメリットを整理します。
社外役員数の削減による負担軽減
監査等委員会設置会社に移行すれば監査役を設置する必要がなくなり、社外監査役も不要になります。社外取締役として監査等委員を2名選任すれば要件を満たすことができるため、従来のように社外監査役2名と社外取締役2名をそれぞれ確保する必要がなく、役員人件費や人材確保の負担を軽減できます。特に社外人材の選任に苦慮する中堅上場企業にとって、大きな利点となります。
取締役会での議決権行使による監督強化
監査等委員は取締役であるため、取締役会での議決権を有します。これにより、社外取締役が取締役会において重要案件の決議に関与できるため、経営に対する監督機能が実質的に強化されます。議案への反対や条件付き賛成など、具体的な意思表示が取締役会内で可能となり、ガバナンスの実効性が高まります。
迅速な意思決定
監査等委員会設置会社では、取締役会の権限の一部を個別の取締役に委任することが可能です。これにより、業務執行に関わる判断がスピーディに下せるようになり、経営判断の迅速化や柔軟性が向上します。特に複雑な事業環境の中で迅速な対応が求められる企業にとって、この仕組みは有効です。
人事の柔軟性向上
監査等委員である取締役の任期は2年であり、社外監査役の4年よりも短く設定されています。任期が短いことにより、企業は社外取締役を柔軟に入れ替えることができ、自社の経営課題に応じた適任者を選びやすくなります。時代や業界の変化に応じた人材登用が行いやすくなる点は、大きな人事上のメリットです。
利益相反取引におけるリスク軽減
監査等委員会が事前に取締役の利益相反取引(競業取引・自己取引など)を承認すれば、その取引について当該取締役の任務懈怠が推定されることがなくなります。つまり、監査等委員会の承認によって、取締役が責任追及されるリスクを一定程度軽減することが可能となります。このような法的な保護が明示されている点は、経営判断を担う取締役にとって安心材料となります。
監査等委員会設置会社のデメリット
監査等委員会設置会社には移行時や運用上で注意すべき課題も存在します。制度上の特徴が企業の規模や業種によっては合わないこともあり、導入前に慎重な検討が必要です。以下では、主なデメリットを解説します。
新体制への移行に手間とコストがかかる
監査等委員会設置会社へ移行するには、株主総会での定款変更、監査役の退任、新たな取締役の選任、社内規程の整備など、多くの手続きを伴います。特に、株主の理解を得て特別決議を通す必要があるため、準備期間の確保と十分な説明が不可欠です。こうした準備には、コンサルティング費用や社内外との調整コストがかかります。
取締役の任期が短縮され経営陣へのプレッシャー増
監査等委員でない取締役の任期は、上場企業においては多くの場合1年とされています。そのため、経営陣は毎年株主の信任を得なければならず、短期的な業績へのプレッシャーが強まる傾向があります。これにより、中長期的な経営ビジョンが立てづらくなるリスクも存在します。
監査等委員(社外取締役)の身分保障が弱まる
監査等委員である取締役の任期は2年とされ、監査役(4年)に比べて安定性に欠けます。また、再任には株主総会の決議が必要であるため、継続性を持って監査業務に取り組む上では不安定な立場となることもあります。このため、特に社外の人材が中長期で独立した監査活動を継続しにくくなる可能性もあります。
監査等委員会は合議制で個々の権限が限定
監査等委員会は合議体としての決議によって初めて権限を行使できる構造であり、個々の委員には単独で調査・報告等を行う権限がありません。これは、従来の監査役が独任制であったのと対照的です。緊急時や即時の対応が求められる場面においては、監査役制度に比べ柔軟性に欠ける可能性があります。
監査等委員会設置会社へ移行するプロセス
監査等委員会設置会社へ移行する際には、法的手続きから社内体制の整備まで多岐にわたる対応が求められます。以下では、移行のプロセスをステップごとに整理し、企業が準備すべき対応内容について解説します。
定款変更の決議を行う
監査等委員会設置会社に移行するには、まず会社の定款を変更し、新しい機関設計を明文化する必要があります。このためには、株主総会において特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)を得る必要があります。定款変更の議案を提案するにあたっては、移行の背景や目的、想定される効果などを株主に丁寧に説明し、理解と支持を得ることが不可欠です。議案の作成には法務・IR・総務などの部門が関与し、文案や説明資料を慎重に準備する必要があります。
取締役および監査役体制の見直しを行う
監査役会を廃止し、監査等委員会を設置することに伴い、役員体制を見直す必要があります。既存の監査役は任期途中で辞任または退任する形となり、その後任として監査等委員となる取締役を新たに選任します。多くの企業では、現行の社外監査役をそのまま社外取締役(監査等委員)として任命する「横滑り」が行われています。取締役会の構成員を見直し、執行取締役との役割分担や構成バランスも再検討することが望まれます。
社外取締役の選任と独立性の確保を図る
監査等委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役とする必要があります。この要件を満たすためには、必要な人数の社外取締役を新たに選任しなければなりません。社外監査役を転任させる場合もありますが、社外取締役としての適格性(業務執行との関係の有無、利害関係の有無など)を十分に確認し、証券取引所の独立役員要件に適合する人材を選ぶことが求められます。
取締役会・委員会の運営ルールを整備する
新たな機関設計に応じた社内ルールの整備が必要です。具体的には、取締役会規程や監査等委員会規程を新たに制定・改訂し、監査等委員会の職務、議事の進め方、報告義務などを明文化します。また、取締役会での議決権の扱いや、重要な業務執行の委任の方法など、実務に即したルール設計が求められます。監査等委員会に関する内部通報制度や調査権限に関する定めも必要に応じて整備します。
社内体制(事務局・内部監査部門)の整備を進める
監査等委員会の業務を円滑に進めるためには、社内に補佐体制を整えることが重要です。常勤の監査等委員を置かない場合でも、監査等委員を支援する事務局や内部監査部門のサポート体制を設けることで、監査機能の実効性を担保できます。また、会計監査人や社内の経理・法務部門との連携体制を確立し、情報の共有や調査活動の効率化を図ることも必要です。
任意の委員会設置を検討する
監査等委員会設置会社では、指名委員会や報酬委員会の設置は法的義務ではありませんが、ガバナンス強化の一環として任意の諮問委員会を設置する企業も増えています。経営陣の選解任や報酬決定に関して一定の透明性や客観性を担保するため、社外取締役を中心とした構成の委員会を設置することは、機関投資家など外部ステークホルダーからの評価向上にもつながります。
移行後の運用と継続的な見直しを実施する
制度移行後も、新体制が適切に機能しているかを定期的に確認することが重要です。監査等委員会の実効性や取締役会の運営状況、社外取締役の関与度合いなどを評価し、必要に応じて委員構成や社内規程の見直しを行います。また、社外役員からのフィードバックを活用し、ガバナンス体制を継続的に改善していく姿勢が求められます。制度導入を単なる形式的なものに終わらせず、実態としても機能する組織づくりを目指すことが大切です。
監査等委員会設置会社の導入はガバナンスと経営効率の両立を図る選択肢
監査等委員会設置会社は、企業がコーポレートガバナンスの強化と経営の効率化を同時に実現するための有力な制度設計のひとつです。取締役会に設けられる監査等委員会によって、社外取締役が経営に対する監督機能を直接的に果たせる点が特徴であり、取締役会での意思決定の透明性や健全性が高まります。また、社外監査役を不要とすることで、社外役員の人数やコスト面での負担も軽減され、実務面でのメリットも大きいといえます。導入に際しては、定款変更や体制整備といった実務的な準備が必要ですが、多くの上場企業が採用を進めており、制度としても十分に定着しつつあります。今後、自社にとって最適なガバナンス体制を検討するうえで、監査等委員会設置会社という選択肢を具体的に検討する価値は高まっているといえるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
経理担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ12選
経理担当者がChat GPTをどのように活用できるか、主なアイデアを12選まとめた人気のガイドです。
プロンプトと出力内容も掲載しており、コピペで簡単に試すことも可能です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
内部監査の目的をわかりやすく解説|設置義務のある会社や不正事例も紹介【テンプレート付き】
内部監査は上場企業に設置義務があり、経営目標の達成やリスクマネジメントを目的に行われます。その際、企業ごとに計画を実施するため、専門的な知識が必要です。 本記事では内部監査の目的を…
詳しくみる内部統制の有効性を検証するCSA(統制自己評価)とは?メリットやデメリットを説明
内部統制のCSAとは、内部監査部門ではなく、該当部門のメンバー自らが監査に携わる統制自己評価のことです。内部統制を進めるうえで、関係者の意識を高めることができ、内部監査を自分ごとと…
詳しくみる徹底解説!コーポレートガバナンスと内部統制の違いとは?
コーポレートガバナンスと内部統制は混同されやすく、違いを明確に説明できる人は多くありません。両者の違いは以下の通りです。 コーポレートガバナンス:主に経営者の不正を防ぐための仕組み…
詳しくみる関連当事者取引とは?開示基準や開示項目、取引した場合の対処法について解説
「関連当事者取引」とは、企業がその経営陣、主要株主、親会社、子会社、関連会社などの関連当事者と行う取引を指します。これらの取引は、通常の市場条件と異なる条件で行われることがあり、そ…
詳しくみる内部統制で情報セキュリティ対策に取り組む方法|必要性についても説明
インターネットを使って業務を行うことが増えた現代において、「情報セキュリティ対策が大切」という言葉はよく耳にすることでしょう。しかし、具体的になぜ重要なのか、漠然とした理由しかわか…
詳しくみる内部統制の強化にワークフローシステムが効果的!メリットや事例を紹介
内部統制のメリットは「オペレーションが安定する」「法令順守を徹底できる」ことですが、一方で誤った効率の悪い内部統制にしてしまうと、業務工数が想定より増加したり、経営の意思決定が遅く…
詳しくみる