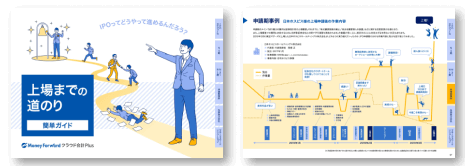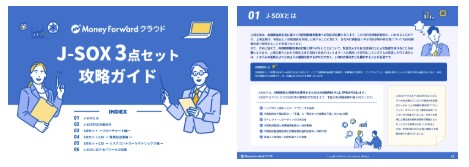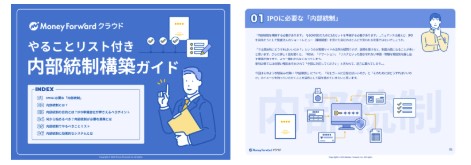- 作成日 : 2025年4月23日
ストックオプションの会計基準は?会計処理や費用計上のタイミングについて解説
ストックオプションは「企業会計基準第8号」に基づいて、費用計上が求められます。適切な会計処理を行うためには、基準の内容や費用計上のタイミングを正しく理解することが重要です。
とくに上場・非上場の違いや無償・有償といった区分によっても処理方法が異なるため、実務上のポイントを押さえておく必要があります。
本記事では、企業会計基準に沿った処理方法について、パターンごとにわかりやすく解説します。
目次
ストックオプションの会計基準とは|ストックオプション付与時のルールのこと
ストックオプションの会計基準とは、企業が従業員や役員にストックオプションを付与する際、財務諸表上でどのように処理・記録するかを定めたルールです。
平成13年11月の商法改正で新株予約権制度が導入され、ストックオプションの活用が進みました。会計基準の目的は、ストックオプション取引の会計処理と情報開示を明確にし、企業の財務情報の透明性を高めることにあります。
現在では、上場企業を中心に多くの企業で活用されています。
ストックオプションに関しては、下記の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
ストックオプションの会計基準の範囲
ストックオプションの会計基準は、企業が株式や株式オプションを対価として提供する一部の取引に適用されます。
具体的には、次の3つのケースが対象です。
- 企業が従業員に対してストックオプションを付与する取引
- 企業が財貨またはサービスの取得において、対価として自社株式オプションを付与する取引であり、(1)以外のもの
- 企業が財貨またはサービスの取得において、対価として自社の株式を交付する取引
参考:企業会計基準第8号 ストック・オプション等に関する会計基準|ASBJ 企業会計基準委員会
なお、上記のいずれかに該当する取引であっても、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」やその他の会計基準の範囲に含まれる場合には、ストックオプションの会計基準は適用されません。
そのため、各取引の性質と目的を正確に見極め、適用すべき会計基準を判断することが重要です。
ストックオプションの会計基準に含まれない取引
ストックオプションの会計基準に含まれない取引には、いくつかの明確なパターンがあります。
まず、自社株式や株式オプションを使用しない取引は、たとえ株価に連動していても対象外です。
また、対価性のない取引も含まれません。通常、株式は代金の支払いとして扱われますが、目的でないと証明できる場合は会計基準の適用対象外となります。
債務を株式に変えるデット・エクイティ・スワップ取引も、適用対象外です。さらに、企業や事業の取得を目的とする場合は、企業結合の会計基準が適用されます。
従業員持ち株制度における奨励金の支給や、敵対的買収を防ぐために特定の相手に自社株オプションを付与する取引も、財貨やサービスの対価とはみなされないため、本基準の対象には含まれません。
会計基準の対象を正しく理解することで、適切な会計処理と情報開示につながります。
上場企業におけるストックオプションの会計基準の概要
上場企業におけるストックオプションの会計基準では、権利確定日前後の各段階での会計処理が定められています。
従業員や役員に付与する場合は、原則として提供されたサービスに対応して発生する費用を、会計基準および適用指針に基づき「株式報酬費用」として費用計上します。
一方、外部の取引先に付与する場合は、受け取ったサービスや資産の内容に応じて「支払報酬」や「機械装置」などで処理されることが一般的です。
また、ストックオプションには、公正な評価額に基づく費用計上が必要です。
会計処理の違いを正しく把握することは、適切な財務報告と企業の透明性確保につながります。
無償ストックオプションにかかる費用計上
無償であっても、ストックオプションは企業からの報酬とみなされるため、会計上は費用として計上する必要があります。適切に処理しなければ、財務情報の信頼性が損なわれる可能性があるでしょう。
以下では、無償ストックオプションにかかる費用計上について紹介します。
上場企業の場合
ストックオプションの公正な評価額とは、ストックオプションの持つ「本源的価値」(算定時においてストックオプションが行使されると仮定した場合の価値)に、「時間的価値」を含めて算定されます。
計算ロジックは、確率分布的に算定された将来の株価をもとに、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引くというものです。具体的には、ブラックショールズモデルや二項モデル、モンテカルロシミュレーションといったオプション評価モデルが用いられます。
オプション評価モデルでは、行使価格や残存期間、株価、株価変動性など、複数の要素を考慮する必要があるため、公正な評価額の算定にあたっては、専門家の助言を受けることが一般的です。
公正な評価額は財務諸表に直接影響するため、信頼性の高い会計情報を提供するうえで重要です。適切な評価手法と前提条件を用いることは、投資家や関係者からの信用を得るうえでも欠かせません。
非上場企業の場合
非上場企業については、株式市場がないため、ストックオプションの公正な評価額について、損益計算に反映させるに足りる信頼性のある見積りが困難な場合があります。
そこで、非上場企業では一般投資家がいないことも考慮し、ストックオプションの公正な評価額に代わり、株価と行使価格の差額である「本源的価値」をもとに費用計上をする特例が認められています。
無償ストックオプションを費用計上するタイミング
無償ストックオプションの費用計上は、公正な評価額をもとに、権利確定日までの期間に応じて按分して行うのが原則です。
勤務条件がある場合は、付与日から条件を満たして権利が確定する日までの期間にわたり、費用を配分します。
勤務条件は明示されていなくても、行使期間が定められ、退職により権利を失うケースがあります。
退職するとストックオプションの権利を失うルールになっている場合には、行使開始日前日を権利確定日とみなし、按分処理を行うのが一般的です。
また、業績条件を含む達成時期が固定されていない場合は、合理的に予測される確定日までの期間に応じて費用を配分します。
勤務条件やその他条件がない場合には、付与日の属する会計期間に全額を一括で費用計上します。条件によって処理が異なるため、適切な判断が必要です。
有償ストックオプションにかかる費用計上
有償ストックオプションは、対価を受け取ってストックオプションを付与する仕組みですが、内容によっては会計上の費用計上が必要になる場合があります。
正しく理解していないと誤った処理につながる可能性があるため注意が必要です。以下では、有償ストックオプションにかかる費用計上について紹介します。
発行価額の費用計上の金額
有償ストックオプションでは、発行時の公正な評価額から払込金額を差し引いた差額が、費用計上の対象です。
差額は、業績条件などの権利確定条件を設定することでストックオプションの価値が下がり、払込金額が公正な評価額を下回る場合に生じます。
結果として、実際の払込金額よりも高い理論上の価値との差が、従業員などの労務提供に対する対価とみなされます。
公正な評価額と払込金額の差が「株式報酬費用」として、費用計上される仕組みです。
有償ストックオプションを費用計上するタイミング
有償ストックオプションの費用計上は、実務対応報告第36号に基づいて行われます。
公正な評価額と払込金額の差額がある場合、差額に対して費用を按分して計上します。対象期間は、原則として付与日から権利確定日までです。
勤務条件が付されている場合、条件を満たすまでの期間に費用を配分します。業績条件があるときは、達成日または合理的に予測される日を確定日とみなし、そこまでの期間に按分します。
なお、払込金額が公正な評価額と同等で、行使制限もない場合には、費用の発生自体がありません。
非上場企業の場合の会計処理について
非上場企業は株価が市場で形成されないため、公正な評価額の算定が難しく、特例的な会計処理が認められています。誤った処理は税務や開示に影響するため、正しい理解が重要です。
以下では、非上場企業の場合の会計処理について紹介します。
ストックオプションについての会計処理については、下記の記事で詳しく説明しているため、ぜひあわせてご覧ください。
本源的価値による会計処理
非上場企業では、公正な評価額の算定が困難な場合、1単位あたりの本源的価値(= 株式評価額 − 行使価格)を用いた会計処理が認められています。
従来は、行使価格を株式評価額と同額に設定することで本源的価値がゼロとなり、費用計上が不要なケースが一般的でした。
しかし、2023年7月に国税庁が新設した通達により、純資産価額等をもとに税制適格要件を満たす権利行使価額を設定できるセーフハーバールールが導入され、「株式時価>行使価格」というケースが増加しています。
上記の場合、単位あたりの「本源的価値 × 付与数」に達するまで、株式報酬費用として按分計上が必要です。評価や計上方法には判断の幅があるため、専門家と連携しながら対応することが重要です。
ストックオプションの会計処理における開示のポイント
ストックオプションの会計処理では、企業会計基準第8号に基づき、財務諸表への注記が求められます。
開示内容は「財務影響」「制度の内容と変動」「見積方法」の3点です。
まず財務影響では、当期に費用計上された金額と株式報酬費用を含む科目名を記載します。
失効があった場合は、戻入益として計上された金額も明記する必要があります。なお、記載には新規付与分だけでなく、過年度付与分で当期に按分された額も必要です。
次に制度の内容と変動では、企業は契約単位で、付与対象者の区分や人数、ストックオプションの数(付与数・失効数・行使数など)、付与日、権利確定条件、行使価格や株価などを開示します。件数が多い場合は条件付きで集約記載も可能です。
見積方法では、評価モデルであるブラックショールズや基礎数値、条件未達による失効数の見積方法を記載します。注記は、制度の内容と財務への影響を正確に伝えるために重要です。
財貨・サービスの取得の対価として自社株式オプションを付与する取引の会計処理
企業が財貨やサービスを取得する際、対価として自社株式オプションを相手方に付与する場合は、従業員に付与するストックオプションと同様の会計処理が必要です。
取得した財貨やサービスの価値は、「付与した自社株式オプションの公正な評価額」と「取得した財貨やサービスの公正な評価額」のいずれか、より信頼性の高い方法で測定可能な金額を用います。
評価額は、原則として契約成立時点の価値を基準に算定します。
ストックオプションの会計基準を理解して自社に合った会計処理を進めよう
ストックオプションの会計処理は、「企業会計基準第8号」に基づき適切に行う必要があります。
無償・有償の違いや行使条件に応じて費用計上の方法やタイミングが異なるため、制度の設計段階からルールを正しく理解し、自社に最適な処理を進めることが重要です。
正しい理解が、企業成長を支える力となるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
税制適格ストック・オプションとは?要件やメリット、令和6年度税制改正に伴う変更を解説
ストック・オプションのうち、税制の優遇が受けられるものを「税制適格ストック・オプション」といいます。言葉にすると簡単ですが、内容が複雑であり、かつ似たようなものもあることから、よく…
詳しくみるCSFとは?目標設定で大切な要素!具体例をもちいて解説
経営戦略においてはKGIやKPIといった指標の達成に向けて事業やマーケティング活動などを行います。これらの指標の設定にあたり、今回紹介するCSF(重要成功要因)を設定することは経営…
詳しくみるABWとは?新しい働き方に合わせたオフィス – メリット・デメリットを紹介
ABWとは、業務内容や気分によって働く場所や時間を決める働き方です。フリーアドレスはオフィス内の自由な席で働くワークスタイルを指すのに対し、ABWはカフェや自宅など自由なスペースで…
詳しくみる相談役とは?設置した方が良い?役割や顧問との違い、報酬の相場を解説
相談役は、会社で生じるさまざまな経営上の問題を解決するために助言を行う役職です。豊富な経験や知見を活かして企業に貢献しますが、不透明な影響力であるとの批判があり日本の国際競争力を弱…
詳しくみる監査等委員会設置会社の取締役の任期は?基本制度や注意点を解説
監査等委員会設置会社は、近年多くの企業が採用しているコーポレートガバナンスの形態の一つであり、IPOを目指す企業にとっても選択肢として注目されています。中でも取締役の任期は、業務執…
詳しくみる監査役とは?役割や権限、選任方法を解説【テンプレート付き】
上場企業では、企業の透明性・ガバナンスの向上と、株主や投資家、市場全体の信頼を獲得・維持することを目的に監査役を設置しています。未上場企業でも、IPOを目指す場合には監査役の設置が…
詳しくみる