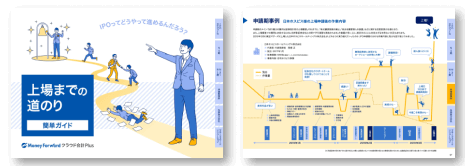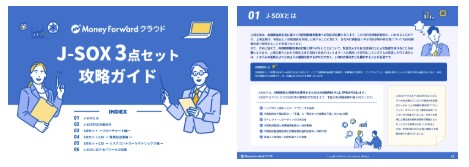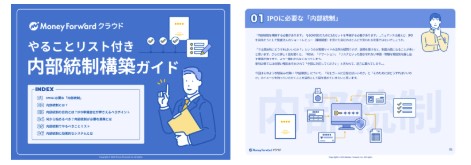- 更新日 : 2025年3月19日
信託型ストックオプションとは?メリットや有効な活用方法を解説!
昨今スタートアップ企業やベンチャー企業で信託型ストックオプションの導入が進んでいます。しかし、従来のストックオプションとはなにが違うのでしょうか?
この記事では、信託型ストックオプションの基本情報を解説するほか、従来のストックオプションとの違いやメリット、注意点などもお伝えします。
目次
信託型ストックオプションとは
信託型ストックオプションとは、受益者である従業員や役員が設定された価格で自社の株を購入できる権利の「ストックオプション」に、信託制度を組み合わせた制度を指します。
信託型ストックオプションは、まず企業の経営者が信託銀行へ資金を拠出し、信託をつくります。続いて信託銀行はその資金で会社からストックオプションを購入・保管します。
受益者(従業員や経営者)は信託期間中に業績・評価に紐づいたポイントが付与され、信託期間満了後には、付与されたポイント数に応じたストックオプションが受け取れるという仕組みになっています。
この仕組みにより、信託を始めたときのストックオプション条件を保管できるため、信託開始後に入社した従業員にも、同じ条件のストックオプションが付与されます。
信託型ストックオプションは新しい選択肢
信託型ストックオプションは従来とは異なる、新しい選択肢の一つと考えられます。信託型ストックオプションとは、いくつかあるストックオプションのうちのひとつで、信託を利用した報酬制度です。発行したストックオプションは、期間満了まで信託銀行などに管理されます。
会社への直接的な成果や業績への貢献度、人事評価に応じてストックオプションに交換できるポイントを役員および従業員に付与することで、信託期間満了時には個々のポイント数に応じたストックオプションを交付できます。
信託型ストックオプションの仕組み
信託型ストックオプションの仕組みは、以下のとおりです。
| 委託者 | 会社の代表取締役など |
|---|---|
| 受託者 | 信託会社など |
| 受益者 | ストックオプションを受け取る役員や従業員 |
| 発行会社 | 株式を発行する会社 |
信託型ストックオプションの導入フロー
まず信託型ストックオプションを導入する際のフローを整理しましょう。
以下は、最初に行う信託契約以降の流れです。
| 誰から誰へ | 何をするか |
|---|---|
| 委託者(代表取締役) →受託者(信託会社) | ストックオプションの時価相当の現金(発行価額)を支払う |
| 受託者(信託会社) →発行会社 | 委託者からを受けたストックオプションの発行時価額を支払う |
| 発行会社 →受託者(信託会社) | 払い込まれた額相応のストックオプションを割り当てる※1 |
| ストックオプションの保管中 発行会社 →受益者(経営者・役員) | ストックオプションに将来交換できるポイントを割り当てる |
| 信託期間満了後※2 受託者(信託会社) →受益者(経営者・役員) | 受益者の獲得ポイント数に応じてストックオプション割り振る |
※1 都度ストックオプションの発行額の決議が行われ、未上場企業の場合は株主総会で、上場企業の場合は取締役会で決定されます。
※2 上場するタイミングや事業売却する時期などを顧みて事前に任意で設定します。
上表の通り、最初にストックオプションをまとめて信託に割り当てることで、さまざまなメリットが受けられます。信託型ストックオプションをまとめて信託に割り当てることで得られる具体的なメリットは、以下のとおりです。
- その時点でのストックオプションの条件(権利行使価格など)を保存できる
- 実際のパフォーマンスや会社への貢献度に応じてストックオプションを付与できるため、後から加わった役員や従業員であっても、モチベーションが上がりやすい
以上から従来型のストックオプションが抱えていた、「基準が曖昧」「手間とコストがかかる」「手続きが複雑」といった課題が解消されます。
従来のストックオプションとはなにが違うのか
信託型ストックオプションと従来のストックオプションの違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 信託型ストックオプション | 従来型ストックオプション |
|---|---|---|
| 権利 | 新株予約権を信託銀行に預け、従業員・役員がその受益権を得る | 新株予約権を直接付与 |
| 譲渡性 | 信託スキームを活用し、受益権を譲渡しやすくするなど柔軟設計が可能 | 原則として本人以外への譲渡は制限が多い |
| 手続き | 信託銀行が中心になって行使手続きを行うため、個人ごとの手続き負担が低減する場合もある | 対象者が行使申請して株式を取得する |
| 税務上・会計上の処理 | 信託の導入により要件を満たせば追加のメリットが得られる場合がある | 通常のストックオプション会計が適用される |
| リスク管理 | 信託として管理することで、受益者保護の仕組みを組み込みやすい | 会社の破綻などの場合、株式価値の毀損リスクをそのまま受ける |
それぞれにメリットとデメリットがあるため、企業の状況や目的に応じて、最適な制度を選定・設計することがポイントとなります。
ストックオプションは4種類ある
ストックオプションには4種類あります。それぞれ整理して解説します。
- 無償税制適格ストックオプション
- 無償税制非適格ストックオプション
- 株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション)
- 有償ストックオプション
1.〜3.は事前交付型で、4.有償ストックオプションは権利付与の際に金銭が発生します。
1.無償税制適格ストックオプション
無償税制適格ストックオプションは、付与対象者の条件や行使期間などの厳しい適格要件を満たせば、権利行使時の給与所得課税が免除される特徴があります。無償ストックオプションの中でも税制優遇措置が施された報酬制度です。
2.無償税制非適格ストックオプション
無償税制非適格ストックオプションは、権利行使時に付与対象者が払い込む金銭(権利行使価格)と権利行使時の株価との差額に応じて最大で55%も給与所得課税されてしまう特徴があります。一方、無償税制適格ストックオプションのような厳しい適格要件を満たす必要はありません。
3.株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション)
株式報酬型ストックオプションは別名「1円ストックオプション」とも呼ばれ、権利行使価格を1円などと超低価格に設定した無償税制非適格ストックオプションをいいます。
権利行使価格設定を限りなく低くでき、権利行使時の株価とほぼ同等のキャピタルゲインが得られるのが特徴です。
4.有償ストックオプション
有償ストックオプションは、1.〜3.の事前行使型の無償ストックオプションとは異なり、権利付与の際に金銭負担が都度生じる報酬制度です。
有償ストックオプションのフローは、まず付与対象者(経営者・役員・従業員)が発行価額を支払い、ストックオプションを購入します。購入後一定期間が経過したのちに、付与対象者が権利行使価格を支払うことで権利を行使でき自社株式が取得できるという流れです。
有償ストックオプションの場合、ストックオプションの取得に毎度支払いが必要になります。しかし適正な時価で購入した有償ストックオプションは給与ではなく、金融商品の取得であるため、無償税制非適格ストックオプションのような給与所得課税が発生しないという特徴があります。
また売却時にはキャピタルゲインに譲渡課税(最大約20%)が発生します。そのため、無償税制非適格ストックオプションとは相対的に税率を抑えられるという特徴もあります。
信託型ストックオプションを導入するメリット
信託型ストックオプションの導入には5つのメリットがあります。このメリットは多くのスタートアップ企業やベンチャー企業が信託型ストックオプションを導入している理由にも直結しています。
以下ではそれぞれのメリットについてひとつずつ詳しく解説します。
即戦力の人材を集められる
スタートアップ企業やベンチャー企業など急成長が見込まれる企業にとって、即戦力となる優秀な人材の確保は重要な課題です。
信託型ストックオプションを導入することで、業績に応じて株価が上昇した際にキャピタルゲインとして従業員へ付与することができ、結果として高い報酬を割り当てることが可能です。魅力的な給与・報酬条件や福利厚生を提示することで優秀な人材を集められるという点で非常に効果的です。
従業員のモチベーションアップにつながる
従業員のモチベーションアップとはすなわち、株価上昇および業績アップに尽力しようとする従業員のやる気アップにつながることを意味します。
信託型ストックオプションによって、自社の株価の上昇で業績に応じたキャピタルゲインを獲得できます。従業員にとってはキャピタルゲインが多ければ多いほど報酬に反映されるので、自社の業績を上げようと目標に向かって尽力できる原動力になりえるといえます。
社外協力者との協力関係が強化できる
社外協力者は、企業の専任顧問やアドバイザー、委託業者などを指します。社外協力者との協力関係の強化の実現とは、社外協力者にも協力事業に対してより一層のモチベーションアップなどが期待できるということです。
ストックオプションは従業員だけではなく、社外協力者への付与も可能です。社外協力者にも付与できれば、担当事業に対して当事者意識を持ってもらいやすくなり、業績向上につながると期待できます。
さらにストックオプションを報酬にすればキャッシュアウトが防げるという効果もあります。
業績評価後に設定を決められる
信託型ストックオプションは最初に、付与対象者や付与率などの詳細設定を発行時に限らず、のちのストックオプションとのポイント交換時に規定内で割当先を決めることが可能です。
信託への保管期間中に付与対象者へポイントを付与し、期間満了後に集計することでポイント比率に見合った付与先、付与率が決定できます。実際の業績への貢献度や業務への取り組む姿勢などを評価した後に、評価に合ったストックオプションを付与できるというメリットがあります。
株価が上がる前の価値をそのまま保管できる
信託は資産を預けた当初の価値をそのまま保管する機能があります。ストックオプションの発行時の条件と価値をそのままに割り当てられるというメリットがあります。
信託型ストックオプションを導入するデメリット
さまざまなメリットがある中、信託型ストックオプションには2つの注意すべき点およびデメリットがあります。
委託者の金銭的負担が増える点と税制適格ではないため給与課税の対象となる点について、それぞれ詳しく解説します。
委託者の金銭的負担が増える
信託型ストックオプションでは、契約時に信託会社に支払う手数料込みでまとまった資金の支払いが必要となります。
ストックオプションの行使金額を確保したうえで、信託会社に支払う手数料も合わせて払い込むため、委託者の金銭的負担が増えてしまいます。
税制適格ではない場合給与課税の対象となる
信託型ストックオプションは、制度が発表された当初、税制適格ストックオプションに該当し、権利を行使しても給与課税されないものと考えられていました。
しかし、国税庁は令和5年に信託型ストックオプションは、税制適格要件を満たさない場合、給与課税の対象となることを示しました。
実質、会社が役職員にストックオプションを付与しているものであり、役職員に金銭等の負担がないことなどから、権利行使価額で株を取得できるという経済的利益は労務の対価に当たると捉えたためです。
令和5年9月6日付の日本経済新聞の記事によると、令和5年の時点で、信託型ストックオプションは上場前後の新興企業を中心に約800社が導入していました。
国税庁の立場を受け、日本経済新聞が信託型を導入済みの上場新興企業を対象にアンケート調査を実施したところ、以下のような結果が出ました。
- 「考えていない」…27社(54%)
- 「考えている・検討中その他」…23社(46%)
国税庁の変更は、制度設計について多くの影響を与えたと言えるでしょう。
税制適格でない場合、所得税や住民税などの負担がかかるだけでなく、社会保険料ものしかかります。結果、受領側の手取りが少なくなってしまい、インセンティブとしての効果が発揮されない可能性が高くなります。
信託型ストックオプションを導入する際の注意点
令和5年7月に改訂された「ストックオプションに対する課税(Q&A)」にて、国税庁は税制適格ストックオプションとして認められる信託型ストックオプションの要件を公表しました。
要件には、信託型ストックオプションの行使は、受益者指定日後2年を経過した日から受益者指定日後 10 年を経過する日までの間に行わなければならないことや、権利行使価格は、信託受益権の付与に係る契約の締結時における時価以上であることなどが盛り込まれています。
これらの要件を満たさない場合、税制適格要件を満たさず、給与課税の対象となるため、制度設計を誤らないよう、注意が必要です。
使い勝手のよさかベネフィット重視か
ストックオプションの導入を検討する際には、「使い勝手の良さを優先するのか、それとも従業員のメリットを最大化するのか」という視点が重要です。
企業側は付与対象者を後で決定できるような柔軟性を求める一方、従業員のベネフィットを優先するのであれば税制適格ストックオプションなどを検討する必要があります。
そのため、どちらの観点を重視するかによって導入スキームが大きく変わり、最終的な導入の可否が左右されます。
たとえば、付与対象者を後から決定できるなどの柔軟性を重視するのか、あるいは従業員側のベネフィットを考慮して税制適格ストックオプションを導入するのかといった選択が、最終的に導入の可否を左右する大きな基準になります。
企業の方針や目的によって最適なストックオプションの形は異なるため、「使い勝手」と「従業員のメリット」の両方を考慮しながら、最も自社に合ったスキームを検討することが重要です。
信託型ストックオプションの会計処理もマネーフォワードへ!
従来のストックオプションと信託型ストックオプションの違いや信託型ストックオプションの種類、導入が増えている背景などを解説しました。十分なメリットがある一方、気を付けるべきデメリットも存在します。
以下の記事では、ストックオプションの会計処理について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
ストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説
上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリッ…
詳しくみるファントムストックとは?仕組みやメリット・デメリット、注意点などを解説
ファントムストックは、企業が役員や従業員に対して提供する金銭報酬の一種です。企業の成長に貢献した役員や従業員を評価し、モチベーションを高めるための仕組みです。この制度では、対象者に…
詳しくみる【ワークシートあり】管理職の定義や役割は?役職者との違いや求められる能力も紹介
Point管理職の役割は? 管理職とは、部門やチームの責任者として、業務と人材を統括する役割を持つ組織の中間層です。 業務管理と人材育成が主業務 役職者やマネージャーとは区別される…
詳しくみるIPO(新規上場)時の役員報酬の決め方は?5つのポイントに分けて解説
企業の成長戦略を描く経営陣や、上場後の透明性を確保するための内部統制体制を整える役員の存在は、投資家からの信頼を得る鍵となります。 本記事では、IPOを目指す企業においての役員報酬…
詳しくみるベスティングとは?人材の離脱防止と従業員のモチベーション向上につながる理由も解説
ストック・オプションでは多くの場合、行使条件として会社の上場が要件となります。 この状況が、未上場の日本のスタートアップにおいてベスティング条件の考え方を特殊なものにしています。 …
詳しくみる社外CFOとは?IPO準備における役割やメリット・活用法を解説
IPO(新規株式公開)を目指す企業にとって、「社外CFO」とは何か、そして導入すべきなのかという疑問を抱く方も多いでしょう。 本記事では、社外CFOの基本的な役割から業務内容、社外…
詳しくみる