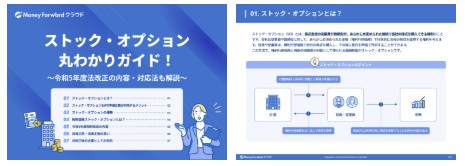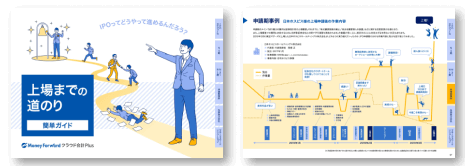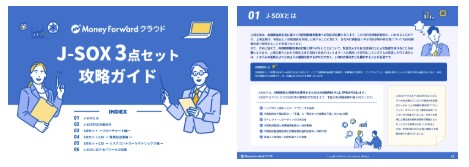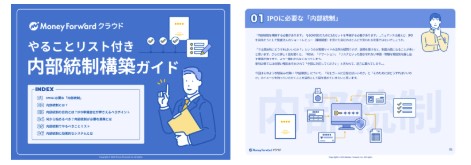- 作成日 : 2024年9月30日
リストリクテッド・ストックとは?概要やメリット、デメリット、導入事例などを解説
リストリクテッド・ストックは、企業の成長や役員・従業員のインセンティブを促進するために用いられ、資本調達や人材の確保・定着において重要なツールです。
そこで本記事では、概要から実際の適用例、そしてメリットとデメリットについて詳しく解説します。
企業の経営者・投資家・これから企業の一員として活躍したいと考えている方々は、リストリクテッド・ストックへの理解を深めることが成功への第一歩となるでしょう。
目次
リストリクテッド・ストックに注目が集まる理由
経済産業省は日本企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上を目指して迅速かつ決断力のある意思決定ができるよう、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。
その一環として、中長期の企業価値向上に資する役員報酬プランの導入を促進するため、「『攻めの経営』を促す役員報酬〜企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引〜」を2017年4月に作成・公表しました。
そして2022年7月に改訂された「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」に基づき、従業員に対する自社株報酬付与に関するQ&Aを追加し、2023年3月に改訂版を発表しました。
日本では、当時の会社法の規定により無償での株式発行や労務出資は認められていなかったので、役員に対して直接株式を報酬として交付することができませんでした。「信託」を利用した新しい株式報酬制度が導入され始めていましたが、株式報酬を導入するための仕組みはまだ十分に整備されていない状況でした。
しかし上記手引を通じて実務的にも簡便な方法で、金銭報酬債権を現物出資する手法を用いることができるようになり、リストリクテッド・ストック導入のための手続きが整理されました。
参考:経済産業省
「『攻めの経営』を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~(2023年3月時点版)」
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 (CGS ガイドライン)」
リストリクテッド・ストックとは
リストリクテッド・ストック(Restricted Stock・譲渡制限付株式)は、その名のとおり、株式が付与されるものの、特定の条件が達成されるまでは譲渡が制限されている株式です。
譲渡制限を解除するには、通常、一定の勤務条件や継続勤務が必要です。条件が満たされない場合には、没収されることもあります。
リストリクテッド・ストックのメリット・デメリット
リストリクテッド・ストックは、企業の戦略的な目標に合致する優秀な人材を確保し、長期的な業績向上を促進するために用いられます。とはいえ、メリットとデメリットが存在するため、運用には適切な理解が求められます。
メリット1:投資家と経営者の利害を一致させる
リストリクテッド・ストックが付与されると、譲渡制限がある状態でも「議決権」と「配当を受け取る権利」が付与されます。つまり、リストリクテッド・ストックが付与された瞬間からその役員・従業員は株主(投資家)としての立場を得ることになります。これにより経営者は投資家の視点を意識した経営を行うため、ガバナンスの向上が期待されます。
メリット2:優秀な従業員を一定期間留まらせる
リストリクテッド・ストックには「勤続年数」などの条件が設定されているため、一定期間、優秀な人材を留める効果(リテンション効果)があります。また、もし従業員が退職する場合には没収することができるため、人材の流出を防ぐ抑止力にもなります。
デメリット:業績へのコミットメントが弱い
リストリクテッド・ストックの条件は「中期経営計画の目標達成」などの業績指標に基づかないため、業績連動型株式に比べて、業績へのコミットメントを促す力が弱いとされています。
事前交付型リストリクテッド・ストックの会計上の注意点
経済産業省から発表された手引きによれば、株式が付与された後には、役員などの報酬債権相当額から、その役員などが提供する役務に基づいて当期に発生した部分を、譲渡制限期間などの合理的な基準に従って算定し、費用として計上する(前払費用などの取り崩しを行う)必要があります。
この他にも会計上の注意事項として以下が挙げられます。
日本では事後交付型より事前交付型が一般的
譲渡制限付株式報酬は役員などに譲渡制限付株式を付与し、一定の勤務条件が達成された場合にその制限が解除されるという株式報酬制度です。もし条件が満たされなかった場合には、付与された株式を会社が無償で回収することになります。
一定期間にわたる譲渡制限が付された株式を事前に役員に付与するものが事前交付型リストリクテッド・ストック(一般的にリストリクテッド・ストックと呼ばれる)であり、勤務条件を満たした後に現物株式を事後的に付与する(または譲渡制限を設けることも可能)ものが事後交付型リストリクテッド・ストック(一般的にリストリクテッド・ストック・ユニットと呼ばれる)です。両者には株式報酬費用が発生した際の処理方法など、会計処理に違いがあります。
日本では事前交付型リストリクテッド・ストックが多く用いられています。そこでここからは、事前交付型リストリクテッド・ストックの会計処理について詳しく説明します。
費用処理の適用期間
リストリクテッド・ストックは役員などに将来の役務提供に対する報酬として金銭報酬債権を付与し、その債権の現物出資として株式を交付する形で提供されます。
そのため、付与された金銭報酬債権に見合った役務が提供される期間にわたって費用を処理するというのが基本的な考え方です。
つまり、役務の提供が見込まれる期間に前払報酬を費用処理するのが原則的な処理であると考えられます。
無償取得時の会計処理方法
付与した報酬債権相当額のうち、譲渡制限解除の条件が達成されずに会社が役員などから株式を無償で取得した部分(役員からの役務提供がなかった部分)については、付与した金銭報酬債権に対する役務が提供されないため、前払費用として計上する根拠がなくなります。
その結果、前払費用などを雑損失として処理することになります。
リストリクテッド・ストック導入の事例:株式会社豊田自動織機
株式会社豊田自動織機は以下のリストリクテッド・ストック制度を導入しました。
目的
取締役(社外取締役などを除く)に対し、中長期的な業績向上と企業価値の向上を目指すインセンティブを提供し、株主と価値共有を進めるため。
制度概要
- 対象取締役に年額最大2億円の株式報酬を支給。支給額は業績に応じて設定。
- 株式は普通株式で譲渡制限付き、年6万株以内の範囲で調整される。
- 支払いは東京証券取引所の終値に基づき決定。
- 譲渡制限期間は3年から30年。
- 制限解除条件は期間満了または任期満了、死亡などの場合。
- 法令違反などがあった場合、株式を無償で回収できる。
- 支給時期は取締役会の決定による。
- 組織再編時には譲渡制限が解除される。
- 副社長・経営役員への適用:上記制度が株主総会で承認された場合、取締役を兼務しない副社長・経営役員にも同様の制度が適用される予定。
参考:株式会社豊田自動織機「譲渡制限付株式報酬制度の導入、及び取締役報酬額の改定に関するお知らせ」
まとめ
リストリクテッド・ストック(制限付株式)は、企業が従業員や経営陣に対して長期的なコミットメントを促すための強力なインセンティブツールです。この記事で述べたように、リストリクテッド・ストックは通常、一定の条件や制限が課されており、その条件を満たすことで株式が完全に付与されます。
ただし、リストリクテッド・ストックには、税務上の扱いや株式の譲渡制限など、注意が必要な点も存在します。リストリクテッド・ストックの適切な活用法をマスターすれば、より効果的な人材管理と企業成長を実現する一助となるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和5年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
IPOで労務監査は必要?実施タイミングや確認ポイントを解説
IPOを検討している企業において、労務監査は必要なのか気になっている人もいるでしょう。労務監査は、企業が労働法規を正しく遵守しているかを調査することで、実施準備・監査の実施・監査報告の3つの手順で行われます。労務監査で指摘されないためには、…
詳しくみる退職後のストック・オプション行使は難しい?理由や裁判例を紹介
一部の例外を除いて、ストック・オプションを行使するためには在職を行使条件としている会社が多く、退職するとストック・オプションが行使できなくなります。しかし一部の例外も存在しており、ストック・オプションの取り扱いが会社によって異なるのも事実で…
詳しくみる監査等委員会設置会社の取締役の任期は?基本制度や注意点を解説
監査等委員会設置会社は、近年多くの企業が採用しているコーポレートガバナンスの形態の一つであり、IPOを目指す企業にとっても選択肢として注目されています。中でも取締役の任期は、業務執行取締役と監査等委員である取締役とで異なる制度が採用されてお…
詳しくみる税制非適格ストックオプションとは?税金・会計処理・確定申告まで詳しく解説
ストックオプションは、スタートアップや上場企業を中心に導入が進んでいる報酬制度です。 なかでも税制非適格ストックオプションは設計の自由度が高く柔軟に活用できる反面、税制優遇がなく税負担や会計処理が複雑になる点に注意が必要です。 本記事では仕…
詳しくみるストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説
上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリット・デメリットを理解し、リスクを踏まえた制度構築が必要です。…
詳しくみるサテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説
テレワークやリモートワークなど、出社を要しない新しい働き方もすっかり定着しています。そのような中で注目されているのが、「サテライトオフィス」です。 当記事では、サテライトオフィスについて、導入事例やメリット・デメリットなどを解説します。働き…
詳しくみる