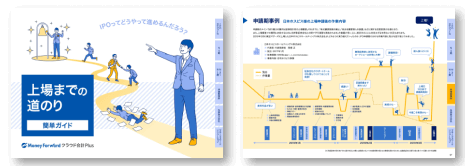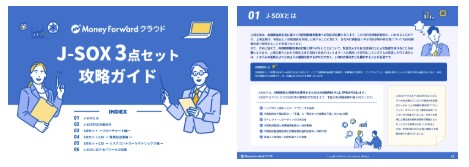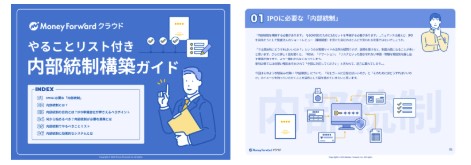- 作成日 : 2025年4月23日
ストックオプションと持株会の違いは?メリット・デメリットや設立手順を解説
上場企業を中心に広く導入されている制度が、従業員持株会です。企業が人材確保や組織の成長を目指す中で、従業員持株会の導入は有効な選択肢のひとつとされます。ただし、制度の導入にはメリット・デメリットを理解し、リスクを踏まえた制度構築が必要です。
本記事では、従業員持株会の制度解説や、似た制度として挙げられるストックオプションとの違いについて解説します。
目次
ストックオプションとは
ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格で、自社株式を将来取得できる権利を従業員などに付与する制度です。報酬の一種として用いられ、とくにスタートアップやベンチャー企業などで、現金報酬を抑えつつ優秀な人材を確保・定着させる手段として活用されています。
ストックオプションを付与された者にとっては、株価が上昇すれば利益を得られるため、企業成長と連動したインセンティブとなります。
ストックオプションの仕組み
ストックオプションの仕組みは、企業が特定の従業員などに対して、将来自社株式をあらかじめ定めた価格(行使価格)で購入できる「権利」を付与するものです。
たとえば、株価が1株1,000円のときに「将来1,000円で株を買える権利」を付与し、数年後に株価が2,000円に上昇すれば、差額の1,000円が従業員の利益になります。
ストックオプションは従業員と企業との間で契約が締結された時点で、権利が付与されます。
行使の際は「権利確定期間(ベスティング期間)」や「在籍条件」などが設けられるのが一般的です。
こうした条件をつけながらストックオプションを発行すれば、企業は従業員の中長期的な貢献や離職防止をはかれます。
従業員持株会とは?
従業員持株会は、社員が自社株を定期的に購入・保有できる制度です。福利厚生や資産形成支援を目的として、導入される制度です。社員は毎月の給与から一定額を拠出し、持株会がまとめて株式を購入し、従業員は持分に応じて株主となります。
多くの企業では、奨励金が購入額の5〜10%程度上乗せされるため、実質的に有利な条件で株を取得できる仕組みとなっています。
株式は証券口座で管理され、一定の条件下で売却も可能です。従業員にとっては企業への帰属意識が向上し、企業側にとっては安定株主の確保につながります。
従業員持株会の仕組み
従業員持株会の仕組みは、以下の通りです。
- 従業員から自社株取得のための原資を募る
※給与からの定額天引きが一般的 - 持株会が自社株式を共同購入する
- 買い付けた株式を、拠出金に応じて分配を行う
企業は奨励金や管理費の負担を通じて、社員の長期的な資産形成を後押しします。株価の変動リスクはあるものの、比較的低リスクの資産運用の手段と言えるでしょう。
ストックオプションと従業員持株会の違い
ストックオプションは、あくまで「株を将来購入できる権利」であり、無償または低価格で付与され、株価上昇時に利益が見込めるインセンティブ報酬です。一方、従業員持株会は社員が自ら資金を拠出して株を購入する制度で、資産形成が主な目的となっています。
前者は成果報酬に近く、後者は福利厚生に近い位置づけです。また、ストックオプションは権利を付与された人だけが行使できるものです。従業員持株会は、制度対象者であれば、誰でも申し込みを行えます。企業の成長ステージや目的に応じて、使い分けることが重要です。
従業員持株会の企業側のメリット
従業員持株会の、企業から見たときのメリットを3点解説します。
従業員のモチベーション向上につながる
従業員持株会では、社員が自社株を保有し、「会社の一員」から「株主」という立場も得ることになります。また奨励金や配当金によって株式をお得に買える点は、日々の業務への前向きな姿勢を引き出す要因となるかもしれません。
企業の業績が自身の資産に直結するため、仕事に対する意識や責任感が高まりやすく、モチベーション向上にもつながりやすいです。企業にとっては、組織の一体感の醸成や人材の定着にも寄与する施策と言えます。
福利厚生の充実になり企業の魅力がアップする
従業員持株会は、資産形成支援を通じて従業員の経済的安定を後押しする仕組みです。給与天引きによる手軽さも相まって、福利厚生としての満足度が高くなります。
また、持株会から自社株を購入する際は、一定の奨励金が上乗せされます。従業員側からすると、大きなメリットと捉えられるでしょう。
こうした制度を整えれば、企業としての魅力が高まり、優秀な人材の採用や定着にもつながります。
自社の経営安定につながる
従業員持株会を通じて、従業員が自社株を継続的に購入・保有することで、企業側は安定株主を確保できます。これにより、自社株の外部への流出を避けられるだけでなく、敵対的買収リスクの低下や、株価の安定にも一定の効果が見込めるでしょう。
従業員株主としての意識が高まり、企業全体のガバナンス強化や長期的な企業価値向上など、よい側面が見込めます。
従業員持株会の企業側のデメリット
続いて、従業員持株会の企業から見たときのデメリットを3点解説します。
配当の有無が、従業員に思わぬ影響を引き起こす
従業員持株会では、配当が従業員の投資リターンの柱となります。企業として配当を出すことは法令上の義務ではありません。
しかし、経営状態を考え、配当を減額ないしは無配当とすると、従業員への思わぬモチベーション低下を引き起こす場合があります。
従業員持株会の株式比率は、株式全体で見ると少ないものです。中長期的に制度を継続するには、こうした配当の扱いを検討することも必要です。
業績や株価によって従業員のモチベーション低下の可能性がある
持株会に加入した従業員は、自社の業績や株価に強く影響を受けます。
株価の下落や配当の減少が続くと、資産価値の減少に直結し、不満や不安につながる恐れがある点は考慮しましょう。
従業員持株会を通じた投資額が大きい場合、業績不振時に従業員のモチベーション低下や不信感が表面化するケースも考えられます。募集する際は、制度のリスクや株式投資の性質を丁寧に説明しましょう。
従業員持株会の運営や手続きの手間が発生する
従業員持株会を設立し運営する場合、後述しますが、手順を踏んで持株会を設立し、適切に運用しなくてはなりません。また、従業員持株会で株式を購入する場合、給与天引きなどの処理が必要となるため、会社側での手続き処理が増加します。
従業員持株会の運営には、そもそも会社側に処理の負担がかかる点を理解し、制度の導入を検討しましょう。
従業員持株会を導入する際のポイント
従業員持株会を導入する際に、配慮しておきたいポイントを解説していきます。
インサイダー取引にならないか注意する
従業員が自社株を定期的に取得する持株会制度では、インサイダー取引リスクへの配慮が必要です。四半期決算前後や重要な経営判断に関する未公表情報を知り得る立場にある社員が株式を購入する場合、金融商品取引法に抵触する可能性があります。
持株会の運営にあたっては「定時・定額購入方式」を採用し、本人の意思で購入・売却を判断できない仕組みにすると、インサイダー取引のリスクを低減できます。
保有比率と決議権について理解しておく
従業員持株会が自社株を一定以上保有すると、株主総会などでの議決権を行使され、経営に影響を及ぼすリスクが生じると懸念を抱く方もいるでしょう。
従業員の不満や内部対立が強まった場合、集団として議決権を活用する可能性はあります。しかし、従業員持株会の株式保有比率は、そもそも非常に少ないのが現状です。
従業員持株会の保有比率がもっとも多いとされるプライム市場でも、保有比率のボリュームゾーンは0.5%未満となっています。また、議決権行使のルールを事前に定め、リスクをさらに抑えることも可能です。
買取価格を明確にする
従業員が退職や制度脱退により持株会を離れる場合、保有株式をいくらで買い取るかは、事前にしっかりとルールを決めておきましょう。買取価格のルールが不明確だと、従業員とのトラブルや不信感につながる場合があります。
一般的に時価(市場価格や終値)を基準としますが、未上場企業の場合は持株会が買い取ります。その際の買取価格は規程に明記し、周知徹底することが重要です。また、未上場企業の場合は、株式の所有者により評価方法が「原則的評価方法」と「特例的評価方法」にわかれます。
持株会は特殊的評価方法を採用することが多いので、この点も理解しておきましょう。
M&Aが行われた際の株式の扱いを決めておく
従業員持株会を導入する際は、M&A(合併・買収)など企業再編時における株式の取り扱いをあらかじめ明確にしておきましょう。M&Aによって自社株が売却される場合、持株会に所属する従業員の資産が影響を受けるため、混乱や不満の原因になりかねません。
企業買収が行われた際は、従業員持株会の株式もすべて買収企業に売却され、従業員は株式対価を得られます。この際、持株会の全会員の同意が必要です。または、持株会を解散し、清算手続きを行う方法もあります。
企業は従業員持株会を設立する際は、想定しうる事態を持株会規程に盛り込んでおきましょう。
奨励金制度の設計を慎重に行う
奨励金は、従業員が拠出した金額に対し、企業が一定割合を上乗せするインセンティブであり、持株会の加入促進や定着率向上に寄与するものです。しかし、奨励金率を高く設定しすぎると企業側のコスト負担が大きくなり、制度の持続性に影響します。逆に低すぎると、加入率が伸び悩む可能性もあるでしょう。
適切なバランスを取るためには、他社事例や自社の財務状況を踏まえた上で、制度開始時だけでなく、定期的な見直しを行うことが重要です。支給条件や上限額の明記も、トラブル防止の観点では有効です。
従業員持株会の設立手順
従業員持株会の設立手順を6つにわけて解説します。
手順1:基本方針を決める
従業員持株会を設立するには、「なぜ導入するのか」といった、導入の目的を明確にしましょう。導入目的には、従業員の資産形成支援や経営参画意識の向上、安定株主の確保などが挙げられます。
目的や期待する効果を明確にしたら、加入条件や拠出金額、奨励金制度などを決めていきます。従業員持株会は企業にとっては長期的な負担となり得るものです。資金繰りも考慮し、年間予算などを見積もりましょう。
手順2:規約や詳細を決める
制度の方針が定まったら、規約や運用の詳細を決定します。具体的には、会員の加入資格、拠出金額の範囲、奨励金の有無、脱退時の取り扱いなどを盛り込んだ「持株会規約」を作成しましょう。
また、株式の購入方法や管理方法についても、証券会社や信託銀行と相談しながら設計する必要があります。
手順3:各役職の人選を行う
持株会の運営には、会長・幹事・会計などの役職選出が必要です。役職者は、制度を公正かつ円滑に運用するための中心的な役割を担います。人選は、各部門からバランスよく選出するのが一般的です。
人事部や経理部など、制度運用に関係する部署と連携を取りながら選定を進めましょう。
手順4:銀行口座を開設し覚書の締結
持株会の拠出金や株式購入資金を管理するための専用口座を金融機関で開設します。あわせて、企業と持株会との間で、株式の取り扱いに関する覚書を締結しましょう。持株会の資金が適切に管理され、株式の購入や保管などの業務がスムーズに行える体制が整います。
手順5:説明会を実施
制度設立後は、従業員に向けた説明会を実施しましょう。制度の目的、仕組み、メリット、リスクなどを丁寧に説明します。株式投資に不慣れな社員にとっては、不安の払拭が重要です。加入方法や奨励金の有無、売却時の注意点なども具体的に案内しましょう。
手順6:会員募集と運用開始
説明会を経て、正式に会員の募集を開始します。加入者が集まったら、実際の拠出・株式購入がはじまり、制度が本格的に運用されます。初回の株式購入や奨励金支給のタイミングなども明確にし、スムーズなスタートを目指しましょう。
運用開始後は、定期的な報告や状況確認を行うことも重要です。
従業員持株会とストックオプションは社員の意欲向上に期待が持てる制度
従業員持株会は、社員が自社株を定期購入・保持でき、福利厚生の側面が強い制度です。一方のストックオプション制度は、インセンティブ報酬の側面が強い制度です。どちらも従業員の意欲を引き出すのに有効ですが、制度設計やガバナンス、法的リスクへの配慮が求められます。
導入を検討する企業は自社に適した制度がどちらかを精査し、順を追って制度設計を進めていきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
ムーンショット目標とは?制定された背景や企業との関わり
ムーンショット目標とは、内閣府の政策の一つであるムーンショット型研究開発制度において掲げられている、9つの目標のことです。日本が抱える問題を解決するために破壊的イノベーションの創出…
詳しくみるCXOとは?企業成長とIPO成功を導く戦略的リーダーについて解説
企業の成長と持続的な競争優位性を確立する上で、「CXO」と呼ばれる役職は不可欠な存在です。特にIPO(新規株式公開)を目指す企業においては、CXOの担う役割が戦略の成否を左右すると…
詳しくみるIPOにおける労務管理とは?重要性やポイント、システム導入の効果を解説
労務管理は、労働時間や雇用契約などの観点から労働を管理する業務です。労務管理は通常の事業運営だけでなく、上場審査を有利に進めるという視点からIPO準備においても重要な役割を担ってい…
詳しくみる取締役とは?役割や責任・給与体系についてわかりやすく解説
取締役とは、会社法に定められている役員のことです。取締役は、企業における業務の執行について意思決定を行う立場にあるため、企業全体の業務について責任を負っています。 今回は、取締役の…
詳しくみるストックオプションに関連する法律は?種類・要件・注意点も解説
ストックオプションは企業の成長を支える戦略的な報酬制度です。とくにスタートアップやベンチャー企業にとっては、現金報酬に代わる強力なインセンティブ手段として注目されています。しかし、…
詳しくみる労働生産性とは?定義や上げるメリット解説!
労働生産性とは、従業員1人当たり、または労働時間1時間当たりどのくらいの生産性を生み出したかを数値化した指標のことです。 労働生産性には、物理的な量を表す物的労働生産性と、付加価値…
詳しくみる