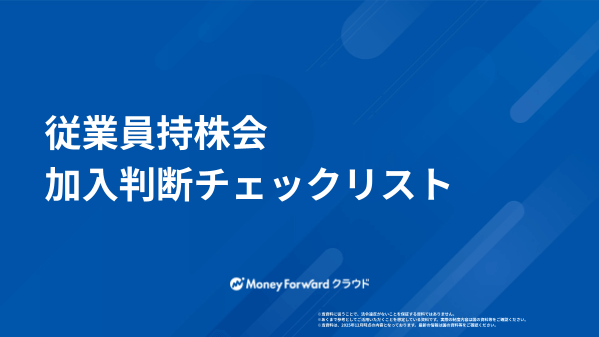- 更新日 : 2025年12月9日
持株会はやめたほうがいい?仕組み・メリット・デメリットを徹底解説
持株会制度は、従業員が自社株を給与天引きで積み立てられる仕組みであり、資産形成と企業へのエンゲージメント向上を両立させるのに向いている制度です。
ただし、株価下落リスクや売却ルールの不透明さが課題となるケースもあるので、導入を検討している企業は、正しい知識を身につけることが重要となります。
本記事では、制度の仕組みから導入のメリット・デメリット、導入時に押さえておくべき注意点までを詳しく解説します。
目次
持株会とは
持株会(従業員持株会)とは企業が従業員に対して、自社株を購入できるように用意した制度です。従業員は毎月の給与から一定額が差し引かれ、その資金で自社株を少しずつ積み立てていけます。
いわば働いている会社の株を自動的に買っていける仕組みであり、長期的な資産形成をサポートする制度として、多くの企業で注目されています。
次項では、持株会の詳しい仕組みについて説明していくので、参考にしてみてください。
なお以下の記事では、持株会設立のプロセスや注意点について解説しています。
従業員が自社株を購入できる制度
一般的に株式を購入するには、自分で証券口座を開設し、株価を確認しながら自分で買う必要があります。
ただし持株会を利用すれば、口座開設や購入の手間をかけずに、勤務先の企業を通じて自社株の購入が可能です。
企業は「持株会」という組織を社内に設け、従業員は会員として加入します。加入者は毎月一定額を拠出し、そのお金を使って会社が従業員の代わりに株式を購入してくれる形です。
購入された株式は基本的に持株会が管理し、従業員は必要に応じて売却したり、退職時にまとめて引き出せたりします。
給与天引きで自動積立が可能
持株会の大きな特徴のひとつが、「給与天引きによる自動積立」です。一度設定をしておけば、毎月の給与から自動的に拠出されるため、手間をかけずに継続的な資産形成が可能になります。
投資に不慣れな人でも、毎月一定額が自動で積み立てられるため、投資のタイミングを見計らうストレスもなく、無理なく続けられるでしょう。
拠出額は会社によって異なりますが、数千円〜数万円の範囲で自由に設定できるケースが多く、生活に負担のない範囲ではじめられるのも特徴です。
会社によって奨励金(補助)が出る場合もある
企業によっては、従業員の持株会加入を促進するために「奨励金(補助金)」を支給する場合があります。奨励金とは、従業員が拠出した金額に対して、会社側が一定の割合で上乗せしてくれる仕組みです。
たとえば、持株会に1万円を積み立てると、企業が10%の奨励金(=1,000円)を上乗せし、実際には11,000円分の自社株が購入できます。
補助がある場合、従業員にとっては自己資金だけで株を購入するよりも効率よくリターンを得られ、普通に投資するよりもお得な制度といえるでしょう。
持株会をやめたほうがいいと言われる理由
従業員持株会は、給与天引きによる自社株の積立や、企業からの奨励金支給といった仕組みにより、資産形成を支援する制度として導入する企業が増えています。自分で手間暇をかけずに投資できることから、自然と加入する従業員もいるでしょう。
しかし魅力的な制度である一方で、「持株会をやめたほうがいい」という声を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。その背景には、株価の変動リスクや売却に関する制約など、従業員にとって見逃せない課題があるためです。
企業として持株会制度を導入・継続する場合は、リスクについても事前に周知し、従業員が納得したうえで加入・運用できるような環境を整備することが求められます。
本章では、「やめたほうがいい」と言われる理由を3つの観点から整理し、制度運用における留意点をご紹介します。
株価が下がるリスクがある
持株会に加入していると、自分の務めている会社の株を自動で毎月購入して、積み立てていくことになります。
しかし株価は企業の業績や市場環境の影響を受けるため、業績が悪化すると、保有している株価にも影響を与える可能性が考えられます。
なお具体的なリスク事例は、以下のとおりです。
- 業績不振による株価下落
- 退職後の株価変動リスク
- 会社が経営危機に陥ると資産価値が減少する など
資産をさまざまな種類に分散投資すると、ひとつの資産の価値が減少しても、全体のリスクを抑えられますが、持株会では「自社株にしか投資できない」ため、リスクが高まります。
そのため、資産形成のために持株会に加入する従業員は、投資先を自社株に依存しすぎるのは、リスクがある点に注意しなければいけません。
株主優待がもらえない
一般的に一定数以上の株を保有していると、その企業から株主優待が送られるケースがあります。たとえば自社商品やサービスの割引券、ギフトカードなど、さまざまな特典が用意されていることも少なくありません。
しかし持株会で保有している株式には、株主優待が適用されないケースが多いです。理由としては、株の名義が「個人」ではなく「持株会」という団体名義になるため、企業側からは個人が株主として認識されないためです。
株主優待を目的に自社株を保有したい場合は、証券会社を通じて個人で株を購入する必要があります。ただし証券会社で購入する場合は、持株会のような奨励金は受けられないため、どちらが得かは慎重に検討しましょう。
自由に売買できない
通常の株式投資であれば、株価が上がったときにすぐに売却して利益を得たり、逆に下がりそうなときに早めに売ったりすることで損失を抑えられます。
しかし持株会では柔軟な売買が難しいケースが多いです。株を売却するには事前申請が必要であったり、現金化されるまでに時間がかかったりするため、タイミングを逃してしまうことも少なくありません。
とくに市場が急変したときには、素早い判断と行動が求められるため、売買の自由度が低い持株会では対応が難しいのが実情です。
従業員が持株会に加入した際に、売却についてのルールをしっかりと伝え、納得したうえで加入してもらうようにしましょう。
企業が持株会を導入するメリット
企業の持株会導入は、単なる福利厚生の充実にとどまらず、経営戦略や組織運営にもよい影響を与えるなど、さまざまなメリットがあります。
従業員にとっては資産形成の手段として魅力的であり、企業側にとっても従業員の意欲向上や人材定着、採用力の強化といった副次的な効果が期待できるでしょう。
ここでは、とくに注目すべき2つのメリットについて詳しく解説します。
従業員のエンゲージメント向上
従業員が自社株をもつと、企業の成長が株価に反映され、その利益が自分の資産として返ってくるため、「自分の働きが会社を成長させている」という実感が生まれます。
このように、株主であるという立場が仕事への責任感や当事者意識を自然と高めてくれるのです。
また、持株会は長期的に資産形成する仕組みであるため、「せっかく積み立てた資産を取り崩したくない」という心理が働き、結果として離職の抑止力にもなります。
企業にとっては優秀な人材を長くつなぎとめる効果があり、組織の安定にも寄与します。
人材採用のアピールポイントになる
現在、多くの企業が優秀な人材の獲得に苦戦しており、採用活動では給与や労働条件だけでなく、「福利厚生の充実度」が大きな選定基準になっています。
そのため、持株会に奨励金制度を組み合わせた制度設計は、企業の魅力を効果的に伝えるアピールポイントとなります。
たとえば、「持株会に加入すると、毎月の積立額の10%を企業が上乗せ」といった具体的な補助制度を設けたとしましょう。その場合求職者に対して「資産形成の支援がある企業」というポジティブな印象を与えられます。
とくに、将来を見据えて長期的に安定した収入や資産を求める人材にとっては、大きな魅力となるでしょう。
企業が持株会を導入するデメリット
持株会は企業・従業員双方にメリットがある一方で、企業側が負担やリスクを抱える側面も存在します。
制度設計や運用を誤ると、従業員の不満を招いたり、業績に悪影響を与えたりする可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
次項では、代表的な2つのデメリットについて詳しく解説します。
配当金を出し続けなければいけない
持株会の導入は多くの従業員が株主となり、「利益が出れば当然配当があるべき」と考えるようになります。
しかし配当金は企業の業績によって左右されるため、配当が出ない年には従業員から不満の声が挙がることも考えられるでしょう。
また「従業員に自社株を持たせているのだから、最低限の配当は維持すべきだ」といった社内プレッシャーが経営陣にかかることもあります。
本来であれば事業投資や人件費に回せる資金が、配当金の支払いに重点をおく事態も想定されるため、企業は配当金の取り扱いに注意が必要です。
株価低迷によるモチベーション低下の恐れがある
持株会に加入している従業員にとって、自社の株価は自分の資産価値に直結するものです。
株価が上昇すればやる気につながる一方で、業績不振などで株価が低迷すれば、「自分の資産が減っている」というネガティブな感情が生まれる可能性があります。
たとえば入社当初に1株1,000円だった株が、数年後には500円になってしまったとします。従業員からすれば「自分の積立が減った」と感じ、会社への不信感や将来への不安が高まり、最悪の場合は離職を検討する原因にもなりかねません。
自社株を従業員に持たせることは、企業と従業員の信頼関係のうえに成り立つ制度であるため、業績悪化時のフォロー体制やリスク説明も不可欠です。
従業員が持ち株会をやめたい場合に必要な手続き
従業員が持株会を脱退したいと申し出た場合、企業としてはスムーズに手続きが進むよう、適切な情報提供とサポートを行うのが重要です。
持株会の脱会にはいくつかのステップがあり、単に積立を止めるだけでなく、保有株式の売却や税務対応など、従業員にとって不明点が多くなる可能性があります。
本項では持株会をやめる際に必要な手続きについて、企業側が把握・説明すべきポイントを3段階に分けて解説します。
手順1:持株会の脱会
まず、従業員が持株会をやめる際には、企業が定めた所定の手続きにしたがって「脱会申請」を行う必要があります。
脱会申請は、持株会事務局や人事・総務部門に対し、申請書を提出する企業が多くなっています。申請期限が月末や特定日などに設定されているケースもあるため、従業員には期日を明確に伝えておきましょう。
脱会が受理されると、翌月以降の給与天引きは停止され、新たな株式の買付は行われなくなります。
ただし、これまで積み立てた株式が自動的に売却されるわけではないため、次に「売却手続き」または「個人口座への移管」が必要となります。
手順2:所有している株の売却
持株会を脱退した後も、従業員はすでに保有している株式を売却するかどうか決める必要があります。
一般的に、売却を希望する場合には証券会社の個人口座を開設し、その口座へ株式を振り替えたうえで、市場を通じて売却する流れです。
この場合、取引は市場価格で行われるため、タイミングによっては売却益や損失が発生します。
なお証券会社を通じた売却では所定の取引手数料がかかり、振替手続きにも数週間かかることがあるため、余裕を持ってスケジュールを組むよう周知しましょう。また一定数以上の株式保有が売却の条件となる場合があるため、事前確認が必要です。
なお非上場企業などでは、会社が従業員から自社株を買い取る「買取制度」が用意されている場合もあります。
このケースでは市場価格での売却とは異なり、買取価格の決定基準や確定申告の要否についてもあわせて説明が必要になります。
手順3:確定申告の有無
従業員が株式を売却して売却益が出た場合は、利益が「譲渡所得」として課税対象になります。ただし口座の種類によって確定申告の要否が異なるため、事前に以下の内容を周知しておきましょう。
| 口座の種類 | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 源泉徴収ありの特定口座 | 証券会社側で自動的に税金が差し引かれるため、原則として確定申告は不要 |
| 源泉徴収なしの特定口座や一般口座 | 売却益が発生すると確定申告が必要 |
なお、課税対象となる譲渡所得は以下のように計算されます。
課税される税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合算した20.315%です。
持株会の最適な運営のためにも、企業は従業員への必要情報の伝達や、支援を行うのが望ましいでしょう。
持株会に加入した場合の確定申告については、以下の記事でも解説しています。
持株会制度を導入する際に押さえておきたいポイント
従業員持株会制度を導入する際には、単に仕組みを整備するだけでなく、従業員が安心して参加できるように制度の運用ルールを明確にするのが重要です。
とくに配当金の取り扱いや、売却時の価格ルールは制度の信頼性に直結するため、事前に社内規程などで詳細を定めておく必要があります。
次項では、導入時に必ず確認・明示しておきたい2つの重要ポイントについて解説します。
配当金の基準を明確にする
従業員が持株会を通じて自社株を保有する場合、配当金の有無とその取り扱いについては事前に明確にしておくべき重要事項です。
まず、持株会名義で保有する株式にも配当が支払われるかどうかを定義します。そのうえで配当金が実際に発生した場合、従業員にどのような形で還元されるのか、また受け取り方法についても明示しましょう。
配当が不透明だと制度の魅力が半減してしまうため、あらかじめ方針を整理し、説明責任を果たすことが制度の信頼性確保につながります。
売却時の買取価格を明確にする
従業員にとって、持株会で購入した株式を「適正な条件で売却できるかどうか」は制度利用の判断基準のひとつです。
上場企業であれば、市場での売却が基本となり、公正な価格での売却が可能です。しかし非上場企業では、企業が株式を買い取るケースが一般的になります。
その場合、買取価格の算定方法や算定基準を、従業員にもわかるようにしておきましょう。
また売却可能な時期や回数などの制限の有無も含めて明示し、従業員が将来的に株式を売却して利益を得られる状況をはっきりとさせておくことで、制度への安心感と参加率向上につながります。
持株会の導入は適切な制度設計が重要
持株会は、従業員の会社に対する帰属意識やエンゲージメントを高め、長期的なモチベーション向上につながる制度です。福利厚生としても魅力的で、人材採用や定着率の向上にも効果が期待できます。
また企業にとっては安定した株主基盤を築く手段にもなります。
しかし従業員が安心して参加するためには、配当金や売却に関するルールを事前に明確にし、丁寧な情報提供を行うのが欠かせません。
制度の目的と運用のバランスをとりながら、企業と従業員双方にとってメリットのある仕組みづくりを行うのが、持株会制度運用において成功の鍵となります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
裁量権とは?定義やメリット・デメリット、裁量労働制について解説!
働き方改革が叫ばれる中、企業には従業員一人ひとりに合った柔軟な勤務体制の整備が求められています。その一つの選択肢として「裁量権の付与」と「裁量労働制の導入」があります。この記事では…
詳しくみるミッションとは?意味やビジョン・バリューとの違い、企業事例を解説
ミッションとは企業に与えられた使命のことで、「存在意義」という意味でも用いられます。社会における企業のあり方や進むべき方向を示すために設定され、バリュー・ビジョンとともに「MVV」…
詳しくみる有償ストックオプションとは?導入のメリット・デメリット、注意点などを解説
有償ストックオプションとは新株予約権の一種であり、特定の価格を支払って株式を取得できる権利を指します。株価が行使価格を上回る場合、その差額が利益となります。 この記事では、有償スト…
詳しくみるスタートアップならではの採用のポイントとは?具体的な実践方法も解説
採用活動が企業の成長において重要な役割を占めていることはいうまでもないでしょう。特に創業間もないスタートアップにとっては、自社に合った人材を見つけて効率的にターゲティングすることが…
詳しくみる取締役とは?役割や責任・給与体系についてわかりやすく解説
取締役とは、会社法に定められている役員のことです。取締役は、企業における業務の執行について意思決定を行う立場にあるため、企業全体の業務について責任を負っています。 今回は、取締役の…
詳しくみるタレントマネジメントとは?導入のメリットや方法、システム利用について解説!
この記事では、タレントマネジメントの基本的な定義から、導入を成功に導くための具体的なステップ、よくある失敗例とその回避策、そして自社に合ったシステムの選び方まで、実務担当者が知りた…
詳しくみる