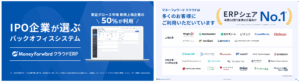- 更新日 : 2024年7月12日
東証一部と二部の違いは?上場の条件やメリット・デメリットを比較
株式市場の東証一部と東証二部はどう違うのでしょうか?そして2022年4月4日以降は東証一部、東証二部はなくなり、プライム市場、スタンダード市場に移行されています。さらに新規上場基準や上場維持基準も変わっています。この記事では、市場再編はなぜ行われたのか、各市場区分はどのような違いがあるのかについて開設しています。東証についての基本的な情報を知りたい人は参考になります。
目次
東証一部と東証二部の違い

東証一部と東証二部は上場基準以外に違いはありません。しかし、東証一部の方が新規上場基準は厳しく、上場できればより投資家からの企業の評価は高まります。会社にとってもステータスとなるため、より資金や優秀な人材が集まりやすくなります。
【市場別】上場基準
| 項目 | 東証一部 | 東証二部 | マザーズ | JASDAQ スタンダード |
|---|---|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 | 400人以上 |
| 流通株式 | ・流通株式数 2万単位以上 ・流通株式時価総額 100億円以上 ・流通株式比率 上場株券等の35%以上 | ・流通株式数 2千単位以上 ・流通株式時価総額 10億円以上 ・流通株式比率 上場株券等の25%以上 | ・流通株式数 1千単位以上 ・流通株式時価総額 5億円以上 ・流通株式比率 上場株券等の25%以上 | ・流通株式数 2千単位以上 ・流通株式時価総額 10億円以上 ・流通株式比率 上場株券等の25%以上 |
| 時価総額 | 250億円以上 | - | - | - |
| 事業継続年数 | 新規上場申請日から起算して、3ヶ年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 新規上場申請日から起算して、3ヶ年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 新規上場申請日から起算して、1ヶ年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること | 新規上場申請日から起算して、3ヶ年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
| 純資産額 | 連結純資産の額が50億円以上(かつ、単体純資産の額が負でない) | 連結純資産の額が正 | - | 連結純資産の額が正 |
| 利益額・売上高 | 以下のAまたはBに適合すること A:最近2年間における利益の額の総額が25億円以上 B:最近1年間の売上高が100億円以上、かつ時価総額が1,000億円以上 | 最近1年間の利益1億円以上 | - | 最近1年間の利益1億円以上 |
※JASDAQグロースは新規上場停止のため未記載
参照:日本取引所グループ 上場審査基準 形式要件(内国株)
【2022年4月】東証一部・二部は廃止される
2022年4月4日付けで東京証券取引所(以降、東証)の再編が実施され、市場区分、上場基準が変更されました。今回、東証の市場区分が再編される理由は以下の2つです。
・市場区分ごとのコンセプトがあいまい
東証一部は大企業、東証マザーズが新興企業というように、本来は市場区分ごとにコンセプトをもたせたほうが投資家にとっての利便性は高まります。しかし、従来の市場は、新興市場を想定している市場区分に老舗企業が上場しているなど、コンセプトがあいまいになっていました。
・上場後、企業価値向上の努力が引き続き行われなくなる
新規で上場するよりも、他の市場区分から移行したほうが上場基準が緩和されている。新規上場基準に比べて、上場廃止基準が緩和されているといった理由から、上場後も企業価値向上を引き続き行わない企業が現れるなどが問題視されていました。
これらの問題を解決するために東証は各市場区分のコンセプトを明確化し、上場維持基準の厳格化をするなどの再編を実施したのです。
変更後の市場区分
市場再編によって、これまでの東証一部、東証二部、東証マザーズ、JASDAQの4つの市場から、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3つの市場に移行されています。
新区分の概要
| 新区分 | 概要 |
|---|---|
| プライム市場 | 多くの機関投資家の投資対象となるような時価総額(流動性)があり、安定株主の株式の保有比率が高くならないような高いガバナンス(企業統治)を備えている企業、及びその企業に投資をする機関投資家や一般投資家のための市場 |
| スタンダード市場 | 一般投資家が円滑に売買できるほどの適切な時価総額(流動性)があり、上場会社として基本的なガバナンス水準を備えている企業、及びその企業に投資をする投資家のための市場 |
| グロース市場 | 高い成長性を実現するための事業計画、またはその進捗が適時・適切に開示されていて一定の市場評価があり、そのうえで事業実績から判断して相対的にリスクが高い企業、及びその企業に投資をする機関投資家や一般投資家のための市場 |
東証一部・二部はどう変わるか
再編前後では、新規上場基準も市場区分の数も異なります。そのため、従来の東証一部は、新市場区分ではプライム市場とスタンダード市場のいずれかを選択、東証二部は、スタンダード市場に移行されることもあります。
東証市場の上場条件
東証市場に上場するためには、各市場区分で定められた上場条件を満たす必要があります。再編後に新規上場をする場合は、従来の東証一部、東証二部の上場条件ではなく、プライム市場、スタンダード市場の上場条件を参考にする必要があります。
プライム市場
プライム市場の上場要件の概要は以下のとおりです。
- 多くの機関投資家が安心して投資対象とできるよう、潤沢な流動性の基礎を備えている銘柄
- 上場会社と機関投資家の間で、建設的な対話を中心に据えて、企業の持続的成長、中長期的な価値向上にコミットする銘柄
- 安定的かつ優れた収益基盤・財政状態をもった銘柄
これらの上場要件をみたすために、プライム市場に上場する企業には以下の様な形式要件を設けています。
プライム市場の上場条件
| 項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 800人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 | 2万単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 100億円以上 |
| 売買代金 | 時価総額250億円以上 | 平均売買代金平均0.2億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 35%以上 |
| 収益基盤 | ・最近2年間の利益合計が25億円以上 または、 ・売上高100億円以上かつ時価総額1,000億円以上 | - |
| 財政所帯 | 純資産50億円以上 | 純資産額が正(プラス)であること |
プライム市場の上場要件は、流通株式比率が他の市場に比べて極めて高い点が特徴です。ただ、これだけでは従来の東証一部の条件とかわりませんが、同時に今回の再編にともない、流通株式数の計算方法も変わっている点がポイントです。
流通株式数の計算式は以下のように変わっています。
【従来の流通株式数の計算式】
上場株式数-(10%以上保有している主要株主が所有する株式数+役員所有株式数+自己株式数)【2022年4月4日以降の流通株式数の計算式】
上場株式数-(10%以上保有している主要株主が所有する株式数+役員所有株式数+自己株式数+国内の普通銀行、保険会社、事業法人などが所有する株式+その他東証が固定的と認める株式)
したがって、持ち合い株を保有している企業の中には、プライム市場の要件をクリアするために手放さなければならないケースもでてくるでしょう。
また、従来の上場維持基準が見直されたことにより、上場維持のハードルがかなり高くなっている点にも注意が必要です。
スタンダード市場
スタンダード市場の上場要件の概要は以下のとおりです。
- 一般投資者が円滑に売買できるほどの適切な流動性の基礎を備えた銘柄
- 持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための基本的なガバナンス水準を備えている銘柄
- 安定的な収益基盤・財政状態を有する銘柄
これらの上場要件をみたすために、スタンダード市場に上場する企業には以下の様な形式要件を設けています。
スタンダード市場の上場条件
| 項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
|---|---|---|
| 株主数 | 400人以上 | 400人以上 |
| 流通株式数 | 2千単位以上 | 2千単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 10億円以上 | 10億円以上 |
| 売買代金 | - | 月平均10単位以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 | 25%以上 |
| 収益基盤 | 最近1年間の利益が1億円以上 | - |
| 財政所帯 | 純資産額が正(プラス)であること | 純資産額が正(プラス)であること |
参照:日本取引所グループ スタンダード市場の上場基準(概要)
流通株式数の計算方法変更の影響を受ける点はプライム市場と同様です。それ以外の部分は、従来の東証二部の新規上場基準、上場維持基準とあまり変動はありません。ただし、上場維持基準の流通株式時価総額は、従来より厳しくなっているので注意が必要です。
東証市場に上場するまでの流れ
上場の申請から承認までの流れは次のようになります。
1.事前確認
上場申請の前に、主幹事証券会社の担当者と、日本取引所自主規制法人の審査担当者との間で公開指導・引受審査の内容や、反社会勢力との関係、審査日程の確認を行います
2.上場申請
申請直前事業年度にかかる定時株主総会終了後に行われます。申請する会社の担当者、主幹事証券会社の担当者を交えて上場申請の手続きをした後、審査担当者から、上場申請理由や、会社の沿革・事業内容・業界の状況・役員や大株主の状況などの聞き取りがあります
3.上場審査
審査担当者が書類をもとに、審査項目に適合しているか確認していきます。不明な点があれば、再度、質問事項を提示し、返ってきた回答書をもとに再度ヒアリングを行います。その後、必要に応じて会社の伝票、帳票などを確認する実地調査、e-ラーニング、公認会計士、社長や役員、監査役の面談も行います
4.東証の上場承認
代表が事業内容や事業計画などの説明会を東証に実施後、問題がなければ上場となり、東証のホームページから上場承認が発表されます
東証市場の上場審査で見られるポイント
東証市場の上場審査では、株主数や流通株式数といった「形式要件」だけでなく、企業の健全性や継続性などの「実質要件」も見られます。
実質要件のチェック項目は以下のとおりです。
- 企業の継続性および収益性
- 企業経営の健全性
- 企業のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性
- 企業内容などの開示の適正性
- その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
各チェック項目の概要、および評価のポイントを解説します。
継続性・収益性
事業を継続的に営み、安定した収益基盤を持っているかどうかが審査のポイントです。
【評価のポイント】
- ビジネスモデルや事業環境、リスク要因を踏まえて、適切に作られている
- 今後、安定的に利益を計上できる合理的見込みがある
- 経営活動が安定かつ継続的に遂行できる状態にある
健全性
事業が公正、かつ忠実に遂行されているかが審査のポイントです。
【評価のポイント】
- 関連当事者やその他特定の者の間で、取引行為や経営活動を通じて不当に利益の供与や享受がない
- 役員の相互の親族関係、構成や勤務実態などが公正・忠実かつ、十分な業務の執行や有効な監査を妨げる状況にない
- 親会社などからの独立性を有している
コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性
コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制が適切に整備され、機能していることが審査のポイントです。
- 役員の適正な職務の執行を確保する体制が、適切に整備・運営されている
- 内部管理体制が適切に整備、運用されている
- 経営活動の安定、継続的な遂行、適切な内部管理体制の維持などに必要な人為が確保されている
など
開示の適正性
企業内容などの開示を適正に行える状況にあるかどうかが審査のポイントです。
【評価のポイント】
- 経営に重大な影響を与える事実などの会社情報を管理し、適時・適切に開示できる状況にある、かつ内部社取引などの未然防止の体制が適切に整備・運用されている
- 企業内容の開示に係る書類が法令に準じて作成されている、かつ投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性がある事項などは適切に記載されている
- 関連当事者、その他特定の者との取引行為や、株式の所有割合の調整により、企業グループの実態の開示を歪めていないなど
その他の事項
その他実質要件についても紹介します。
【評価のポイント】
- 株主の権利内容、および行使の状況が、公益や投資者保護の還元から適当である
- 経営活動や業績に重大な影響を与える係争や紛争などを抱えていない
- 反社会的勢力の経済活動に関与することを防止するために社内体制を整備。関与の防止にも努めている、およびその実態が公益や投資者保護の観点から適当と認められる
など
まとめ
東証一部と東証二部は上場基準以外に違いはありません。ただ、東証一部は上場基準が極めて厳格化されているので、企業に対する投資家の評価は極めて高くなります。
2022年4月4日から東証の再編が行われ、東証一部、東証二部はプライム市場または、スタンダード市場に移行されました。今後、上場基準を参考にする際は移行後の市場の内容を確認することが必要なので注意が必要です。新市場ではこれまでの市場の問題点を改善するため、新規上場基準と上場維持基準が厳しくなっています。上場を検討している方は、各市場の特徴を理解して自分の会社に合った方法を選びましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
マネーフォワード クラウドERP サービス資料
マネーフォワード クラウドERPは、東証グロース市場に新規上場する企業の半数※1 が導入しているクラウド型バックオフィスシステムです。
取引データの自動取得からAIによる自動仕訳まで、会計業務を効率化。人事労務や請求書発行といった周辺システムとも柔軟に連携し、バックオフィス業務全体を最適化します。また、法改正に自動で対応し、内部統制機能も充実しているため、安心してご利用いただけます。
※1 日本取引所グループの公表情報に基づき、2025年1月〜6月にグロース市場への上場が承認された企業のうち、上場時にマネーフォワード クラウドを有料で使用していたユーザーの割合(20社中10社)
よくある質問
東証一部と東証二部の違いは?
上場基準が異なります。東証一部は東証二部より上場基準が厳しく、その分、上場できれば投資家からの評価や企業のステータスは上がりやすいです。
市場再編後の市場区分は?
2022年4月4日以降、市場区分はプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に再編されました。従来の東証一部上場企業はプライム市場かスタンダード市場、東証二部上場企業はスタンダード市場に移行しました。
上場審査で見られるポイントは?
企業の継続性や収益性、健全性、コーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性、開示の適正性が主に見られるポイントです。その他にも株主の権利内容、係争や紛争の有無などの実質要件があります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
情報統制とは?内部統制の強化にITへの対応が必要な理由を解説
内部統制を実施するにあたり、ITへの対応を早急に進める企業も多いのではないでしょうか。しかし、IT業務に関しては、経理担当者や経営者本人ではなくITシステムの管理ができる技術を持った人が担当するはずです。 この記事では、内部統制を進めている…
詳しくみるIPO広報の役割は?求められることや実践のポイントを解説
IPO(新規株式公開)は企業にとって大きな転機です。企業の魅力を投資家に効果的に伝えることで、信頼を得て株式の成功を収めることができます。 本記事では、IPOにおける広報の重要性や戦略を詳しく解説します。 IPO広報とは IPO広報とは、企…
詳しくみるTCFDとは何かわかりやすく解説!開示項目や賛同方法・日本企業の事例も
気候変動への対応が急務とされる現代において、企業や投資家の間で重要性が高まっているのが「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」です。 このフレームワークは、気候変…
詳しくみる上場とは?株式上場(IPO)のメリット・デメリットをわかりやすく解説
上場というと「大手企業が多い」「株価がつく」「給料がいい」など、良いイメージを持つ人は多いでしょう。しかし、具体的に上場企業と非上場企業の違いや、そもそも上場の条件は何かと問われると、少し考えてしまう人も多いのではないでしょうか。 上場を目…
詳しくみるEDINETとは?重要性やTDnetとの違いをはじめメリット・使い方を解説
EDINETは金融庁が運営する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことを指し、開示書類の提出や閲覧を24時間365日行うことができます。EDINETの対象は有価証券報告書や大量保有報告書などであり、…
詳しくみる上場企業が行う決算開示のスケジュールは?段階に分けて流れを解説
企業には決算と呼ばれる、業績や財務状況を開示する仕組みがあります。上場企業は3ヶ月ごと、もしくは1年ごとに決算報告書を公開しなければなりません。しかし、決算開示はただ資料を作って公開すればいいというわけではないのです。 本記事では、決算・決…
詳しくみる