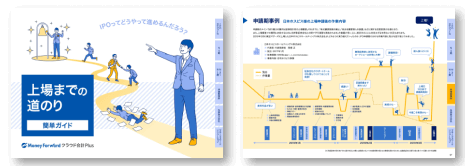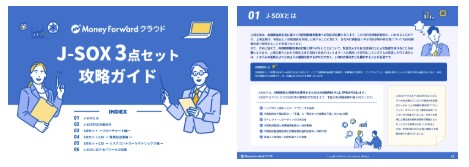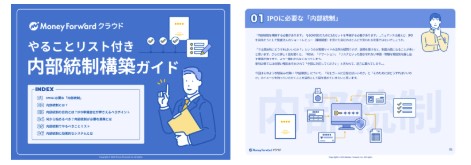- 作成日 : 2025年4月23日
非上場企業のストックオプション活用方法!導入の流れや会計処理を解説
ストックオプションは企業が役員や従業員に対して、あらかじめ決められた価格で将来自社株を購入できる権利を与える制度です。
将来的に上場(IPO)を目指している非上場企業がストックオプションを導入すれば、人材確保や従業員のモチベーション向上の手段として有効に働く可能性があります。
この記事では、自社にストックオプションを導入するための基礎知識やメリット・デメリット、会計処理などについて解説します。
目次
非上場企業におすすめ?ストックオプションの基礎知識
ストックオプションは、スタートアップなどの非上場企業が、IPO(新規株式公開)を目指す過程で導入することが多い制度です。
まずは従業員のストックオプションの活用例を、具体的に説明します。
たとえば自社へ転職した従業員に対して、入社時に「1株100円で買える権利」を5,000株分付与し、従業員が株を購入したとしましょう。
その後、会社が上場を果たし株価が500円に上がった場合、従業員は1株あたり400円の株価の含み益を得られることになります。
仮に5,000株分購入し売却すれば、従業員は200万円 = 400円(購入時100円との差額)×5,000(株)の売却益を得られます。
このように、従業員にとっては基本的にメリットのある制度ですが、会社としては制度の運用にデメリットがともなう部分もあるのです。
また、のちほど詳しく説明しますが、会計処理や税務上の取り扱いにも注意が必要です。
導入を検討する際は税理士や会計士へ相談するとよいでしょう。
非上場企業がストックオプションを導入する主なメリット
非上場企業がストックオプションを導入するメリットを、詳しく解説していきます。
従業員のモチベーションの向上につながる
ストックオプションの導入は、従業員のモチベーションの向上につながります。
企業としての成長(≒株価の上昇)が従業員の利益に直結し、株価が上がるほど従業員が受け取れる売却益も増えていくためです。
非上場企業が上場を果たして株価が値上がりすれば、従業員は数百万単位の売却益を得られる可能性もあります。
そのため、各従業員の業務への意欲が高まり全社的なパフォーマンス向上が期待できます。
一方で、上場後は株価の下落がモチベーションの低下を引き起こしてしまう懸念もあるため、注意が必要です。
採用強化につながる
ストックオプションの導入は採用強化にもつながります。
創業したての非上場企業では、給与水準の高い大手企業などと同額の給与を提示することが難しい場合があります。
しかし、ストックオプションを導入していれば、将来的に従業員は高額な報酬を得られる可能性があり、自社への応募を検討している人材に対して強いアピールポイントになるのです。
その裏付けとして、就職・転職サイトでは、検索時にストックオプションの有無を設定できるサイトも実際に存在しています。
優秀な人材を獲得しやすくなれば企業の成長スピードも加速し、より早い上場を目指せるようになるでしょう。
非上場企業がストックオプションを導入する主なデメリット
ストックオプションの導入にはデメリットもともないます。
付与の条件に差があると従業員間に不和が生まれる
ストックオプションの付与の条件に差があると、従業員間で不和が生じる可能性があります。
たとえば社内でストックオプションについての話題が活発になり、「Aさんは◯株分も持っているが、Bさんは少ししか付与されていないらしい」といった噂が広まると、従業員間に不満が広がりやすくなります。
その結果、従業員のモチベーションが逆に下がる可能性もあるでしょう。
そのため、ストックオプションを付与する際は納得感のある基準を設けておくことが大切です。
たとえば「勤続年数」や「役職」など、客観的な指標を基準にすると公平性を保ちやすくなります。
また、付与の基準が明確であっても、その内容が従業員に十分に伝わっていなければ不満が生まれる原因になります。
付与の目的や判断基準について、説明会を設けるなどして社内での合意形成を図るようにしましょう。
株式を売却したあと従業員が離職するおそれがある
ストックオプションの売却益を目的に入社した従業員が、上場後にすぐさま離職してしまうおそれがあります。
制度設計がしっかりしていないと、場合によっては短期間での大量離職へつながる場合もあります。
このような離職リスクを抑えるためには、一定の勤続期間が経過しないとストックオプションの権利を行使できない「ベスティング条項」の導入がおすすめです。
ベスティング条項では、毎年一定割合ずつしかストックオプションを行使できないよう定めることもできるため、従業員の定着に有効です。
適切な制度設計ができていないと「会社に愛着はなく上場後の売却益を得たらすぐに辞める従業員」や「短期的な利益のみを求める従業員」が社内に増える可能性があります。
長期的に働いてもらうためにも、書類選考や面接をしっかり行い、ミスのない制度設計をして離職リスクに備えましょう。
非上場企業がストックオプションを導入・行使する流れ
ここからは、非上場企業がストックオプションを導入・行使する流れを簡単に解説していきます。
1.募集要項の決定と通知
ストックオプションを発行するには、株主総会の特別決議で募集事項を決定する必要があります。
- 内容・数
- 無償発行の場合にはその旨
- 1個あたりの払込金額またはその算定方法
- 割当日
- 払込期日を定めるときは、その期日
引用:ストックオプションの導入を考えています。どのようにして導入を行えばよいのか、教えてください。 | ビジネスQ&A | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
株主総会で募集要項を決定したら、従業員にストックオプションの案内を行いましょう。
2.新株予約権の割当てと払込
新株予約権(ストックオプション)の申し込みを希望する従業員に対して、新株予約権の割当てを行います。
また、譲渡制限株式を扱う非上場企業の場合は、株主総会の特別決議で申し込み者への割当てを決定する必要があります。
新株予約権を申し込む従業員に対しては、商号、募集事項、払込取扱機関の3点を伝えましょう。
そして会社が新株予約権の割当てを行った後、有償ストックオプションの場合は、従業員からストックオプション発行時の価格の払込をしてもらいます。
払込は、募集要項で定めた期日までに行ってもらうようにしましょう。
なお、以前は従業員が証券口座を開設する必要がありました。
しかし、令和6年(2024年)の税制改正により、「発行会社自身による株式管理スキーム」が制定され現在は不要になっています。
ストックオプションの種類については、下記の記事で詳しく解説しています。
3.新株予約権原簿の作成
ストックオプションの発行が完了したその日から、企業は遅滞なく「新株予約権原簿」を作成し、以後も管理していく義務があります。
この原簿には、ストックオプションを付与された従業員や取締役の氏名や住所、付与された内容(数や権利行使価格など)を記載します。
4.登記手続き
ストックオプションを新たに発行した際、2週間以内に変更登記の申請が必要になります。
また、税制適格ストックオプションの場合は、ストックオプションの付与に関する調書を所轄の税務署長へ提出しなければなりません。
この調書の提出期限は、ストックオプションの付与から翌年の1月31日までとなっています。
手続きに不明点がある場合、自己判断をすると法律に違反するおそれもあるため税理士や公認会計士へ相談しましょう。
5.ストックオプションの行使
上記手続きの完了後、新株予約権を割当てた従業員から定められた行使期間内に、ストックオプションの権利の行使を受けます。
権利が行使されたら、信託銀行とやり取りして株式の発行処理を行いましょう。
また、発行会社自身による株式管理スキームの場合は、発行した株式は自社で管理します。
ストックオプションの権利を行使するか否かは従業員が任意に選択でき、新株予約権が割当てられていても、権利の行使は義務ではありません。
ストックオプションの制度設計時の注意点
ストックオプションの制度設計をする際、注意したいポイントを2つ解説します。
会社が上場しなかった場合の対応
会社が上場しなかった(できなかった)場合の対応を、あらかじめ決めておきましょう。
上場を見据えている会社がストックオプションを発行する際、権利行使の条件としてIPOを設定することが多いです。
この場合、会社が上場できなければ従業員はストックオプションの権利の行使ができず、権利行使期間を過ぎれば権利は消滅してしまいます。
そのため、会社が予定していた時期に上場できなかった場合、従業員は株式を得られず業務へのモチベーションが大きく低下するおそれがあります。
上場審査に落ちる理由は業績の未達や内部管理体制の不備などさまざまですが、いち早く原因を突き止め次回の審査を通過できるよう対策を行いましょう。
また、従業員へは今後の見通しを早急に説明し不安を取り除くようにするとよいでしょう。
非上場時にストックオプションの権利を持つ従業員が退職した場合の対応
ストックオプションの権利を持つ従業員が、上場前に退職した場合の対応も決めておきましょう。
上場前に従業員が退職してしまった場合の権利の取り扱いは、企業によってさまざまです。
たとえば行使条件を「在職中のみ」と定めておけば、従業員が退職後に権利を行使することはできません。
従業員にとっては残念かもしれませんが、上記のような制度設計であれば、離職を食い止め定着率の向上を促せる可能性もあります。
一方で企業によっては、これまでの社内での働きを労うために退職後も行使の猶予期間を設けるケースもあるでしょう。
ストックオプションは大きなお金が動く制度であるため、退職後の行使の可否が大きなトラブルに発展するおそれも十分あります。
最悪の場合、訴訟などの法的リスクが生まれる場合もあるため、自社の状況を踏まえて十分な検討を行いましょう。
非上場企業が知っておきたいストックオプションの会計処理
この章ではストックオプションの会計処理について、例を挙げて説明していきます。
会計処理に当たっては評価単価(適正な評価額)の決定が必要になり、上場企業の場合は株式市場の株価をベースに評価単価を計算します。
一方で非上場企業の場合は、純資産法やキャッシュ・フロー法といった評価単価の算定方法や、「本源的価値」での会計処理が可能です。
この記事内では本源的価値を使って計算していきます。
会計処理の計算式
本源的価値の計算式は下記になります。
▼本源的価値の計算式
※この例ではストックオプション発行時の株価(5,000円)ー権利行使価格(4,000円)=本源的価値(1,000円)と仮定
なお、今回の権利行使価格はセーフハーバールールに基づき、財産評価基本通達(国税庁が定めた相続や贈与において発生した財産の計算方法)で計算した、ストックオプション発行時の株式評価額です。
▼会計処理の例の条件
20名がストックオプションの権利を行使し、10名が権利を失効
上記の条件を基に、ストックオプションの会計処理について解説していきます。
また、ストックオプション発行時の株価が権利行使価格以下である場合、本源的価値がゼロになるため費用計上の必要はありません。
令和6年(2024年)の税制改正によりセーフハーバールールを導入する前は、費用計上を行うことは稀でした。
1.ストックオプションの付与~権利確定時
従業員や役員へのストックオプションの付与日から権利確定日までの間、期間に応じて会計処理が必要になります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| (株式報酬費用)30,000円 | (新株予約権)30,000円 |
この際の計算は、「対象者(30名)× 評価単価(1,000円)=30,000円」となります。
付与額は株式報酬費用として計上し、貸方の勘定科目は新株予約権とします。
また、権利確定条項がない場合や、権利確定日の予測ができない場合は付与日に費用の計上を行いましょう。
2.ストックオプションの権利行使時
20人がストックオプションの権利を行使した場合、下記のように会計処理を行います。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| (預金)80,000円 (新株予約権)20,000円 | (資本金)100,000円 |
計算方法は、「ストックオプションを行使した人数(20人)× 行使価格(4,000円)=80,000円」となります。
貸方には、預金と新株予約権の合計値を資本金として計上します。
3.ストックオプションの権利失効時
従業員が権利を行使しなかった場合の会計処理は下記のようになります。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| (新株予約権)10,000円 | (新株予約権戻入益)10,000円 |
計算方法は「権利を失効した従業員の数(10人)× 評価単価(1,000円)=10,000円」です。
ストックオプションの権利が失効したため、当初計上していた新株予約権を取り崩し、行使されなかった分の新株予約権戻入益を計上するという形になります。
ストックオプションのより詳しい会計処理の方法については、以下の記事を確認してみてください。
ストックオプションは自社にあった制度設計が重要
ストックオプションは従業員のモチベーション向上や優秀な人材の確保に役立つ一方で、公平性の確保や早期退職リスクの管理が課題になります。
上場を目指す企業にとって有用な制度ですが、会計処理や税務上の取り扱いは難しいため、専門家の力を借りて制度設計を行うとよいでしょう。
メリット・デメリットや導入の流れをよく理解して、自社に合った制度を構築していきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
リストリクテッド・ストックとは?概要やメリット、デメリット、導入事例などを解説
リストリクテッド・ストックは、企業の成長や役員・従業員のインセンティブを促進するために用いられ、資本調達や人材の確保・定着において重要なツールです。 そこで本記事では、概要から実際…
詳しくみる取締役とは?役割や責任・給与体系についてわかりやすく解説
取締役とは、会社法に定められている役員のことです。取締役は、企業における業務の執行について意思決定を行う立場にあるため、企業全体の業務について責任を負っています。 今回は、取締役の…
詳しくみるファントムストックとは?仕組みやメリット・デメリット、注意点などを解説
ファントムストックは、企業が役員や従業員に対して提供する金銭報酬の一種です。企業の成長に貢献した役員や従業員を評価し、モチベーションを高めるための仕組みです。この制度では、対象者に…
詳しくみるCXOとは?企業成長とIPO成功を導く戦略的リーダーについて解説
企業の成長と持続的な競争優位性を確立する上で、「CXO」と呼ばれる役職は不可欠な存在です。特にIPO(新規株式公開)を目指す企業においては、CXOの担う役割が戦略の成否を左右すると…
詳しくみる監査役とは?役割や権限、選任方法を解説【テンプレート付き】
上場企業では、企業の透明性・ガバナンスの向上と、株主や投資家、市場全体の信頼を獲得・維持することを目的に監査役を設置しています。未上場企業でも、IPOを目指す場合には監査役の設置が…
詳しくみるマネージャーとは?意味や役職・仕事・必要性や求められる能力・育て方を解説
マネージャーという言葉を仕事、スポーツ界、芸能界など様々な場面で耳にするのではないでしょうか。組織をマネジメントするにあたって、マネージャーは欠かせない存在です。この記事ではマネー…
詳しくみる