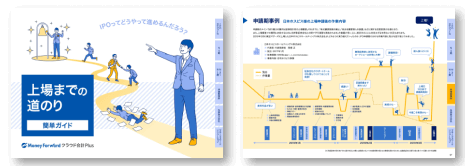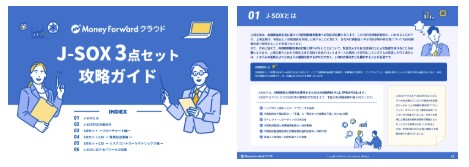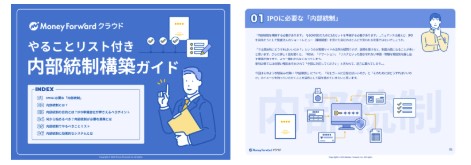- 作成日 : 2025年4月23日
ストックオプションの平均付与率は?基本から注意点まで徹底解説
ストックオプションを導入する際、平均でどれくらい付与するものなのか、わからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、実態調査に基づいた平均付与率をはじめ、制度の基本、導入のメリット・デメリット、注意点までを網羅的に解説します。
今後、ストックオプションの導入を検討する企業は、最適な制度設計を行うためにもぜひ参考にしてみてください。
目次
ストックオプションとは|自社株を決まった価格で買える権利
ストックオプションとは、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利です。
主に役員や従業員のインセンティブとして付与されます。株価が上昇した際に権利を行使することで、安く買って高く売ることができ、利益を得られます。税制適格ストックオプションであれば、株式取得時ではなく売却時にのみ課税される仕組みです。
ストックオプション制度は、1997年の商法改正で導入され、2002年からは新株予約権制度の整備により、導入企業が増加しました。
ストックオプションは、優秀な人材の確保やモチベーション向上につながる制度として、多くの企業で活用されています。導入にあたっては、制度の仕組みや税制の扱いを正しく理解することが重要です。
ストックオプションについては、下記の記事で詳しく解説しているためぜひあわせてご覧ください。
ストックオプションの平均付与率
ストックオプションの平均付与率とは、発行済株式総数に対して発行されているストックオプションの割合を指します。
東証の「コーポレート・ガバナンス白書2023」によると、公開会社全体の29.3%が制度を導入しており、グロース市場では79.7%と高水準です。
また、スタートアップ企業に関する「令和5年度産業経済研究委託事業」の調査では、非上場企業も含めて83.1%が導入しており、人材確保や資金調達の手段として活用されています。
参考:コーポレート・ガバナンス白書2023|株式会社 東京証券取引所
権利行使時期の実態
スタートアップ企業においては、税制適格要件を満たすため、ストックオプションの付与から2年経過後に権利行使を可能とする設計が主流であり、全体の55.1%を占めている結果となりました。
2年間の制限は、税制適格ストックオプションの必須要件である「付与決議日から2年以上経過後に行使可能」という規定に基づいています。
その他のケースでは、「付与から一定期間経過後(2年以外)」が8.7%、「上場から一定期間後」が31.9%を占めており、企業によって異なる設計が採用されていることがわかります。即時行使可能とする企業も一部存在しますが、割合は少数です。
また、「権利行使期間が2〜10年(未上場の創業5年未満企業は2〜15年)」という適格要件に対して、約40%の企業が課題を感じているという調査結果もあります。 とくに、ディープテック系企業などからは「現行ルールでは行使期間が短すぎる」との声が挙がっています。
上記のように、制度設計では税制適格を意識しつつも、事業特性に応じた柔軟な対応が必要です。
ストックオプションを導入するメリット
ストックオプションは、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上、企業成長への意識共有などに効果的な制度です。
導入の目的や得られる効果を正しく理解することが重要です。以下では、ストックオプションを導入するメリットについて紹介します。
1. 従業員のモチベーション向上につながる
ストックオプションを導入することで、従業員や役員のモチベーション向上が期待できます。
株価が上昇すれば利益を得られる仕組みのため、自社の業績向上に対する意欲が高まります。また、業績が伸びるほどストックオプションの価値も上がるため、日々の業務に対する責任感や目標意識が強くなるでしょう。
ストックオプション制度は社外の協力者にも付与が可能であり、当事者意識を高めるだけでなく、継続的な関係づくりにもつながります。
2. 優秀な人材の確保につながる
ストックオプション制度は、優秀な人材の確保を目的として導入されることがあります。
とくに資金に余裕のないスタートアップ企業では、現金報酬だけで人材を惹きつけることが難しい場合があります。将来的な株価の上昇によって得られる利益を報酬として提示できる点が魅力です。
ストックオプションは、値上がりを見込んだインセンティブとして機能するため、資金負担を抑えつつ人材を引きつけられます。また、在籍期間が長いほど有利になるため、早期離職の防止にも役立ちます。
3. 従業員にリスクがない
ストックオプション制度は、従業員にとってリスクの少ないインセンティブ制度です。
万が一、株価が下落しても、権利を行使しなければ損失は発生しません。自己資金による株式投資では、株価の変動によって購入時よりも価値が下がる可能性があり、価格変動リスクを伴います。
一方で、ストックオプションは、株価が将来上昇した際にのみ行使すればよいため、不利なタイミングでの行使を避けられます。従業員にとって、安心感のある制度といえるでしょう。
ストックオプションを導入するデメリット
ストックオプションは多くのメリットがありますが、一方で企業・従業員の双方に注意すべきデメリットも存在します。
制度を正しく運用するためには、リスクや課題も把握しておくことが重要です。以下では、ストックオプションを導入する際の各デメリットについて紹介します。
1. 株価の下落でモチベーションが低下する可能性がある
ストックオプション制度は、株価上昇による利益を期待できる一方で、株価が下落した場合にはモチベーション低下の原因となることがあります。
とくに、制度を魅力に感じて入社した従業員や取締役にとっては、オプションの価値が下がることで、期待していた経済的メリットが得られず意欲を失う可能性があるため注意が必要です。
企業の業績とは無関係に、外部環境や市場の変動によって株価が下落するケースもあり、従業員の意欲に影響を与えるリスクが存在します。
2. 権利行使後に社員が離職する可能性がある
ストックオプション制度を目的に入社した社員は、権利を行使して利益を得た後、会社にとどまる動機を失い退職する可能性があります。
とくに、離職の懸念がある社員が制度を利用し、キャピタルゲインを確保したタイミングで退職するケースも少なくありません。
社員がストックオプションを行使した直後に退職してしまう事態を防ぐには、制度設計に工夫が必要です。たとえば、一定期間の在籍を条件に行使を認めたり、在籍年数に応じて行使可能な権利数を段階的に増やしたりする方法が効果的です。
3. 既存株主が保有する株の価値が下がる可能性がある
ストックオプションの発行により、株主が保有する株式の価値が下がる可能性があります。
既存株主の保有する株の価値が下がる理由は、発行済株式数が増えることで1株あたりの価値が希薄化するためです。ストックオプションの発行には、原則として株主総会の決議が必要ですが、発行数や対象範囲によっては希薄化の影響が大きくなる場合があります。
そのため、発行にあたっては慎重な判断が求められます。
ストックオプションを活用する際の注意点
ストックオプションは効果的な制度ですが、設計や運用を誤るとトラブルや課税リスクにつながる可能性があります。制度の仕組みや法的要件を正しく理解し、慎重に活用することが重要です。
以下では、ストックオプションを活用する際の注意点について紹介します。
ストックオプションの影響力については下記の記事で詳しく説明しているため、ぜひ参考にしてみてください。
1. 株価が安いうちに発行する
ストックオプションの権利行使価額は、発行時点の株価を基準に設定されます。そのため、株価が安いうちに発行しておけば、将来的に株価が上昇した際に得られるキャピタルゲインが大きくなります。
資金調達のために増資を予定している場合は注意が必要です。増資によって株価が大きく上昇すると、増資後に発行されるストックオプションの魅力が低下する可能性があります。
制度の効果を最大化するには、株価が上がる前の発行が重要です。
2. 発行数に上限がある
ストックオプションの発行数には法令上の明確な上限はありません。しかし、株主総会の承認が必要であり、実務上は一定の制限を設ける企業が多くみられます。
発行割合が大きすぎると、既存株主の持ち株比率が下がり、株式価値の希薄化につながるため、株主の利益を損なうリスクがあります。
そのため、誰に・いつ・どれだけのストックオプションを発行するかは、将来的なIPOの設計を踏まえて慎重に検討することが重要です。過度な発行は制度の信頼性を損ねるため、バランスの取れた運用が求められます。
3. 1回で発行する
ストックオプションの発行回数には、法的な制限はありませんが、むやみに複数回に分けて発行すると税制上の問題が生じる可能性があります。そのため、できるだけ1回でまとめて行うことが望ましいとされています。
税制適格ストックオプションの要件は発行のたびに確認が必要であり、各回の株価に応じた適切な権利行使価額を設定しなければいけません。
たとえば、1回目の発行時点で株価が100円でも、その後の増資により株価が200円に上昇した場合、2回目・3回目の発行では新たな株価を基準にする必要があります。要件を満たさなければ税制非適格とみなされ、課税額が増えるリスクもあるため注意が必要です。
4. ストックオプション導入を長期的に考える
ストックオプションを導入する際は、短期的な効果だけでなく、長期的な視点で制度設計を行うことが重要です。
一度発行すると影響は数年間にわたって続くため、会社の中長期的な事業計画や将来の資本政策と整合性が取れているかを確認する必要があります。
発行タイミングや付与対象、発行数などは、将来の資金調達やIPOにも関わるため慎重な検討が必要です。また、制度の運用にあたっては、専門家の意見を取り入れることでリスクを最小限に抑えられます。
5. ストックオプション付与の基準を明確にする
ストックオプションを活用する際は、付与の基準を明確に定めることが重要です。
対象者の選定には、会社への貢献度や勤続年数など、客観的で納得感のある指標を用いる必要があります。基準が曖昧なまま運用すると、権利を得られなかった従業員の間で不公平感や不満が生じ、組織の士気低下につながる可能性があります。
とくに成長段階の企業においては、限られたリソースを適切に配分するためにも、誰に・なぜ付与するのかを事前に説明できる設計を立てることが重要です。
ストックオプションの導入は平均付与率にとらわれない設計をしよう
ストックオプションの平均付与率は参考になりますが、平均だけをみて基準に設計するのは危険です。
企業の成長フェーズや採用戦略、人材の貢献度などによって、最適な付与の形は大きく異なります。重要なのは、制度の目的を明確にし、自社にとって本当に効果的なストックオプションのあり方を見極めることです。
平均にとらわれず、戦略的な制度設計を意識しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
上場までの道のりかんたんガイド
はじめてIPO準備を行う企業向けに上場までの流れに加え、フェーズごとの課題とその解決策を解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、上場フェーズごとの必要な動きについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
執行役員とは?取締役や管掌役員との違いについて解説!
執行役員とは、取締役が決めた経営方針に従い、業務を執行する役職です。役員という名前のため間違えやすいですが、会社法で定義された役員ではなく、各企業が任意で設置します。執行役員の定義や役割、取締役や管掌役員との違いに加え、執行役員制度を導入す…
詳しくみるフィードバックとは?意味や効果的なコツ、企業の実践例についてわかりやすく解説
ビジネスにおいて、フィードバックはとても重要です。実際、さまざまな場面でフィードバックが行われています。しかし、フィードバックを行う方法やメリットを理解して利用されているでしょうか。 今回は、ビジネスにおけるフィードバックの目的、フィードバ…
詳しくみるエンゲージメントサーベイとは?目的や効果、実施方法を解説
エンゲージメントサーベイとは、従業員のエンゲージメントを可視化するアンケート調査のことです。適切な質問項目を設定し、結果を分析することで自社の課題解決に活かせます。 今回はエンゲージメントサーベイの概要や進め方、無駄にしないポイントなどを解…
詳しくみるIPOの成功を左右する組織作りとは?組織戦略のポイントを解説
IPO(新規株式公開)は、企業の成長における重要なステップであり、資金調達や企業の知名度向上など、多くの利点をもたらします。 このIPOを成功させるには、単なる財務戦略や上場手続きだけでなく、組織体制の適切な整備も必要です。組織体制が整って…
詳しくみる攻めの経営を促す役員報酬のインセンティブプランについて解説
現代のビジネス環境は変化のスピードが加速し、企業に「攻めの経営」が求められています。 単なるコスト削減や効率化では競争に打ち勝つことは困難で、中長期の企業価値向上を見据えて、役員報酬のインセンティブプランを策定する必要があるでしょう。 そこ…
詳しくみるムーンショット目標とは?制定された背景や企業との関わり
ムーンショット目標とは、内閣府の政策の一つであるムーンショット型研究開発制度において掲げられている、9つの目標のことです。日本が抱える問題を解決するために破壊的イノベーションの創出を目指す目標で、2024年または2050年までの実現を目指し…
詳しくみる