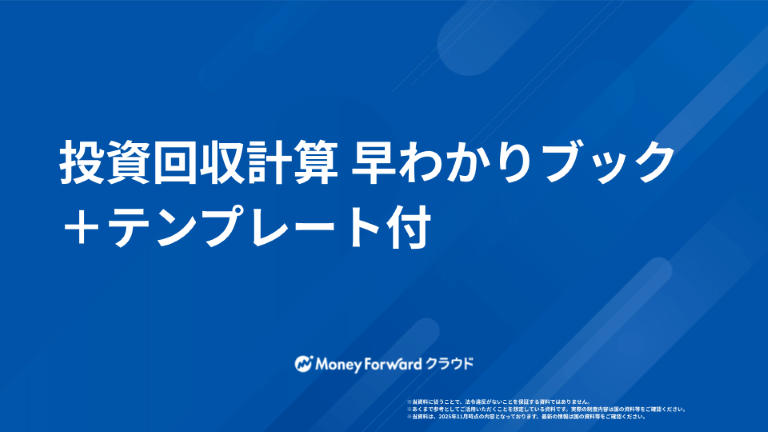- 更新日 : 2024年7月17日
投資回収計画とは?投資回収期間の目安や計算式・評価方法を解説【テンプレート付き】
事業を成功に導くためには、明確な計画と的確な実行が不可欠です。その中でも、投資回収計画書は、事業の採算性を判断し、投資の回収期間を明確にするための重要なツールです。投資家にとって適切な計画書は、投資対象の収益性を見極め、資金の流れを明確にするために欠かせません。
本記事では、投資回収計画書の概要や計算方法、作成方法について詳しく解説します。
目次
投資回収計画とは

投資回収計画とは、投資を実行した際にその資金をどのように回収するかを詳細に示す計画のことです。
投資回収計画は、まず投資対象の詳細な分析から始まります。これには、市場調査や競合分析、対象事業の収益性の評価が含まれます。
こうした分析を通じて、投資がどの程度のリターンを生み出すかを予測し、それに基づいて計画を策定します。
投資回収期間の目安

投資回収期間の目安は、企業の規模や資本力により異なります。従来、投資回収期間は5年前後が一般的でしたが、現在の不透明な経済環境では長期的な投資判断がリスクを伴います。
特に中小企業では、投資回収期間は2年以内が望ましいとされていますが、資本力が不十分な場合には予定が延びる可能性があり、経営が悪化するリスクも高まります。
そのため、投資回収期間は1年以内の短期を目指すことが、長期化による経営体力の消耗を防ぐために有効です。
投資回収期間の計算方法

投資回収期間の計算式は、以下のとおりです。
まず、投資総額を明確にすることが重要です。投資総額には、初期投資費用だけでなく、投資後に必要となる運転資金や追加のコストも含まれます。
例えば、新しい設備を導入する際には、その購入費用だけでなく、設置費用やメンテナンス費用も投資総額に含める必要があります。
次に、年間キャッシュ・フローを計算します。年間キャッシュ・フローは、その投資によって得られる年間の現金獲得額を指し、それは、総収益から減価償却費を除いたの経費を差し引いたものであり、実際に手元に残る現金です。
ここで重要なのは、正確な収支予測を行うことです。市場調査や過去のデータ分析を基に、現実的な収支見通しを立てる必要があります。
投資回収期間は、投資総額を年間キャッシュ・フローで割ることで求められます。例えば、投資総額が1000万円で、年間キャッシュ・フローが250万円である場合、投資回収期間は1000万円を250万円で割った4年となります。
この計算により、投資が何年で回収できるかを明確に把握できます。
設備投資の採算性の評価基準

投資回収ができているか、設備投資の採算性を評価する基準は、主に以下のとおりです。
【採算性の評価方法】
- 回収期間法
- 正味現在価値(NPV)法
- 内部利益率(IRR)法
- 投資利益率(ROI)法
詳しく解説します。
回収期間法
回収期間法は、投資した金額をどれくらいの期間で回収できるかを計算することで、投資の妥当性を評価します。
回収期間法で用いる計算式は、以下のとおりです。
回収期間法は、まず投資総額と年間キャッシュ・フローを把握することから始まります。投資総額には、設備の購入費用、設置費用、運転資金など、投資に関わるすべての費用が含まれます。
一方、年間キャッシュ・フローは、投資によって生み出される年間の純利益を指します。これは、収益からすべての運営費用や維持費を差し引いた金額です。
具体的な計算は、投資総額を年間キャッシュ・フローで割ることで行います。例えば、投資総額が5000万円で、年間キャッシュ・フローが1000万円の場合、回収期間は5000万円を1000万円で割った5年となります。これにより、投資が5年で回収できることがわかります。
正味現在価値(NPV)法
正味現在価値(NPV)法は、投資によって得られる価値を示す指標です。
計算方法は、以下のとおりとなります。
まず、正味現在価値法は、将来得られるキャッシュ・フローを現在価値に換算するための割引率を設定することから始まります。この割引率は、企業の資本コストや期待される投資収益率などを考慮して決定されます。割引率が高いほど、将来のキャッシュ・フローの現在価値は低くなります。
次に、投資から得られる年間キャッシュ・フローを年度ごとに割引率で割り引いて現在価値を算出します。
例えば、将来のキャッシュ・フローが年間1000万円で、割引率が5%の場合、1年目のキャッシュ・フローの現在価値は約952万円(1000万円÷1.05)、2年目のキャッシュ・フローの現在価値は約907万円(1000万円÷1.05^2)となります。
その後、すべての将来キャッシュ・フローの現在価値を合計します。この合計額から初期投資額を差し引くと、正味現在価値(NPV)が求められます。NPVが正であれば、その投資は収益を生むと判断され、負であれば投資の採算性は低いと判断されます。
例えば、将来キャッシュ・フローの現在価値の合計が5000万円で、初期投資額が4000万円の場合、NPVは1000万円となり、これは投資が収益を生むことを示します。
内部利益率(IRR)法
内部利益率(IRR)法は、投資から得られる将来のキャッシュ・フローの現在価値の合計が投資総額と等しくなる割引率を求める方法です。
計算式は、以下のとおりです。
内部利益率は、投資総額と将来キャッシュ・フローの現在価値の合計が等しくなる割引率です。例えば、ある設備投資の初期費用が1000万円で、将来5年間にわたって毎年300万円のキャッシュ・フローが得られるとします。
この場合、内部利益率は、そのキャッシュ・フローの現在価値の合計が1000万円になるような割引率を計算することで求められます。
まず、初期の割引率を設定し、キャッシュ・フローの現在価値を計算します。次に、計算結果が投資総額に等しくなるように割引率を調整していきます。このプロセスを繰り返すことで、正確な内部利益率が求められるのです。
内部利益率法の利点は、投資の収益性を一つの数値で示すため、他の投資案件との比較が容易である点です。
また、IRRが企業の資本コストを上回る場合、その投資は採算が取れると判断できます。例えば、企業の資本コストが5%で、IRRが8%であれば、その投資は収益性が高いと見なされます。
しかし、内部利益率法にも限界があり、特にキャッシュ・フローのパターンが複雑な場合や複数の内部利益率が存在する場合、IRRの計算が難しくなることがあります。
さらに、IRRは割引率の1つの目安でしかなく、他の経済的要因やリスクを考慮しないため、総合的な判断が必要です。
投資利益率(ROI)法
投資利益率(ROI)法は、投資に対するリターンを測定する指標であり、投資の成果を評価するために広く用いられています。
計算方法は、以下のとおりです。
まず、投資によって得られる利益を明確にします。これは、投資対象から得られる総収益から、運営費用や維持費用などの関連コストを差し引いた純利益です。例えば、新しい設備を導入することで年間1000万円の追加収益が見込まれ、運用費用が200万円かかる場合、純利益は800万円となります。
次に、投資総額を確認します。投資総額には、設備の購入費用、設置費用、運転資金など、投資に関連するすべての費用が含まれます。例えば、設備の購入費用が5000万円であれば、これが投資総額となります。
ROI=800万円÷5000万円×100=16%
この計算結果から、投資利益率は16%であることがわかります。つまり、投資総額の16%のリターンが得られるという意味です。
IPOには投資回収計画書の作成が必須

投資回収期間を短くするためには、実現可能な長期的な経営方針やビジョンを計画した経営計画書を作成することが重要です。
経営計画書は社内で目標を共有するだけでなく、銀行や出資者などのステークホルダーに対するアピール材料としても利用できます。
会社設立時だけでなく、重要な節目での振り返りや見直しの際にも、経営計画書を作成することが必要です。
投資回収計画書(IRR)テンプレート-無料ダウンロード
投資回収計画書を作成するとなれば、フォーマットを1から作成し、記入していかなければなりません。
しかし、テンプレートを利用することで、あらかじめ用意されているフォーマットに必要事項を記入するだけで作成できるため、工数を大幅に削減できます。
以下から無料で投資回収計画書のテンプレートを活用できるので、ぜひダウンロードしてみてください。
まとめ
投資回収計画とは、投資した資金をどのように回収するかを示す計画で、市場調査や競合分析を基に策定します。
従来、投資回収期間は5年前後とされていましたが、昨今では不景気が続いていることから、1年以内の短期間での計画をするのがおすすめです。
適切な計画書は、投資対象の収益性を入念にチェックでき、資金の流れを明確にして事業拡大を測れるようになります。
正確な投資回収計画書を作成し、事業拡大を図りましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務管理3つのポイント
IPOに向けて資金調達を行いたくても、財務管理に課題があると資金調達がスムーズに進まないことも少なくありません。
本資料では、財務管理を効率よく行うための3つポイントとVCに聞いたレイターステージのリアルなチェックポイントを解説します。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
N-3期を目指すための3つのポイント
「N-3期を目指しているが、数年たっても次の段階へ進めない」とお悩みのIPO準備企業も多いのではないでしょうか。
本資料では、IPO準備スケジュールの全体像から、N-3期に目指す上でよくある課題とおさえておきたい3つのポイントを解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けの業務効率化と内部統制強化を実現するクラウド会計ソフトです。
銀行やクレジットカード連携で取引データを自動取得、AIによる自動仕訳で会計業務を効率化。周辺システムと連携することで、二重入力や確認工数を削減します。また、仕訳承認機能やユーザーごとの権限・ログ管理機能を搭載しており、内部統制にも対応。SOC報告書も提供しています。
よくある質問
投資回収計画とは?
投資回収計画とは、投資を実行した際に資金の流れを明確にした計画書のことです。 投資がどの程度のリターンを生み出すかを予測し、戦略を策定するために必要となります。
投資回収にかかる期間は?
従来、投資回収期間は5年前後が一般的でしたが、現在の経済環境があまり良くないことを考えると、1年以内と短期間に設定するのがおすすめです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
加重平均資本コスト(WACC)とは?計算式や手順・平均についてわかりやすく解説
加重平均資本コスト(WACC)は、企業の投資判断や事業評価に重要な指標であり、その理解と適切な活用は企業の財務戦略を立てる上で不可欠です。ビジネスをしていく上では、負債コストと株主…
詳しくみるファクタリングに担保は必要?ABLとの違いや利用するメリットを解説
ファクタリングは担保不要で利用できるため、動産・債権担保融資(ABL)とは異なる資金調達の手法です。迅速に融資を受けられる点と信用力がない企業でも利用できる点が主なメリットです。 …
詳しくみるベンチャーキャピタルとは?種類、メリット・デメリットなどを解説
ベンチャー企業がスタートする際に直面する大きな課題の一つは資金調達だと考えられます。この課題に対処する手段として、ベンチャーキャピタルからの資金調達が挙げられます。 本記事では、ベ…
詳しくみるエンジェル投資家とは?メリット・デメリットや探し方、出資相場を徹底解説
創業したばかりのスタートアップにとって、資金調達は最初の難関です。その有力な選択肢として注目されるのが「エンジェル投資家」です。 本記事では、エンジェル投資家の定義やベンチャーキャ…
詳しくみるIPO(新規上場)の必要資金は?上場準備や維持にかかる費用も解説
企業が上場する際、フェーズごとに多額の費用が発生し、支払先も多数存在します。IPOへの参加を検討する際、どれほどの資金が必要かを正確に理解することは、資金計画の立て方に影響を与える…
詳しくみるシリーズAとは?投資ラウンドの意味や調達額・シリーズBとの違いを解説
スタートアップにとって資金調達は、事業を成長させるうえで非常に重要な業務です。しかし、資金調達=資本関連の意思決定は後で修正がきかないものが多く、ポイントをよく理解したうえで決定し…
詳しくみる