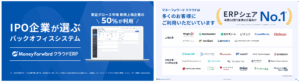- 更新日 : 2024年7月17日
戦略立案に欠かせない競合分析とは?目的や実施手順などを解説【テンプレート付き】
「競合」を分析する機会は、ビジネスにおけるさまざまな場面に存在します。営業担当者が顧客に提案する際にライバルを分析する場合や、経営層が中長期の戦略を描く場合、商品開発者が新ブランドを起案する場合などが挙げられます。
したがって、競合分析はほとんどのビジネスパーソンにとって必須のスキルであるといっても過言ではありません。本記事では、その競合分析の目的や実施方法など、全体像を解説します。
目次
競合分析とは
まずはじめに、競合分析を行うための目的や位置付けを解説します。
競合分析の目的
競合分析は基本的に、自社の新サービスや既存製品などがシェアを獲得するために、ライバル企業・製品との違いを見出すことを目的とします。
言い換えれば、競合分析によって自社の強みや弱みを明確化することが重要です。
競合分析の位置付け
新サービスや既存製品、または全社戦略を検討する際など、現状を分析し今後の方針・戦略を決める機会は多く存在します。そのステップは、基本的に大きく次の3段階に分かれるといえるでしょう。
1. マクロ環境分析:PEST分析、ファイブフォース分析など
2. 市場環境分析:3C分析、SWOT分析など
3. 戦略・戦術策定:STP、4Pなど
まずはマクロ環境分析によって、既存のルールや習慣を大きく変えうる要素、および現状の市場構造を特定します。
次に、自社の立ち位置や顧客のニーズ、競合の状態から、進むべき方向性を明らかにするために市場環境の分析を行います。競合分析とは、主にこの市場環境分析に位置付けられることが一般的です。
最後に、どの市場で戦い、どうやって勝っていくかについての戦略および戦術を策定し、進むべき方向性を示します。
競争戦略とブルーオーシャン戦略
次に、競合分析によって示唆される戦略の方向性として、競合の種類を確認した上で代表的な2つのテーマを紹介します。
「競合」の種類
単に「競合」といってもその意味するところは幅広く、大きくは直接競合と間接競合、代替競合の3つに分けられます。
まず直接競合とは、同じサービス・製品群で展開するプレイヤーのことを指し、3つの分類の中で最もイメージがしやすいでしょう。例えば、トヨタにとっての日産自動車やホンダなどが挙げられます。
次に間接競合とは、同じサービスや製品カテゴリーではあるものの、直接的にシェアを奪い合う機会が少ない相手のことです。上記と同じトヨタを例にすると、高級車メーカーやスポーツカーメーカーなどが該当します。
最後に代替競合とは、同じカテゴリーではないものの顧客の視点に立った際に、その検討の選択肢として並列されるものが含まれます。トヨタにとってはタクシーやバス、電車などがその例だといえるでしょう。
競合分析による2つの戦略の方向性
競合分析を行った結果、示唆される方向性としては主に次の2つが挙げられます。
1. 競争戦略:コストや付加価値によって、既存のプレイヤーと差別化する戦略
2. ブルーオーシャン戦略:全くの新市場やカテゴリーを創出する戦略
競争戦略
競争戦略とは、マイケル・ポーター教授によって提唱された概念で、現代のビジネスにおいて頻繁に用いられています。
基本的には直接競合や間接競合のプレイヤーに対して、低コストまたは高い付加価値で差別化を行い、シェアの獲得を狙う戦い方を採ります。例えば、スターバックスが自社の製品に高付加価値を付与することで、ドトールなどの直接競合に対して差別化を行うことなどが挙げられるでしょう。
競争戦略はさらに、幅広いターゲットに対して低コストまたは高付加価値を狙うか、ニッチなターゲットに対して行うかで4パターンの戦略に細分化することも可能です。
ブルーオーシャン戦略
競争戦略は既存のカテゴリーの中でどのように戦うかを示すのに対し、完全に新しい市場を作る場合の戦略としてはブルーオーシャン戦略が挙げられます。
これは主に、直接競合や間接競合よりも代替競合を意識して、新しい市場の創造を狙う戦い方です。例えば、アメリカのサウスウエスト航空が、従来の「飛行機は長距離移動手段である」という視点のみならず、機内サービスなどを最低限にし、車や電車の代替として中短距離の移動を安く行うことに焦点を当てて、LCC市場を創ったことなどが良い例です。
このようなブルーオーシャン戦略は基本的に競争戦略と異なり、低コストと高付加価値の両方を狙う方向性を示唆します。
競合分析の実施方法
続く本章では、競合分析を実際に行う際のステップやフレームワークを解説します。
検討ステップ
競争戦略およびブルーオーシャン戦略ともに、大枠としては先述のマクロ環境から始まり、市場環境分析、戦略・戦術の策定の流れを経ることは変わりません。
その中でも競合を分析する際の方法について、競争戦略とブルーオーシャン戦略に分けて詳しく解説します。
競争戦略における競合分析の手順
競争戦略において競合分析を行う際は、直接競合・間接競合を中心に下記の7つのステップを踏むことがおすすめです。
1. 直接および間接競合の企業を特定しリストアップする
2. 比較したい指標・項目を選定する(例:価格、ターゲット顧客、品質など)
3. リストアップした競合ごとに、比較指標・項目に関する情報を収集する
4. 自社も含めて競合とのマッピングを行い、ポジションを可視化する
5. 競合と比較した自社の強みと弱みを明確化する
6. 市場の機会や脅威も見据えた上で、低コストか高付加価値か、自社が戦うべきポイントを特定する
7. 具体的に達成するためのアクションプランを策定する
ブルーオーシャン戦略における競合分析の手順
ブルーオーシャン戦略においては、まず代替競合を特定する必要があるため、競争戦略とは異なる下記の5つのステップを踏むことが一般的です。
1. 検討カテゴリーにて既存サービスや製品が提供している機能の要素を洗い出す(例:航空業界なら、価格・機内食・手荷物預かり・座席の広さ・座席のランクなど)
2. 代替競合となるサービスや製品を特定する
3. 顧客目線で、既存の製品やサービスにも代替競合にもない要素を抽出する(例:便の本数など)
4. 上記の追加要素を提供するにあたって、減らしたり取り除いたりすることができる要素を見極める(例:サービスの質・座席の快適さなど)
5. その要素を実現するためのアクションプランを策定する
代表的なフレームワーク
続いて、上記の競合分析を進めるために有効なフレームワークをいくつか紹介します。
競争戦略 – 競合分析に関するフレームワーク
- ファイブフォース分析:買い手と売り手の交渉力、新規参入と代替品の脅威、既存競合の競争性の5つの観点で分析を行い、業界構造や業界的な利益率の高低を見極める
- 3C分析:市場(Customer)・自社(Company)・競合(Competitor)の観点から分析を行い、市場の動向や成功要因などを特定する
- SWOT分析:自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)・市場の機会(Oppotunity)・脅威(Threat)の4つの要因を分析し、現状を把握した上で進むべき方向性を見出す
ブルーオーシャン戦略 – 競合分析に関するフレームワーク
- 戦略キャンバス:先述のように機能を洗い出し、横軸に項目を並べ、縦軸にその提供レベルを設定しグラフ化する
- アクション・マトリックス:洗い出した機能に対して、取り除く・減らす・増やす・付け加えるの4つのアクションを検討する
競合分析のテンプレート – 無料でダウンロード
本記事の最後に、上記で解説してきたステップを、より簡易的かつ汎用的に行うためのテンプレートを紹介します。
本テンプレートを基準にしながら、ここまでのポイントを加えてアップデートし、自社に最適な競合分析を行うための資料としてご活用ください。
まとめ
競合といっても、直接競合や間接競合、代替競合などの種類が存在し、どの競合を意識するかで戦うべき方向性も異なります。
その方向性は大きく競争戦略とブルーオーシャン戦略に分けられるため、新サービスや既存製品がどちらを向くべきかを見定めることが肝要です。
両アプローチによってステップや用いるフレームワークも異なるため、それぞれの違いを意識しながら、適切な競合分析を実践できるようになりましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
マネーフォワード クラウドERP サービス資料
マネーフォワード クラウドERPは、東証グロース市場に新規上場する企業の半数※1 が導入しているクラウド型バックオフィスシステムです。
取引データの自動取得からAIによる自動仕訳まで、会計業務を効率化。人事労務や請求書発行といった周辺システムとも柔軟に連携し、バックオフィス業務全体を最適化します。また、法改正に自動で対応し、内部統制機能も充実しているため、安心してご利用いただけます。
※1 日本取引所グループの公表情報に基づき、2025年1月〜6月にグロース市場への上場が承認された企業のうち、上場時にマネーフォワード クラウドを有料で使用していたユーザーの割合(20社中10社)
【期間限定】会計ソフトの移行費用を最大70万円分還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
キャンペーンの対象条件やサポート内容など、詳細は下記バナーよりご確認ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マザーズから東証一部への昇格条件は?新市場区分の上場条件を説明
「マザーズから東証一部へ昇格するにはどうすればいい?」と疑問に思っている経営者の方も多いのではないでしょうか?マザーズから東証一部へ昇格するには、一定の条件をクリアする必要がありま…
詳しくみるIPO時に必要な株価算定とは?各手法や実施するタイミングなど全体像を解説
自社の株式価値を外部に示さなければならないシーンは、スタートアップの経営者にとって少なくないでしょう。投資ラウンドでの資金調達やM&A、事業承継、上場時など、未上場の企業で…
詳しくみるKPIとは?ビジネスにおける指標をわかりやすく解説!
PointKPIの役割とは? KPIとは、最終目標達成に向けた業務プロセスの進捗や成果を定量的に可視化する重要な指標です。 KGI達成に向けた中間指標 SMART原則で設計が基本 …
詳しくみる上場ゴールとは?意味や要因、回避するためのポイントを解説
上場ゴールとは、IPOに際する利益獲得を目的に上場したと見られる状況を揶揄する表現です。経営陣が売却益の獲得をゴールに見据えて上場することはもちろん、ノウハウや能力不足でも上場ゴー…
詳しくみるブックビルディング方式による株価の決定とは?特徴や入札方式との違いなどを解説
Pointブックビルディング方式の特徴は? ブックビルディング方式とは、投資家の需要に基づいて株式の公募価格を決定するIPO時の主流な価格設定方法です。 仮条件内で投資家が申告 需…
詳しくみる2022年4月に廃止された「一部上場企業」とは?再編成後の市場区分も紹介
一部上場企業とは、東京証券取引所の市場第一部に株式を公開した企業を指す言葉です。2022年に4月に廃止となったと知っていても、現在はどのような分類になっているのか、疑問を持っている…
詳しくみる