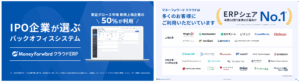- 作成日 : 2024年7月29日
危機管理広報とは 重要性やプロセス、成功のポイントを解説
危機管理広報とは、自然災害や不祥事などの危機発生時に行う広報対応を指します。スピーディーかつ真摯な態度での広報対応により、企業のイメージ低下を防ぎやすくなります。
本記事では、危機管理広報の重要性や事前準備、危機発生時の対応プロセスなどを解説します。また、危機管理広報を成功させる4つのポイントも紹介します。
目次
危機管理広報とは
はじめに、危機管理広報の定義と重要性を解説します。
危機管理広報の定義
危機管理広報とは、自然災害や事件、不祥事などの危機が発生した際にに行う広報PR対応です。またその対応を行う部門や担当者を指すこともあります。
危機管理広報の重要性
危機管理広報は、発生した危機による悪影響を最小限に抑えて、企業のイメージ低下や事業停止などの事態を回避する目的で行います。
企業活動は、常に自然災害や事件・事故のリスクにさらされています。また、それらの対策を施しても労働災害や企業不祥事(データ改ざんや不正会計など)が発生するリスクを0にすることはできません。
こうした危機が顕在化した際の広報を適当に行うと、投資家などのステークホルダーのみならず、社会や世論から批判を受ける恐れがあります。特に近年は、SNSの普及によりちょっとした不用意な発言が大きく波及し、企業イメージの低下を招く事態も想定されます。
こうした事態を避けるためにも、企業にとって適切な危機管理広報が不可欠です。
危機管理広報に関する事前準備
危機管理広報を行うにあたっては、危機が顕在化する前の事前準備が不可欠です。具体的には、以下の3つの業務を行います。
リスクの把握と評価
危機管理広報の業務では、想定されるリスクを全て洗い出し、それぞれの重大度を評価する必要があります。
どのような危機が生じ得るかを事前に把握することで、いざというときに的確な方法・内容で広報を行いやすいためです。また、重大度を特定し各リスクに優先順位をつけることで、同時多発的に複数の危機が生じた際に、効果が大きいものから迅速に実行し被害を最小限に留めやすくなります。
広報担当者だけでなく、実際の職場(工場やオフィスなど)で働く人の意見を参考にすると、抜け漏れなくリスクを把握することができます。
マニュアルの策定
リスクを把握したら、広報視点で危機対応のマニュアルを策定します。
具体的には、危機発生時における各従業員の対応や役割、責任者、広報(情報発信)のツールや方法、情報収集のプロセスなどを盛り込みます。事前にマニュアル化しておくことで、危機発生時に迅速かつ円滑な対応が可能となります。
社内関係者に向けたトレーニングの実施
マニュアルを策定したら、日頃から社内関係者に広報のトレーニングを実施しておくことも重要です。日頃から訓練していないと、メディア対応で不用意な発言を行うなどして、企業イメージの低下を招く恐れがあるためです。
危機管理広報のプロセス・業務内容
実際に危機が発生した場合、危機管理広報として以下の業務を実施します。
1.代表者や責任者への連絡
2.情報収集および現状把握
3.対応方針の策定
4.情報開示
5.事実誤認の確認と訂正
この章では、危機管理広報として行う業務内容を上記の流れに沿って解説します。
手順1:代表者や責任者への連絡
危機が発生したら、即座に組織や企業の代表者(または責任者)に連絡します。
代表者の指示によって緊急対策本部が設置され、それ以降は本部が情報収集や各種対応を一手に担います。
代表者指揮によって危機対応の窓口を一本化することで、情報の錯綜や混乱を回避することができます。
手順2:情報収集および現状把握
次に、発生した危機に関する情報収集および現状把握を実施します。
発生現場に足を運び、事情を知る社員などから直接ヒアリングすることが重要です。情報収集に際しては、以下の着眼点に沿って現状を整理します。
- 事実の把握(何が、どこで、いつ、どのように発生し、どのような被害が生じたのか)
- 責任の所在
- 発生原因
- 追加で発生し得る危機の有無
上記事項を把握したら、緊急対策本部を中心に関係者全員で共有を図ることが重要です。
手順3:対応方針の策定
事実を把握したら、それに沿って今後の対応方針を策定します。
具体的には、情報開示・謝罪の方法やコメント内容、企業方針、再発防止策などを検討し、これらの事項をまとめた「ポジションペーパー」を作成します。作成したポジションペーパーは、弁護士などの専門家からチェックしてもらうことが一般的です。
なお、日頃から想定される対応方針や報道用資料のひな型などを作成しておくと、よりスピーディーに方針を策定できる可能性があります。
手順4:情報開示
方針策定が完了したら、それに沿って情報開示を行います。
自社HPにおける報道用資料(プレスリリース)の公開や緊急記者会見(必要であれば)などを実施します。
手順5:事実誤認の確認と訂正
SNSやニュース、新聞などにおいて、事実を誤認されていないかをチェックします。
仮に事実と異なる情報が報道されたりSNSで拡散されたりした場合、企業イメージの低下を招く恐れがあるためです。事実と異なる内容を見つけた際には、報道機関やSNSアカウントの持ち主などに連絡し、修正を依頼します。
危機管理広報を成功させる4つのポイント
危機管理広報の対応を誤ると、かえって企業イメージの低下につながるリスクが高まります。こうした事態を防ぎ広報活動を成功させるには、以下4つのポイントを押さえることが重要です。
ポイント1:スピーディーに情報開示する
危機管理広報では、迅速な情報開示が最も重要です。
なぜならば、重大な危機であるほど、開示が遅れた際に企業イメージやブランド力の低下につながりやすいためです。またSNSなどで事実無根の情報が拡散されてしまい、イメージ低下に拍車をかける恐れもあります。
遅くとも危機発生から8時間以内、人命などを左右する場合は2〜4時間以内の公表が望ましいでしょう。
ポイント2:誠実で真摯な対応を徹底する
スピードと同じくらい重要なのが、誠実さや真摯さです。
たとえ迅速に情報開示できたとしても、言葉遣いが悪かったり、嫌々または投げやりな態度が出ていたりすると、企業イメージが大きく悪化してしまいます。
また表面上の言葉遣いなどは丁寧でも、会見の際に華美な格好であったり、高級ホテルなどで会見していたりすると、緊急時の対応として相応しくないと判断され得るため注意が必要です。
ポイント3:事実をありのまま的確に説明する
危機管理広報を行う際には、事実をありのままに説明することも重要です。
特に不正会計などの不祥事の場合、不都合な事実を隠したいという意図が開示内容に反映されてしまうことがあります。
後から虚偽の情報であることが判明すると、より印象を悪化させることになるため、事実のみを伝える姿勢が不可欠です。その時点で不明な情報に関しては、正直に調査中である旨を伝えましょう。
ポイント4:広報戦略の見直しと改善を図る
事前に計画策定やトレーニングを行っていても、緊急のトラブルに対して100%完璧な対応を行うことは困難です。1つのトラブルに対する危機管理広報の対応が完了したら、対応の過程や結果に関する分析を行い、広報のプロセスや発表内容・形式などの改善を図ることが重要です。
これによって、次回以降の危機管理広報の質を高めることが可能になります。
まとめ
危機管理広報は、企業のイメージ低下などを防ぐ手段として非常に効果的です。特に近年はSNSの普及によって、短時間で事実無根の情報や自社の瑕疵が拡散されやすい傾向があります。
そのため、今後はより一層スピーディーかつ真摯な態度で危機管理広報を行う重要性が高まると考えられます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
やることリスト付き!内部統制構築ガイド
内部統制を基礎から知りたい方・内部統制の導入を検討している担当の方・形式だけになっている内部統制を見直したい方におすすめの人気ガイドです。
内部統制の基本と内部統制構築のポイントをギュッとまとめています。
【令和7年度 最新版】ストック・オプション丸わかりガイド!
ストック・オプションの概要や種類、IPO準備企業がストック・オプションを利用するメリットに加え、令和6・7年度税制改正の内容についても解説した充実のガイドです。
IPOを検討している企業様はもちろん、ストック・オプションについて学習をしたい企業様も含め、多くの方にご活用いただいております。
J-SOX 3点セット攻略ガイド
すべての上場企業が対象となるJ-SOX(内部統制報告制度)。
本資料では、IPO準備などでこれからはじめてJ-SOXに対応する企業向けにJ-SOXの基本からその対応方法までをまとめた、役立つガイドです。
マネーフォワード クラウドERP サービス資料
マネーフォワード クラウドERPは、東証グロース市場に新規上場する企業の半数※1 が導入しているクラウド型バックオフィスシステムです。
取引データの自動取得からAIによる自動仕訳まで、会計業務を効率化。人事労務や請求書発行といった周辺システムとも柔軟に連携し、バックオフィス業務全体を最適化します。また、法改正に自動で対応し、内部統制機能も充実しているため、安心してご利用いただけます。
※1 日本取引所グループの公表情報に基づき、2025年1月〜6月にグロース市場への上場が承認された企業のうち、上場時にマネーフォワード クラウドを有料で使用していたユーザーの割合(20社中10社)
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
IPO投資とは?メリットやデメリット・当選確率を高める方法について解説
IPO投資を検討している人の中には、、メリットやデメリットをあらかじめ理解したうえで始めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。また、IPOを目指す企業の人であっても、IPO…
詳しくみる情報統制とは?内部統制の強化にITへの対応が必要な理由を解説
内部統制を実施するにあたり、ITへの対応を早急に進める企業も多いのではないでしょうか。しかし、IT業務に関しては、経理担当者や経営者本人ではなくITシステムの管理ができる技術を持っ…
詳しくみるリスク管理委員会(リスクマネジメント委員会)とは?役割や目的を解説
現代社会では、複雑化とグローバル化が進展し、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。このような状況下において、企業が持続的な成長と発展を遂げるためには、将来起こり得るリスク…
詳しくみるスチュワードシップコードとは?コーポレートガバナンスコードとの違いや改訂状況を解説
スチュワードシップコードとは、機関投資家の望ましい姿や行動を定めた指針です。機関投資家がスチュワードシップコードを導入すると、企業の中長期的な成長や利益増大が促進されるというメリッ…
詳しくみる企業経営に欠かせない経常運転資金とは?計算方法や不足時の対応方法などを解説
ニュースや新聞で「黒字倒産」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 企業経営において、売上と利益は非常に大事ではありますが、それだけでは実際に健全なビジネスを…
詳しくみるJASDAQ上場とは?東証一部・二部・マザーズとの違いや審査基準を解説
将来的に、株式市場への上場を考えているけれど、何から始めてよいかわからないと考えている事業主もいるのではないでしょうか。2022年4月から、東京証券取引所の市場区分が再編されたので…
詳しくみる