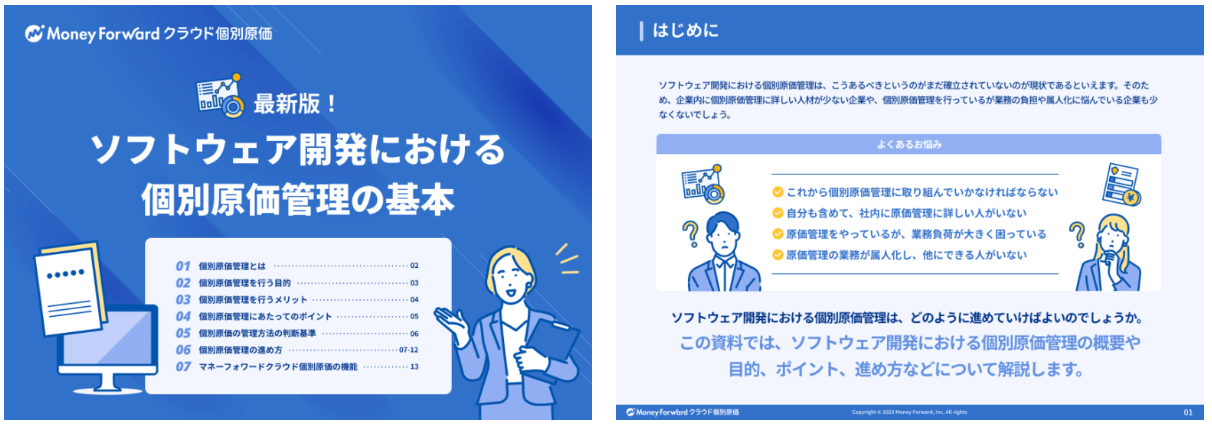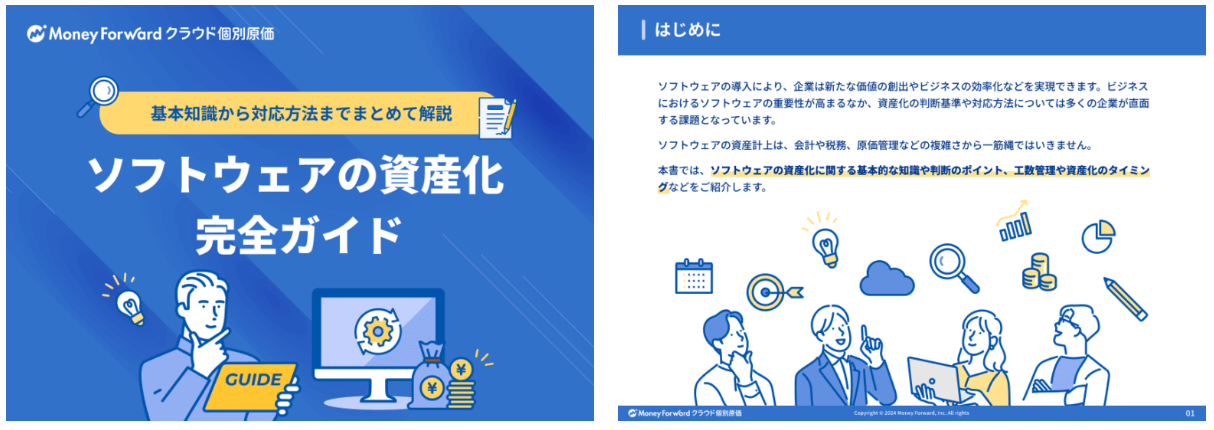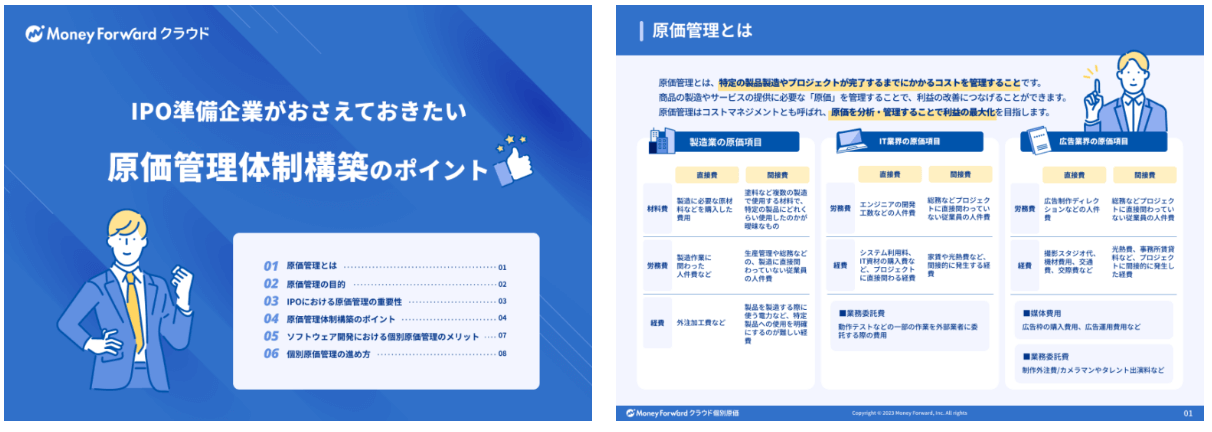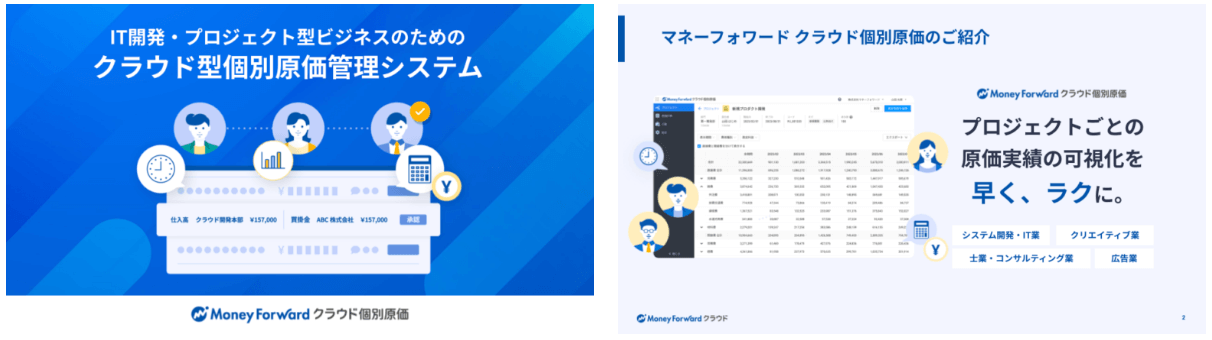- 更新日 : 2025年8月19日
間接工数とは?多いと何が問題?直接工数との違いや削減の取り組みを解説
間接工数とは、製品やサービスの生産に直接関わらない業務に使われる時間のことです。会議、資料作成、社内のやり取りなど、これらの業務は、積み重なると企業の利益を大きく圧迫します。特に中小企業では、限られた人員で運営されているため、間接工数が多いと本来の生産活動に十分な時間が割けなくなります。この記事では、間接工数とは何か、なぜ削減が求められるのか、適正な管理方法をわかりやすく解説します。
目次
間接工数とは
間接工数とは、製品やサービスに直接かかわらない作業にかかる時間のことです。
製造現場やオフィスでは、作業時間は大きく「直接工数」と「間接工数」に分かれます。直接工数は、たとえば部品を組み立てる、商品のパッケージを行うといった、売上に直結する作業に使われる時間を指します。一方で間接工数は、会議への出席、報告書の作成、道具の準備、作業記録の入力など、直接的に製品やサービスに手を加えるわけではない作業に使われる時間です。
この区別は、作業の効率性や原価の適正化を図るうえで重要な意味を持ちます。なぜなら、間接工数が増えると、見えないコストが積み重なり、利益が圧迫されることがあるからです。特に中小企業では、少人数で業務を回す場面が多く、1人あたりの間接作業が増えると、本来注力すべき作業に時間が割けなくなります。
また、近年では働き方改革やDXの推進により、業務の効率化が求められています。こうした背景もあり、「間接工数の見える化」と「削減」が経営課題として注目されるようになりました。
間接工数と直接工数との違い
間接工数と直接工数の違いは、「作業が売上や製品に直結しているかどうか」です。
たとえば、製造ラインで部品を加工する作業は直接工数です。その作業がなければ製品は完成しません。一方で、その加工に必要な工具を準備する作業や作業後に使った道具を片づける時間は間接工数です。これらの作業も業務に必要ですが、売上を直接生み出すわけではありません。
間接工数として分類されるのは以下のような作業です。
- 会議や打ち合わせの参加
- 書類の記入、データ入力
- 工具・資材の準備や片づけ
- 業務報告の作成
- システム操作や確認作業
一方、直接工数に該当するのは以下のような作業です。
- 部品の組立や加工
- 商品の包装や出荷準備
- 顧客対応(販売、サポート)
- サービスの提供(例えば、介護や飲食)
このように、直接工数は作業そのものが最終成果物に直結しており、原価や利益を算出する際の基準になります。間接工数はそれを支えるための活動であるため、いかに最適化するかが業務改善の鍵となります。
間接工数の特徴
間接工数は特定の製品に直接結びつかず、複数の製品や業務にまたがる点が特徴です。企業全体の運営に必要な活動が含まれるため、可視化や配賦が難しく、原価管理を複雑にします。
また、間接工数には固定費と変動費が混在します。事務職の給与は固定費的性格を持ちますが、消耗品や修繕費は変動費となります。これらを適切に管理しないと、利益管理が不正確になりかねません。
間接工数の測定と計算方法
間接工数の正確な管理には、「測定」と「計算」の両方が必要です。作業時間の記録から分類、集計、そして費用配賦までを一連の流れとして整理することで、業務のムダを可視化し、効率化につなげることができます。
時間の記録
最初のステップは「時間の記録」です。多くの企業では、日報や週報、タイムカード、工数管理ツールなどを使って業務時間を記録しています。以下のような方法があります。
- 作業日報への記入
毎日の作業時間を記入します。作業名と時間をセットで記録することで、後から集計しやすくなります。 - 工数管理ソフトの導入
デジタルツールを使うと、リアルタイムでの入力や集計がしやすくなります。部署単位や業務別に自動分類できる機能を持つソフトもあります。 - 作業ログの可視化
PC操作ログやアプリ利用時間の記録から、実際の作業内容を分析する方法もあります。オフィス業務では特に有効です。
分類のルール決め
記録した時間は、「直接工数」と「間接工数」に分けて集計する必要があります。そのためには、会社や部署ごとに分類ルールを定めておくことが重要です。
例えば、以下のような基準で分けると明確になります。
- 商品・サービスに直結する作業 → 直接工数
- 社内向けの準備・報告・管理業務 → 間接工数
分類のルールが曖昧だと、作業内容の分類が人によってブレてしまい、データの信頼性が下がってしまいます。最初に分類例を示し、誰が見ても同じように判断できる仕組みにしておきます。
データの集計と見える化
分類されたデータは、業務ごと・部署ごとに集計して、グラフや表などで「見える化」することが大切です。全体に占める間接工数の比率や、特定業務への偏りが見えてきます。
例えば、あるチームの間接工数が全体の50%を超えていた場合、どの業務に時間がかかっているのかを掘り下げ、改善策を考えることができます。
測定を継続的に行えば、改善前後の変化も確認でき、取り組みの効果検証にもつながります。
集計した間接費を配賦する
集計した間接費を、合理的な基準(例:直接労働時間、生産量、売上比率など)に基づいて、製品やサービスに分配します。これを「配賦」と呼び、例として以下のような手順で行います。
- 月間間接費:300万円
- 製品Aの直接作業時間:1000時間
- 製品Bの直接作業時間:2000時間
- 合計3000時間 → 配賦率:300万円 ÷ 3000時間 = 1000円/時間
→ 製品A:1000時間 × 1000円=100万円
→ 製品B:2000時間 × 1000円=200万円
間接工数の正確な把握と配賦は、原価の精度を高め、ムダな作業の洗い出しにもつながります。時間の使い方を定量的に見直すことで、改善対象が明確になり、業務効率や利益率の向上に直結します。
間接工数が多いと何が問題?
間接工数が多すぎると、利益に直結しない作業に時間が偏り、会社全体の生産性が下がります。
直接工数が売上や製品に関係する作業であるのに対し、間接工数はサポート的な作業です。これが必要以上に多いと、本来力を注ぐべき作業にかける時間が減り、結果としてコストが上がり、利益が出にくくなります。
例えば、1日のうち半分以上を会議や社内処理に使っている職場では、実際の売上に関わる活動が後回しになってしまいます。これでは人件費ばかりが増え、利益率の低下につながります。
間接工数が多い職場で起こる問題
間接工数が過剰な状態になると、以下のような問題が発生します。
- 人手不足感が強まる
作業時間が足りなくなるため、慢性的な残業や納期遅れにつながりやすくなります。 - 人件費が上がる
直接工数に対して間接工数の比率が高いほど、同じ成果を出すために多くの人や時間が必要になります。 - 業務の優先順位があいまいになる
本来不要な作業にも時間を割いてしまい、何を最優先に取り組むべきかが見えなくなります。 - 従業員のモチベーション低下
作業の成果が見えにくい仕事ばかりになると、やりがいや達成感が得られにくくなります。
これらの問題は、部署全体の働き方に悪影響を及ぼし、長期的には離職や品質低下の原因にもなります。
たとえば、製造現場で間接工数が大きい場合は、会議や指示待ち、準備・片付けといった業務に時間を取られすぎている可能性があります。このような場合、作業手順の見直しや情報共有の仕組み改善が求められます。
また、「本当に必要な作業か?」という視点で見直すことも重要です。ルーティン化してしまった無駄な業務や、不要な承認プロセスなども対象になります。
間接工数が多すぎると、会社全体のパフォーマンスにブレーキがかかります。まずは現在の割合を測定し、業務の中身を具体的に見直すことが、ムダを減らす第一歩です。
間接工数を最適化するには
間接工数の最適化は、短期的な効率化にとどまらず、長期的な視点で業務の質を高める取り組みが求められます。
なぜ“最適化”が重要なのか?
削減だけに焦点を当てると、必要な業務まで減らしてしまい、業務品質や従業員の働きやすさに悪影響を及ぼすおそれがあります。そこで重要なのが「最適化」という考え方です。
最適化とは、「必要な作業に適切な時間と資源を使い、不要なムダをなくす」ことです。つまり、削るべきところは削り、残すべきところは強化するバランスの取れた運用が必要です。
継続的な改善にはPDCAが有効
間接工数の見直しは、一度きりで終わらせるのではなく、継続的に取り組むべきです。改善活動においては、次のようなPDCAサイクルを意識すると効果的です。
- Plan(計画):間接工数の現状を把握し、改善目標を設定
- Do(実行):業務改善やツール導入などの施策を実施
- Check(確認):効果測定を行い、削減結果を検証
- Action(改善):課題があれば施策を見直し、再実行
この流れを繰り返すことで、業務の質を高めながら、ムダを継続的に減らすことができます。
従業員の意見を取り入れる
実際に間接業務を行っている現場の声は、改善のヒントの宝庫です。「どの作業が煩雑か」「どこにムダを感じているか」といった従業員の意見を集め、業務改善に反映させることで、納得感のある改革が進みます。
さらに、改善に関与することで従業員の意識も変わり、自主的な効率化の動きが生まれる土壌が育ちます。
テクノロジーの進化を活かす
ITツールやAI技術の進化により、これまで人手に頼っていた間接業務の多くが自動化できるようになっています。定型作業は積極的にテクノロジーに任せ、人がやるべき業務に集中できる体制を整えることが、間接工数最適化の鍵です。
業務内容や社内体制が変わった場合には、導入済みツールの運用方法を定期的に見直すことも重要です。
間接工数の最適化は、見えにくい領域の改善ですが、実行することで得られる効果は明確です。コスト削減だけでなく、従業員の生産性向上、業務のスピードアップ、管理精度の向上といった多方面での成果が期待できます。
間接工数を削減するには?
間接工数の削減は、業務の効率化とコスト最適化に直結します。不要な業務の見直しやツール導入によって、限られたリソースを本来の業務に集中させることが可能になります。
業務プロセスを見直す
最も効果的なのは、日常業務を見える化し、無駄を洗い出すことです。「ECRSの原則(排除・統合・再配置・簡素化)」を使って見直すと、削減ポイントが明確になります。
- 排除(Eliminate):存在意義のない業務をやめる
- 統合(Combine):類似業務をひとつにまとめる
- 再配置(Rearrange):業務の順番や担当を最適化
- 簡素化(Simplify):複雑な処理をシンプルに設計
例えば、定例会議が週3回ある企業では、回数や参加人数を減らし、議題を事前共有するだけでも大きな工数削減につながります。
マニュアルの整備
業務が属人化していると、作業にばらつきが出て工数が膨らみます。そこで、作業手順を標準化し、誰でも同じ手順で対応できるようにマニュアルを整備します。これにより教育コストも削減され、安定した業務遂行が可能になります。
ITツール・システムを活用する
ITの活用は、間接工数削減の強力な手段です。以下のようなツールが効果的です。
- ワークフローシステム:申請・承認の自動化
- RPA(自動化ツール):定型作業をボタン一つで処理
- 会計・経費精算ソフト:手入力の削減
- 社内チャットツール:メールより迅速なコミュニケーション
これらのツールは、入力ミスの防止、処理スピードの向上、重複作業の排除にもつながります。
アウトソーシングの活用
自社で行う必要のない間接業務は、外部に委託するのも有効です。たとえば、給与計算や経理、システム保守などを専門業者に依頼すれば、社員はコア業務に集中できます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
工数管理をエクセルで行う方法は?表の作り方やポイントを徹底解説
エクセルでも、工数管理は十分に対応可能です。特別なツールを導入しなくても、エクセルを活用すれば、タスクの進捗やコスト、各担当者の作業時間を可視化できます。 本記事では、エクセルで工…
詳しくみるクラウド型ERPでバックオフィスのテレワークを可能に
コロナ禍の影響や働き方改革など、昨今の状勢に合わせてバックオフィス部門でもテレワークを導入する動きが増えています。しかしバックオフィス部門は紙ベースの作業が多く、テレワークを導入で…
詳しくみるソフトウェア仮勘定とは?利用目的別、会計処理のポイントと留意点を解説
近年、ソフトウェアは企業活動において不可欠かつ重要な資産となっていますが、その開発や導入には経費がかかります。ソフトウェア仮勘定は、企業がソフトウェアの制作(開発)にかかる費用を正…
詳しくみるERPで原価管理を行うメリットをわかりやすく解説
原価管理とは原価を最適化できるように管理することです。原価管理は生産コストを下げるためにも、製品の品質を維持するためにも必要で、企業の利益に直接関係します。さらに、正確な原価管理は…
詳しくみる個別原価計算とは?メリットや注意点、計算方法、効果的なツールを解説
個別原価計算とは、製品やプロジェクトごとに原価を計算する方法です。多品種少量生産を行う製造業やプロジェクト単位で活動するコンサルティング業界・サービス業界などで多く用いられています…
詳しくみる災害時に役立つBCPとは?企業の事例や災害対策との違いを解説
近年、日本各地で地震や台風、感染症などの災害が頻発しています。企業は、有事の際でも事業を続けるため、BCP(事業継続計画)の策定が不可欠となりました。 本記事では、BCPの基本的な…
詳しくみる