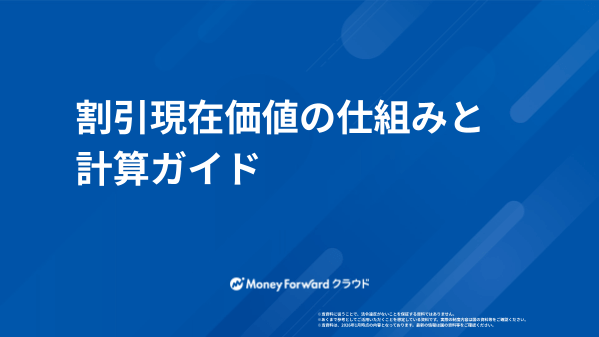- 作成日 : 2024年7月22日
割引現在価値とは?計算式やビジネスでの応用例などを解説
割引現在価値とは、時間経過による変動を考慮して将来の資産価値を算出する方法です。
M&Aや不動産投資をはじめとする企業の会計基準などでは、将来の収益性やリスクを考慮して適切な価値を算出することが重要であり、その際に利用されるのが割引現在価値です。ただし割引現在価値は、不確実性を含む点や評価者の主観に左右される点に注意する必要があります。
本記事では、割引現在価値の計算式やビジネスでの応用例、そして限界やリスクについて解説します。
目次
割引現在価値(DPV)とは
はじめに、割引現在価値(DPV)の概要について解説します。
割引現在価値(DPV)とは
割引現在価値とは「貨幣価値」を算出する方法の1つであり、英語ではDiscounted Present Value(DPV)と呼ばれています。
一般的に、貨幣(あるいは企業価値など貨幣に換算できるもの)の価値は常に一定ではなく、時間の流れとともに変化するものです。
例えば「現在もらえる100万円」と「1年後にもらえる100万円」は価値が異なります。なぜならば、1年後に得られる100万円は、インフレや物価の変動により、その価値が目減りする可能性があるためです。さらに、将来の不確実性やリスクも考慮されるため、将来の金額は現在の金額よりも低く評価されることが一般的です。
割引現在価値は、このような考え方に基づいて時間経過による変動分を考慮した上で「将来もらえる貨幣の価値」を算出します。
現在価値と将来価値
割引現在価値を理解するためには「現在価値」と「将来価値」という言葉の意味を把握しておく必要があります。
「現在価値」は、割引現在価値と同じ意味を持つ言葉であり、将来のある時点で受け取ると予想される貨幣(または貨幣に準ずるもの)が持つ「現在の価値」を表す値です。
一方で「将来価値」は、現在の貨幣(または貨幣に準ずるもの)が将来どの程度の価値になるかを示しています。
なぜ割引現在価値が重要なのか
割引現在価値という考え方は、ビジネスにおいて重要な意味を持っています。
例えば企業がM&Aなどを行う場合は、対象企業の価値を踏まえた上で買収金額を設定する必要があります。
一般的に買収金額を算出する際は、時価総額や負債から企業価値を設定する方法や、純資産などを指標とする方法がありますが、これらの手法では企業が将来にわたり創出する利益やリスクなどが考慮されません。
しかし、割引現在価値を利用すれば、収益性や企業が抱えるリスクなどを踏まえた価値の評価が可能になります。
このように「現在の価値」だけではなく「将来的に得ると見込まれるものの現在の価値」を算出できる点が、割引現在価値が重要だといわれる理由です。
割引現在価値の計算方法
割引現在価値の計算方法は次のとおりです。
| 割引現在価値 = n年後の資産価値 ÷(1 + 割引率)^ n年(期間) |
上記の計算方法からもわかるとおり「n年後の資産価値」が高額であるほど割引現在価値は上がり、割引率や年数が大きいほど割引現在価値は下がります。
下記に割引現在価値の具体的な計算例を紹介します。
| 前提条件 | 割引現在価値の計算例 |
|---|---|
| ・5年後の100万円 ・割引率:10% | 100万円 ÷(1 + 0.1)^ 5年(期間) = 100万円 ÷ 1.61051 = 62万921.323306円 |
| ・3年後の100万円 ・割引率:20% | 100万円 ÷(1 + 0.2)^ 3年(期間) = 100万円 ÷ 1.728 = 57万8,703.7037円 |
このように同じ100万円でも、割引現在価値を考慮するとその価値は大きく変動することがわかるでしょう。
割引現在価値に関するビジネスでの応用例
本章では、ビジネスシーンにおける割引現在価値の応用例について解説します。
M&A
M&Aや事業譲渡などを行うにあたり、企業や事業の価値を算出するために割引現在価値を活用します。
企業や事業そのものの価値を算出するのは非常に難しい作業だといえます。
決算情報を見ればビジネスの状況を把握することはできますが、それらはあくまでも該当する会計年度の情報でしかありません。
例えば、今年は大型な設備投資や人員増強などを行ったため赤字に転落したものの、来年以降は大幅な収益が見込めるというケースも珍しくないのです。
割引現在価値を用いれば、将来獲得するであろう収益や考えられるリスクなどを加味した上で、企業や事業の価値を算出できます。
不動産投資
不動産投資においては、物件の価値を算出するために割引現在価値が活用されています。
どのような投資であっても、良い成績を残すためには投資金額に対してどの程度の利益を上げられるか(投資対効果)を考慮して判断を行う必要があります。
不動産投資では、不動産そのものの売却額はもちろん、将来にわたり得られる可能性がある家賃収入をはじめ、管理にかかる費用などをリスクとして勘案することが重要です。
このようなときでも、割引現在価値を活用すれば投資物件の価値をより正確に算出できるでしょう。
会計基準
割引現在価値は会計基準にも活用されています。
会計基準における活用の具体例は次のとおりです。
これらは、将来的に発生する収益や債務をはじめ、キャッシュフローなどを現在価値から割り引いた結果を財務諸表へ反映する決まりとなっています。
割引率の決定方法
割引現在価値の算出では、割引率が重要な鍵を握ります。なぜならば、前述のとおり割引現在価値は割引率によって大きく変動するためです。
割引率の決定にあたっては主に次の2つを用います。
- リスクフリーレート
- リスクプレミアム
リスクフリーレートとは、主にリスクがない(または低い)商品から得られる収益を指します。リスクプレミアムとは、期待できる収益からリスクフリーレートを引いた値のことです。
リスクが上昇すればリスクプレミアムが高くなり、割引率も上がります。
割引率は、さまざまなリスクをどう捉えるかによって異なるため、財務担当者などと十分に議論することが重要です。
割引現在価値の限界とリスク
ここでは、割引現在価値の限界とリスクについて解説します。
不確実性が含まれてしまう
割引現在価値を算出するためには、未来の売上高や利益の予測値を用います。
それらの予測値はさまざまな分析によって精度を高めてはいますが、経済状況や技術革新をはじめ他社の動向など、外的要因に左右される可能性もあります。
その結果、不確実性が含まれる評価となる点には注意しましょう。
評価者の主観に左右される
割引現在価値を算出するためには、リスクを割引率に正しく反映することが重要です。しかし、全てのリスクが割引率に正しく表れない可能性もあります。
また、評価者の主観によってリスクの大小が変わるケースもゼロではありません。このように、評価者によって割引現在価値自体の結果が大きく異なる点も注意すべきポイントの1つです。
まとめ
割引現在価値とは、時間経過による変動分を考慮した上で「将来もらえる貨幣などの現在の価値」を算出する方法です。
割引現在価値は、M&Aや不動産投資をはじめ会計基準でも活用されており、さまざまなビジネスにとって重要な考え方だといえます。一方で不確実性が含まれる点や、リスクの捉え方などが人によって異なる点には注意が必要です。
割引現在価値の具体的な計算方法を記憶する必要はありませんが、さまざまなシーンで利用できるため、その概念はしっかりと把握しておきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
予実管理の煩雑さは大きな課題です。手作業に依存した業務プロセスやデータの連携不足、エクセルによる予実管理に悩む企業も多いのではないでしょうか。
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説しています。
間接部門のコスト削減ガイド
バックオフィスのスリム化にお悩みではないでしょうか。経営改善の一環としても、バックオフィスの業務効率化はとても重要です。
本書では、間接部門の役割や抱えがちな課題に加えて、コスト削減のメリットとその進め方について解説します。
2025年の崖までに中堅企業がやるべきこととは
2025年の崖は、大企業だけではなく、中堅企業においても対応が求められる重要な課題です。
2025年の崖の現状や解決に向けて中堅企業がやるべきこと、バックオフィスシステムの見直し方を解説した人気のガイドです。
マネーフォワード クラウドERP サービス資料
マネーフォワード クラウドERPは段階的に導入できるコンポーネント型クラウドERPです。
会計から人事労務まで、バックオフィス全体をシームレスに連携できるため、面倒な手作業を自動化します。SFA/CRM、販売管理、在庫・購買管理などの他社システムとも連携できるため、現在ご利用のシステムを活かしたままシステム全体の最適化が可能です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
コモディティ化とは?発生原因や脱却に向けた戦略を解説
コモディティ化とは、さまざまな要因により製品の価値が失われ、汎用品化(価値が低下)することを指します。 昨今ではSDGs経営が注目を集めていますが、未だ大量生産・大量消費という社会…
詳しくみる【M&A】PMIにおける税務リスクとは|主な課題と対応策を解説
M&A後の統合プロセス「PMI」において、税務は重要な課題のひとつです。税務処理の違いや過去の申告ミスが発覚すると、予期せぬ税務リスクを抱える可能性があります。この記事では…
詳しくみる自社に最適な多角化戦略を見つける3ステップと成功事例、メリット・デメリットを解説
中小企業の経営者や事業責任者の中には、「自社の事業が鈍化している」「将来の既存事業のリスクに備えたい」と考えている方も少なくありません。 しかし、「多角化戦略って具体的に何をすれば…
詳しくみるはじめての予算管理!プロから学ぶ、予算管理の進め方のポイントとは
Manageboardでは、「はじめての予算管理 ~プロから学ぶ、予算管理の進め方のポイントとは!数々の予算管理立ち上げを支援してきたノウハウを徹底解説!~」セミナーを開催しました…
詳しくみる予算管理とは?基本情報や管理手順、効率的な管理方法などを解説
予算管理とは、企業活動における予算の計画や実績把握、改善などの予算にまつわる管理活動のことです。 主な目的は企業利益の確保であり、そのためには定期的に予算の進捗状況を確認することが…
詳しくみる売上管理とは?基礎知識や管理上のポイント、効率化に役立つツールを解説
売上管理とは、自社の売上目標の達成を目的に、売上目標の達成率や売上の前年比・前期比などを管理する活動を指します。 売上管理では、自社にとって必要な管理項目を明確にした上で、管理ルー…
詳しくみる